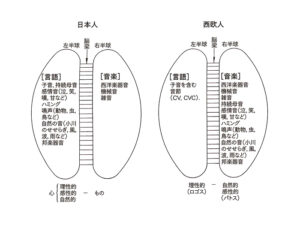小人閑居為不善日記|変わらない男――トム・ヴァーレインと《イニシェリン島の精霊》 |noirse
変わらない男――トム・ヴァーレインと《イニシェリン島の精霊》
Tom Verlaine and The Banshees of Inisherin
Text by noirse
※《イニシェリン島の精霊》の内容に触れています
1
 マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテットの来日公演を見に行った。アヴィシャイ・コーエンやブラッド・メルドーとの仕事で名を轟かせた現役最高峰レベルのドラマーで、素人でも凄みが伝わる技巧の数々にすっかり魅了された。
マーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテットの来日公演を見に行った。アヴィシャイ・コーエンやブラッド・メルドーとの仕事で名を轟かせた現役最高峰レベルのドラマーで、素人でも凄みが伝わる技巧の数々にすっかり魅了された。
帰り道、思い出したのはデヴィッド・ボウイのことだった。ジュリアナはボウイの《ブラックスター》(2016)に参加している。このアルバムには他にもダニー・マッキャスリンやベン・モンダーなど今をときめくジャズ・プレイヤーが集結していて、それまでなかったボウイのジャズ路線を打ち立てた。だがリリース3日後の1月10日、ボウイはガンで世を去ってしまった。
 ボウイは変わり続けることを恐れなかった。初期はフォーク寄りだったが、グラムロックに移行して世界規模の成功を収める。しかしグラム路線に拘泥はせず、ソウル、クラウト・ロック、ディスコ/ファンク、インダストリアル、ドラムンベースと、次々に新しい衣装を纏っていく。常に変わり続ける、それが彼の命題だった。
ボウイは変わり続けることを恐れなかった。初期はフォーク寄りだったが、グラムロックに移行して世界規模の成功を収める。しかしグラム路線に拘泥はせず、ソウル、クラウト・ロック、ディスコ/ファンク、インダストリアル、ドラムンベースと、次々に新しい衣装を纏っていく。常に変わり続ける、それが彼の命題だった。
そんなボウイが最後に選んだのがジャズだった。まだ若かったジュリアナやマッキャスリンは今ほど有名ではなく、このアルバムで名前を轟かせたと言っていい。ボウイは残された時間が短いことを知りながらスタジオ入りしたらしいのだが、付き合いの長い仲間や気心の知れたミュージシャンではなく、初めて組む若手と最後になるかもしれないレコーディングに挑むという点に、ボウイの矜持が伝わってくる。
あれから年が明けたこの時期は、ふとボウイのことを思い出してしまう。特にこの1月は、厳しいニュースの続く1ヶ月だっただけに。
2
 この1月は、ロックリスナーにとってはつらい年明けとなった。三大ギタリストのひとり、ジェフ・ベック。元ザ・バーズ、アメリカン・ロックの偉人デヴィッド・クロスビー。ニューヨーク・パンクを代表するバンド、テレヴィジョンのギタリストにして詩人トム・ヴァーレイン。サディスティック・ミカ・バンドやイエロー・マジック・オーケストラの高橋幸宏。そして日本を代表するロックンロール・バンド、シーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠が、相次いで亡くなったからだ。一人ずつ取り上げるほどの余裕がないので、今回はトム・ヴァーレインについてのみ触れていきたい。
この1月は、ロックリスナーにとってはつらい年明けとなった。三大ギタリストのひとり、ジェフ・ベック。元ザ・バーズ、アメリカン・ロックの偉人デヴィッド・クロスビー。ニューヨーク・パンクを代表するバンド、テレヴィジョンのギタリストにして詩人トム・ヴァーレイン。サディスティック・ミカ・バンドやイエロー・マジック・オーケストラの高橋幸宏。そして日本を代表するロックンロール・バンド、シーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠が、相次いで亡くなったからだ。一人ずつ取り上げるほどの余裕がないので、今回はトム・ヴァーレインについてのみ触れていきたい。
テレヴィジョンはニューヨーク・パンクを代表する存在だが、たった1年半ほどで解散してしまい、高い評価とは裏腹に商業的成功とは縁がなかった。けれど彼らの音楽に漂う死の匂いは、その短命を先取りしていたと思う。衝動のままに突き進むようなよくあるパンクバンドと違い、テレヴィジョンの張り詰めたサウンドと厭世的な歌詞は、ヴァーレインなしには実現しなかったろう。
キャデラックが墓場から走ってきて
側に停まって、乗り込むように誘ってくる
やがてキャデラックは墓場へ引き返していった
ぼくはそこに降りるしかなかった
(中略)
覚えてるよ
どのように闇が幾重にも重なっていったかを
思い出す
稲妻が光自身を引き裂いたところを
ぼくは耳を澄ましていたんだ
降りしきる雨音に
聞こえてきたんだ
なにものかが息をひそめているのが
テレヴィジョン〈トーン・カーテン〉(1977)
 ヴァーレインはさっさとバンドを解散させたあと、淡々とスローペースな活動を続けていった。彼ほどの才能があれば成功を得ることも、シーンの中核に居続けることもできただろう。けれどもそういう道は選ばなかった。
ヴァーレインはさっさとバンドを解散させたあと、淡々とスローペースな活動を続けていった。彼ほどの才能があれば成功を得ることも、シーンの中核に居続けることもできただろう。けれどもそういう道は選ばなかった。
ソロデビュー作《醒めた炎》(1979)に〈キングダム・カム〉という曲がある。「王国が来る」という歌で、要は来世のことだ。詩人ヴァーレインが死のイメージに魅了されていたのは間違いないだろう。
ボウイは《スケアリー・モンスターズ》(1980)で、〈キングダム・カム〉をカバーしている。彼も〈スペイス・オディティ〉(1969)、〈ロックンロールの自殺者〉(1972)、〈セブン〉(1999)など、死について歌うことが多かった。
だがボウイにとってのそれは疑似的な死、つまり変化のことだったのだろう。一方ヴァーレインの音楽性はテレヴィジョンの初作で既に完成しており、その後はポツポツと同系統の作品をリリースするのみだった。
ヴァーレインはボウイと違い、変われない男だった。変わることのないまま年老いて、やがて若いころから夢想していた死に追いつかれて、逝ってしまった。
3
 ジュリアナの公演が終わったあと、まだ時間があったので映画館に立ち寄り、《イニシェリン島の精霊》という作品を見てきた。《スリー・ビルボード》(2017)でアカデミー賞二部門受賞に輝いた、マーティン・マクドナー監督最新作。原題は《The Banshees of Inisherin》で、バンシーとはアイルランドの言い伝えで、人の死を予言する妖精のことだ。
ジュリアナの公演が終わったあと、まだ時間があったので映画館に立ち寄り、《イニシェリン島の精霊》という作品を見てきた。《スリー・ビルボード》(2017)でアカデミー賞二部門受賞に輝いた、マーティン・マクドナー監督最新作。原題は《The Banshees of Inisherin》で、バンシーとはアイルランドの言い伝えで、人の死を予言する妖精のことだ。
舞台は1923年、内戦で荒れるアイルランド付近の小島。主人公は酪農で生計を立てる平凡な独身男パードリック。ある日彼がいつものようにフィドル弾きの親友コルムをパブに誘ったところ、すげなく断られる。理由を尋ねると、「おまえが嫌いになった」、「もう話しかけないでほしい」と切り出されてしまう。
「音楽を作ったり、思索をする時間がほしい」、「だからおまえの退屈な話に付き合う暇はないんだ」。コルムの突然の心変わりを受け入れられないパードリックはしつこく喰い下がるが、コルムも頑として応じない。ふたりの諍いは次第にエスカレートしていく。
田舎の二人の男の些細ないざこざ。ちっぽけな話だが、劇作家出身のマクドナーらしく慎重にメタファーを織り交ぜ、寓話のように描かれている。角度を変えれば別れ話がこじれたようにも見えるし、内戦を背景に、理解し合えない人間たちの普遍的な業を浮き彫りにしたようでもある。
わたしが気になったのは、音楽のために今までの関係を見直したいというコルムの言葉だ。パードリックは気のいい男ではあるが教養はなく、音楽に関しても無知だ。コルムはもう初老に差し掛かっていて、この先何があるか分からない。今まではパードリックの他愛ない話に付き合っていたが、残された時間の重みに気付き、昔からの夢、目標に打ち込みたくなったのだろう。
コルムの姿勢は極端とは言え立派なもので、見習いたいくらいだ。しかし、一方的に縁を切られたパードリックがコルムに執着する気持ちも分かる。パードリックには同居の妹がいて、島ではめずらしく読書が趣味の知的な人物なのだが、彼女は退屈な生活を厭っており、アイルランド本島に引っ越してしまう。妹とコルムが生活の中心だったパードリックは、突然孤独の底に突き落とされてしまう。
コルムも妹も変化を望み実行する行動力と強い心を持っているが、パードリックにそれはない。そもそも趣味も夢も人生の目的もない彼には、コルムや妹の気持ちを理解することができない。毎日楽しく過ごせればそれでいい、そんな男なのだから。
しかしそれはそんなに悪いことだろうか。変化は大事だ。しかし周囲に軋轢を生んでまで変化する必要はあるのだろうか。人に迷惑をかけていたり、大きな欠点があるのなら変わるべきかもしれないが、そういうわけでもない。実際にコルムは急激な変化を望んだばかりにパードリックとのあいだに軋轢を生み、大きな代償を払うことになる。
平和で波風の立たない気楽な人生を送りたかったパードリックも極端な行動に出てしまい、「どちらかが死ぬまで終わりはない」とまで口にする。そこにはそれまでのパードリックの姿はない。彼も否応なく変化してしまったのだ。
4
終盤、謎めいた老婆が、人が二人死ぬとバンシーのように予告する。パードリックとコルムにのっぴきならない事態が待ち受けているのではと身構えるも、結局とある人物が一人死ぬのみで、二人は生き延びたまま映画は幕を下ろす。もう一人死んだのは誰なのか、観客それぞれが考えろといういやらしい作りだが、コルムが生きていたというのはパードリックが見た幻で、本当は死んでいたと解釈することもできるだろう。
さらに言うと、パードリックとコルムを、一人の人間として考えることもできる。この作品はこの二人と妹に、イニシェリン島において選択可能な生きかた――退屈な人生を送るか、波風が立つのも厭わず変化を選ぶか、島を出ていくか――を配分しただけの、シンプルな骨格で成り立っている。
こうして並べると妹の選択が妥当なようにも見えるが、本島でも内乱が起きていて、この先穏やかな生活が送れるかは分からない。こうした図式はこの小島に限らず、どんな場所でも当てはまることだろう。
変化すること自体は容易いかもしれない。重要なのはそれを自らのスケールに、身近な人間関係に、生活パターンに、ずっと続いていく毎日に定着させることにある。SNSで加速化する情報社会はしきりに変化を促し、変わることを美徳だと嘯いてくる。その圧倒的な情報量を前に、変わらなくてはいけないのではないか、変わらないのはよくないのではと思うこともあるだろう。しかしそれはもしかしたら、バンシーの囁きかもしれないのだ。
わたしもできればボウイのように、変化を恐れずにいたい。けれどわたしはきっと、パードリックに近い人間だ。ものごとが次々と変わっていき、周りの人々も少しずつ立ち去ってゆく。できるのは時が過ぎ去っていくのをただ茫然と眺めるだけ。けれど、そういう生きかたも、そう悪くないかもしれない。そこにバンシーの呼ぶ声が聞こえてくるとしたら、ヴァーレインが奏でるギターのような音なのかもしれない。
(2023/2/15)
———————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中