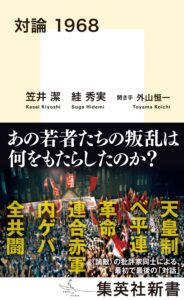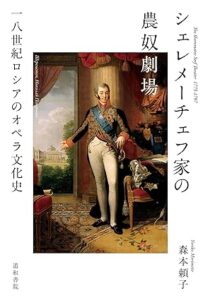Books|対論 1968|西村紗知
著者:笠井 潔、絓 秀実
聞き手:外山 恒一著
集英社新書
2022年12月出版 1,100円(税込)
Text by 西村紗知 (Sachi Nishimura)
多くの批評文には状況に対する提言が含まれているものである。だから、過去の批評文を読むにあたって、状況への理解が不可欠となる。批評を書くことは理論的な枠組みの運用である。理論的な枠組みは過去の批評文から取り出すことが多い。そんなわけで、状況への理解をないがしろにするわけにはいかない。その中で重要なトピックのひとつが「68年」である。しかし私は「68年」的な話題が苦手だ。最近はいろいろと仕事をさせてもらう機会が増え、自分自身の批評文で扱う題材もだいぶ取り留めがない感じになってきたが、自分がやっていることは、革命が起こらない前提で物を考えることなのだと思っている。解放としてではなく、拘束力の獲得によって可能となるものとしての「自由」について考えていくことが、現時点での私の批評の方向性である。そうはいっても、今現在のマイノリティー・ポリティクスについて考えるにあたって、「68年」を避けて通ることはできない。しかし「68年」は登場人物と出来事が多すぎて気後れする。そんな次第で本書を手に取った。
本書に収録されているのは、笠井潔と絓秀実という同学年の論客の対論だが、実際には、彼らの二回り下の世代に属する外山恒一がインタビューし、話の方向をまとめていったものという具合である。外山の導線の引き方がきれいで、笠井と絓の語りが、単なる思い出話にならないようになっている。「ジッパチ」「日大全共闘」「華青闘告発」「川口大三郎事件」など、まず覚えるべき固有名詞がどれかがわかるようになっている。絓秀実の労作『革命的な、あまりに革命的な』で挫折した私のような人間にはたいへんありがたかった。
対論の趣旨は一貫して、全共闘を正当に評価せよというところにあるようだ。小熊英二『1968』は「ベ平連と全共闘を何か対立的なものであったかのように描いている。両者を分断し敵対させ、彼が理解しえたベ平連の側のみを正当化するという作為を感じるね」(笠井の発言、54頁)と批判されている。それと「フェミニズム批判」の項目では、外山が「フェミニズムの前身たるウーマンリブのような運動が登場しえたこと自体が全共闘運動の一つの成果なのに、そこにいたる過程での恨みつらみに囚われすぎて、“全共闘なんてろくでもなかった”とフェミニストたちがあまりにも言いすぎたんです」と二人に言っている。これに対し絓が「今の若いフェミニストたちには、どうせ全共闘を批判するなら“上野千鶴子批判”まで進んでほしい」などと応答しているが、これについてはあまりピンとこなかった。上野千鶴子を批判する人は何人もいるけれども、全共闘批判を経てそうしている、というのがぱっと思いつかない。いまどきのハッシュタグポリティクスの旗手が、全共闘世代に的を絞って批判しているところを見たことがない。それとその流れで田中美津再評価の機運についても触れられているが、それをやっている人は私の知り合いに一人しかいない。
ツイッターで、運動をやっている人や運動に関心がある人をフォローしていないと、飲み込みにくい内容なのかもしれないとは思った。というより、ツイッターで「そういえば、この人どういう方かしら……?」となる運動界隈のアカウントがいくつかあるわけだが、本書を読んでいるとその他己紹介として読めるようなところがある(花咲政之輔、模索舎、牛嶋徳太朗、千坂恭二など)。その点、ツイッターは運動の撤退戦の主戦場としての側面があるのだろうな、と改めて感じた次第である。
他にも、「あ、そうなんですね……」となるくらいの論点がたくさんあった。「戦後民主主義」という言葉が本書では基本的には悪口としてしか用いられていない点、「赤」から「緑」への動向については基本的に批判的に捉えられている点、村上春樹の作品における全共闘の扱いについてがそれである。これらについてはもう少し、体系的な著作を手に取るなどして時間をかけて検討していきたいと思う。
◆目次◆
序章 対話の前に
第一章 1968
第二章 1968以後
終章 国家と運動のこれから
(2023/1/15)