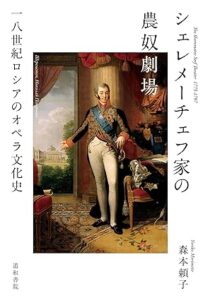Books|個人メディアを十年やってわかったこととわからなかったこと ― オルタナティブ・ネット・音楽シーン|田中里奈
個人メディアを十年やってわかったこととわからなかったこと ― オルタナティブ・ネット・音楽シーン
 What I Have Found Out and Haven’t After Ten Years of Running a Self-Publishing Medium: Alternative, Internet, Music Scene
What I Have Found Out and Haven’t After Ten Years of Running a Self-Publishing Medium: Alternative, Internet, Music Scene
山本 佳奈子 著
by Kanako Yamamoto
オフショア
2022年6月出版 1000円(税別)
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
2011年7月から10年間にわたり、アジアにおける広範な文化実践者たちのさまざまな活動について、ウェブ記事と対面イベントの両面で発信し続けてきた個人メディア『Offshore』。その立ち上げから運営までをひとりで行ってきた山本佳奈子が、これまでの10年間を踏まえて「わかったこと」と「わからなかったこと」をまとめた、限定300部の冊子である。ちなみに『Offshore』は、2022年8月に紙媒体の文芸誌『オフショア』として再開され、同誌のオンラインショップと全国各地のセレクト系書店で販売されている。
同書は3篇のエッセイから構成されている。話し口調で書かれた各篇は10~20頁ほど。山本がさまざまな現場で感じ、考えてきたことの反省を等身大に描いた文体は非常に読みやすい。ただし、「読者がただ他人の反省会を聞かされているような印象に陥らないような構成を考え」1たと山本自身も記しているように、一個人の当事者性をひょいと跳び越えて、山本とは異なるフィールドにいたかもしれない読者の鳩尾を何度も深く抉ってくる。
3つのキーワード:オルタナティブ・ネット・音楽シーン
第一篇の「オルタナティブについてわかったこと——形骸化するオルタナティブと、仕事化されないオルタナティブ」で、山本はシンガポールのアーティストであるザイ・クーニンとの、「アンダーグラウンド」の定義をめぐる議論を思い出す。「何かしら危険や事情があり地上に上がれないもの」を指してきた語であるにもかかわらず、メインストリームに与しない独立したメディアの表面的なカッコ良さに憧れ、「オルタナティブ」を自称することで必然的に生まれる責任を回避してはいなかったか。
山本の個人レベルの反省は、今日のインターネット世界におけるコミュニティの問題へとシームレスにつながっていく。第二篇の「ウェブやSNSについてわかったこと——エコーチェンバーのネットにちょうど良いサイズの社会を求めて」で、山本はウェブメディアの運営者として、インターネットとSNSがユーザーと情報に溢れたオープンな場であるように見える反面、実際には近しい嗜好を持つ者同士の閉鎖的なコミュニティが乱立し、小集団内の当たり前が増幅・強化されていることを確認する。山本は、このようなエコーチェンバー(反響室現象)によってメインストリームが失われつつあることを「民主的過程」と一部肯定したうえで、多数派の対極を行くことで存在価値を高めてきた「オルタナティブ」の存在意義の揺らぎを改めて警告する。第一篇が「オルタナティブ」に属する者の内的視点だとすれば、第二篇はインターネット世界全体における「オルタナティブ」の配置の概観を示しており、これらがひとつの問題を内と外から描いていたことがわかる。
第二篇に登場した自閉的なコミュニティ性という問題は、第三篇「日本の音楽シーンについて、わからなかったこと——興行ビザ/ツアー収支とギャラ定額制/対バン文化」で、ウェブとは異なる文脈の中に改めて発見される。山本は、今度は海外アーティストの来日ツアーの企画・制作の立場から、海外アーティストの招聘に求められる興行ビザにおいて、ライブハウスにおける小中規模の興行が法令上度外視されてきたことを指摘する。
特筆すべきは、ここで山本が「大小様々なサイズ、規模、レイヤーがあって、やっと豊かな芸能文化が育まれることは、公共文化政策においても常識」と一刀両断すると同時に、「音楽業界の誰も[…]改善を求めていないから、放置されているだけなのではないだろうか」と、業界内部における共謀的沈黙——「最も確実なイデオロギー効果とは、実行されるためには言葉を必要とせず、自由放任と共謀的沈黙を必要とする」2——にも目を向けている点だ。
以降のページでは、来日ツアーを黒字化すべく「先輩」に相談した山本が、自分のやりたい方向性とことごとく合わないアドバイスをもらってモヤモヤする話が続く。グッズや日本盤CDの販売で儲けるのが定石。日本盤には歌詞対訳や日本語解説を付けて、デザインも日本規格に合わせるべき。日本以外のアジアからのアーティスト単体ではライブの採算が取れないから対バン(1つのライブイベントに複数のバンドが入れ替わりで出演する形態)にして、集客力の強いバンドのギャラを予算から優先的に支払うのが当たり前……。
何と(または誰と)抱き合わせで売れば商品価値が高まるのかという指標で動き、そのように消費されてきた日本の音楽シーンに、「圏外からきたアジアの音楽家やバンド——つまりまったく異なるハビトゥスを持った者たち——を放り込んで、商業的にも芸術的にもがっちり成功するなんていうことが、どうしても考えられない」という山本の結論は絶望的だ。「音楽を聴く人こそ、積極的に日本語以外の言語を受容できるんじゃないか」という素朴でありふれた期待は、音楽を聴く人こそ自らの所属するコミュニティから出ようとせず、エコーチェンバーの快さに浸りきって分断と棲み分けを推進する片棒を担いできたという事実で黒塗りされる。
だが、山本は同書を展望のない形で終わらせてはいない。
有名性や話題性を掛け算した対バンを計算・構築できる人材ではなく、美術でいう学芸員か図書館でいう司書のような、知見に富んで技術があり、創造的でプロフェッショナルで、調査と研鑽に飽きない人材が、音楽イベントを企画するような世界にならないだろうか。卓越化や闘争の道具としての音楽ではなく、本当に音楽を聴かせるための場づくりをできる人材が、Covid-19の収束までに育たないだろうか。
学芸員や司書が疲弊している現状を思い起こすと暗澹たる気持ちになってくるが、ここで山本が言いたいのは、一元的な価値基準の再生産によって稼働している業界に対して、別の価値基準を差し挟める余地がもしあるとしたら、それは、古今東西の広範な領域をカバーする専門性があって、なおかつ実際に企画を立ち上げて運営できる実務能力も有した専門職に違いない、ということだろう。もっと言えば、そのような専門職を養成する場が整備されておらず、現場ごとの不文律をまねぶところからスタートせざるを得ない状況が暗に示唆されている。山本のようにトライ&エラーを繰り返して辛うじて生き延びた少数精鋭になって初めて問題に気づけるのだとしたら、状況の改善に至る道ははてしなく遠い。
「私たちが行なっていることを考える」ために
もっと悪いことに、この問題は日本のライブハウスの音楽シーンに限った話では決してない。演劇学者のリチャード・シェクナーは1992年の時点で、「21世紀に演劇は弦楽四重奏となり、愛されてはいるものの極端に限定されたジャンルとなるだろう」と警鐘を鳴らしていたが3、結局のところ、演劇学者の内野儀が2021年に指摘した通り、21世紀の演劇は実践を相互につなげて考えることすら困難なほどに「破片化」してしまった4。自分の属しているジャンル内ですら覚束ないくらい、各実践がエコーチェンバーの中に引き篭もってしまったと考えることもできるだろうし、ひょっとしたら、自分のフィールドだけに焦点を絞るから何も見えなくなってしまうのかもしれない。
 音楽評論家の柳樂光隆は、『Jazz The New Chapter』を創刊するにあたって、「ジャズ評論家の言葉の大半は、新たに出てきたジャズを聴く耳にではなく、ただ自分自身と狭い身内にのみ向けられている」と断じ、「この20年、ジャズの歴史は記されてこなかったのにほとんど等し」いと言い切っている5。そのうえで、「現在までのあらゆるトレンドにも目を向けながら、ジャズやそれ以外の音楽(ここが重要だ)を聴き続け、様々な場所に執筆してきたスペシャリスト」こそが「90年代以降の拡散してしまったジャズの動きや、その音楽にまつわる文脈を正確に捉えることができている」と述べている6。
音楽評論家の柳樂光隆は、『Jazz The New Chapter』を創刊するにあたって、「ジャズ評論家の言葉の大半は、新たに出てきたジャズを聴く耳にではなく、ただ自分自身と狭い身内にのみ向けられている」と断じ、「この20年、ジャズの歴史は記されてこなかったのにほとんど等し」いと言い切っている5。そのうえで、「現在までのあらゆるトレンドにも目を向けながら、ジャズやそれ以外の音楽(ここが重要だ)を聴き続け、様々な場所に執筆してきたスペシャリスト」こそが「90年代以降の拡散してしまったジャズの動きや、その音楽にまつわる文脈を正確に捉えることができている」と述べている6。
柳樂の指摘で重要なのは、内と外を行ったり来たりしながら、様々な場所で発信し続けるというバランス感覚——身内での共謀的沈黙に与せず、かといって蚊帳の外から無責任に発言するよそ者になることも良しとしない状態とでも言ったらいいのだろうか——を「スペシャリスト」たちに求めている点だろう。それは、「私たちが行なっていることを考える」(ハンナ・アレント)行為と言い換えられるかもしれない7。
自分と異なる嗜好や背景を有した複数の他者と偶然出会い、交流できる確率の高い世界が自分のまわりから失われつつある(あるいは、そもそも存在しなかった)ことに気づけるかどうかという問題は、魚が自分の泳いでいる水の状態を把握するくらい難しい8。だが、当たり前に押し流されているさなかに溺れてしまわないために、山本の言うところの「自分が消化できる情報の実際量を見極め、ウェブ世界であっても身体的に振る舞うことのできる感覚を取り戻」すことは決して不可能ではない。情報を呑みすぎて沈んだり、逆に漫然とただプカプカ浮かんだりするのではない、「息継ぎ」のできるちょうどいい塩梅。同書を読んでいると、なんだかそう振る舞えるようになれる気がしてくるから不思議である。
(2022/11/15)
——————–
- 以下、脚注がついていない限り、引用元は『個人メディアを十年やってわかったこととわからなかったこと ― オルタナティブ・ネット・音楽シーン』。
- Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice, p. 170(今村仁司・港道隆訳『実践感覚』みすず書房、1988年、p. 220)。
- Schechner, R. “A New Paradigm for Theatre in the Academy,” TDR 36, no. 4 (1992): 8.
- 内野儀「脱領土化/再領土化から〈破片化〉へ」『Assembly』7, ロームシアター京都, 2021年、33頁。
- 柳樂光隆「はじめに」『Jazz The New Chapter』シンコーミュージック、2014年、4頁。
- 同上。
- Arendt, H. The Human Condition, University of Chicago Press, 1958(志水速雄訳『人間の条件』筑摩書房、1994年). アーレントの引用につなげるにあたって、神谷ハヤト「レコ屋のジャズ担当が選ぶ、2020年個人的ベスト」(note記事、2021年1月20日)および岸井大輔「ハンナ・アレント『人間の条件』を毎週1節づつ・45週で全文読み解く」(連続講座、2022-23年)から大きな示唆を得た。
- 故デヴィッド・フォスター・ウォレスが2005年にケニオン・カレッジの卒業式で語った名スピーチ『これは水です』(邦訳:阿部重夫、田畑書房、2018年)が思い出される。