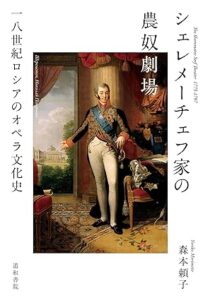Books | 映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形|西村紗知
映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形
稲田豊史著
光文社新書
2022年4月出版 990円
Text by 西村紗知 (Sachi Nishimura)
近頃、コンテンツ受容の仕方に変化が起こっているらしい。「倍速視聴」といわれるもののことだが、「若者」は(実のところこの「若者」という言葉も、何歳から何歳まで、と具体的に決 まっているわけではない)、映画を早送りで見て、音楽でさえ早送りで聞くことがあるらしい。
デジタルネイティブ世代の中でも若い層である「Z世代」が、ある種の編集感覚に基づいて、コンテンツを意のままにしているのだろう。思えばゼロ年代に花開いた「n次創作」文化もすっかり定着し、今の10~20代は、TikTokに自分で編集した映像を挙げることも造作のないことなのかもしれない。こうした状況に伴いプライバシーや著作権のイメージもかなり変わってきているわけだが、消費者が情報を主体的に発信するという状況を当たり前のものとして生きている世代なのだから、コンテンツの消費の仕方もまたそれ以外の世代とは違っていて当然だ。彼らにとってコンテンツもまたなにがしかのパーツのひとつであろうし、事実、ラップミュージックに代表される、既存の音源をサンプリングしてつくられるタイプの音楽を、彼らは好んで聞いていることだろう。
人は「新しい時代」や「理解のできない若者」といったイメージをよく好んで用いるので、倍速視聴に代表されるファストな消費態度は、固定観念やそれに対して抵抗感を抱いている人の価値観に引っ張られるようにして、これまでの似たような社会現象との比較などの手順を経ることもないまま、脚光を浴びている節がある。人はまた「若者はいつの時代も変わらないものだ」というのも好きである。いつの時代にも難しいのは、こういう話題で実態に即した言説をつくりあげることの方だと思うのだが。
本書もまた、「まず、倍速視聴は若者に多い習慣ではあるが、若者だけの習慣ではない。 さらに、倍速視聴は筆者が同意しかねる習慣ではあるものの、そこにネガティブキャンペーンを張りたかったわけではない。現象を俎上に載せ、論点を可視化することで、議論のゴングを鳴らしたかった」(295頁)とは書いてはありつつも、著者自身 が抱いた違和感から出発し、その違和感のまま最後まで進むので、若者批判的な形式に縛られない著作とは言い難い。倍速視聴を実践している「若者」と、倍速視聴などされたくはない、映像作品の脚本家などの「作り手」両方のインタビューを織り交ぜることで当事者性も確保されてはいるものの、特に倍速視聴を好む人々の言い分は、本書のストーリーに沿ったものしか存在していないように見える。
なぜそう思うかというと、倍速視聴に関する積極的な意見でさえ、「彼らは常に時間に追われ、友人との話を合わせるために致し方なく、わかりにくいものを忌避するメンタリティーが優勢なので」といった具合にネガティブな著者の時代診断にそのまま結び付けられてしまっているからだ。
たまたまそういう当事者しかインタビュイーにいなかっただけかもしれないが、本書には倍速視聴こそ美的経験だ、と思う人間に対する想像力がほとんど欠けてしまっていると思う。
実際、Youtuberの動画で、喋っていない間の時間を事あるごとにカットし切り詰めるように編集しているものがしばしば散見されるように思うのだが、これを見るとき、スキップの操作をしなくともあらかじめスキップされたものを見ているのも同然なのである。ちなみに私が 念頭に置いている動画は、情報として摂取するようなものではなく娯楽としてこれ自体を楽しむようなものである。コマ送りの感覚は、これ自体独特の審美性がある。とにかく、Youtuberの動画の視聴経験は、倍速視聴の感受性を準備するものなのではないか、と思うのだがどうだろう。
また私はたまにホロライブのVTuberの切り抜き動画を見るのだが、それは生配信のアーカイブを見ると長いので時間がもったいないからそうするのだという動機がまったくないわけでもないが、切り抜き動画には切り抜き動画特有の面白さがあると思う。例えば生配信のどの部分を切り抜くかという、切り抜き職人の技を楽しんで観る人は少なくないのではないか。それに、生配信は本来見るだけのものではない。コメントを書き込んだりスパチャを投げたりして参加するものである。
こうして、快適だ、ではなく美的だと、つまり倍速視聴は面白いという感受性は実際に存在するように思う。倍速視聴を好む人々にとってコンテンツは「作品」ではなく共に時間を過ごす「場」なのではないか。これはそれほど珍しい視点でもないと思うのだが、なぜこういう視点が欠けているのか。
それは本書がコンテンツとして前提しているのが動画ではなく映画という、作家性や文脈や教養など、ファストならざるものが内包されたものだからというのが一因であろうが、そのことと関連して、本書のいくらか没歴史的なところも指摘したいと思う。特に90年代以降に、本書が問題にしているような話題は集中的に扱われた時期があったように思うのだが、コンテンツの消費について論じた、評論家の仕事が参照されていないようである。宮崎勤の部屋にある大量の見切れないほどのビデオテープを見て、自分の生きる世界もまたもはや情報の集積としてしか捉えられないという現実から評論を立ち上げていた90年代の大塚英志。「物語消費」から「データベース消費」への転換を示した東浩紀『動物化するポストモダン』。評論家の仕事の参照なしに、「最近は評論が読まれなくなっている」(本書で言われている評論とは映画評論のことなのだが)というトピックに紙幅が割かれているので(211-233頁)、なんとなく釈然としない心地になる。
他にも指摘したい点はたくさんあるのだが、ゲーム実況に対する理解(266-269頁)は看過しがたい。「ゲーム実況文化は、メーカー(販売促進)、ゲーム実況者(視聴回数のアップ)、ユーザー(買うべきかどうかの見極め)がそれぞれの望みを果たすことで、「WIN-WIN-WIN」を創出している」とあるが、そうなったのはここ10年以内のものだろう。ゲーム実況者は元々、メーカーにとっては著作権侵害をする者だったはずだ。
ゲーム実況のことひとつとっても、例えばメーカーからの案件をこなすようになってメーカー側に寝返った実況者は数知れずといった具合だったと記憶するが、こういう実況者とメーカーとの駆け引きを見て、落胆する視聴者も多くいたものだろう。自分たちの消費は結局生産者側の都合に回収されてしまう、と。こういう経験をした人なら、きっと、倍速視聴に罪悪感を感じることはないだろう。倍速視聴は産業構造に対する、ささやかな反撃の一端なのかもしれない。
誰が流出させたか、誰が編集したかわからない動画を楽しんでいたという点では、実況者当人でなくとも視聴者もまた著作権侵害に加担していたものだった。その動画の視聴経験は(あの、動画の独特のきめの悪さよ!)、どこか悪い喜びに満ちていたものだったし、そういうインターネット的な審美性を、「若者」は、口外はせずともどこか心の奥底にしまっているのではないだろうか。
インターネット的な審美性は恥ずかしいものだ。だから本書のような内容の仕事には、なかなかあがってこないだろう。そうして、昨今になって倍速視聴という態度になってあらわれたものの来歴は、抜け落ちたままとなる。無理もない。今から20年くらいの間だったか、ひどい時代があったものだ。今振り返ればコンプライアンス的にひどいものだったり著作権的にまずいものも多分に含まれているので、身に覚えがある人であっても、あまり語りたくはない。
そんなふうにして私は、本書を読むことを通じて、インターネットの負の遺産にいろいろと思いを巡らすばかりであった。倍速視聴は物事のほんの一端に過ぎないだろう。
(2022/10/15)