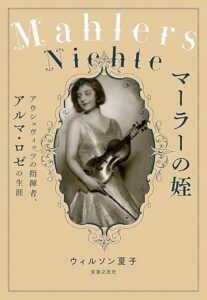円盤の形の音楽|ソロモンのハンマークラヴィーア|佐藤馨
Text by 佐藤馨(Kaoru Sato)
〈曲目〉
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
Disc1
[1]-[4] ピアノソナタ第28番イ長調 作品101
[5]-[8] ピアノソナタ第29番変ロ長調《ハンマークラヴィーア》 作品106
Disc2
[1]-[2] ピアノソナタ第27番ホ短調 作品90
[3]-[5] ピアノソナタ第30番ホ長調 作品109
[6]-[8] ピアノソナタ第31番変イ長調 作品110
[9]-[10] ピアノソナタ第32番ハ短調 作品111
ソロモン
〈録音〉
1951-56年、ロンドン
ベートーヴェンのピアノソナタ第29番が「ハンマークラヴィーア」の通称で知られているのは作曲者の意図とは何ら関係無いが、それにもかかわらず、このソナタのある側面を示唆しているように見えるのは面白いことだ。つまり、この大曲が他でもない「ピアノという楽器」のために作られたという事実を端的に表明しているように感じられてならない。
これまでも多く言われてきたが、この曲はピアノ作品史における一つの頂を成す。作品の規模や内容の面でも、求められる演奏技巧の面でも、ベートーヴェンの創造力は他が比肩しようのない怪物をここに生み出した。彼はピアノという楽器がもつ可能性の限界に挑んでいたのか、はたまた尽きせぬ創造の霊感が偶然にもピアノ音楽の極点に一致しただけなのか。いずれにせよ、ピアノができることの全てがこの数十ページに詰まっている、そんなドラマチックな思いが湧き上がってくる。このソナタこそが「ピアノとは何ぞや」という問いに対する答えである、そのような思いに駆られる人々にとって、ピアノそのものを指した「ハンマークラヴィーア」が作品の呼称にあてがわれるのは、もはや必然と言っていいことなのかもしれない。演奏不可能のレッテルに対して「50年経てば人も弾く!」とベートーヴェンが予言したという逸話も、ピアノ演奏の未来に託された作品として、伝説的な風格を強調しているのだろう。
一方で、あまりに雄大で深遠な内容が、ピアノの枠に収まりきらずより交響楽的なものを志向しているように感じられるのは無理からぬことである。シューベルトの《グラン・デュオ》D812についてシューマンは交響曲のリダクションではないかと疑ったが、こうした楽器の表現性の際を攻めるような曲には、管弦楽的な響きの錯覚が付きまとってきた。実際、シューマンの友人であるヨアヒムは《グラン・デュオ》を管弦楽に編曲した。同じように、《ハンマークラヴィーア》にもまた往年の大指揮者フェリックス・ワインガルトナーによる管弦楽版がある。後者の実演を聴いてみると、なるほど、多彩な楽器群が織りなす豊かな音色のアンサンブルがいかにも交響曲らしく響くし、本来のソナタが持っていた巨大なキャラクターもオーケストラの大きな構えにぴったりくる。ベートーヴェンの交響曲にもかなり接近する瞬間があり、思わずドキッとさせられる。
それでも、この魅力的にあつらえられた編曲を聴けば聴くほど、やはりこれはピアノ曲であるべきだと感じてしまう。この編曲はオーケストラというパッケージに無理なく収められている。この「無理」のなさが最大の痛手だ。それは原曲にあっては演奏者を最も悩ませるが、同時にこの「無理」が、作品に取り組むピアニストに全身全霊を傾けつくすことを余儀なくさせる。冒頭一発目から左手の命がけの跳躍に始まり、技術的な課題が40分以上にわたって襲ってくる。技術に余裕があっても、今度は果てしない音楽の最奥にピアノというたった一つの楽器で分け入っていくという難行が与えられ、無事に生還する保証もない。これらの無理難題が与えられ、そして無理を実現させようというピアニストの闘いがあって初めて、このソナタの前代未聞な威容が露わになる気がする。無理を強いるがゆえに、いっそうこの曲はピアノのための曲なのだ。
ソロモンは闘いの勝利者である。彼の演奏は、いかなる難所をも踏破する輝かしい技巧と突破力に支えられているが、それは鍵盤に立ち向かう英雄臭さとは無縁で、むしろ鍵盤を支配する王侯の高貴さを纏っている。冒頭のファンファーレも、英雄の勇ましい跳躍であるよりは、君臨し統べる者が発する鋼の号令である。彼は88の鍵盤を遍く見下ろす高みに立つ者だ。第1楽章では威光に満ちた楽節の数々を手中に収めながら覇業を指揮し、その前進にはいささかの不安もない。第2楽章のスケルツォでは軽やかな騎馬の優美な様を彷彿とさせる。急に脱線したようなフレーズも、ソロモンは上品かつ節度あるユーモアの中に回収していく。その後やって来るのが、全体のおよそ半分を占める長大な第3楽章。ここまで丹念に突き詰められ、じっくりと積み上げられていく演奏はなかなか耳にしない。ソロモンの求道者然としたストイックな姿勢が、音楽の間延びや途切れを退け、この楽章の本当の最果てへと我々を連れていく。私は祈りや慈しみといった単語を使いがちだが、この演奏にはただただ感謝を述べるほかない。心からの感謝を。第3楽章の結尾で音楽が天上に達したとすれば、第4楽章の冒頭はまだ雲の上から響いてくるのだろう。徐々に雲の切れ間から音楽がはっきりと漏れ聞こえるが、やがて直下してくる一筋の電は縦横無尽のフーガの口火を切る。ソロモンはこの電をもその手に宿し、圧倒的な推進力でもって約束された勝利へと突き進むのみである。全てを踏み越え、全てを鳴り響かせる彼の前に、聴く者はもはや跪くしかない。
(2022/9/15)
〈Tracklist〉
Ludwig van Beethoven
Disc1
[1]-[4] Piano Sonata No.28 in A major, Op.101
[5]-[8] Piano Sonata No.29 in B-flat major, Op.106 «Hammerklavier»
Disc2
[1]-[2] Piano Sonata No.27 in E minor, Op.90
[3]-[5] Piano Sonata No.30 in E major, Op.109
[6]-[8] Piano Sonata No.31 in A-flat major, Op.110
[9]-[10] Piano Sonata No.32 in C minor, Op.111
Solomon
〈Recording〉
1951-56, London
—————————————
佐藤馨(Kaoru Sato)
浜松出身。京都大学文学部哲学専修卒業。現在は大阪大学大学院文学研究科音楽学研究室に在籍、博士後期課程1年。学部時代はV.ジャンケレヴィッチ、修士ではCh.ケクランを研究。博士では20世紀前半のフランスにおける音と映画について勉強中。敬愛するピアニストは、ディヌ・リパッティ、ウィリアム・カペル、グレン・グールド。