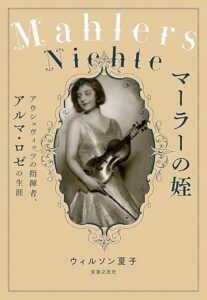Pick Up (2022/08/15)|「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022」全プログラム発表記者会見|田中 里奈
「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022」プログラム発表記者会見
“KYOTO EXPERIMENT – Kyoto International Performing Arts Festival 2022” Full Lineup Announced
京都芸術センター、2022年7月19日
July 19, 2022, The Kyoto Art Center
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
画像提供:KYOTO EXPERIMENT
主催:京都国際舞台芸術祭実行委員会[京都市、ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)、京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)、京都芸術大学 舞台芸術研究センター、THEATRE E9 KYOTO(一般社団法人アーツシード京都)]
※各画像はクリックで拡大表示
——
2022年7月19日、大雨で鴨川の水位が河川敷スレスレの高さまで上昇する中、10月1日~23日の間の4度の週末に繰り広げられる「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022」(正式名称が長いので、界隈の人はよく「KEX(ケックス)」と呼んでいる)の全プログラムが、記者会見で本芸術祭のプログラムディレクター3名(川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップ)から発表され、参加アーティストも対面または動画でコメントを寄せた。
新型コロナウイルス感染症に端を発するさまざまな問題が長期化する一方で、国を跨いでの移動が再び可能になり、それぞれがリスクを負いながら活動を再開しつつある。そんな状況の中で、国際芸術祭のあり方も、パンデミック以前のやり方を見直したり継続を試みたりしながら、再構成している最中である。本稿では、KYOTO EXPERIMENT 2022のキーワードとして掲げられた「ニューてくてく」とプログラム構成、そして、本年から初めて導入されたクラウドファンディングについて、記者会見の内容を報告する。記事の後半では、国際芸術祭をいま開催することの意味について、少し考えを広げてみたい。
※本記者会見で発表された開催プログラムの詳細および最新情報については、KYOTO EXPERIMENT公式サイトのニュース、または7月19日のプレスリリースにて確認することができる。
キーワードは「ニューてくてく New teku teku」
今年で13年目を迎える「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」の本年のキーワードは、「ニューてくてく」。2021年秋のキーワードである「もしもし?!」では、パンデミックによる身体の不在と、目の前にいない他者への呼びかけに向き合っていたが、今年はそこから一歩先に進んだ印象がある。
オンラインミーティングや配信を通じて身体への意識が希薄になり、実際にどこかへ足を運ぶことが億劫になった今日、「てくてく」と足を使って歩く行為を、改めて(=「ニュー」)考え直してみる。人類が二足歩行を始めてから、歩くことを通じて、人が考え、移動し、誰かと考えを共有し、あるいは無目的に時間の移ろいをただ感じてきた。その人類史の中に、今日の「てくてく」はどのように位置づけられるのだろうか?
KYOTO EXPERIMENTが自らを「実験 experiment」と称しているように、「ニューてくてく」も実験を生み出すためのきっかけであり、全プログラムを包括するテーマのような位置づけではない。京都国際舞台芸術祭実行委員長の天野文雄が冒頭のあいさつで、昨年のキーワードと「なんか似たような」感じがすると発言していたが、音として聞いたときに覚える昨年との類似性と印象の柔らかさに反して、多くの拡がりを持ったキーワードだと、筆者は思う。
3つのプログラム
KYOTO EXPERIMENT 2022の全プログラムは、3種に大別される。(1)京都や関西の文化をアーティストが中心となってリサーチする「Kansai Studies(カンサイ・スタディーズ)」、(2)国内外の先鋭的なアーティストを迎えて上演する「Shows」、(3)上演と社会とをトークやワークショップなどでつなぎ、多様な角度から考えていく「Super Knowledge for the Future [SKF]」だ。
Kansai Studies: 3年間のリサーチ成果を発表
和田ながらとdot architectsによる2020年からの3年間にわたるリサーチの成果を、演劇作品『うみからよどみ、おうみへバック往来』として上演する。ちなみに彼らは、2020年度は「水と琵琶湖」、2021年度は「お好み焼き」というテーマでリサーチを行い、その成果を芸術祭期間中の展示とイベントの形で発表していた1。地道なリサーチのプロセスを可視化し、鑑賞可能な形で公開するという彼らの手法は、どことなく博物館の展示のようで面白かった。さらに、演劇作品がこれまで、最終的な上演の内容で評価を決められがちだったことに対して、調査と制作のプロセスをも含めた別の発表方法を開く可能性を示してもいた。本年の展開が注目される。
Shows: 国内外から11演目をラインナップ
本年は11演目の公演が予定されている。さまざまな手法で既存の境界を横断する演目群を、筆者の偏った見方で分類することは好ましくないが、こと実験的な芸術祭に関して言えば、誰かの引いた補助線でラインナップが見やすくなったり、新たな関心を引く助けになったりすることがあることから、あえて以下のように整理し、紹介する。
まず、目に留まるのは、映像をなんらかの形で採り入れた作品群だ。スペースノットブランク(小野彩加、中澤陽)と松原俊太郎との協働による新作『再生数(Views)』では、演劇の上演と映画の上映をリアルタイムで表現する。メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子の新作『Bipolar』では、3.11後に志賀が撮り続けてきた映像に、三者のコラボレーションによる実験的なノイズ・ミュージックの爆音が重ねられる。
同じく映像を使いつつも、次の2作品は空間を隔てたどこかを想起させる。梅田哲也による新作『リバーウォーク』は、京都中央信用金庫 旧厚生センターを歩き回りながら鑑賞するツアー型パフォーマンスだ(同じ会場で、7月末現在、ブライアン・イーノによる展覧会が絶賛実施中)。ベルリン出身のミーシャ・ラインカウフによる『Encounter the Spatial―空間への漂流』展では、海底の国境を記録した『Fiction of a Non-Entry(入国禁止のフィクション)』(2019)や、大都市の地下水路をめぐる『Endogenous Error Terms(内生的エラー)』(2019)といったビデオ・インスタレーションが展示される。
個人や国の歴史を再構成し、考えるきっかけをもたらす作品群も光る。タイ出身のジャールナン・パンタチャートによる新作『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ(I Say Mingalaba, You Say Goodbye)』では、2014年のタイでのクーデター、2021年のミャンマー・クーデターを経て、タイとミャンマーとの間でのリサーチと協働に基づいた戯曲を発表する。イラン出身の劇作家・パフォーマー・元ジャーナリストのアーザーデ・シャーミーリーの『Voicelessness―声なき声』(2017)は、ディストピア化した2070年を舞台にして、今の時代の出来事が次世代からどのように判断されるのかを問いかける。
また、次の3作品では、特殊な状況の中で生じる関係の背後にある構造について、考えることができそうだ。英国のフォースド・エンタテインメントによる2作品のうち、『もしも時間を移動できたら(To Move In Time)』(2019)は題名と同じ質問を展開させていくモノローグで、もう一方の『リアル・マジック(Real Magic)』(2016)は他者の頭の中を当てようとするクイズショー形式になっている。ティノ・セーガルによる『これはあなた(This You)』(2018)は、京セラ美術館の日本庭園を訪れた人同士がビューワーと翻訳者になり、その場で束の間に立ち現れる遭遇を作品として楽しむライブ・アートだ。
そして、身体を介して身体そのものについて問いかけていく作品群がある。サマラ・ハーシュの『わたしたちのからだが知っていること(Body of Knowledge)』(2019)は、観客それぞれが受話器の向こうのティーンエイジャーと対話する参加型演劇だ(今回のバージョンの出演者は公募で決定される)。フロレンティナ・ホルツィンガーの『TANZ(タンツ)』(2019)は過激な表現ずくめの話題作で、ベルリン演劇祭Theatertreffen 2020に選ばれたことでも知られる。チーム・チープロ(松本奈々子、西本健吾)の新作『女人四股ダンス(Menstruation Sumo Dance)』はKYOTO EXPERIMENT初の公募選出で、相撲の「四股」と女性の「月経」をテーマにしたダンス作品だ。
Super Knowledge for the Future [SKF]: 一緒に考える場をつくる
「未来のための超知識」とでも訳せるだろうか。上記で挙げた上演について、あるいは社会のさまざまな問題や課題について考える場を提供するプログラムである。「Shows」の参加アーティストを招いたトークやワークショップのほかに、「ニューてくてく」を実践するための山歩きプログラム(共催:京都伝統文化の森推進協議会)や、和田華子によるLGBTQ勉強会、「アートとポリティクス」と銘打たれたトークシリーズがある。会期中のコミュニティラジオ(DJ: 渡邉裕史)と、森山直人による批評プロジェクトも、引き続き実施される。
ミーティングポイント@ローム・スクエア
フェスティバル期間中、ローム・スクエアに出現する「ミーティングポイント」を担当するのは、CMTK(森千裕、金氏徹平)だ。大型のレンチキュラー印刷を用いて、鑑賞者の立ち位置に応じて見えるものが変化する巨大インスタレーション作品を制作する。
KYOTO EXPERIMENT初のクラウドファンディング
同芸術祭はじめての試みとして、7月19日より、READYFORでふるさと納税型クラウドファンディングを実施している。コロナ禍、国際情勢の変化、円安といった複合的な要因により、海外アーティストの招聘に必要な渡航・宿泊費が高騰したところに、さらに京都市の行財政改革が追い打ちとなり、同芸術祭の予算はパンデミック以前と比べて半分以上減少したためである。これまでにさまざまな助成制度や企業協賛を通じてやりくりしてきたが、全体で約2000万円の資金難を抱えている。
今回のクラウドファンディングの目標金額は400万円で、9月8日まで寄付を受け付けている。1万円からの寄付が可能で、7月31日の時点で寄付総額は75%に達している。
(2022/08/15)
—
1 これまでの記録は「Kansai Studies」で参照することができる。