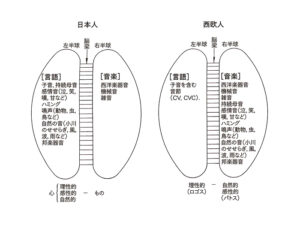プロムナード|音楽のネガティブ・ケイパビリティー|大田美佐子
音楽のネガティブ・ケイパビリティー
negative capability of music
Text by 大田美佐子(Misako Ohta)
2022年3月の初旬、チャイコフスキー作曲の《1812年》の演奏を中止した各地のオーケストラの対応の賛否について、とあるメディアからコメントを求められた。私は以下のように回答した。
チャイコフスキーの《1812年》はナポレオンのロシア遠征の年で、その音楽のなかにはロシア軍の行進、ロシア帝国国歌が刻印されています。これまで世界の演奏会で愛聴されてきたチャイコフスキーの名曲から、戦争やリアルポリティクスの亡霊を呼び起こしたのは、いうまでもなく現在のロシア-ウクライナ情勢です。今、まさにロシア軍侵攻の下で生命の危機に直面しているウクライナ市民はもちろんのこと、戦争反対という普遍的な価値観の下にも、この作品を聴く精神的なゆとりを失っているのは致し方のないことなのかもしれません。
昔の作品であっても、「今」の時代に生身の演奏家と聴衆が空間を共有して楽しむのが音楽の宿命であり、音楽体験は「今」の状況に大きく左右される面があります。昔の作品の響きに「何を聴くのか」は演奏家や聴衆の自由ですが、その音楽芸術がもつ意味の多層性も現実の戦争の前には、沈黙を強いられてしまうということなのでしょう。このような時代には、音楽のもつ多層的なメッセージは単純化されてしまいがちです。音楽は、戦争の悲惨さを想起させることで反戦を伝えることもできれば、戦争のない世界を想起させる穏やかな作品で、反戦を伝えることもできるのです。演奏会で、観客に何を伝えたいのか、どんな作品を共有したいのかは、この厳しい時代にあって、オーケストラにまさに問われている重要な問いかけだと思います。
それ以来、ずっと、この問題が気になっていた。
ウクライナの諸都市への爆撃で(もちろんシリアへの爆撃でも)、鉄骨を露わにし、見る影もない建物に囲まれ生き延びた普通の人々の生活を見るたびに、やりきれなさと同時に想い浮かぶ光景がある。1955年、第二次世界大戦後に分割統治されたベルリンに、戦後初めて渡ったクルト・ヴァイル夫人の俳優ロッテ・レーニャが、《三文オペラ》が鳴り響いていた1920年代を想い、やり場のない望郷の念に駆られ、言葉もなく立ち尽くす姿。
「戦争」による破壊で、やり場のない望郷の念に立ち尽くす人は後を絶たないだろう..。
ウクライナ危機で露呈した壁崩壊後の世界の亀裂には、あらためてショックを受けた。ライフワークとして研究してきた《三文オペラ》もクルト・ヴァイルという作曲家や作品も、20世紀前半の二つの戦争や、それに続く冷戦によって、大きな影響を受けてきた。亡命作曲家ヴァイルの研究は、「戦争を知らない子ども」であった私にとって、戦争を考えるきっかけとなり、「冷戦とその和解のプロセス」を象徴する存在だった。冷戦終結は甘い見通しに過ぎなかったのか。

 1993年、私は生誕地の町おこしのシンボルになったクルト・ヴァイルに会いに、壁崩壊後の東ドイツの都市、デッサウを初めて訪ねた。観光局に紹介された宿泊先は市民の家の間借り。いわゆるドイツ語で言うところの「プラッテンバウ」、つまりプレハブビルのような味気ない建物だった。それでも、建物内部には、人の生活の温かみが感じられた。宿泊先の居間は清潔で小綺麗。家具は座面に黒い皮が貼ってあるパイプ椅子で、バウハウス・デザインの名残あるモダンなもの。朝食は香りの良いコーヒー、チーズとハムに白いパンが二つ、ブルー・オニオン柄の愛らしい器にみかんとキウイが綺麗に詰めてあり、時にはバナナも。豪奢でなく質実剛健ながら、そこにあった豊かな生活を感じさせた。家主のメンツさんは子供が育ち上がった初老の元小学校の先生。極東からクルト・ヴァイルの音楽を聴きに来た珍しい来訪者に最初は怪訝そうにしていたが、毎年通ううちに、少しずつ日常会話を交わすようになった。チケットが一般市民には高額過ぎて手が届かないことや、時には体制の変化を受け入れつつも、将来の不安や西側の旧東独の生活への誤解について憤るなど、本音を語ることもあった。手入れの行き届いた愛車のトラバントに乗せてもらったりもした。東西の冷戦が終わり、生誕地デッサウのフェスティバルを通じて里帰りをしたヴァイルと彼の音楽は、デッサウの人々のなかで少しずつ鳴り響くようになっていった。(写真左は日本からのアーティストも参加した1995年のクルト・ヴァイル・フェスト。写真右は、1994年、デッサウの中心部に乗り捨てられた東ドイツの名車トラバント)
1993年、私は生誕地の町おこしのシンボルになったクルト・ヴァイルに会いに、壁崩壊後の東ドイツの都市、デッサウを初めて訪ねた。観光局に紹介された宿泊先は市民の家の間借り。いわゆるドイツ語で言うところの「プラッテンバウ」、つまりプレハブビルのような味気ない建物だった。それでも、建物内部には、人の生活の温かみが感じられた。宿泊先の居間は清潔で小綺麗。家具は座面に黒い皮が貼ってあるパイプ椅子で、バウハウス・デザインの名残あるモダンなもの。朝食は香りの良いコーヒー、チーズとハムに白いパンが二つ、ブルー・オニオン柄の愛らしい器にみかんとキウイが綺麗に詰めてあり、時にはバナナも。豪奢でなく質実剛健ながら、そこにあった豊かな生活を感じさせた。家主のメンツさんは子供が育ち上がった初老の元小学校の先生。極東からクルト・ヴァイルの音楽を聴きに来た珍しい来訪者に最初は怪訝そうにしていたが、毎年通ううちに、少しずつ日常会話を交わすようになった。チケットが一般市民には高額過ぎて手が届かないことや、時には体制の変化を受け入れつつも、将来の不安や西側の旧東独の生活への誤解について憤るなど、本音を語ることもあった。手入れの行き届いた愛車のトラバントに乗せてもらったりもした。東西の冷戦が終わり、生誕地デッサウのフェスティバルを通じて里帰りをしたヴァイルと彼の音楽は、デッサウの人々のなかで少しずつ鳴り響くようになっていった。(写真左は日本からのアーティストも参加した1995年のクルト・ヴァイル・フェスト。写真右は、1994年、デッサウの中心部に乗り捨てられた東ドイツの名車トラバント)
それは「第二次世界大戦の爪痕」を前にアメリカ国民となっていたレーニャが言葉を失ったように、「冷戦の終結」も完全なる勝敗などを意味しない、とメンツさんの存在が教えてくれたかのようだった。
戦争は完全なる勝敗、「勧善懲悪」の陶酔に人々を誘う。しかしながら、その下で生命を繋ぐ人々の生き様は多様で、正解などない。「答えがない」は、今を生き抜く鍵のようにも感じられる。精神科医で作家の箒木蓬生は、その著『ネガティブ・ケイパビリティー』(2017,朝日新聞出版)で、この言葉を「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」(p.3)として紹介している。この言葉を初めに使ったとされる詩人のジョン・キーツは「真の才能は個性を持たないで存在し、性急な到達を求めず、不確実さと懐疑とともに存在する」(p.27)との理解に至ったと言うが、「答えが出ない」舞台や音楽、アートに開かれた広大な地平こそ、人々の「ネガティブ・ケイパビリティー」を喚起する触媒になり得る。「答えが出ない」状況のなかで、人々は問いを深め、寛容の感情が育っていく。
冒頭の問いかけから三月が過ぎ、私は大阪のフェスティバル・ホールで、上岡敏之指揮の読売日本交響楽団が奏でるチャイコフスキーの交響曲第6番《悲愴》を聴いた。久しぶりのオーケストラでのロシア音楽。演奏会前は、どう聞こえるのだろう、と多少不穏な気持ちになった。しかし実際には、各楽章、演奏者の圧巻の集中力でみじろぎできず、伝説になるだろう一夜に立ち会えたと感じられた名演に音楽の自由を謳歌した。「答えのない」芸術の豊かさを、あらためて噛み締めた。
(2022/7/15)