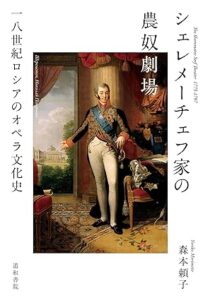Books|メンデルスゾーンの宗教音楽|栗原詩子
 メンデルスゾーンの宗教音楽:バッハ復活からオラトリオ《パウロ》と《エリヤ》へ
メンデルスゾーンの宗教音楽:バッハ復活からオラトリオ《パウロ》と《エリヤ》へ
星野宏美 著
教文館
2022年3月出版
2000円(税別)
Text by 栗原詩子 (Utako Kurihara)
フェーリクス・メンデルスゾーン(1809-1847)の功績として名高いJ.S.バッハの《マタイ受難曲》再演(1829)は、宗教文化的な謎に満ちている。
イエスの磔刑とその前後を描く受難物語は、4つの福音書ごとに様々な描かれ方をとるが、「マタイ福音書」に基づくディスクールには、他の福音書には見られない「血の呪い」場面(27章25節)が盛り込まれている。この文言は歴史的に、キリスト教系権力がユダヤ系人口を「神殺しdeicide」として扱い、彼らを迫害する口実として、たびたび言及されてきた。したがって、ユダヤ教改革派の主導者として名高いモーゼス・メンデルスゾーン(1729-1786)の孫であるフェーリクスにとっても、4種のディスクールの中で最も痛みの多いものであったはずだ。
ピラトは手の付けようがなく、かえって騒動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗って言った。「この人の血について、私には責任がない。お前たちの問題だ。」 民はこぞって答えた。「その血は、我々と我々の子らの上にかかってもいい。」
マタイ27章24-25節(聖書協会共同訳/バッハでは第50曲に相当)
ただし、上述の祖父モーゼスは、保守派でなく改革派のユダヤ的賢人である。その同時代人レッシングは、「アブラハムの神」を奉じる3つの宗教(ユダヤ・キリスト・イスラム)を対立から協調へと導く『賢者ナータン』を戯曲作品(1779)として着想するにあたって、モーゼスを念頭においたと言われるほどである。したがって、メンデルスゾーン家には、今日で言うところのエキュメニズム(超教派)的な考え方が浸透していたとも推測できる。
それにしても、である。フェーリクスが、わずか7歳にして福音派の教会でキリスト教に改宗した背景には、本人の信仰上の選択よりも、息子を社会に同化させようとする両親のはからいが透けて見える。かつて15世紀スペインの異教追放令は、表面上は「キリスト教への改宗者」を大量に産み、彼らは生き延びるために、ハムを始めとする豚肉を摂取することで、ユダヤ教なりイスラム教なりからの脱皮を世間に表明した。フェーリクスが20歳でタクトをとった《マタイ受難曲》上演には、ユダヤ教からの脱皮を表現するための踏絵という側面もあったのだろうか。
日本におけるメンデルスゾーン研究の第一人者・星野宏美氏が教文館から著した『メンデルスゾーンの宗教音楽』は、こうした疑問や逡巡に直接踏み込むのではなく、むしろそうした宗教文化的な問いの緊張感を保ったまま、宗教音楽をめぐるフェーリクスの4つの音楽活動を丁寧に検証している。バッハの2つの大作《マタイ受難曲》《ミサ曲ロ短調》の再演活動と、フェーリクス自身の2つのオラトリオ《パウロ》《エリヤ》の作曲活動から炙り出されるのは、表面的な垣根を独自の仕方で「越境」していくメンデルスゾーンの姿である。
バッハ作品の再演について、「作曲家の死後、忘れ去られる運命にあった」大作に、「息吹を与え、音楽史の不朽の名作として蘇らせた」(21-22頁)といった、おなじみの記述も見られる。しかし、星野氏が余すところなく言及しているように、ベルリンでは指揮者ツェルターがジングアカデミーを中心として、すでに1815年から《マタイ受難曲》が練習され(27頁)、1828年には《ミサ曲ロ短調》が再演(64頁)されている。今後は、「忘れ去られる」といったディスクールの必要性は徐々に薄くなっていくかもしれない。
そして、この本には、もうひとつ、啓蒙的な英雄伝と根本的に異なって見える点がある。バッハ作品の再演当時に作られた筆写譜や、メンデルスゾーンの自筆譜について、そのファクシミリ写真を紙面にうやうやしくレイアウトして済ませるのではなく、広範で先端的な研究成果を盛り込んで、筆写譜・自筆譜から何がわかり、何が問われるべきかを掘り下げていくからだ。たとえば《マタイ受難曲》の通奏低音を担当した楽器については、まずそこで鳴り響いた音色を、次には演奏習慣の時代的変遷をめぐる問いを、さらに、演奏習慣の都市間の差を検討する。この第一段階では、1829年ベルリンにおける復活上演が鍵盤音楽である(ただしシュライプ製フォルテピアノ説とエスターライン製チェンバロ説の2つが拮抗)、のに対し、1841年ライプツィヒにおける上演でコントラバスと2台のチェロが用いられたことが語られる(40-43頁)。第二段階として、2上演における楽器選択の違いが、上演場所(教会かホールか)による「聖俗の違い」に基づくのか、それとも、ブルジョワ主体の七月革命やドイツ関税同盟の成立といった、世界観の変更を含む12年間の「新旧の違い」に基づくのかという検討(43-44頁)に踏み込む。第三段階として、1841年用に作成された弦楽譜に書き込まれたレチタティーヴォ楽譜(福音史家)とスコアを照合すると、ベルリンとライプツィヒにおける標準音(一点ラの何ヘルツでとるか)についても知見が得られるという(49-51頁)。
本書における《マタイ受難曲》の記述は、1829年の歴史的復活上演ではなく、1841年の再演を中心に繰り広げられるので、少なからぬ読者が、はじめのうち面食らう可能性はある。しかし次第に、1841年にスポットをあてることこそ、第一に、上記のような精密な検討の前提であること、そして第二に、輝かしいキャリアにもかかわらず、ヨーロッパにおけるユダヤ差別を背景に、フェーリクスならびにメンデルスゾーン一家が直面した問題(32頁・33頁)に光をあてる鍵であることに思いが及ぶだろう。
さて、カトリック信徒であったシューベルトすらドイツ語で《ミサ曲》(1827)を作曲しはじめていた初期ロマン派の時代に、「プロテスタンティズムの音楽の代表」(102頁)たるJ.S.バッハが、カトリック基準の公式ラテン語典礼に基づいて作った《ミサ曲ロ短調》をドイツ語圏で再演するのはたやすくなかった。キリスト教文化内の「越境」をめぐる、この困難について、フェーリクスと父アブラハムの書簡から説き起こすのは(102-104頁)、メンデルスゾーン研究家として、いわば当然のことだろう。だが、社会状況と演奏習慣に寄せる深い関心から、星野氏は、バッハ没後に《ミサ曲ロ短調》がいかに上演されてきたかの独自調査(88-99頁)へと駆り立てられたようである。1786年から1859年の37件の整理から「普遍的(ルビ「カトリック」ママ)な教会の声としてのミサ曲が、当時の新しい音楽生活の隆盛の波にのりにくかった」(101頁)という事情が、この調査から見えてくる。直接的には、全曲演奏の企画が実現形としては部分演奏にとどまりつづけた背景を説明しているが、同時に、ミサ曲そのものの複雑な成立事情や楽譜伝承に専心してきた従来のバッハ学を拡張・整理する試みとして重要である。
著作の後半部では、2人の預言者、すなわち旧約のエリアと新約のパウロを中心にすえたメンデルスゾーン自身の2つのオラトリオ(それぞれ1846年と1836年に作曲)が検討される。
オラトリオ《パウロ》(1836)は、バッハと同じルター派の聖句表現から自身で書き起こしたリブレットを用いるなど、《マタイ受難曲》を「強く意識」(113頁)して書かれたようだ。本文では、レチタティーヴォとアリアと合唱を交互に配置した二部全45曲が、細部に至るまで、いかに《マタイ》に迫る内容を構成するかが詳述されている。ストーリーは、正統ユダヤ教主義を探究するファリサイ派の学者として、イエスの弟子筋を厳しく迫害していたサウロ(パウロのユダヤ名)が、イエスの顕現体験をへてパウロと名乗るようになり、アテネやローマ帝国領マケドニアなどの会堂(シナゴーグ)で宣教し、やがてローマ帝国の下で殉死するまでを描いている。パウロは、ナザレのイエスを「肉においてはダビデの子(中略)霊によれば復活によって神の子」(「ローマの信徒への手紙」1章3-4節)と語って「三位一体」の萌芽的理念を表明した人物でもある。作曲家を取り巻く人物の回想によれば(162-164頁)、フェーリクス自身は、オラトリオ全45曲の中でパウロの回心の場面(第15-16曲)に篤い思い入れを抱いていたようだ。幼児期にキリスト教への入信・受洗を済ませていても、宗教的越境の意味について幾度となく自省を迫った社会状況をうかがわせる。
オラトリオ《エリヤ》は、バーミンガムで初演されたため、ドイツ語での作曲後からまもなく英訳されたという意味で、地理的・言語的な「越境」を体現する楽曲といえるだろう。新約のパウロが「一神教」の世界拡大に尽力したのに対し、旧約のエリヤはイスラエル国内に向けて「一神教」の純化を説いた預言者であるから、一見対照的な人物が描かれていることになる。《エリヤ》のリブレットも、作曲家が自ら起こしたものだが、特にアリアの歌詞分析には、神学と音楽学の両軸にわたる星野氏の慧眼が冴えている。当時の代表的神学者のエリヤ理解との差異を剔抉した上で、「ふたりの神学者と彼らの専門的な著作の調査はことごとく却下される(中略)私たちの問いは、専門的な神学よりも、建徳的な文献、なかでもとくに説教集に向けられるべき」(214頁)と述べるのだ。最終的に、当時影響力のあった伝道者クルムマッハー(1796-1868)が「エリヤの言葉から新約聖書の言い回しを強調して引き出している」(215-218頁)例を丹念に拾って、メンデルスゾーンの手になる歌詞表現への影響をつぶさに明らかにしていくのだ。
旧約聖書のキリスト教的解釈(Interpretatio Christiana)については、現代ドイツを代表する新約学者も次のように述べて、旧約神学と新約神学との結節点としてのパウロ像を示している。
パウロ神学には深いところで変化した旧約聖書理解がある(中略)重要なのは一つの相関関係である。つまり、キリストにおける神の終末的なわざは旧約聖書からのみ理解され、反対に旧約聖書は福音の使信からのみ十全の意味において捉えられる
(ハーンI上: 278)
星野氏によれば、「《パウロ》に取り組んでいる最中にメンデルスゾーンがエリヤを次なるオラトリオの題材候補として念頭に置いた可能性は十分にある」(166頁)という。オラトリオ《パウロ》の前半にあたる第1部の終曲は、ローマ書簡で「聖書がエリヤの箇所で伝えていること」への想起をうながすパウロの言葉(11章2節)を歌詞としているからだ。
このように本書からは、ロマン派の音楽家メンデルスゾーンが、演奏者としてのバッハ理解を下敷きにした上で、預言者エリヤと使徒パウロを選択し、音楽家としての全力量をもって自らの宗教的スタンスを表現したことの意味が、強く迫ってくる。本書を手元において、繰り返し読み返したいと思う。
(参考文献)フェルディナンド・ハーン『新約聖書神学I 上』大貫隆・大友陽子訳、日本キリスト教団出版局、2006。
(2022/6/15)
——————————————————–
栗原詩子 Utako Kurihara
東京生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒、同大学院修士課程修了。新潮社主催「グラモフォン・ジャパンCD批評新人賞」受賞。九州大学芸術工学部(旧・九州芸術工科大学)音響設計学科にて勤務(助教)する傍ら、論文「音楽分析的観点によるマクラレンのアニメーション作品研究」の審査により九州大学で博士号(芸術工学)を取得。著書に『物語らないアニメーション:ノーマン・マクラレンの不思議な世界』(春風社)、訳書に『現代音楽を読み解く88のキーワード』(音楽之友社)、『ハリウッド映画と聖書』(みすず書房)など。現在、西南学院大学国際文化学部教授。