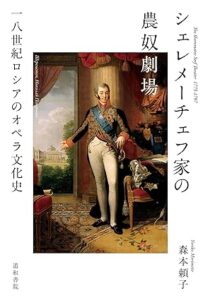Books|はじめての西洋ジェンダー史|大河内文恵
 はじめての西洋ジェンダー史:家族史からグローバル・ヒストリーまで
はじめての西洋ジェンダー史:家族史からグローバル・ヒストリーまで
弓削尚子 著
山川出版社
2021年11月出版
2300円(税別)
Text by 大河内文恵 (Fumie Okouchi)
最近、私の読書傾向に変化が生じている。言うまでもなく、ロシアによるウクライナ侵攻によるものだ。ウクライナおよびスラブ圏もしくは東欧に関するもの、そして戦争関連に目が向くようになった。なぜ人は戦争をするのか、してしまうのかといったことを知りたいと思いながら、いろいろなものを読み漁っているなかで出会った1冊を取り上げたい。
「ジェンダー」という言葉は、21世紀になって誰にでも聴き馴染みのある用語となったが、その言葉が包含する意義や影響の及ぶところについては、知られていないことが多いと読みながら実感した。
山川出版社のサイトによれば、本書は「著者が早稲田大学の教養科目としておこなう授業をもとに、家族史からグローバル・ヒストリーまでをあつかう入門書」だという。なるほど、7つの章がそれぞれ1回の授業のようにそれだけで完結しつつ、相互に関連させながら進んでいくのは、ですます調の語り口とあわせて、講義を聞いているような感覚をおこさせる。それゆえ、豊富な引用文献を用い情報量の多い充実した内容ながら、この分野の素人であっても読みやすい。
ジェンダーというと、ともすればイデオロギー的な主張だととらえられたり、感情的で一方的なものだと敬遠されがちであるが、本書では、性別の捉え方の変遷を時代別に整理する中で、当時の文献や資料を引用することで、俯瞰的な視点と同時代的なミクロの視点を両立させ、客観的でありつつ感情的な側面も取りこぼさないという絶妙な視座を獲得している。
第1章「家族史」でいきなり私たちの家族観は覆される。衝撃だったのは、教会の記録から復元された17世紀イギリスの一般民衆の結婚年齢である。シェークスピアの『ロミオとジュリエット』のジュリエットは14歳で結婚しており、古い時代は早婚のイメージを持たれがちだが、17世紀前半の平均初婚年齢は、男性28.2歳、女性25.9歳と現代の私たちの感覚とあまり変わらないという。歴史人口学という分野によるこうした研究成果は、王侯貴族を対象とした従来の歴史学からは見えてこなかったものである。
政略結婚の多かったことで知られる17~18世紀の貴族の結婚が、「互いに愛していようがいまいが、互いに誠実であろうとなかろうと、二人の間にただ共通の体面保持の義務に必要な程度の僅かな夫婦関係しかなかろうが、どうでもよかったのである」(エリアス『宮廷社会』74~75頁より引用)というのは、現代の私たちの感覚からは理解しがたいもののように思われる。そしてその感覚は民衆であってもあまり変わらず、体面保持が労働力確保に変わるだけのことだという。
昨今、歴史上の時代を扱うドラマなどで、側室の存在を描くのに、当然のこととしてではなく、正室はそれを嫌がり、夫は後ろめたく思い、周囲から白い目で見られるといった描写がなされるのをしばしば見かける。現代の感覚としては正しいのだろうが、歴史的には歪められているように感じてしまうのは私だけだろうか。
では、このような前時代的な結婚観・家族観から、いわゆる伝統的家族観に転換されるのはいつなのだろうか。それについて考える前に、そもそも男女という二元論の起源を第4章「身体史」でみてみたい。私たちは人間という種には男と女という性別があると当然のように考えているが、古代から近世までは男と女は基本的には同じものであるという相対的性差(ワンセックス・モデル)でとらえられていた。それが解体され、絶対的性差(ツーセックス・モデル)が確立されたのは、科学における変化ではなく、「認識論の変化、社会・政治の革命的転換の結果」であるらしい。
つまり、私たちは男と女という生物学上の性差の後から、社会的性差であるジェンダーが確立されたと思っていたけれど、実はまったく逆で、社会的性差が必要だったから、男と女という性別が明確に区別されるようになったというのである。これはある意味、コペルニクス的転回である。
戦うために大きな身体を持ち、強い腕力と精神を備えた男というものが求められる世界、それはすなわち戦争である。男女の違いが大きく分化したのは、まさに近代国民国家の誕生とともに徴兵制が各国でおこなわれるようになってからなのである。それ以前の戦いは主に傭兵によっておこなわれており、彼らは「国」のために戦うのではなく、いわば「仕事」として戦っていたのだという。
ジェンダーという一見、戦争とはかけ離れているように見える概念が、実は戦争の存在と不可分なものであると気づいたとき、戦争を語ることの難しさの一端が見えた。それと同時に、弓削は「西洋の拡張の歴史を非西洋のジェンダーの観点から再考するには、(中略)性別二元論に回収しきれない、非西洋地域の諸制度にも目を向けることが必要」と説く。
本書の中では、両性具有者、同性愛者、異性装、カストラートといった、性別二元論からこぼれ落ちた人々への言及が多くみられる。特に21世紀になってから、性的マイノリティに対する眼差しが、以前のそれとは変わってきているのは周知のことである。また、音楽に興味のある向きには、上記のカストラートのほか、ジェンダーの記号としての楽器の話、孤児院の設立とその衰退など、関連する話題を随所に見出すことができることも付け加えておきたい。
最後に、第2章「女性史」より、「普通」「一般」「人間」といった概念について触れておきたい。本書で挙げられている例は普通選挙、一般兵役義務、人権宣言といった当たり前に使われている用語である。これらの用語はいずれも男性のみを対象としており、普通・一般・人間の中に女性は含まれない前提であった。現代では女性にも選挙権はあるし、そんな昔のことを言われてもと思われるかもしれないが、こうした刷り込みは性別以外にも存在しうる。無意識に刷り込まれてしまったものに気づくことは誰にとっても難しい。物事を考える際のヒントとなるトピックがふんだんに盛り込まれた本書を、折に触れて何度も読み返したいと思う。
(2022/4/15)