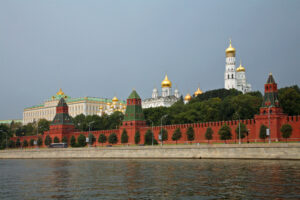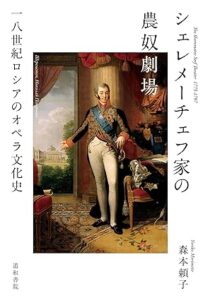Pick Up (2022/3/15) |ウクライナ侵攻で露呈した音楽の「政治性」|能登原由美
ウクライナ侵攻で露呈した音楽の「政治性」
Russia’s invasion of Ukraine unfolds the politics of music
Text by 能登原由美(Yumi Notohara)
欧米の音楽界の危機
2月24日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まった。以後、戦況は日ごとに激しさを増し、ついには原子力発電所への攻撃も行われるなど、プーチン政権の常軌を逸した体質が次第に露わになってきた。もはやヨーロッパ全体、ひいては世界をも戦火の渦に巻き込みかねない様相を呈している。こうして本稿を書いている時でさえ、戦慄を覚えるようなニュースが耳に飛び込んできて、心はいっこうに落ち着かない。
一方、侵攻開始から2週間余り。欧米の音楽界は大きく揺れている。2年にもわたって続いてきた新型ウィルスによる打撃からようやく回復するかに見えたのも束の間、この度の危機で新たな問題が浮上してきたのである。ここにきて、西洋の音楽文化は第二次世界大戦以降でもっとも深刻な影響を受けることになるのは間違いないだろう。
そこで本稿では、アメリカとヨーロッパの、主にクラシック音楽の世界で起きている出来事をまとめるとともに、そこに潜む問題点や現時点での筆者の見解を述べたい。ただし、毎日のように世界各地で新たな動きがあり、その情報をすべて把握することは不可能に近い。しかも、ジャーナリストでもないため世界各地の生の声を届けることは難しく、新聞記事などに頼らざるを得ないのが実情だ。よって、ここで述べることは、あくまで筆者が入手できた二次資料を元にしたものであることを、あらかじめ断っておく。
「プーチン支持者」の末路:ゲルギエフとネトレプコ
軍事侵攻の2日前、ニューヨーク・タイムズがある記事(1)を掲載した。パンデミックにより中止されていたコンサート活動再開の様子を紹介する内容である。けれどもここで注目したいのは、新型ウィルスとは別の、ある懸念について触れられた部分だ。つまり、その週末に行われるウィーン・フィルのニューヨーク公演で、指揮台に立つ予定のヴァレリー・ゲルギエフに対する抗議活動が計画されているというものである。現代を代表する指揮者の一人と言われるこのロシア人については、彼の地の大統領、ウラジーミル・プーチンと長年親しい関係にあることや、2014年のロシアによるクリミア併合で彼を支持する立場を表明していたことなどから、かねてより異議を唱える声があった。今回のツアーでも、抗議団体によるデモが予定されていたわけだが、それに対してウィーン・フィルのダニエル・フロシャウアー楽団長は、「彼は演奏家として行くのであり、政治家ではない」と、ゲルギエフを擁護する声明を発表していたことも合わせて報じられていた。ただし、これらの内容は記事全体の割合からすると短く、やがて彼に対するブーイングが世界中に沸き起こるとは、この記者さえ予想できなかったのではないか。
24日の現地時間午前5時、ロシア軍がウクライナ全土の軍施設へ砲撃を始める。「第二次世界大戦以降、ヨーロッパにとって最も暗い時」と形容されるなど、世界は一挙に不穏な空気に包まれることになった。それからほどなくして、ウィーン・フィルが方針転換を発表した。つまり、25日の公演については、ゲルギエフに代わってヤニック・ネゼ=セガンが指揮を執ることが決定されたのだ。会場となるカーネギー・ホール側も、「政治的な見解を表明することに対し罰するべきではない」(2)と、当初は音楽と政治的行動とは分けて考えるべきとの態度を見せていたが、ここにきて指揮者の交代を発表。そればかりか、ピアノ独奏を予定していたロシアのピアニスト、デニス・マツーエフも降板させられた(代役はこの時点では未定。その後、チョ・ソンジンに決定)。彼はゲルギエフ同様に、クリミア併合に賛同するプーチン支持者として知られており、それが理由であることは間違いないだろう。
その後、ゲルギエフにとっては過酷な裁定が続く。まず、ミュンヘン市長が28日を期限として侵攻を非難する声明を公にするように求め、行われない場合はミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者のポストを解任する旨を伝えた。結局、ゲルギエフは期日までに回答することはなく、その身分を剥奪されることになる。続いて、ゲルギエフのマネジメントを引き受けてきたマルクス・フェルスナーが、契約を打ち切ることを発表。さらに、ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者、エジンバラ国際音楽祭名誉総裁、スイスのヴェルビエ音楽祭監督の地位など、次々と要職を失うことになった。さらに、カーネギー・ホールやルツェルン音楽祭などが、ゲルギエフとその手勢であるマリインスキー劇場管弦楽団の公演を中止するなど、彼が関わることになっていた行事のキャンセルが各地で相次いだ。
こうして、世界の舞台をまたにかけ活躍していたゲルギエフは、プーチンによるウクライナ侵攻からわずか5日間で、そのほとんどの指揮台から引き摺り下ろされることになった。
ただし、プーチン支持者としてゲルギエフが槍玉に挙げられたのは、今回が初めてではない。というのも、2008年に南オセチアをめぐってロシアとグルジアの間で起きた紛争の直後、破壊された首都で野外コンサートを指揮したゲルギエフは、自らもオセチア人の血を引くことを述べながら、ロシアによる制圧を歓迎する演説を行っている(3)。あるいは、2013年に制定された「同性愛宣伝禁止法」や翌年のクリミア併合など、数々の暴挙を行うこの指導者に一貫して追随する態度を見せ続けたことから批判の対象となってきたのである。そもそも、サンクトペテルブルクのキーロフ劇場(その後、改称してマリインスキー劇場)で芸術監督をしていた1992年、ゲルギエフは同副市長であったプーチンと出会い、以後、劇場運営のための便宜を図ってもらうなどしていた。つまり、プーチンとは数十年に及ぶ深い繋がりがあり、しかもその軍事行動や差別的姿勢も踏まえて支持を貫いてきたゲルギエフに対しては、アメリカなどで繰り返し非難の声が上がっていたのである(4)。
一方、ロシア出身で当代きってのプリマドンナの1人、アンナ・ネトレプコもゲルギエフと同様に、プーチン政権の行動を支持する立場を明示していたことから、かねてより抗議の対象になってきた(例えば2015年のメトロポリタン歌劇場の公演では、カーテンコールの最中に聴衆の一人が舞台に駆け上がり「反プーチン」の垂れ幕とともに抗議する事件があった)。 そのため、24日に始まった軍事侵攻により、翌25日にデンマークで予定されていたコンサートが中止となる。また、オペラの殿堂、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場も「プーチンを支持するアーティストは使わない」と表明するなど、一挙にその立場が危ういものとなった。沈黙を通しているゲルギエフとは異なり彼女の場合、27日にはSNSを通じて侵略戦争に反対する意思を表すが、政治的見解や母国への非難を表明するか否かについては、あくまで個人の自由であるとも主張。プーチンに対する態度が曖昧な上にゲルギエフを擁護する姿勢が露わになったことで、さらなる批判を浴びる結果となった。そればかりか、舞台上でゲルギエフと手を取り合う過去の写真もアップ(上記も含め、ネトレプコがアップして批判された記事はいずれもすでに削除されている)。ゲルギエフとの盟友関係を誇示する姿勢を改めて示したことで、火に油を注ぐ事態を招くことになった。その結果、3月3日には、ネトレプコ自身がメトロポリタン歌劇場での今後の契約を破棄すると発表。報道によれば、劇場側はプーチン支持を撤回するよう促したが、彼女は最終的にその説得に応じなかったという(5)。その後、バイエルン国立歌劇場はゲルギエフとネトレプコ両氏との関係の打ち切りを発表。また、ミラノのスカラ座やスイスのチューリッヒ歌劇場も彼女の出演予定を撤回した。世界の歌姫は、わずか1週間で活躍の舞台をすっかり失ってしまったのである。
このように、プーチンの支持者と見なされてきた音楽家たちは、この軍事侵攻により欧米の音楽界から「追放」される結果となった。けれども、問題はそれだけに留まらなかった。
ロシア音楽や文化に対する圧力は必要か?〜反戦と音楽のジレンマ
軍事侵攻が始まった24日から25日にかけての2日の間に、キリル・ペトレンコ、セミヨン・ビシュコフ、エフゲニー・キーシンなど、ロシアにつながりをもつ音楽家が相次いで文書や映像などで抗議声明を出した。もちろん、軍事力では圧倒的に勝る大国ロシアが、隣の小国ウクライナを武力行使によって従わせようという構図なのだから、祖国とはいえその愚行を非難したとしてもなんら不思議はない。
けれども、そうした声を取り巻く空気にやがて微妙な変化が見られ始めるようになる。例えば、軍事侵攻が始まった当時モスクワにいた、NHK交響楽団首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィは、26日に予定通りロシア・ユース・オーケストラを指揮する。その際、自身のサイトに声明を出すのだが、そこではロシア政府とプーチンを非難する一方で、「ロシアの若い音楽家たちに罪はない」とも述べている。無論、彼が降板すれば、この戦争に反対し独裁者の行動に心を痛めている無実の若者たちに、さらなるダメージを与えることになることを指しているのであろう。一方で、この言葉の裏には、侵略を断行した政権のみならず、彼の国に住む人々やその文化全体に対する眼差しが厳しくなりつつあること、さらに言えば、その国に関わること自体に弁明の必要性が生じていることを示しているようにも思われる。母国の暴挙を公に批判したロシア人音楽家たちの行動も、世界を敵に回したこの国、とりわけこの政権からの距離を明示しておく必要があったゆえとも考えられるだろう。
実際、すでにロシア音楽全般が各地で敬遠されるようになっていた。70年近い歴史をもち、「歌の国際試合」とも言えるユーロビジョン・ソング・コンテストは、26日にはロシアの参加禁止を決定。ポーランド国立歌劇場は、予定していたムソルグスキーのオペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の上演中止を3月2日に発表。「沈黙によってウクライナへの連帯を示す」と説明する。また、イギリスの王立劇場は、夏に予定していたボリショイ・バレエ団の公演中止を発表。同国では、すでにイギリス国内を巡演していたロシアのバレエ団が、残りの公演の中止を余儀なくされる事態になっていた。そればかりか、ロシアのバレエ学校を卒業したダンサーによって構成され、イギリスを拠点に活動するロシア国立オペラ(Russian State Opera)も、その名前から公演のキャンセルが相次いだ。劇団の運営者によれば、名前は「ブランド」にすぎず、ロシア政府から資金提供なども一切受けていないという(6)。要するに、この時すでに、「ロシア」という名前自体がマイナス・イメージになり始めていたのである。
こうした動きは音楽界に限ったことではない。それを象徴的に示すのが、ロシアへの「文化的制裁」の呼びかけである。
国際美術館会議のサイトに、ある文書が掲載されている。ウクライナの芸術・文化関係者らの署名入りで、ロシアへの文化的制裁の請願書への賛同を求めるものだ(その中にはオペラ歌手や作曲家の名前も含まれている)。冒頭では、「文化は政治的プロパガンダに追従してはならない」とし、「国際的な文化領域でのロシアの存在を制限する」よう訴えている。具体的な項目が6つ挙げられており、例えばロシア政府に関わるプロジェクトの禁止のほか、国際コンクールや音楽祭にロシア人の参加を認めないこと、ロシア文化を報道しないことなどが列挙されている。ともすれば、コンクールに参加するロシア人全てが「政治的プロパガンダ」であるとみななすかのようにも受け取れる。
確かに、ゲルギエフやネトレプコといった「プーチン支持者」のように、その暴力的政治姿勢を讃える音楽家などについては「プロパガンダ」とみなしても良いかもしれない。けれども、こうしたロシアの芸術文化全般を一律に「ボイコット」することは、果たして必要なのだろうか?
こうした動きを推奨するものとして、経済制裁同様、文化的に圧力を与えることがロシア国民へのメッセージともなり、政権打倒への奮起に繋がるといった見方がある。「スポーツや文化は、弾丸や爆弾を止めることはできないが、圧力を与えることはできる」との主張だ(7)。とはいえ、文化的制裁によって必ずしも同国民が「政権打倒」へと駆り立てられるとは限らない。他国から排除されることにより、逆に敵意や憎悪が芽生え始めることも大いに考えられる。むしろ、その可能性の方が大きいだろう。文化を遮断することは人間相互の交流の機会をなくすことでもある。対話のないところに友好関係は生じないことは、普段の社会生活を考えればすぐにわかることだ。たとえ、制裁という強硬手段によって一時的に戦争を止めることができたとしても、その間に失われた相互理解や共感を取り戻すまでに、どれほどの時間を要することになるか。その代償の方がはるかに大きいように思われる。
あるいは、「ロシア文化のボイコット」を支持する意見の中に、作品の上映などで発生した税金がロシア政府に納められることにより、間接的に戦争支援に繋がると指摘する声もある(8)。これは経済制裁と同じ観点に立つものであり、確かに否定できない。とはいえ、凍結された巨額の銀行資産やオイル・マネーとは異なり、ロシア人アーティストやその作品の使用によって得られる税収の消滅が、かの政権を倒すほどのダメージを与えるとは到底思えない。むしろ、先にも述べたように、制裁が今後の世界にもたらす社会的、精神的損害の方がより深刻だろう。
そもそも、政治状況によって特定の音楽や文化を全面的に排除することは、ナチスがユダヤ人音楽家や彼らの作品を禁じたことと同じではないか。あるいは、敵国の音楽文化を禁じた第2次世界大戦中の日本のやり方と同じと言っても良いかもしれない。国を守るため、愛する人を守るためという「正義」を掲げて、偏った(誤った)基準に基づく集団行動を要請するのは、全体主義の考え方だ。さらに言えば、こうした特定の文化の排除は、差別意識の醸成にも繋がりかねない。音楽などの芸術は、様々な感性や自由な価値観を是とし、それによって一層豊かに育まれていくものだ。むしろ多様性を認め合う社会を形成するために、その力を利用するべきではないだろうか。
こうしたなかで、一つの救いとなったのは、「ロシアへの文化的制裁」に異を唱えるかのような動きが音楽界において見られたことだ。つまり、3月5日、国際音楽コンクール世界連盟は「ロシアとベラルーシの参加者についての見解」を発表する。同連盟は、「政権のイデオロギーを代弁している人と、リスクを冒しながらも反戦の意を表明している人とが区別されないまま、両国出身の音楽家たちが一様に孤立しつつある」ことを危惧する。その上で、「国籍によって、その国の政府を代表するとみなしたり、イデオロギーを代弁していると判断したりすることは出来ない」とし、あらゆる国の参加者に対して「良心と尊厳と慈愛とともに」接するとしている。
また、これに先立つ3月3日、アメリカのヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールは、3月6日から始まるコンクールの参加者のうち、15名がロシア人であり、そのうち8名はモスクワ在住であることを明らかにしつつ、いずれも「ロシア政府に関わりのある者ではない」として、参加を認めることを発表した。コンクールも重要な文化交流の場であり、政治状況によって特定の国や民族が遮断されることがあってはならないだろう。
音楽は、常に政治や権力と深く関わってきた。ベートーヴェンの『歓喜の歌』のように、明らかに政治的主張の含まれた作品ばかりでない。たとえ題材そのものや、作者や奏者個人の思想には政治イデオロギーがほとんどないとしても、それらの意思とは関係なく時に権力に利用され、あるいは翻弄されてしまうのである。この度の出来事は、それを如実に露呈させるものとなった。これを書いている最中にさえ、ロシアの指揮者、トゥガン・ソヒエフが、フランスとロシア双方の国の楽団の音楽監督を辞任したというニュースが飛び込んできたのだ。
彼はフランスの楽団側からプーチンに対する見解を明らかにするように求められた結果、「2つの文化のどちらか一つをえらぶことはできない」と辞任の決断に至った理由を述べている。もちろん、彼の家族や知人にまでリスクが及ぶ可能性がある以上、本心を明らかにすることなどできないだろう。スターリン時代など知らないはずのこの指揮者は、「音楽をやる際にこれまで一度も国籍を考えたことなどない」と話すが、どうやら時代は半世紀以上も前に逆戻りしてしまったようだ。
(2022/3/15)
- Javier C. Hernández, “Global Tours Were Key for Orchestras. Then the Pandemic Hit.” The New York Times, February 22, 2022.
- Javier C. Hernández, “Valery Gergiev, a Putin Supporter, Will Not Conduct at Carnegie Hall.” The New York Times, February 24, 2022.
- Tom Service, “Music as politics: Gergiev’s South Osetia concert.” The Guardian, August 22, 2008; Arthur Lubow, “The Loyalist.” The New York Times Magazine, March 12, 2009.
- Alex Ross, “Imperious.” The New Yorker, October 28 2013.
- “Soprano Anna Netrebko withdraws from Met performances rather than renounce Putin.” The Guardian, March 3, 2022.
- 以上、“Ukraine crisis: Russian ballet company’s remaining UK tour dates cancelled.” BBC NEWS February 28, 2022.
- Nadine Dorries, “Sport matters to Vladimir Putin – we can use it to cause him real pain.” The Telegraph, March 2, 2022.
- Alex Marshall “To Boycott Russians, or Not? In Film and Beyond, That’s the Question.” The New York Times March 4, 2022.