プロムナード|あんまり良くない時代に|田中 里奈
あんまり良くない時代に
→In the Not So Good Times (in English)
Text by 田中里奈 (Rina Tanaka)
ウクライナ侵攻に対する芸術界の反応
「あんまり良い時代じゃないね」。2月24日の東京オペラシティで催された東京フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会(於:東京オペラシティ)でアンコール曲を演奏する前に、井上道義はこう切り出した。日本時間で前日の晩、ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めたことを受けての発言であると、暗に理解された。
ウクライナ侵攻に対する芸術界の対応は早かった。少なくとも、私が辛うじて追うことのできた3つの言語において、ニュースは絶え間なく耳に入ってきた。ベルリン・フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者キリル・ペトレンコや、チェコ・フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者セミヨン・ビシュコフ、バイエルン州立歌劇場の音楽監督ウラディーミル・ユロフスキ――いずれもロシアにルーツを有した音楽家たち――は即座に声明を出した。
ロシアにおける動きも早かった。モスクワのメイエルホリド・シアター・センターの芸術監督エレーナ・コワルスカヤは2月24日、「殺人者のために働き、彼から給料をもらうことなどできない」と声を上げて辞任した(1)。2月25日には、国際演劇評論家協会ロシア・センターがウクライナ・センターに向けて、「自国の政府によってウクライナの人々に行われている唾棄すべき軍事行動を非難し、この戦争への反対を明らかにするための署名をはじめ、あらゆる手段を用いて抗議を表明する」とメッセージを送った(2)。このエッセイを書いている今も、トーマス・ザンデルリングが侵攻への抗議のために、ノボシビルスク・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督を辞任したというニュースを見たばかりだ。
ゲルギエフ解任をめぐって
出演取り止めに関する大きな指針となったのが、ヴァレリー・ゲルギエフをめぐる一連の報道だ。2月24日、ウィーン・フィルハーモニーはニューヨークのカーネギー・ホールで開催を予定していた演奏会の全日程で、「親プーチンの人気指揮者(der putinfreundliche Stardirigent)」(3)ゲルギエフの出演をキャンセルした(同演奏会の初日に出演するはずだった「ロシア人」ピアニストのデニス・マーツエフも急遽降板となった)。これまでに、ミラノ・スカラ座や、フィルハーモニー・ド・パリ、スイス・ヴェルヴィエ音楽祭、ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団といった名だたる団体がゲルギエフの出演を取り止めるか、あるいは彼との関係を完全に解消した(4)。
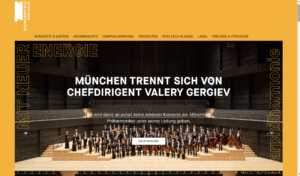
3月1日、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団がゲルギエフを首席指揮者から解任するにあたり、ミュンヘン市長のディーター・ライターは次のように発言した。「現状において、オーケストラとその観客、市民、そして市政に対して、[プーチンとの決別という]明確なシグナルを出さない限り、今後も協働していくことはできなかった。それが実現しなかったとなれば、即時解任しか残されていない」(5)。
「市政」という語にも表れている通り、上記の発言を、ミュンヘン・フィルの公的な経済・運営基盤と、ドイツに特有の文化政策的枠組みを抜きにして考えるべきではない。だが一方で、特定の政治的つながりを有した芸術家に対する断固とした態度は、戦後ドイツのナチス期への反省を連想させる。その関連で、ダニエル・バレンボイムによる「平和のためのコンサート」が、3月6日にベルリン・オペラ広場で――1933年にナチスによる焚書が起こったその場所で――催されたことは示唆的だ。
文化セクターにおける「魔女狩り」
「平和のためのコンサート」で、ロシア人ピアニストを妻に持つバレンボイムは、自分のウクライナ人の祖父母――第二次世界大戦中にソ連からアルゼンチンに逃れ、現在はベラルーシに住んでいる――に言及しつつ、文化的なボイコットはロシア人芸術家に対する「魔女狩り」になりかねないと警鐘を鳴らした(6)。
少し前に、ドイツ文化・メディア担当大臣クラウディア・ロートも同様の発言をしたばかりだった。「私は、ロシア文化・芸術のボイコットに向かう傾向、ロシア人だからという理由で芸術家に疑いの目を向けること[…]を止めるよう、警告します」(7)。
言うまでもなく、この警告は「物事を未然に防ぐ」ためのものではなく、「すでに起こっていることを止めるように」説いている。ここ2週間ほど、実際にロシア関連の楽曲を差し替えたコンサートは全世界から繰り返し聞こえてきた。芸術関連の報道をチェックしていても、「ロシア人」「ロシア出身の」という語が頻出していることは明らかだ。国際的に活躍してきたロシア出身の芸術家たちは、侵攻が始まってすぐにきっぱりとした立場の表明を強いられたし、迅速に発言しないことも「答え」とみなされた。日常はあっという間に「敵」と「味方」の二分法的な考え方に吞まれてしまった。
それで思い出すのは――むろん、類似性を安易に見出すべきではないことは百も承知で、あえて例に出したいと思う――、2020年1月、イタリア・ローマのサンタ・チェチーリア音楽院が、渡航歴に限らず、すべての「東洋人」学生のレッスンを中止すると発表したことだ(8)。その後、日本への入国が長期的に制限され、多くの留学生が足止めされていることを考えると、まったく皮肉というほかない。突然、「敵」とみなされることは、イプセンの『人民の敵』を参照する必要も無いくらい、ごく当たり前に起こる。
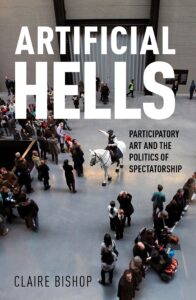 芸術 vs. 政治、または芸術の政治性
芸術 vs. 政治、または芸術の政治性
芸術や文化の政治性についての議論を追っていると、「文化と政治を混同するべきではない」という言説によく出くわす。この言説は決して誤ってはいない。ウィーン・フィル団長のダニエル・フロシャウアーが、ゲルギエフ降板に際してもなお、「文化は政治的論争の駒になってはならない」と述べ、「音楽は我々をつなぐものであり、分け隔てるものではない」(9)と強調したことは、前述のように芸術界もまた敵味方で急速に分かれ始めている状況において、言うまでもなく重要だ。
しかし、だからこそ、私がいっそう重要だと思うのは、芸術活動がどうあっても政治的にしかなり得ないという前提に立つことで見えてくるものだ。この前提は、国や地方自治体、ある種の権威にとって有益となりうる政治的な芸術パフォーマンスに対して向けられているのではない。なぜなら、芸術は、環境に対応する限りつねに社会関与的であると同時に、「日常の議論で抑圧されている矛盾を伝達する能力、そして世界と私たちの関係をあらたに構想するための可能性を拡げる[…]経験をもたらす能力を有している」(10)。
クレア・ビショップの芸術観を援用するならば、ウクライナ侵攻に対する芸術界の一連の反応を、緊迫した国際情勢を映す鏡、または理想論的な連帯の希求としてみなすだけでは不十分だ。ウクライナ侵攻に端を発する「環境」の急変において、芸術から発される乖乱的な問いかけにこそ、目を向ける必要がある。
ユロフスキによるプログラム変更
2月26日~27日のベルリン放送交響楽団による演奏会(指揮:ウラディーミル・ユロフスキ)は、プログラムが大幅に変更された。演奏会の冒頭にウクライナ国歌が加わり、さらに、チャイコフスキーの「スラヴ行進曲」の代わりに、ウクライナ国歌を作曲したミハエル・ヴェルビツキーの「交響的序曲第1番」が演奏されることになった。ウクライナ国歌の演奏ののちに行われた8分間のスピーチの中で、指揮のユロフスキは、現状における自らの立場にはっきりと言及し、プログラムを変更した意図を各楽曲の歴史的背景に基づいて丁寧に説明している(これに関しては、辻見達郎氏が詳細に報じている)。
特筆すべきは、スピーチ終盤でユロフスキがチャイコフスキーの多面性に触れている点だ。曰く、皇帝アレクサンドル3世の庇護下で君主制主義の作曲家として活躍する一方で、抒情的で反体制的な作曲もみられる――ユロフスキ曰く、「ショスタコーヴィチが意識的に行ったことを、チャイコフスキーは無意識的にやってのけた」(11)。「スラヴ行進曲」、および「交響曲第五番」の最後の部分で描き出された「空虚で騒々しい国家権力、輝かしいツァーリの力」はまたの機会に、と言ったのち、ユロフスキはこう続けた。「個人的に、あの交響曲の結びは極度に脅迫的(extrem bedrohlich)で、とてもアクチュアルだと思う」。
ユロフスキのスピーチは、なぜ今、あえて演奏会を催して、これらの楽曲を演奏するのかという問いに対して、社会と芸術の両側面から回答しているように思われる。まず、彼自身が述べているように、ウクライナ侵攻に際して黙するのではなく、戦争に対して集団で異を唱えるために。次に、いっそう注意深く見るべき点として、演奏される条件によってさまざまに解釈され、演奏される音楽作品を、その作品にまつわる歴史と現在の環境を照らし合わせながら鑑賞するために。後者は、エドワード・サイードの言葉をあえて借りて言い換えるならば、「他の社会について知る必要などないという感覚」ではなく、「僕らはどこに向かっているのかということについての自覚」である(12)。自覚というよりは、たえずそう問いかけると言った方が、本稿の文脈に沿うかもしれない。
いま、なぜこの演目をやるのか
「僕らはどこに向かっているのか」だと漠然としているので、もう少し具体的に、「いま、なぜこの演目をやるのか」という問いにしてみる。私がこの問いを真面目に考え始めたのは、オーストリア・ヴィーンのミュージカルに対する当てこすりとも思えるような報道と、それに対する劇場の執拗な応答を繰り返し目にしてきたからだった(実のところ、ご当地ミュージカルの作り手の国籍に妙にこだわりたがるヴィーン各紙の特徴が、ウクライナ侵攻に際した各報道を読んでいた私に、記事内の言葉の選び方に注視を促すに至った)。
問いについて考え続けているうちに、問いの対象には自分も入っていた。演劇公演や演奏会に足を運ぶたび、上演の内容を理解しようと試みることは、上演を観ている私の認識を批判的に検討することでもあった。芸術鑑賞では誰もが個別的な体験をするが、「なぜ自分はそのように感じたのか」を突き詰めていくと、鑑賞当時の自分のコンディションに影響を受けた部分とそうではない部分が見えてくることがある。コロナ禍初期の緊急事態宣言と公演中止ののち、劇場で久々に芝居を観た折、俳優同士の接触や距離の近さにいちいちヒヤリとしたことは、私のパーソナルスペースの変化を認識するのに十分な体験だった。
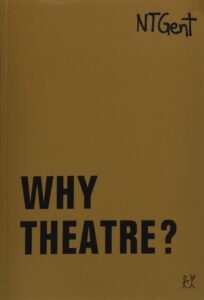 コロナ禍で出版された書籍『なぜ演劇か(Why Theatre?)』には、「なぜ演劇か」という問いに対する、計106人のアーティストからの回答が収録されている。一番最初のページに載っているのは、シリア出身の劇作家ムハンマド・アル=アッタールの回答だ。2011年のシリア革命からの内戦を振り返り、コロナ禍よりもずっと前から「いま、なぜ」を刻一刻と変化する状況の中で問いかけてきたアル=アッタールは、次のように結んでいる。
コロナ禍で出版された書籍『なぜ演劇か(Why Theatre?)』には、「なぜ演劇か」という問いに対する、計106人のアーティストからの回答が収録されている。一番最初のページに載っているのは、シリア出身の劇作家ムハンマド・アル=アッタールの回答だ。2011年のシリア革命からの内戦を振り返り、コロナ禍よりもずっと前から「いま、なぜ」を刻一刻と変化する状況の中で問いかけてきたアル=アッタールは、次のように結んでいる。
わかるのは、私たちはポスト真実の時代における政治の衰えとファシズムの高まりの証として演劇を作っていることだ。私たちは演者と観客が問題を発見し、よく考えることのできる場所として演劇をつくる、私たちと私たちの世界をもっと良く理解するために。それにそう、私たちは、稽古中や、暗闇の中で座って舞台を見つめている時に経験する楽しさのために演劇をつくる。だが、私はこうも確信している、私たちが生きている今日のような、大いなる不確定と変化の時代には、演劇の役割と重要性に関する私たちの理解への新たな挑戦が生まれるだろうと。そして、新たな答えも。答えは、試行し、繰り返し深く考えることを通じてのみ導き出すことができる。(13)
この稿で最初に挙げた井上道義の言葉に戻ってみる。「あんまり良い時代じゃない」のは今に始まったことではない。だが、「良い」か「良くない」かは別として、ここまで見てきた考えの断片は、ひとつの方向を指し示しているようにみえる。芸術が、「日常の議論で抑圧されている矛盾を伝達」し、「世界と私たちの関係をあらたに構想するための可能性を拡げる」こともあるのだとすれば、芸術を鑑賞しに行く(または自宅で鑑賞する)ことには、心を癒したり、平和に向けて世界がひとつになることを願ったりするだけでなく(いっそ白状するが、私はそういう目的に全然乗れない)、現状から少し距離を取って現状を見つめ直す行為「も」、実は知らず知らずのうちに含まれている。それは、ここまで私が書いてきたような堅苦しいプロセスではなくて、気づけばちょっと楽に感じる類のものだと思う。この、先の見えない時代に。
(1) Broadway World, “Director Of Moscow’s State Theater Resigns In Protest Of Ukraine Invasion,” February 24, 2022.
(2) 国際演劇評論家協会日本センター「AICT-IATCロシアセンターからウクライナセンターへのメッセージ」2022年2月26日。
(3) APA, „Wiener Philharmoniker spielen ohne Gergiev in New York,“ 24. Februar 2022.
(4) 毎日新聞「ヴァレリー・ゲルギエフ、相次ぐ降板や解任」2022年3月2日。
(5) Münchner Philharmoniker, „Pressemtiteilung 1. März 2022“, 1. März 2022.
(6) Deutsch Welle, „Großes Solidaritätskonzert für Ukraine in Berlin“, 6. März 2022.
(7) Die Zeit, „Roth warnt vor Boykott russischer Kunst und Kultur“, 4. März 2022.
(8) 朝日新聞「国立音楽院「東洋人へのレッスン中止」 新型肺炎」2020年1月30日。
(9) APA, 24. Februar 2022.
(10) Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso Books, 2012(訳書、p. 12; p. 432).
(11) 以降のユロフスキの発言は、Deutschlandfunk Kulturのラジオ放送に基づく。
(12) A. グゼミリアン編『バレンボイム/サイード 音楽と社会』中野真紀子訳、みすず書房、2004年、p. 202
(13) Mohammad Al Attar, “A Constant Journey of Doubt and Experimentation,” In: Kaatje De Geest, Carmen Hornbostel and Milo Rau, eds., Why Theatre?, Verbrecher Verlag, p. 18.
(2022/03/15)


