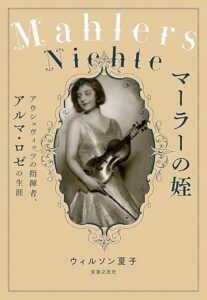円盤の形の音楽|続・究極のタラレバ―ミケランジェリの室内楽|佐藤馨
続・究極のタラレバ―ミケランジェリの室内楽
Text by 佐藤馨(Kaoru Sato)
 〈曲目〉*10枚組のうち、該当のDisc1のみ記載 →foreign language
〈曲目〉*10枚組のうち、該当のDisc1のみ記載 →foreign language
Disc 1
[1]-[3] モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 KV450
[4]-[6] モーツァルト:ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調 KV493
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアノ)
[1]-[3] エドモン・ド・シュトウツ指揮、チューリッヒ室内管弦楽団
[4]-[6] ジャン=ピエール・ワレズ(Vn)、クロード=アンリ・ジュベール(Va)、フランク・ダリエル(Vc)
〈録音〉
[1]-[3] 1974年 [4]-[6] 1972年
前回はリパッティのベートーヴェンという話をした。調べてみると、彼のレパートリーにはベートーヴェンが含まれていたようで、ワルトシュタイン・ソナタは演奏会でも披露していたし、ピアノ協奏曲第5番はレコーディングの計画もあったらしい。往年の音楽家の未発表音源が今になってリリースされるということも珍しくない昨今、かなり可能性は低いが、リパッティについても今後の進展を期待しつつ、新しくベートーヴェンの録音が発掘される日に遠く思いを馳せよう。このような願望が噴出してくる演奏家はリパッティだけではない。内田光子のバッハ、アンドラーシュ・シフのリスト晩年、ヴィルヘルム・ケンプのフォーレ、これらは聴きたい or 聴きたかった録音の最たるものである。選曲に関して、演奏者にはそれぞれの美学があり、外野が自らの欲望をぶつけるものではなかろうが、こうしたタラレバはふと湧き上がると抑えがたい。
そしてタラレバは作曲家単位の話だけではない。例えば、ソロばかりで目立っている人がこっそり室内楽をしていたなんていうのは、私としては大変に心くすぐられる話だ。そもそも室内楽が好きということもあるが、こうした珍しい音源に出会った時のワクワクはその他の音源とは比べものにならない。
まず一つにはソリストとばかり思っていた奏者への固定観念が自分の中で打ち壊される快感、もう一つはその人の音楽的な振れ幅を目の当たりにできるドキドキ感、最後には愛好家としての多少の覗き趣味、これらが出会いの高ぶりの中にいつも付きまとっている。蓋を開けてみれば、「結局ソリストでしかなかったな」との感想を持つこともしばしばだが、たいていの場合、ソロの演奏だけでは知られなかった演奏家の別の一面を垣間見ることができ、リスナー冥利に尽きるといったところだ。
この流れで思い出すのが、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリである。完璧主義者、強靭なテクニックと透徹した音色、キャンセル魔など、このピアニストについては様々なイメージが伴っていることだろう。
私が最初にミケランジェリを聴いたのは、ラヴェルのピアノ協奏曲の有名な録音だった。かなり俯瞰した演奏という印象で、どんな箇所でも一歩引いた位置から精妙にピアノを操作しているようだった。しかし第2楽章になって、この距離感が一転して音楽に対する慈しみのように聴こえてきた。「心は熱く、頭は冷静に」の究極的な形とでも言うのだろうか。おそらく、入り込みすぎないこの適切な遠さでしか実現できない、静かな温かさだったのだろう。今でもこの演奏は私の中で絶対的な指標として君臨している。
非正規も含めて数多くの録音が出回っているミケランジェリ、そのほとんどはソロか協奏曲となっているが、たった一つ、室内楽を共演した音源が残っている。1972年に録音された、モーツァルトのピアノ四重奏曲第2番である。
私がこの録音を知ったのは、2005年にリリースされた廉価盤10枚組のなかに収められていたからなのだが、初めて見たときは本当に目を疑った。まさか、孤高の騎士ミケランジェリが他人と室内楽をしていたとは。聴く前はさぞやちぐはぐな出来と予想していたが、ここでのミケランジェリは意外なほど室内楽に順応しており、醍醐味である他の奏者との押し引きを心得ているようだった。ピアノが主体になりがちな曲とはいえ、自分だけが突っ走ることもなく、各楽器の歌に耳を傾けながらカッチリと作品をまとめている印象である。没入したり、逆にドライになったりもせず、大きく全体を見渡しながらも要所で彼ならではの節回しが見られ、特に第2楽章では繊細な音色も相俟って巨匠の歌の至芸が感じられる。
全体に安定感を保って進んでいく演奏だからこそ、そこから外れたちょっとした歌の揺らぎに最大限の味わいが感じられるのだ。過干渉にならない彼独自の距離感がここでも活きていると言うべきだろう。たしかに、モーツァルトの百面相的な楽しさや軽快さとは離れたところにあるが、むしろ紆余曲折を挟まず、クリアに音楽を積み上げていく明快さは小気味よくさえある。
アンサンブル全体として落ち着いた滋味深い仕上がりとなっているのは、ミケランジェリ本人の音楽性でもあろうが、それ以上にこの作品を献身的に彫刻していこうとするワレズをはじめとした他の奏者たちと、その態度が合致しているからであろう。最上の名演とは言わずとも、個人的にはとても好きな演奏の一つで、演奏家の個性が表立つのではなく、純粋にモーツァルトの音の並びの美しさに触れる演奏だと言えよう。
たまにはこんなモーツァルトも良い。何より、いつものケランジェリとは少し違った、わずかに親密さを湛えた表情が思い描かれるようで微笑ましい。ここでの彼に少しばかりの可愛らしさを感じるのは私だけだろうか。こんなミケランジェリがもし「大公」を弾いていたら、果たして…。
(2022/2/15)
—————————————
〈Tracklist〉
Disc 1
[1]-[3] Mozart:Piano Concerto No.15 in B-flat Major, KV450
[4]-[6] Mozart:Piano Quartet No.2 in E-flat Major, KV493
Arturo Benedetti Michelangeli, piano
[1]-[3] Edmond De Stoutz, Züricher Kammerorchester
[4]-[6] Jean-Pierre Wallez (Vn), Claude-Henry Joubert (Va), Frank Dariel (Vc)
〈Recording〉
[1]-[3] 1974 [4]-[6] 1972
——————————
佐藤馨(Kaoru Sato)
浜松出身。京都大学文学部哲学専修卒業。現在は大阪大学大学院文学研究科音楽学研究室に在籍、博士後期課程1年。学部時代はV.ジャンケレヴィッチ、修士ではCh.ケクランを研究。演奏会の企画・運営に多数携わり、プログラムノート執筆の他、アンサンブル企画『関西音楽計画』を主宰。敬愛するピアニストは、ディヌ・リパッティ、ウィリアム・カペル、グレン・グールド。