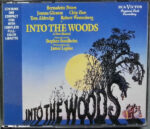ミュージカル「INTO THE WOODS」|田中 里奈
ミュージカル『INTO THE WOODS』
Musical Into the Woods
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
日生劇場、2022年1月11日~31日(鑑賞日:1月15日)
【スタッフ】
作詞・作曲:スティーヴン・ソンドハイム
脚本:ジェームズ・ラパイン
演出:熊林弘高
翻訳・訳詞:早船歌江子
音楽監督・指揮:小林恵子
美術:杉浦充
照明:笠原俊幸
音響:山本浩一
衣裳:原まさみ
ヘアメイク:鎌田直樹
ムーブメントディレクター:柳本雅寛
指揮:大河内雅彦
歌唱指導:やまぐちあきこ、横山達夫
演出助手:田丸一宏
舞台監督:藤崎遊
宣伝美術:三堀大介(SIREN Inc.)
宣伝写真:石黒淳二
宣伝衣装:藪内勢也
宣伝ヘアメイク:栢木進(su-su)、masato at B.I.G.S.(marr)
【キャスト】
赤ずきん(「赤ずきん」):羽野晶紀
シンデレラ(「シンデレラ」):古川琴音
継母・実の母(「シンデレラ」)、ばあば(「赤ずきん」):毬谷友子
継姉フロリンダ(「シンデレラ」):湖月わたる
継姉ルシンダ(「シンデレラ」):朝海ひかる
王子(「シンデレラ」)、狼(「赤ずきん)」:廣瀬友祐
執事(「シンデレラ」):花王おさむ
ジャック(「ジャックと豆の木」):福士誠治
母親(「ジャックと豆の木」):あめくみちこ
ラプンツェル(「塔の上のラプンツェル」):鈴木玲奈
王子(「塔の上のラプンツェル」):渡辺大輔
ナレーター、謎の男:福井貴一
夫(「パン屋」):渡辺大知
妻(「パン屋」):瀧内公美
魔女:望海風斗
巨人(声の出演):麻実れい
スウィング:則松亜海 杉浦奎介
パフォーマー:井上尚子 梶田留以 児玉彩愛 渋谷亘宏 西田健二 矢嶋美紗穂 吉﨑裕哉
主催:梅田芸術劇場/ぴあ
企画・制作:梅田芸術劇場
—
はじめに
1995年に販売されたスーパーファミコンのゲーム『スヌーピーコンサート』に、こんな場面がある。天才音楽少年シュローダーがおもちゃのピアノを弾いている。プレイヤーには、彼の演奏内容が楽譜として彼の横に見えている。だが、画面が自動で右にスクロールしていくと、音符の代わりに五線譜に引っかかっているのは、なんと豆とツタである。そこに農夫の恰好をしたスヌーピーとウッドストックがやってきて、豆をせっせと回収する。楽譜を失ったシュローダーはキョトンとしている…。どういう場面かというと、「シュローダーが失くしてしまった楽譜の捜索」を請け負ったスヌーピーなのだが、「楽譜」が何なのかわかっておらず、彼の思い描く「回収」がイメージとして面白おかしく示されているのだ。その後、スヌーピーは見当違いなウッドストックの導きに従い、妙ちきりんな森の中を探し回ることになる。
上記の視覚的イメージは、梅田芸術劇場主催ミュージカル『INTO THE WOODS』について、筆者が問題にしたい2点をずばり言い表している。楽譜に書かれていた音符が豆とツタにかわってしまった音楽は、ミュージカル作品にいかなる作用をもたらすのか。また、それをひとつの公演としてどのように評価することができるのか。
ミュージカル『INTO THE WOODS』
本題に入る前に、まず作品について確認しておきたい。『イントゥ・ザ・ウッズ(Into the Woods)』は、昨年2021年に亡くなったばかりのスティーヴン・ソンドハイムが作曲・作詞、ジェイムズ・ラパインが脚本を担当したミュージカル作品だ。1986年にカリフォルニア・サンディエゴで初演されたのち、翌1987年のブロードウェイ公演でトニー賞3部門(脚本賞・楽曲賞・主演女優賞)を受賞。その後、2002年にはリバイバル版が話題となり、2014年にはディズニーによる映画版が公開された。なお日本では、2004年の新国立劇場で宮本亜門の演出・振付によるバージョンが初めて上演されてから、これまでに3種のバージョンの計4公演が打たれている。
『イントゥ・ザ・ウッズ』の物語は、心理学者ブルーノ・ベッテルハイムによる『昔話の魔力』(1976、邦訳は1978)に着想を得て、著名なグリム童話の複数からの引用をもとに構成されている。第1幕では、『赤ずきん』、『ジャックと豆の木』、『ラプンツェル』、『シンデレラ』の主人公たちが同じ国に暮らしていることが提示され、元の童話通り、めいめいの願いが叶えられ、ハッピーエンドを迎える。第2幕では、死んだ巨人の妻が復讐のために国を破壊しに現れ、登場人物間での責任のなすりつけ合いが起こる。多くの犠牲の中で、すべての物語の原因となった出来事が明かされる。4つの物語を結ぶのは、魔女のかけた不妊の呪いを抱えたパン屋の夫婦と、謎めいたナレーターの男――本作で唯一、ソンドハイムとラパインによって創作された童話である。
『INTO THE WOODS』(本稿では、作品自体をカタカナ表記、今回の公演を公式サイト1ほかに従い英語表記として、以下区別する)では、近年演劇の分野でたびたび話題に上ってきた演出家・熊林弘高、ドラマ・舞台等で脚本と翻訳を担ってきた早船歌江子、そして、スイス・ハルヴィル城オペラほかで指揮し、過去にソンドハイム作品を振ったこともある小林恵子を筆頭に、スタッフもキャストも、演劇・映像・音楽劇などのさまざまな分野から集められている。なお、ひとくちに「音楽劇」と言っても、その範囲がオペラからミュージカルやヴォードヴィル、あるいは日本で言えば、宝塚歌劇、劇団四季、2.5次元ミュージカルまで幅広いことは、日本で「音楽劇」を一度でも観たことのある人にとって当たり前かもしれないが、今回の公演にもあてはまる。
ミュージカルとして不成立?——「普通のミュージカル」論に向けて
さて、『イントゥ・ザ・ウッズ』は、マーベルコミックの『アベンジャーズ』よろしく、登場人物が文字通り「主役級」ばかりの作品である。このために、一見するとスターシステムと親和性の高そうな作品である。実際に、『INTO THE WOODS』の公演プログラムの挨拶文に書かれた、「ミュージカル、ストレートプレイ、音楽、映像と様々なエンタテインメントで名実ともにトップを担うキャスト」の集合体という表現は、彼らのスター性を担保すると同時に、必ずしもミュージカルの素質を有さないかもしれない演者の存在をほのめかしてもいる。
挨拶文はキャストの紹介に続いて、演出に言及している。「このミュージカルの楽譜やテキストに対する、深く鋭い分析と理解に基づきながら」も、「深淵なテーマ」へとアプローチした熊林の演出が、「おとぎ話を、人間の深層心理を描いたものとして捉え直し、大人向けのミュージカルに仕立てる」という作品そのものの試みに合致しているのだと、ここではっきり説明しているのが面白い。見方を変えれば、原作を曲解した演出だと非難されることを見越して先手を打ったように見える。はたして筆者は観劇後、この一文を読み返して頭を抱えてしまった。
終演直後の筆者の判断において、『INTO THE WOODS』という公演はミュージカルとして成立していなかったようにみえた。なぜなら、この作品の基本要素である音楽を、複数の演者が十分に——あるいはまったく——歌いこなせていなかったからだ。例えば、1曲目の「プロローグ:イントゥ・ザ・ウッズ」からして、日生劇場で聞いたものは、オーケストラの演奏を除いて、楽譜やブロードウェイ初演版のレコーディングで確認可能な旋律やハーモニーとは別物だった。いかにすぐれた演者がキャストとオーケストラにいたとしても、音楽の構成上、個々人の卓越したパフォーマンス――魔女役の望海風斗や、2人の王子役の廣瀬友祐(狼役と兼任)と渡辺大輔は、特筆すべき健闘ぶりだった――が公演全体の質を挽回することは困難だった。
ミュージカル『イントゥ・ザ・ウッズ』に歌唱力は必要か?
ソンドハイムの楽曲は、秒単位で変わる拍子や転調の連続、早口で韻を踏んだ歌唱といった要素が難解であると国内外でたびたび評されてきた。それと同時に、聞けばすぐにソンドハイムだとわかる独特の音楽のスタイルは、作曲者自身による解題だけでなく、音楽分析の対象にもなっている2。
『イントゥ・ザ・ウッズ』の場合、音楽的構成には明快なルールが見て取れる3。もっともわかりやすいのが、キャラクターと作品のテーマごとに設定されたライトモチーフ(または「ディティー」4)である(図15)。各ライトモチーフは、反復の中で他のモチーフと交流し、変容していく。長2度上昇——ソンドハイム曰く、抑圧された願望の現れ6——のあと、完全4度7上昇からの短7度下降が特徴的な「願い(Wish)」のモチーフは、叶えたい願いを有した複数のキャラクターによって劇中で執拗に反復され、各キャラクターのモチーフに派生していく。長2度からの完全4度上昇はシンデレラ、パン屋夫妻、ジャックの母の計3つのモチーフに共通しており、さらに短7度下降は前者2つに認められる。「プロローグ」の冒頭に顕著に表れているが、各モチーフは短い断片となり、演者が細かな中断を経つつ、順番に歌いつなぐことで、自分のモチーフを展開する。
さらに、「願い」と同様に作品全体の基盤となっている「魔法の豆(Beans)」のモチーフは物語の始まりを担う5つの豆を模して5つの音から成り、長2度上昇と短7度下降が隠れている。魔法の豆による願いの成就が物語の根幹にあることは、このように音楽にも表れている。前述の通り、「願い」が「プロローグ」で執拗に繰り返し歌われるのに対し、「魔法の豆」はキャラクターによって歌われる前に一度演奏されることにより、魔法の豆がキャラクターの願いに先行して、すべての物語の元凶となっていることが暗示される。その後、魔法の豆をめぐるさまざまなトラブルに直面したキャラクターがこのモチーフを歌うことになったり、あるいは暗示的なハーモニーとして背後で響いていたりする。モチーフの相互関係はそのまま作品全体の見取り図になっているのだ。

図1:『イントゥ・ザ・ウッズ』に登場するモチーフ一覧をHorowitzが書き起こしたもの(抜粋)。楽譜左端に書かれた表記はキャラクターの略称である(C=シンデレラ、J=ジャック、B=パン屋、BW=パン屋の妻、JM=ジャックの母)。
「魔法の豆」に端を発する「願い」の派生がめいめいに育ち、モチーフ間の差異を明らかにしていく楽曲全体の構造において、音が継続的に外れている事態は、各モチーフを独立した旋律とみなし、キャラクター間の関係性を支える中心軸を欠くということだ。むろん、関係性を提示する軸は音楽以外にも複数用意されている。だが、音楽と脚本とが密接につながっており、音楽がサブテキストをしばしば担うソンドハイムの作品において8、音楽なしに機能するものとは思えず、また、独立したそれぞれの要素とはみなしがたい。
演出の意図とキャスティング
作品の音楽的構成について、『INTO THE WOODS』の翻訳・訳詞、音楽監督、そして演出の三名が共通認識として持っていたことは、公演プログラムに掲載された対談における発言の数々——「曲の構造と言葉の意図が一致している」(早船)、「書かれている楽譜を忠実にやることによって、[演出と音楽の意図の合致も]実現します」(小林)、「すごく計算されて書かれてい[…]るものを、われわれがちゃんと汲み取らなくちゃいけない」(熊林)——から、断片的に読み取れる。
ただし、演出家・熊林個人の意図するところは曖昧である。インタビューの断片から、演技指導や演出の実際を導き出すことには無理があるが、最終的に舞台から観客に向けて歌を届ける出演者の視点から熊林の考えをトレースすることに意味があると思い、ここで少し追ってみたい。熊林は出演者のひとりである望海風斗に対し、「音をちゃんと歌うというよりも、楽譜が見えないように、最後はセリフを言っているかのようにその曲が完成することを目指したい」と説明する一方で、「ミュージカルと言っても、芝居、音楽劇だ」とも発言している9。
実際に望海はラップ調でリズムの早いパートを含めて、難解な楽曲を物語の一部分としてなめらかに位置づけていた。一方で、音楽の持つ軽やかさやテンポの良さを、音楽ではなく登場人物の動きや台詞によって創出しようとする試み——関西弁を用いたツッコミや、コミカルな掛け合いやマイム——は、物語の展開をいちいちかえって中断させていた。ここでもなお、『イントゥ・ザ・ウッズ』における音楽と脚本の有機的な関係は見えてこない。
ところで、『INTO THE WOODS』におけるキャストは、複数の演者がインタビューで認めているように、熊林やプロデューサーからのオファーか10、あるいはオーディションによって11、選出された。このことに鑑みると、選出の基準はあくまでもキャラクターとの親和性や演者の存在感にあり、前述したソンドハイムの音楽的形式に求められる水準は、十分に考慮されていなかったのではないか。
では、ミュージカルに歌唱力は本当に必要なのか。たしかにミュージカルに歌はつきものだ(2020年6月、同ジャンルの巨匠アンドリュー・ロイド=ウェバーが、感染防止を目的とした〈歌わないミュージカル〉を英国政府から打診されたという例外は置いておいて12)。だが、『マイ・フェア・レディ』(1956)のヒギンズ教授を演じたレックス・ハリソンが話すように歌い、リバイバル版がブロードウェイで現在上演中の『ザ・ミュージック・マン』(1957)にラップスタイルの曲が登場したように、さらに日本で言えば、2.5次元ミュージカルの一部が演者の成長を「売り」にして最初から完璧な歌唱を求めないように、必要な歌唱力の種類や質は作品によりけりである。
ミュージカル史に照らしてみれば、歌唱力の需要に大きく関わる転換点は、演者の見せ場として副次的に用いられることの多かった歌のパートが、『オクラホマ!』(1943)を経て、物語の展開や登場人物の描写に欠かせない要素として認められていったことだ。ある楽曲がきちんと機能しないと次の展開が意味不明になってしまうような作品において、楽譜の通りに歌えて、歌詞を聞き取れる風に発声してくれる演者は不可欠である。
その一方で、昨年7月のキャスト発表時に、熊林は「普通のミュージカルではありません!」というコメントを寄せていることにも注目したい。そもそも日本のミュージカルにおける「普通」とはなんだろうか。少なくとも筆者の理解では、ミュージカルに「普通」という形容詞は見当違いである。「ミュージカル」という汎称のもとには複数のサブジャンルやスタイルが集っていて、その小カテゴリごとの「普通」がある。そこを混ぜこぜにしている限り、クオリティの担保は困難な気はするが、この問題を演出家の無理解だけにすんなり帰結させるわけにはいかない。この状況を考える際、もう一歩踏み込む必要がある。
近年、マンネリ化した上演方法の限界を超えるために、異なるジャンルの専門家を積極的に招聘した公演が目立つようになりつつある。ただし、従来とは異なる視点を導入したことの効果を十全に評価するために本来不可欠な「従来」への視点が、実際の公演を評価する際にすっぽりと抜け落ちてしまうということも、残念なことにしばしば起こっている。こうなると、単に「異なる視点を導入した」ことしか評価の視野に入らず、公演自体も表層的な攪拌に留まらざるをえない。それらを「門外漢による見当違いのチャレンジ」と一蹴し続けるのならば、今後同様の手法で実施された公演への期待値は相応に下がり、関係者と物好きだけが劇場に足を運ぶことになる(もうそうなっているかもしれない)。重要だと思うので繰り返すが、音楽的理解を伴わない演出家やプロデューサーの役割を認めるためには、もっと広い視野から、何が機能不全で何が革新的だったのかを峻別する必要がある。
これらの前提を確認したうえで、筆者は結論として、『INTO THE WOODS』は公演として評価する水準に達していないと判断した。楽譜から音楽的に逸脱する意義が上演から見えてこない以上、カレーライスをカレー抜きで注文して出てきた料理を「カレーライス」ともはや呼べないように、この公演は「普通のミュージカル」の逸脱ではなく、不出来である。それを「異なる視点の導入」という語でごまかすことはすべきでないし、越境的な活動に奏功してきた先人たちに鑑みれば、「門外漢」という言葉で切り捨てることも不要である。
日本ミュージカルの基準のあいまいさ
さて、音楽的なクオリティを伴わないミュージカル公演が日本で成立しうるのは、クオリティの高低が客入りに決して影響しないことを主催者側が先刻承知しているからであり、さらに、集客性とは異なる指標をミュージカル業界が必要としていないからであろう。問題の一端は、専門性を有した評価者の不在、または、そのような評価を顧みてこなかった業界の構造にある。
包括的なフィードバックがこれまでまったくなかったわけではない。1999年に日本で再演されたミュージカル『リトル・ナイト・ミュージック』(演出:ジュリア・マッケンジー、音楽監督:宮川彬良、主催:TBS/ホリプロ)を観た扇田昭彦は、ソンドハイムの作風を「誰にでもアピールする作品でもないが、磨きあげた「ファイン・アート」としては輝かしい水準に達している」と紹介したうえで、当時の日本のミュージカル界は「近年急成長を遂げているとはいえ、まだ発展途上の段階を完全には抜け出していない」と一刀両断している13。続けて、扇田は上演を次のように評している。
『リトル・ナイト・ミュージック』は、ソンドハイム作品の中でももっともクラシック音楽色の強いミュージカルだから、出演者は難しい曲を惚れ惚れするくらいの歌唱力で歌いこなし、観客を堪能させてくれなくてはならない。その点、今回の配役は十分ではなかった。[…]五人の合唱アンサンブルはクラシック系の歌手をそろえていたから、安心して聴くことができたが、主役クラスの歌にはかなりバラつきがあった13。
今、こんな風にのびのびと批評することが困難になったと言ってしまっては懐古主義にすぎるが、広範な分野をカヴァーした扇田のような評者が今日少なくなったことが悔やまれてならない。上記の批評をまとめた『ミュージカルの時代』(2000)の中で、扇田は「音楽劇の表現の可能性をもっと柔軟に、間口を広く考える必要がある」14とはっきり述べていた。ここで言われている柔軟性や間口の広さの意義は、22年を経てもなお未収穫のまま、ツルばかりが野放図に伸びて目の前にぶら下がっている。
(2022/2/15)
- 梅田芸術劇場「ミュージカル『INTO THE WOODS』」
- 本稿の脚注で直接言及した研究のほか、代表的な先行研究には次のものがある。Gordon, J. Art Isn’t Easy, Da Capo Press, 1992; Banfield, S. Sondheim’s Broadway Musicals, University of Michigan Press, 1993; Swayne, S. How Sondheim Found His Sound, University of Michigan Press, 2005. なお、音楽に注目した研究のほかに、米ミュージカル史における位置づけや脚本への文学的アプローチなど、複数の試みがある。
- 本稿における音楽分析に際して、以下の論考を参照した:Hudlow, A. M., Harmony, voice leading, and drama in three Sondheim musicals, Dissertation, Lousiana State University, 2013; Purin, P. C. L., “I’ve a Voice, I’ve a Voice”: Determining Stephen Sondheim’s Compositional Style Through a Music-theoretic Analysis of His Theater Works, Dissertation, University of Kansas, 2011.
- 本稿では、分かりやすさを優先して「ライトモチーフ」という語を用いた。ただし、ソンドハイム自身は、「ライトモチーフ」を固定的で完成された主題という意味で用いており、作中でさまざまな形に自由展開し、時に断片化もする主題を「ディティー(ditty)」と呼んで区別していた(Mankin, N., “The PAJ Casebook #2: ‘Into the Woods,’” Performing Arts Journal, 11 (1), 1988: 46-66)。ただし、前掲したHorowitzの対談では「ライトモチーフ」という語が用いられていることも併せて確認したい。
- Horowitz, M. E., Sondheim on Music: Minor Details and Major Decisions, The Less is More Edition, Rowman & Littlefield (Kindle), 2019 [2010], Location 1430の図より抜粋。
- 同上 (Kindle), Location 1433.
- 記事公開時は「短4度」としたが、「完全4度」の誤りだったため、公開後に修正した。
- 前掲Horowitz (Kindle), Location 137.
- クランクイン「望海風斗、宝塚退団後“自分でいる時間”に戸惑いも “舞台で歌うことが好き”と改めて実感」、2021年12月29日。
- チケットぴあ「『INTO THE WOODS』羽野晶紀「この年になっても初めてのことができるのは、ありがたいこと」」2021年11月12日;Classy「望海風斗さん「今は、目標を探しているところ」卒業後の心境をインタビュー!」2021年12月18日;ANAN「瀧内公美、初ミュージカルに挑む 「人前で歌うのはお酒を飲んでいるときくらいでした」」2022年1月17日。
- エンタメOVO「【インタビュー】ミュージカル「INTO THE WOODS」古川琴音「悔いが残らないように」引っ越ししてまで臨んだオーディションで勝ち取った初ミュージカル」2022年1月7日;アイデアニュース「「心をえぐる演出に、そこまで行くかと」、『INTO THE WOODS』 福士誠治(上)」2022年1月11日。ただし「オーディションに呼ばれた」と古川が発言しているように、公募制ではなく、プロデューサーと演出家が選出した候補者の中から選ぶ形式のオーディションだったのではないかと推察される。
- NY Post, “Andrew Lloyd Webber: UK government wants musicals ‘without any singing,’” June 19, 2020.
- 扇田昭彦『ミュージカルの時代』キネマ旬報社、2000、p. 233.
- 同上、pp. 233-4.
- 同上、p. 298.