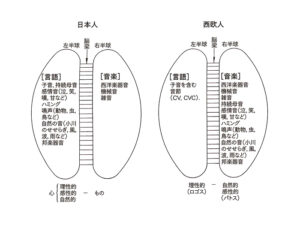プロムナード|ザ・ドリフターズの遺産|戸ノ下達也
ザ・ドリフターズの遺産
Successions from the drifters
Text by 戸ノ下達也 (Tatsuya Tonoshita)
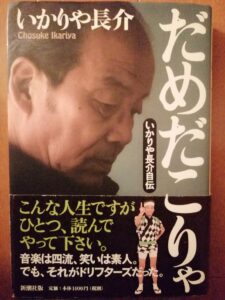 あなたの専門は何かと問われると、戦時期から戦後の社会と音楽文化の考察と答えている。その課題の根底には、市井の人びとの日常に息づく音楽文化のいとなみを見据えたいという意識がある。この日常に息づく音楽の典型が、J-POPなどのポピュラー音楽であり、労働や祭礼の音楽であり、また日常に密着した笑いや風刺、諧謔、社会批判の音楽だろう。これらの音楽は、人びとの心情や本音の表現にほかならない。
あなたの専門は何かと問われると、戦時期から戦後の社会と音楽文化の考察と答えている。その課題の根底には、市井の人びとの日常に息づく音楽文化のいとなみを見据えたいという意識がある。この日常に息づく音楽の典型が、J-POPなどのポピュラー音楽であり、労働や祭礼の音楽であり、また日常に密着した笑いや風刺、諧謔、社会批判の音楽だろう。これらの音楽は、人びとの心情や本音の表現にほかならない。
特に、笑いや風刺の音楽は、古川ロッパや榎本健一などの喜劇役者の表現、戦時期から現在に通底する「替歌」や「軍隊ソング」、戦後のクレージーキャッツやザ・ドリフターズなどのコメディアンの表現などに見られるように、その時々の社会状況と連動した音楽文化の表象だろう。中でも、ザ・ドリフターズは、1970~80年代の社会と音楽文化を考える上で、重要なポイントとなるアーティストである。
ザ・ドリフターズは、TBSテレビ「八時だョ!全員集合」やフジテレビ「ドリフ大爆笑」などのテレビ番組で、音楽と身体や装置を駆使した表現で数々のギャグ・コントを見せてくれた。2004年にいかりや長介さんが逝去され、2020年には惜しくも志村けんさんが逝去された現在、ライブでザ・ドリフターズの5人のコントを実見することは不可能になってしまった。
もっとも、2021年12月31日にテレビ東京系列で放映された「第54回・年忘れにっぽんのうた」では、加藤茶さん、仲本工事さん、高木ブーさんの3人が出演して「替歌メドレー」やコントを披露してくれた。3人でも、往時のドリフの片鱗を彷彿させてくれるひと時だった。
さらに、映像に残されたドリフのコントは、今でも私たちを魅了している。
ザ・ドリフターズの業績で私が特に注目するのは、「ドリフ大爆笑」での軍隊や戦後占領期の矛盾や風刺、哀惜をテーマとしたコントだ。これらの軍隊という戦時期の表象や、敗戦直後の社会を描いたコントは、ストーリーと音楽、ドリフのセリフや表情、所作が一体となって、抱腹絶倒の中にも批判や風刺に対する共感が内在する、実に奥深い芸術であり、次代に語り継ぐべき歴史のひとこまを刻印している。
このドリフのコントを活字で表現することはなかなかに難しいが、いくつか事例を挙げておきたい。
まずは「ドリフ五連隊」のコント。
起床喇叭で飛び起きるドリフ隊員だが、いかりや班長の点呼で、加藤隊員が起きていないことが判明。
怒ったいかりや班長は、宿舎で熟睡の加藤隊員の耳元で、《起床喇叭》《朝だ元気で》《競馬ファンファーレ》を立て続けに吹奏するが、加藤隊員は微動だにしない。
そこで、しびれを切らしたいかりや班長が、《Taboo》を吹奏すると、突然加藤隊員が起き上がり「ちょっとだけョ、あんたも好きねェ」の決めゼリフ。
ここで吹奏される楽曲が、場面の状況や時代を象徴する楽曲が厳選されていることはまさに脱帽だ。
次は「茶のラッパ手」のコント。
いかりや班長のもと、明日から訓練を行う部隊で、喇叭が吹けない加藤喇叭手に消灯喇叭を吹けとの命令。何とかドレミファの音が出て調子に乗って喇叭を吹きまくり、最後は《競馬ファンファーレ》でいい加減にしろ、とオチがつくコントでも、加藤喇叭手が消灯喇叭を「新兵さんは辛いんだね、また寝て泣くのかね…」という「替歌」で確認する場面が象徴的だ。
他にも敗戦直後のラジオ放送を想定した「素人のど自慢大会」のコント。
まず国民服姿の会社員という高木ブーが《長崎のザボン売り》、闇屋の志村けんが《銀座カンカン娘》、小学生の仲本工事が《とんがり帽子》、復員兵の加藤茶が《異国の丘》《あゝモンテンルパの夜は更けて》《長崎の鐘》《僕は特急の機関士で》などを絶妙なセリフと表情でオチを交えて歌唱する。特に戦災孤児と思わせてその実は違う仲本、戦争の辛酸な記憶がよみがえって歌えなくなる加藤のオチは、敗戦の混乱や諸相を見事に表現している。
「八時だよ!全員集合」は、いかりやが台本の企画構成による生放送だったが、「ドリフ大爆笑」は、いかりやによれば、「この番組がスタートした時のメインの構成作家は、前川宏司さんだった〔中略〕私は、ホン(引用者注・台本)を絶対に直さないことを約束した「たとえ、つまらなくても直しません。必ずそこで膨らませてみせます。その代わり、ちゃんとしたものを書いてください」(いかりや長介『だめだこりゃ』(新潮社、2001年)166~167頁)
「前川さんとの約束は実行することが出来たと思っている。私は彼のホンを直さなかったし、彼も気合を入れて、いいものを書いてくれた」(前掲書167頁)
とのことで、「ドリフ大爆笑」では、前川の見識がドリフの絶妙なコントとなって昇華したことが紹介されている。
また「ドリフ大爆笑」のオープニングテーマは、放送開始当初は《月月火水木金金》、その後はお馴染みの「ド、ド、ドリフの大爆笑…」で始まる《隣組》のメロディーの流用だったことも、また笑いや諧謔の中に、歴史の歩みを潜ませていたことを象徴している。
しかし台本がいかに優れていようとも、演じるアーティストの意識や理解、演技の力が無ければ、優れたコントにはならないだろう。そこには、やはりドリフのリーダーである、いかりやの戦争体験が大きく影響しているのではないか。
1931年11月に東京都墨田区で生まれたいかりやは、1944年春に静岡県富士市に疎開する。その後、父親が召集されて、「残された私たちは幸せどころではない。働き手を失い、ツテのあった軍需工場も没落したことも手伝って、たちまち困窮した。もはや着道楽だった祖母の着物を食料にかえて命をつなぐところまで追い詰められた。いわゆる「タケノコ生活」である」(前掲書19頁)という切羽詰まった生活環境にあった。そのような状況にあって、「(引用者注・1945年)三月十日は常にも増して、物凄くやかましい音を立てて、大群が飛んで行った。私は、これは只事じゃないとおもって、表に飛び出した。しばらくは音も消え、あたりは真っ暗闇だった。やがて東の空が明るく輝きはじめると、間もなく富士山の右側までオレンジ色に染まっていった。私は茫然と立ちつくした。このとき、美しくさえ見えたその光の下で、私たちの住んでいた東京下町はすっかり焼き払われてしまったのだ」(前掲書20頁)
いかりやの、疎開や、故郷が焦土と化した東京大空襲などの戦争体験が「ドリフ大爆笑」の軍隊コントの根底に息づている。
これらの軍隊コントは、いずれも音楽と演技、衣装や装置によって、軍隊という組織や戦争に対する矛盾や悲哀、批判が見え隠れしている。しかもコントから聞こえる音楽は、その時々の時代背景を忠実に再現したものであることも重要だ。これらのコントが受容された背景には、戦争体験や戦争を起因とする経験を共有する世代が社会の担い手だった1970~80年代のテレビ番組という事情があるだろう。同時代の共通体験があれば共感や納得が得られる反面、その時代背景への理解が無いと、この楽曲は何か、どのような意味があるのか、なぜ「笑える」のか理解できないだろう。
私たち、ドリフを知る世代の責務は、このドリフのコントの意味する時代状況やメッセージを発信し伝えることだろう。コントの中で、戦争の時代の歴史を凝縮し、その矛盾や悲哀、批判を表現したザ・ドリフターズの遺産をしっかりと受け止め、次代に伝えていきた。
(2022/1/15)