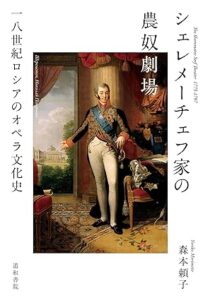Books | 批評の教室 ――チョウのように読み、ハチのように書く|西村紗知
批評の教室 ――チョウのように読み、ハチのように書く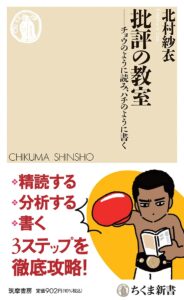
北村紗衣著
ちくま新書
2021年9月出版 902円
Text by 西村紗知 (Sachi Nishimura)
この頃自分がなにを書いているのかわからないと思うことが増えた。もっと言えば、なにを書いているのかはわかるけれども、この文章のことを総体として捉えたとき、文章が生み出されたあとのことも考えたりすると、結局自分がなにをしたことになるのかよくわからない、と思うことが多くなった。
本当に、書いているだけだ。もちろん読者がいないと成立しないことくらいはわかっている。批評対象の側の人々と交流したい気持ちがない。批評家同士ともできれば星の友情がいい。そうしたわけで、自分の文章から社交の契機がますます感じられなくなっている。
書くペースも明らかに遅くなった。今まさに書いているこの文章もすでにだいぶ締切が過ぎているのであるし、書き始める踏ん切りがつかなくなることが増えた。書くことが決まらないから書き始められないのではない。書くことは決まっている。むしろ、書くことが決まっているからこそ書き始められない。この頃は自分に書けることの限界をコンサート会場で悟ってしまうようになり、書く段階になって自分から文章表現や価値判断を絞り出すのにぎりぎりまで自分を追い込んだとて、会場で悟った以上の成果が出ることもなく、とにかく詮無い。
そんなとき、本屋で『批評の教室 ――チョウのように読み、ハチのように書く』を見かけた。「チョウのように読み、ハチのように書く」。なんて素敵な副題だろう。うだうだ言ってるばっかりじゃだめだ、こういう本を読まないと。
本書は初心者向けの批評の指南書で、主に小説と映画のための具体的な方法が示されている。
失敗しやすいポイントの例示が豊富なのでわかりやすい。「作品内事実認定の間違い」、「自分の性的な嗜好を冷静に把握しておくこと」、「テクストを社会背景の中で考える」、「「社会が決めた条件づけ」を暴くとイヤがる人がいる」などなど。
そして他にも特徴と言えそうなのが、日本の文芸評論の固有名詞がほとんど登場しないことだ。著者の専門のこともあってか、基本的には英米系の批評理論が根底にあるようで、日本の文芸評論・政治批評の界隈をにぎわせてきた批評家の名前は登場しない(小林秀雄とか江藤淳とか加藤典洋とか)。ある種健康な本である。私もたまには健康な文章を書きたいと思う。
本書の売りは、「■第四章 コミュニティをつくる――実践編」だろう。ここで著者とその指導学生とが、『あの夜、マイアミで』『華麗なるギャツビー』という2本の映画についての評をそれぞれ書き、互いの原稿に校正レベルのコメントを残しつつ、最終的にディスカッションをする。
作品を掘り下げて、互いにその体験を共有し合うコミュニティ形成に向けて、批評のメソッドが収束していく。コミュニティ形成に力点が置かれていることが、本書の意義深いところだ。自分がなにを書いているのかわからない私には、その意義が身に染みる。
【目次】
■プロローグ 批評って何をするの?
■第一章 精読する
1 精読とは?
ストーキングが許される場所はテクストだけ/精読の始まり/探偵になるために
2 精読のためにすべきこと
作品内の事実を認定しよう/作品が言っていることを読み取ろう/
トイレには死が潜んでいるので、少しだけパラノイアになろう/
ヒロインに優しくする男はだいたい口説こうとしている/
自分に邪な性欲があることを自覚しよう
3 精読のためにすべきではないこと
みんなウソをついているので、誰も信じないようにしよう/
ウソを見抜けるようになろう/とりあえず作者には死んでもらおう/
作者は死んでも歴史的背景は殺さないようにしよう
■第二章 分析する
1 批評理論とは?
巨人の肩の上に立とう/インフィニティ・ウォーの勝ち方/社会が決めた条件づけ/
一見簡単そうに見えて……
2 タイムラインに起こしてみる
デレク・ハートフィールド作戦/怪物を飼い慣らす/タイムワープにご用心
3 とりあえず図に描いてみる
人物相関図に起こしてみる/詩も図にできる/物語を要素に分解する/
『リア王』とおとぎ話/モチーフ早見表を作る
4 価値づけする
うまく書かれているか、ヘタに書かれているか/愛はどこからくるのか/
作品の「友達」を見つける/ネットワーキングの方法/ウサギは全部追いかけろ
■第三章 書く
1 書き始める
自分は芸術家だということは覚えておこう/一箇所から切り込もう/
タイトルは自分を縛るためにつける/暗い嵐の夜じゃダメ
2 切り口を提示し、分析する
うなぎをつかまえよう/食に殉じるごん狐/書けない時は照明を褒める(かけなす)
3 書くためのテクニック
自由にのびのび書いてはいけない/ほとんどの人間はラスキンじゃない/
ただの人間の感動には誰も興味はない/オレに話してんのか?/
ルビッチならどうする?/ルールすべてを無視しなさい/
あなたが蓮實重彦ならどんなに型にはめても結局は蓮實重彦になる/
人に好かれたいと思うのはやめよう
■第四章 コミュニティをつくる――実践編
1 『あの夜、マイアミで』
2 『華麗なるギャツビー』
■エピローグ
もっと学びたい人のための読書案内
参考文献
本書は小説や映画が具体的な批評対象として挙げられているけれども、たとえ音楽が批評対象でも、基本的には本書に書かれていることが守られるべきだと思った。
ただ、「■第二章 分析する」に関しては、音楽特有の(特に現代音楽)問題が絡んでくるので守りたくても難しいところがある。音楽からは「あらすじ」「題材」「テーマ」というものがそれ自体としてどうしても切り取りにくい。
「■第一章 精読する」で指南されていることは、総譜と録音があれば成立するだろう。作者が言っていることでなく作品が言っていることを読み取るべきというのは、当然そうだ。問題は、総譜も録音もなく、「あらすじ」「題材」「テーマ」といったものに自己省察を向けた音楽作品に対して、どう接するかということだ。そういう音楽作品が、現代音楽では大半を占めるのである。音楽批評の勝ち方はいつだって厳しいということが改めてわかった。でもそこは音楽批評の醍醐味ということで、個々人の執筆者がそれぞれの方法論で乗り越えていけばよいのだろう。
テクスト理論が音楽批評に適用可能かというのはそれほど問題にならない。むしろ問題になるのは、テクスト理論からコミュニティ形成に至るダイナミズムが、果たして音楽批評に可能か、というこの点だけだ。本書で示されている、自由に議論できる風通しのよいコミュニティというのが、音楽批評の世界でも実現できるかどうかだ。
本書を読んで実際に批評人口が増えるかどうかは私にはわからない。けれども、少なくとも本書は、批評という営為全体の記述に成功している。それが第四章の存在意義だ。「作品をもっと深く掘り下げたい」「作品についての感想を言い合いたい」という比較的自然な人間の欲求に対し、本書は批評という営為を一般社会というもっと大きなコミュニティに、いわばプレゼンしている。一般人と批評家の橋渡しといってもいいだろう。批評家の普段やっていることはこうだ、あなたは批評家が嫌いというけれども、意外と簡単そうでしょう、といったように。
そうして本書は実のところ、批評の生存戦略という切実な目的をそれとなく担っているように見える。個人的には、これで少しは批評を楽な気持ちで書ける社会になるといいのにな、と能天気に祈ってばかりなのだった。
(2021/10/15)