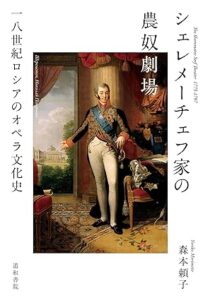Books|『虹む街』|田中里奈
虹む街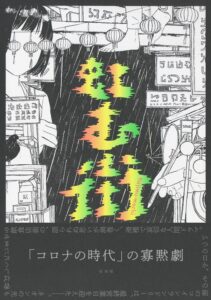
タニノクロウ著
Nijimu-machi
by Kuro Tanino
白水社
2021年6月出版
2400円(税別)
Text by 田中里奈(Rina Tanaka)
『虹む街』――上演版と書籍版
2021年6月にKAAT 神奈川芸術劇場の中スタジオにて上演された、庭劇団ペニノ主宰・タニノクロウによる新作『虹む街』の書籍版である。三度目の緊急事態宣言下で出版されたこの本は、上演版と同様、極めて独特な印象を与えてくる。
1時間半の上演版では、スタジオ内に造り出された、横浜・野毛を思い起こさせる雑然とした飲食店街の中に、日常的すぎて非日常的にすら見える生活の断片の数々が現出していた。ただし、そのごくささやかな複数の出来事が、横に長い舞台の上手と下手の端々で、あるいは精緻に作られた死角の多い舞台美術のどこかで同時多発的に起こるので、それらすべてを視界に収めることは不可能だった。私たちが日常の出来事をくまなく観察しないのと同じように、神の視点を諦めて、うまく折り合いを付けるほかなかった。よくぞKAATで上演したと思う反面、観る人を選びそうな作品でもあった。
上演版を観続けるのがしんどかった人にとって、書籍版はちょうどいいガイドブックになるかもしれない。どこをどういう順番で観ていけば物語の道筋が見えるのかを、書き手自らの視点で示してくれるからだ。
ただし、この本は上演版の単なる脚本では決してない。何せ、上演版には登場しなかったキャラクターや場面がさりげなく挿入されている――とはいえ、戯曲の再現を必ずしも目指さない今日の演劇で、そういうことはたびたび起こるのだが。
なによりも、この本の特徴は、小説風の体裁で実際とは異なった(またはコロナ禍におけるさまざまな制約が無ければ、ひょっとしたら実現したかもしれない)上演の内容を叙述しつつ、作者であり、演者であり、そして観客でもある〈誰か〉の率直な視点を、諸所に「滲ませ」ている点にある。
読み進めていくと、複数の視点から描き出される上演と観劇体験に、私がKAATで見た上演の断片的なイメージと、それを客席から眺めていた私の個人的な体験が、重なり合ったり、あるいは異なる別個のものとして対置されたりする。一貫した筋がなく、行動と発話の断片が不意に現れては消えていく上演は、朝に見た夢を思い出しているかのような、現象学的な知覚が伴った。上演中にできることと言えば、「なんだこれは?」と思っている自分と周りの観客の反応を客観的に眺めながら、不可解や退屈を覚えた時間も、それに付き合っている自分の行為も、ひっくるめて楽しむことくらいだ。だから、書籍版の冒頭を読んだとき、「そうそう、そう思っていた」と膝を打ってしまったのだ。
それにしても全くセリフがない作品だ。[…]セリフのほぼない作品を割と抵抗なく見られているのはやはりコロナのせいなのか。[…]私はどうだ?私は今日……喋って……ないか。劇場の受付で自分の名前を伝えたくらいか。コンビニでも最近は声を出さなくなったな。そんな状況に慣れきってしまったのか。(1)
この本には、コロナ禍の日常から地続きのところで、この作品を生み出している〈誰か〉――もちろんタニノクロウのことなのだが、テキストはタニノ自身のことにも他人事のように言及するので、あえてここでは書き手の視点を特定の人物と思い込まないことにする――の思考の不連続な連続がある。「舞台の幕が無事に上がりさえすれば、非日常がそこにある」ような、私たちの多くが「舞台」と聞いて真っ先に想像するような劇場公演とはすっかり対照的である。
わけがわからなさすぎる演劇(の本)
 『虹む街』は、良くも悪くも「ポストドラマ的」だ。ハンス=ティース・レーマンが1999年に『ポストドラマ演劇(Postdramatisches Theater)』で提唱したこの概念には、ごく限られた専門書や批評に目を通してきた私の理解の範疇において、次の2つの意味合いが備わっている。まず、ドイツ現代演劇を中心に広く理解されている意味――近代ヨーロッパで生まれ、今もなお西洋演劇の中央に根付いている「ドラマ」(戯曲文学に基づいた演劇)の「後(ポスト)」にやってきた、1960-70年代以降の脱措定的(2)な演劇の傾向――があり、さらに、前者の意味が世界的な演劇学やパフォーマンス研究に影響を及ぼした結果、今日のドイツ語圏でありがちな「わけがわからなさすぎる演劇」に対して送られる、肯定とも否定とも取れる投げやりなコメントとしての二次的な意味である(3)。
『虹む街』は、良くも悪くも「ポストドラマ的」だ。ハンス=ティース・レーマンが1999年に『ポストドラマ演劇(Postdramatisches Theater)』で提唱したこの概念には、ごく限られた専門書や批評に目を通してきた私の理解の範疇において、次の2つの意味合いが備わっている。まず、ドイツ現代演劇を中心に広く理解されている意味――近代ヨーロッパで生まれ、今もなお西洋演劇の中央に根付いている「ドラマ」(戯曲文学に基づいた演劇)の「後(ポスト)」にやってきた、1960-70年代以降の脱措定的(2)な演劇の傾向――があり、さらに、前者の意味が世界的な演劇学やパフォーマンス研究に影響を及ぼした結果、今日のドイツ語圏でありがちな「わけがわからなさすぎる演劇」に対して送られる、肯定とも否定とも取れる投げやりなコメントとしての二次的な意味である(3)。
ポストドラマ的という視点を書籍版『虹む街』に投じてみると、これを小説か戯曲かという二項対立で切り分けようとする試み自体が誤りであるように思われる。なぜなら、既存の区分を超えたところに生じてきた新たな演劇的フォーマットもまた、「ポストドラマ的」なもののひとつとして論じられてきたからだ。もはや戯曲と呼ぶことのできない「演劇テキスト(Theatertext)」(4)の存在に鑑みれば、『虹む街』に対する「言語によるフィクションの新たなジャンルの可能性」という佐々木敦の評にも頷ける(5)。
これまでのタニノ作品では、舞台美術や音楽、俳優の身体の現前に、演劇テキストと同等かそれ以上の重きが置かれていた。非日常的であると同時に、執拗なまでに作り込まれた細部の生々しさが生み出すシュールレアリスティックな世界観は、日本における今日の演劇の中でも非常に独特だ。書籍版では、劇場に入る前から叙述が始まり、上演(で起こらなかったこと)の描写、そして上演中の連想や余所見――「そういえば隣のおっさん開始十分からずっと寝てたな。気持ちは分かるよ。「人間ドラマ」と捉えるにはハードル高いよなこれ」(6)――のシームレスな接続が、タニノ「らしい」テイストだと思わせる。実際、この本を注意深く読んでいくと、書き手の連想の中に『ブレイドランナー』まで出てきて、『虹む街』という創作活動の総体がタニノによる昨年のVR作品と通底していることが分かる。演劇というジャンルに位置づけられながらも、インスタレーションや美術作品との親和性も見られてきた彼の作風からすれば、テキストという場における観劇体験の創出もまた、驚くべきではない。あるいは、コロナ禍において活動の自粛と制限、そしてさまざまな形での非対面へのシフトを余儀なくされてきた劇場という場の「滲み」でもあるのかもしれない。
「コロナの時代」の寡黙劇
ところで、この書籍の帯には、〈「コロナの時代」の寡黙劇〉という文句が付いている。実際、書籍版『虹む街』ほど、コロナ禍の演劇を体現した作品はないと思う。
ただし、私はまだ、「コロナ禍の演劇」という語を素直に受け容れることができずにいる。コロナ以前の私の日常には、演劇が一定の地位をたしかに占めていた。そこに起こった取り返しのつかない変化を、そんな風に、さも当然のパラダイムシフトのように言い換えないでほしいと思ってしまう。だが、その反面、ペストの流行が芸術活動とその成果に否応なしに痕跡を残してきたことを私たちは知っている。だから、今日の演劇がきっとそう呼ばれる時代も来るのだろう。
コロナ禍の今日に演劇をやることはしんどい。それを観る側もしんどい。なのに、私たちは余りにもこれまで通りにやろうと踏ん張りすぎている気がしてならない。その現実に両足を踏ん張りながら、この『虹む街』を手に取った時、書き手の、時として非常に辛辣なのに、時にナイーヴでロマンチストな心情の吐露の素直さが目に留まる。それは、必ずしも「弱さ」として切って捨てられるべきものではない。
 そこで思い出されるのが、2020年11~12月に世田谷パブリックシアターで上演された『幸福論』の公演プログラムに、瀬戸山美咲が寄稿した次の言葉である。
そこで思い出されるのが、2020年11~12月に世田谷パブリックシアターで上演された『幸福論』の公演プログラムに、瀬戸山美咲が寄稿した次の言葉である。
新型コロナウイルスはもともとあった亀裂をさらに大きくしました。ぎりぎりのところで踏ん張っていた多くのものたちが失われました。それでも私たちはまだ「強くなれ」と言われ続けている気がします。でも、必要なのは弱いままで生きられる世界だと思います。(7)
『虹む街』のテキストは、作品のタイトルにもなっている「虹む」という語についてもさまざまに考察を巡らせ、その中で、雨粒のようにきらりと光る言葉をこぼしていく。「全ての登場人物が街の中で、それこそ「成果・報酬のない営み」に時間を使い、生きているじゃないか。そして、私はそこに極めて人間的な何かを見出そうとしているのだから。」「この作品との付き合いは、観ている間に不随意に溢れ出てしまう言葉と、それに抗おうとする感性との戦いのように感じる[…]。ことばは放散を許された兵器のようなものだ。またはウイルスのように自己複製と変異を繰り返す」。
『虹む街』は演劇の変異かもしれない。だがそれは、「ニューノーマルの演劇」などと、演劇史の新章を飾るキャッチーなタイトルではない。そうではなく、進退窮まった状況――「この悲惨な社会状況下で、このような多くの人が共感出来ないものを世間は許すだろうか。言語化することの難しい、解釈を拒むような作品は生きていくことが出来るのだろうか」(8)――における演劇の自己否定的な自己言及の果てに生まれ出た何かだ。だからこそ、批評されるべき作品なのだと思う。
——————————————-
(1) タニノクロウ『虹む街』白水社、2021年、27頁。
(2) 「脱措定的」という語は、平田栄一朗による発表「脱措定的な差異としてのポストドラマ演劇」(日本演劇学会分科会西洋比較演劇研究会例会、2017年12月16日)に基づく。
(3) 2021年のベルリン演劇祭テアータートレッフェン(Theatertreffen)で注目すべき10作品に選ばれたゴブ・スクワッド『ショウ・ミー・ア・グッド・タイム(Show Me A Good Time)』では、出演者の一人がベルリンに移り住んでから「ポストドラマ的演劇にはもうウンザリ(I was sucked in postdramatic theatre)」と発言したのは――もちろん冗談としてだが――記憶に新しい。
(4) Poschmann, Gerda, Der nicht mehr dramatische Theatertext: Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramaturgische Analyse, De Gruyter, 1997.
(5) 佐々木敦「タニノクロウ『虹む街』――フィクションの新たな可能性」『文學会』2021年8月号、pp. 362-363.
(6) 注1同書、125頁。
(7) 世田谷パブリックシアター「現代能楽集X『幸福論』~能「道成寺」「隅田川」より」、2020年11月29日~2020年12月20日。
(8) 注1同書、127頁。
(2021/8/15)