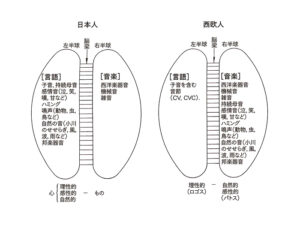漢語文献学夜話|Enemies and Allies|橋本秀美
Enemies and Allies
Text by 橋本秀美(Hidemi Hashimoto)
一
数年前に恩師倪其心先生の文集編集の計画が起動し、同門諸先輩のご尽力で、昨年既に集められる限りの文章は集められていたが、その中に一篇だけ日本語のものが混じっていた。倪先生は、東京大学で一年教鞭を執られていた間に、学会講演をされた。中国語の講演原稿を日本語に翻訳したものが、学会機関誌に掲載されているのだが、原稿は既に散逸してしまったようだ。中国語の文集に日本語の講演録が入るのも奇妙だし、殆どの読者にとっては読解不能なので、私と家内で中国語に翻訳し、三日前にようやく完成させることができた。
翻訳に時間がかかったのは、諸事情で中々まとまった時間が取れなかったからだが、私自身、内容に強い興味を引かれなかったことも、延び延びにしてしまった原因だ。倪先生の講演は、中国古典文学の世界では、阮籍の『詠懐詩』が高く評価される一方で、玄学(魏晋の王弼・何晏らを代表とする思想で、存在も概念も、全ては「無」が根本だとし、「無」を体得するべきことを主張した。)には否定的評価しか与えられていないが、矛盾してないか?と問う。そして、『詠懐詩』は正に玄学思想を体現した作品であることを論じられ、『詠懐詩』を玄学から切り離して評価する定説は否定されるべきだ、とされた。非常に説得力が強く、真にその通りと思われるのだが、何やら当たり前のことを回りくどく説明しているような気がしてしまった。
思うに、前世紀後半の社会主義中国において、形而上学や玄学は、悲観的・消極的態度で現実を受け容れ、階級闘争の闘志を殺いでしまう反革命的思想として批判の対象だった。だから、文学史上無視できない重要作品である『詠懐詩』には高い評価を与えながら、玄学は駄目だけど、という限定が自然と付けられるようになっていたのだろう。文学的評価が、政治的評価によって歪められていた、と言ってもよい。倪先生は、物事の本質を考える強い能力を持っておられたので、そうした一種の欺瞞状態を指摘せずには居れなかったのであろう。政治状況が変わって、現在では玄学にも肯定的評価が与えられるようになっているから、倪先生が問題とされた問題は既に存在せず、逆に何をわざわざ議論しているのか、という印象を私も持ってしまっていた。翻訳し終えて、一通りきちんと読んだ今にして思えば、問題の問題は別として、倪先生の論考は『詠懐詩』と玄学の関係に丁寧な説明を与えたものとして読むに値する。
二
学者が論文を書く時は、大抵他の学者たちを読者として想定している。出発点は学界の共通認識で、それを修正増補して、よりよい認識を提供しようとする場合が多い。出発点としての学界は、時と所によって様々なので、前提となる共通認識も異なるが、一人の学者は、自らの属する学界の常識から自由になることが難しい。倪先生の三十年前の論考は、現在の学界の常識で見ると「何を今更」と思われかねないが、三十年前に『詠懐詩』を論じようとすれば、まず当時の学界の前提が矛盾していることから話を始めざるを得なかったということだろう。
私自身も、随分長い間「学界の常識」と格闘してきたように思う。傍から見れば独り相撲かもしれないが、本人にしてみれば、常識が間違いだということを認めてもらえなければ、自分の考えは全く理解されないということになるので、どうしても常識批判をせざるを得なかった。学界の常識では、清代の学術は漢学と宋学に分かれ、宋学が主観的に道徳・倫理思想を論じることを主としたのに対し、漢学は客観的で論理緻密な考証を旨として漢代の学術を復興せんとしたとされる。しかし実際には、清代「漢学」のものの考え方は、漢代の学者たちとは全く異なり、むしろ宋代の学者たちと共通している。例えば、王引之の『経義述聞』は清代「漢学」の代表作として広く認められ、最高級の評価を与えられているが、多くの観点は宋・元の学者が既に指摘しているもので、論証材料を加えたりしてはいるが、アイデアはパクリだと言われても仕方ないものだ。だから、私は清代の学者たちは、鄭玄の学術を正しく理解していない、と言わざるを得なかった。前世紀九十年代の古典学術研究の世界において、清代の「漢学」者たちは天高く輝く星々であり、「彼らは全く分かっていない」という私は、天に唾する者のように見られがちだった。幸い、この二十年で古典学術研究は格段に進歩し、多くの若い人たちが成果を積み重ねている結果として、清代「漢学」を無暗に持ち上げる風潮には既に歯止めがかかってきたから、もう私が吠える必要も無い。
三
学生に教えられた、印象深い思い出をご紹介したい。現在の学界の宋代版本に関する常識は、趙万里の『中国版刻図録』によって作り上げられたものだ。趙万里は王国維の弟子だが、若い頃から版本学の第一人者として活躍し、宋版の全貌を見通す認識の枠組みを作り上げた。その認識は、調査・研究した版本の種類が増えるにつれて、どんどん変化し、より精確なものとなっていったが、その最終的認識が1960年の『中国版刻図録』に示されている。残念ながら極左社会において趙万里は迫害を受けて亡くなってしまい、その版本学の成果も長く顕彰されることがなかった。八、九十年代から、版本学が再び注目されるようになり、影印本が続々と作られ、教科書も何種類も出版されるようになったが、少なくとも宋版に関して言えば、『中国版刻図録』の枠組みを踏襲しながら、それが趙万里の個人的認識であったことを忘れ、認識そのものに何らの発展も無いどころか、その水準はむしろ低下していた。
私は『中国版刻図録』の宋代部分を少し丁寧に読む機会が有ったので、趙万里の認識の変化の跡を辿り、彼の探求過程から多くのことを学ぶことができた。偶々、私が編集委員に名を連ねていた雑誌『版本目録学研究』が、趙万里生誕百十周年の特集をやることになり、趙万里の思い出などを綴った文章が何本か集まってきたが、趙万里の版本学を正面から論じた文章が無かったので、蛮勇を振るって家内と『中国版刻図録』の書評を書いてみた。出版後半世紀を経ているが、この本は未だに常に立ち帰るべき出発点であり、しかもそこには大量の重要な問題が未解決のまま残されていることを、様々な角度から具体的に指摘し、自分としては満足の出来だった。そして最後に、版本学の教科書なんぞ読むだけ無駄だから、さっさと捨てて『中国版刻図録』を読め、というような一言を加えた。尤もらしく受け売りをひけらかすだけの教科書の類に対する嫌悪感は、吐き出さずには居られなかったのだ。
書いたものを、まず学生に読んでもらった。その学生は、「大変結構だけど、最後は頂けない。読者に八つ当たりしても、読者を不快にするだけではないか。」と言ってくれた。ハッと目が覚めた思いで、最後の一文を書き換えた:「像這樣神奇的書,人間少有,能不喜愛嗎?(こんな奇跡のように素晴らしい本、好きにならずにいられようか)」。日本語だとちょっとぎこちないが、この一文は気に入っている。
四
南北朝・隋・唐初の経学書から勉強を始めた私は、隋の劉炫らによって南北朝の学術が根底から否定されるのを目の当たりにした。それは、具体的な観点の否定ではなく、学術方法のお約束を根底から否定する学術革命で、それまでの学界で高く評価されていた議論が、全く価値の無い冗談に変わってしまった。学術の前提は時と所によって変わる。その結果、「正しい」学説も変わらざるを得ない。つまり、「正しい」学説は真理ではない。だから、そのことを書いた学位論文の題記に、私は「学術の為に読書するなんて御免だ、読書の役に立つなら学術も悪くないが」というようなことを書いた。
何だかんだと言いながら、その後二十年、結局少なからぬ論文を書いてきたが、今般在外研究で、ごく一部分ながら『礼記』鄭注を読む機会を得て、ようやく読書の道に戻ってこれたような気がしている。今や、私にとっての問題は単純な読解で、それをどう解釈するか、そこに現れた学説をどう理解するか、どう評価するか、等々の問題には関わらない。読解は、読んで鄭玄の考えを知ることだ。
他人の考えが分かるというのはどういうことか?本当に分かるのか?分かっているかどうか確かめる方法は有るのか?そういった根本的な疑問には、答えることができない。
思うに、鄭玄注を読んで、鄭玄の言っていることがよく分からない、ちょっとすっきりしない、或いは、よく分かった、完全に分かる、という感覚は、社会生活を送る人間に本質的に備わる言語コミュニケーション能力に基づくもので、この感覚を否定されてしまえば、日常生活も成り立たなくなる。そこを疑って、反省的分析を加えていくことは、哲学的に意味有る探究だが、その為に実際のコミュニケーションを否定してしまっては本末顛倒だ。この文はこういう意味だ、という私の読解は、それが見当はずれでなければ、多くの人にも納得してもらえる。唐代以降の多くの学者たちが皆鄭玄の意図を曲解していて、私の理解だけが正しい、と言えば、常軌を逸した誇大妄想と思われかねないが、そうではない。昔の学者よりも私の方が能力が高い、という訳ではなく、昔の学者たちはそれぞれ自分の学術を前提に鄭玄の注を利用するばかりで、私のように鄭玄の気持ちを知りたいという欲求は持っていなかった、というに過ぎないからだ。
今や、私は自分の学説体系も学術の前提も必要としない。もともと無学だから、そんなもの持っていないが。勿論、空っぽの自分がテキストに向き合うというのは言い過ぎで、読解する私には、当然最低限の言語・文化情報が備わっていなければならない。それでも、私の読解した内容を他人に説明する際には、既存の学説体系や学術の前提を借りる必要が無い。ということは、私の読解の結果見えてくる世界が、現在の学界の常識と如何に懸け離れたものであろうと、私は全く気に掛けることなく、ただ読解を進めて行けばよいということだ。
齢五十五を前に、終に私は自由を得て、学界の常識は私の敵ではなくなった。敵が消えた代わりに、今や私は時代や場所を越えて、中国古典を読む全ての人々と同じ道を歩いている。
(2021/4/15)
◆編集部より
本コラムは橋本氏のご都合によりしばらく休載となります。
—————————
橋本秀美(Hidemi Hashimoto)
1966年福島県生まれ。東京大学中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系副教授、教授を経て、現在青山学院大学国際政治経済学部教授。著書は『学術史読書記』『文献学読書記』(三聯書店)、編書は『影印越刊八行本礼記正義』(北京大出版社)、訳書は『正史宋元版之研究』(中華書局)など。