小人閑居為不善日記|世界の法則を回復せよ――本格ミステリと陰謀論| noirse
世界の法則を回復せよ――本格ミステリと陰謀論
Restore the Rules of the World
Text by noirse
1
 お前は誰だ?
お前は誰だ?
おれは何者なんだ?
いったいどうなってるんだよ?
真実はこうさ
嘘にきまってるぜ
真実は存在するんだからな
2000年代半ばからインディーロック界で頭角を現した、アリエル・ピンクの〈Lipstick〉の一節だ。女の子を付け狙う殺人者の歌だが、曖昧な世界でもがき苦しむ者の混乱が、迷宮めいたサイケデリック・サウンドによく合っている。
ホワイトハウス襲撃事件当日。ドナルド・トランプが彼の支持者たちに向けて行った集会の中にアリエルと、彼と親交のあったシンガー、ジョン・マウスがいた。突入には参加しなかったようだが、レーベルは彼らに契約破棄を突きつけた。
ロックミュージシャンにはアナーキーな政治信条を持つ者も多い。トランプのように型にはまらない過激な非・職業政治家にシンパシーを抱くこともあるだろうし、そう不思議なこととも思わない。
むしろ驚いたのは、日本にトランプ支持者が多く存在するという事実だ。ネット上でよく見かけるのはおろか、トランプ支持のデモまで繰り広げている。
支持者の中には著名人もいる。何故か音楽家に目立つ傾向があり(わたしの観測範囲の問題かもしれないが)、有名どころではラッパーのKダブシャインやジャズミュージシャンの菊池成孔が支持を表明している。
とはいえ彼らも、選挙が奪われたなどの陰謀論を鵜呑みにしているわけではない。しかし例外もある。去る1月、ベテランのミステリ作家島田荘司がfacebookに投稿した記事が話題となった。トランプ支持はおろか、バイデンの勝利は不正選挙の結果だと論じていたためだ。
もともと島田の作品や発言には反米保守思想やミソジニーの気配が横溢しており、いくつか手掛けていたノンフィクションも客観性に疑問が残るなどの「伏線」はあったため、読者は失望こそすれど、不思議には思わなかったようだ。わたしも同様だったが、むしろ今回の件で考えさせられたのは、島田が牽引してきた本格ミステリというジャンルが、そもそも陰謀論と親和性があるのではないかということだった。
2
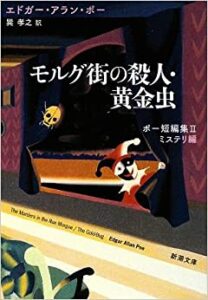 本格ミステリというジャンルは二面性を持つ。史上初の推理小説とされる〈モルグ街の殺人〉(1841)の作者、エドガー・アラン・ポーを見ると分かりやすい。
本格ミステリというジャンルは二面性を持つ。史上初の推理小説とされる〈モルグ街の殺人〉(1841)の作者、エドガー・アラン・ポーを見ると分かりやすい。
ポーの作品を大雑把にふたつに分けてみよう。片方は〈アッシャー家の崩壊〉や〈黒猫〉などのゴシック小説。もう一方は〈モルグ街の殺人〉や〈盗まれた手紙〉などの推理小説だ。
ゴシック小説は、神秘的で超自然的な、あえて言えば「野蛮な」領域にある。かたや推理小説は、基本的にそうした「迷信」を科学的な思考で撤廃するという意識の上で書かれている。19世紀は啓蒙思想が定着し、産業革命により社会が激変し、無神論者が増加した、合理的思考が持てはやされた時代だ。推理小説は、実に19世紀的な小説と言っていいだろう。
しかしこれをもって推理小説を「合理的思考が野蛮な迷信を駆逐せんとしたジャンル」と位置付けるのは早計だ。前述の通りポーはゴシック小説も手掛けており、その数は推理小説よりずっと多い。きっと読者も、合理的思考を快哉を持って受け入れながら、こっそりとゴシック小説を紐解き、昏い歓びを味わっていたに違いない。
 不測の事態が起きたとき、現実的な打開策を模索する一方で、奇跡的な解決を願って神に祈る。人間とはそういう矛盾した生き物だ。ポーだけではなく、どんな推理作家も多かれ少なかれ合理的思考と野蛮な想像力を併せ持っているのだ。
不測の事態が起きたとき、現実的な打開策を模索する一方で、奇跡的な解決を願って神に祈る。人間とはそういう矛盾した生き物だ。ポーだけではなく、どんな推理作家も多かれ少なかれ合理的思考と野蛮な想像力を併せ持っているのだ。
これは別にわたしの持論ではなく、ミステリ読者なら「何を今さら」という内容だ。島田荘司も自身の創作論でポーを引き合いに出しながら、本格ミステリは「幻想的謎と、高度な論理性を有する形式」だと説いている(〈本格ミステリー論〉)。
山奥の古びた洋館。嵐の夜の密室殺人。快刀乱麻を断つが如き名探偵。二次大戦中に黄金時代を迎え、乱歩や正史らが日本に定着させた本格ミステリの様式は、いつしか古めかしいものとして遠ざけられていた。それが80年代後半になり、フレッシュな新人が次々とデビューして、再びの最盛期を迎える。これは俗に「新本格ムーブメント」と呼ばれている。
その仕掛け人のひとりが、《占星術殺人事件》(1981)でデビューした島田荘司だった。高度経済成長が頂点を迎える中、島田は野蛮な想像力を爆発させ、シーンにインパクトを与えたのだ。
3
 数年後、新本格ムーブメントの中核のひとりである法月綸太郎が、「後期クイーン的問題」なる問いを提示した(〈初期クイーン論〉)。批評家の諸岡卓真はこう説明する。
数年後、新本格ムーブメントの中核のひとりである法月綸太郎が、「後期クイーン的問題」なる問いを提示した(〈初期クイーン論〉)。批評家の諸岡卓真はこう説明する。
その結論を敢えて乱暴にまとめてしまえば、〈探偵はどんなに論理的に推理を行ったところで、唯一絶対の真実には到達できない〉〈完全な本格ミステリは存在しない〉ということになる。
(諸岡卓真《現代本格ミステリの研究》)
限定状況で他殺体が発見され、現場には血痕のついたハンカチが落ちている。探偵はハンカチの持ち主を犯人と特定し、事件を解決する。しかしそのハンカチが真犯人が探偵を欺くために仕掛けた「偽の手がかり」だったら、この解は成立しない。
探偵は手がかりの真偽を完全に把握することはできない。それは神の次元に立つ作者も同じだ。たとえ作品が真犯人の自白で終わったとしても、その解決が真実であると、作家自身でさえ保証することはできない。本格ミステリの代表的作家エラリー・クイーンがキャリア後期にこのジレンマに陥ったことにより、「後期クイーン的問題」と名付けられた。
これはあくまで抽象的な議論に過ぎず、実際の創作には関係ないとしりぞけた作家も多い。たしかにそうかもしれない。議論も今では沈静化している。けれどこの問題、わたしは今でも強く印象に残っている。何故なら後期クイーン的問題は、世界観の問題でもあるからだ。
この手がかりは本物なのか、偽物なのか。こういった思考はフィクションの中だけに鎮座するものではない。この報道は正しいのか。SNSで拡散されているこの記事は釣りではないのか。目の前に広がるこの世界は、はたして本物なのか。「真犯人」が仕掛けた、かりそめの現実なのではないか――。
ミステリの根底には世界への懐疑が横たわっている。目の前で壊れつつある世界を合理的思考で繋ぎ止めるのが推理小説、とりわけ本格ミステリというジャンルだ。そしてそれは、現実世界で生きることの縮図でもある。
4
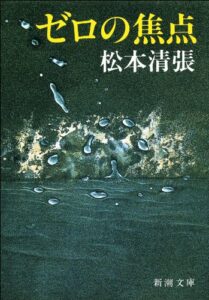 世界の法則を回復せよ。黒沢清の映画《カリスマ》(1999)に登場するフレーズだ。人智を越えた状況で人が殺されるとする。神の御業か悪魔の所業か、周囲の人間の常識は崩壊する。探偵はそれを合理的に解決し、彼らの「世界の法則を回復」させる。
世界の法則を回復せよ。黒沢清の映画《カリスマ》(1999)に登場するフレーズだ。人智を越えた状況で人が殺されるとする。神の御業か悪魔の所業か、周囲の人間の常識は崩壊する。探偵はそれを合理的に解決し、彼らの「世界の法則を回復」させる。
そうした本格ミステリの「回復」という側面を、一部の作家は主題へと接続していった。たとえば松本清張は探偵(刑事)の解決によって国家や企業の暗部を告発する作品を集中的に書き、社会派ミステリというジャンルの発展に寄与した。探偵の力によって社会の法則を回復させるというわけだ。
 もっと個人的なケースもある。《姑獲鳥の夏》(1994)などの京極夏彦の妖怪シリーズは、個人の世界認識の歪みを妖怪に取り憑かれた状態だと置き換え、それを推理による解決で「祓う」というように変換してみせた。本格ミステリが持つ形式は、人間の病理を回復させる役割も果たすのだ。
もっと個人的なケースもある。《姑獲鳥の夏》(1994)などの京極夏彦の妖怪シリーズは、個人の世界認識の歪みを妖怪に取り憑かれた状態だと置き換え、それを推理による解決で「祓う」というように変換してみせた。本格ミステリが持つ形式は、人間の病理を回復させる役割も果たすのだ。
今回の島田荘司の件は、陰謀論に絡め取られたのもさることながら、トランプ支持という点でも失望を招いている。島田も社会派ミステリをいくつも上梓しており、弱者に寄り添う姿勢が特徴だった。それがマイノリティを貶めて憚らない人物を支持したのだから、反発は免れ得まい。
けれど、島田は世界の法則の破壊と回復を繰り返すうちに、異なる世界に踏み込んでしまったと考えることもできる。後期クイーン的問題を踏まえれば、真実を保証するものなど何もない。不確かな世界の中で真実の誘惑を退け続けるのは、きっと難儀なことだろう。
 後期クイーン的問題が議論されていたのと同時期に、アンチミステリというジャンルが小さな流行を呼んでいた(麻耶雄嵩《夏と冬の奏鳴曲》など)。定義するのは厄介だが、ここでは簡単に「ミステリの底を割ったミステリ」としておこう。批評家の巽昌章は、アンチミステリについてこう論じている。
後期クイーン的問題が議論されていたのと同時期に、アンチミステリというジャンルが小さな流行を呼んでいた(麻耶雄嵩《夏と冬の奏鳴曲》など)。定義するのは厄介だが、ここでは簡単に「ミステリの底を割ったミステリ」としておこう。批評家の巽昌章は、アンチミステリについてこう論じている。
それは要するに、「本格推理小説は論理による技巧の遊戯に過ぎないが、その論理を徹底した果てに何か別の場所に抜ける門が開いているのではないか」という発想の象徴だった。
(巽昌章《論理の蜘蛛の巣の中で》)
いくら論理を積み重ねていっても、そこに出口はない。何処までいっても答えはなく、問いを繰り返すしかない。アンチミステリにはその無限回廊からの解放という側面があるのだと、巽は述べている。
これはまるで人間の生そのものだ。大半の人は、答えのない問いを自分に突きつけることなどしない。どうにかやり過ごしながら、目の前の生活を追いかけることでなんとか生きている。しかしそうできない人もいる。満たされない人生に不満を抱き、目先の回答に安易に飛びつく人もいれば、自問自答に苦しみ、謎のスパイラルから降りてしまった者もいるだろう。陰謀論に魅了されるとは、そういうことではないだろうか。
島田荘司の問題からは、失望ややりきれなさよりも、ミステリ作家の業、そして人間の業をあらためて感じてしまう。合理的思考と、野蛮な想像力。どちらも人間には必要だ。陰謀論が放つ奔放さは、野蛮な想像力そのものだ。そう考えると、どうしても陰謀論者を笑うことができないのだ。
(2021/2/15)
———————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


