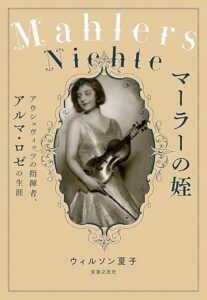Pick Up (20/11/15)|『マーレリアーナ』船山隆|丘山万里子
『マーレリアーナ Maleriana』船山隆
Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
 音楽学者、評論家の船山隆が春の叙勲記念に『マーレリアーナ』(新刊私家本)を上梓した。1980年代に発表したエッセイ、論文、新聞雑誌原稿、シンポジウム記録を全5章にまとめたもの。内容は以下。
音楽学者、評論家の船山隆が春の叙勲記念に『マーレリアーナ』(新刊私家本)を上梓した。1980年代に発表したエッセイ、論文、新聞雑誌原稿、シンポジウム記録を全5章にまとめたもの。内容は以下。
第1章 マーラー評伝(『マーラー』カラー版 作曲家の生涯/新潮文庫)
内容略
第2章 マーラー紀行
異邦人マーラー、ヒトレスク(白い湖)紀行、彼の音楽に「くに」はなかった
第3章 マーラーの美学
マーラーの二重性、音楽にもとづく音楽、音楽についての音楽、人は常に立ち戻る
第4章 マーラーを語る
マーラーの魅力、わが友アンリ=ルイ、マーラー「復活」、マーラーとR・シュトラウス、
対談「マーラーの時代と音楽」柴田南雄×船山隆、「なぜ今マーラーか」津山国際総合
音楽祭シンポジウム
第5章 マーラー年表
グスタフ・マーラー年譜、グスタフ・マーラー受容関連年表
船山のマーラーへの愛と見識を編み上げた一冊と言えよう。
筆者が音楽評論を志した学生の頃、船山は眩しいスターに映った。『音楽芸術』誌でデビュー(65年「音楽と沈黙」24歳)、続いて『季刊芸術』(67年創刊/遠山一行、江藤淳、高階秀爾、古山高麗雄)に『武満徹論』(68)を発表した。この季刊誌には文芸評論の大久保喬樹も『パリの静かな時』(船山の5歳下)を寄稿しており、評論界の新しい波の到来を知らせた。音楽・美術・文芸を横断する独自の編集は筆者を魅了し、こういう<骨と美>のある評論を書きたいという欲望は、彼らによって点火されたと言える。
ついでに言うと、遠山は筆者に『季刊芸術』刊行の12年を非常に誇らかに語っており(氏はその種の自慢話は一切しなかったのだが)、逝去後訪問したご自宅書庫にずらり並んだ『季刊芸術』に、評論にかけた氏の夢跡(40代半ばからの)を見て、その意味をずしり重く感じたのだった。「若い人に、全く自由に書いてもらった」そこから、船山も大久保も巣立ったのだ。筆者もそれに列なれたら。そんな夢を持たせてくれる「場」だった。
船山の『武満徹論』は、実験工房で活躍していた秋山邦晴『日本の作曲家たち 上・下』(78)に先立つものだが、以降の船山の現代音楽シーンでの活躍は華々しいものであった。筆者が現代日本作曲家論を評論の軸としたのは、秋山、船山両氏の仕事からの示唆だ。西欧の勉強も必要、だが、現代日本の作曲家たちの仕事を書き残すのは自分たちにしかできまい、と。
したがって武満、三善晃、松村禎三、と行く先々で船山の文章に、仕事に出会い、多くを知り学んだ。
『現代音楽 音とポエジー』(73)収録の「武満」「三善」「黛」論、「ペレアス」「春の祭典」「ブーレーズ」などを含む現代・前衛論は、教養啓蒙の世代から独自の視点を持った新たな音楽評論の「語り」を示した画期作ではないか。東西内外を自在に往還する眼と識、その文章の持つ美しさ、も含め。
同時に、それは戦中派作曲家による日本の現代音楽最盛期にこそ咲いた華でもあった。
『マーレリアーナ』はマーラー関連に絞られる。というのも、それまでの仕事の中でとりわけマーラーへの言及が多く、そこで繰り返し語られるのがその辺境性、との気づきがあったから。あとがきに、こうある。
もちろんマーラーの音楽は、ドイツ音楽に根差しているものの、チェコスロヴァキアの民謡その他にも源をもつ、いわゆる“デラシネ(根無し草)”の精神による音楽である。私がマーラーに強くひかれるのは、自分もまた“異邦人” “デラシネ”であるからだろう。
西洋音楽の伝統のない郡山で音楽を学んできた私は、ストラヴィンスキーの音楽を研究し始めたときから、辺境の人間、地方の人間の音楽探求にひじょうに強い興味を持ち続けてきた。自分史とマーラー探求の道が重なったのだと思う。
第2章の「異邦人マーラー」で、船山は『交響曲第1番』第3楽章の葬送行進曲について、
この「葬送行進曲」は「ボヘミアの楽団」の音楽のパロディであると同時に、ベートーヴェンの『交響曲第3番』の「葬送行進曲」のパロディになっているとさえいえるだろう。 マーラーにとっては、ボヘミアとモラヴィアの民俗音楽も、ドイツ・オーストリアの伝統的な芸術音楽も、そこに完全に帰属することのできない対象であったのだ。
そうしてカリシュト散策ののちに回ったイーグラウのカフェで窓越しの激しい雪を眺めながら、「マーラーにとってカリシュトやイーグラウは “殉教の地”でも、音楽的な郷里でもなかったのではないか」と呟くのだ。
第3章の最後に置かれた「人は常に立ち戻る」(99『別冊レコード芸術』)は、その意味で示唆的だ。「人は常に立ち戻る On revient toujours」というシェーンベルク晩年の言葉を引き合いに、ブーレーズ、 R・シュトラウス、ドビュッシー、マーラー、最後にベリオを添えて語るこの一文は船山の面目躍如たるものがある。
最後の節から引いておく。
ブーレーズやベリオといった、いわゆる前衛音楽家たちは、ドイツ語の分離動詞の前綴り“zurück” に象徴されるような回帰と復帰という現象のなかにいると考えてよいだろう。ブーレーズはラテン民族の血とフランスの文化に回帰しながら、R・シュトラウスやマーラーやスクリャービンの音楽の“トランスクリプション”と “トランスレーション”の仕事を続けているからである。おそらくこのような“zurück”の現象は、ブーレーズ、ベリオだけでなく、広く世界の音楽界に認められるのではないのだろうか。さらに巨視的な視点に立てば、冷戦の終結、ソ連の解体、バブルの崩壊以降、政治の世界や経済の体制そのものが、回帰と復帰に向かっているとは言えないだろうか。おそらくこのような現象は、20世紀という一つの時代が成熟し崩壊しつつあることと深く結びついてくるのだろう。
そうして、あとがきの終わりに、本書を生涯の最後から2番目の著作とし、すでに執筆を開始した『武満徹評伝』を終えてラストワークとしたい、と締めくくる。
季刊芸術『武満徹』から半世紀を経て、氏もまた「立ち戻る」のである。
(2020/11/15)
——————————
本書は私家版(11月10日刊行)につき、東京コンサーツへの FAX申し込みとなり、期限は11/30まで。
FAX:03-3200-9882
その他の詳細:https://funayama2020.peatix.com/?lang=ja