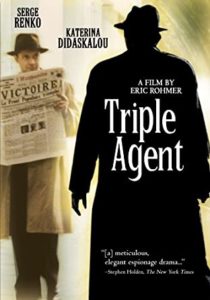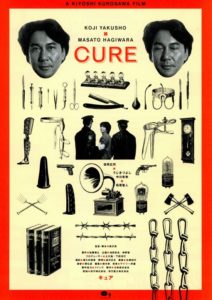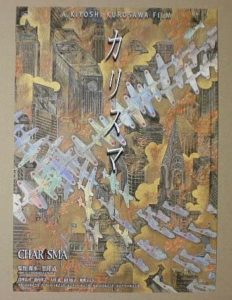小人閑居為不善日記|狂っているのは誰か――《スパイの妻》について|noirse
狂っているのは誰か――《スパイの妻》について
Who’s Crazy――About “Wife of a Spy”
Text by noirse
※《スパイの妻》、《CURE》、《カリスマ》の結末に触れている箇所があります
1
この原稿を書いている今、アメリカでは大統領選が一区切りついたところだ。事態は混迷を深めたが、ひとまずはジョー・バイデンが勝利宣言するまでに漕ぎつけた。わたしはトランプが勝つと予想していたが、民主党やその支持者を見くびっていたようだ。見識のなさが露呈したが、とはいえ民主党が勝つに越したことはない。
大変なのはこれからだ。ねじれ議会になる可能性が指摘されているし、そうでなくともバイデンは、身内にサンダースやオカシオ=コルテスなどの急進派を抱えている。彼らをコントロールできなければ財界からの支持を得られないだろうし、一方でトランプ支持者をも包摂していかなくてはならない。
バイデンは、COVID-19の感染者が多い地域にロックダウンを命じるかもしれない。そうすればトランプ支持者の反対を買うのは必至だ。トランプは変わらず、いや今まで以上に自由に発信を続け、煽ることだろう。
トランプは複数の疑惑の渦中にある。逮捕されても不思議ではないし、それを免れるため国外脱出するのではとの憶測まで飛び交っている。どうなるにせよそうした顛末は、トランプを悲劇のヒーローとして神格化させるだろう。それどころか、ただでさえフェイクニュースや陰謀論を信じている支持者に、「真実を訴えていたトランプが権力者によって排除された」と解釈させかねない。それを喧伝する者も必ず出てくる。彼らの疑念は、4年後の大統領選に跳ね返ってくるだろう。
けれども、今回の事態を引き起こしたのは、トランプ自体に特別な資質が備わっていたということではない。イメージ戦略に関しては天性の才能の持ち主だったかもしれないが、それ以外の点ではその辺のガサツな白人のオヤジとそう変わりはしまい。問題は法制度にある。アメリカの大統領制度は、一定のパーソナリティを備えた人物がその座に就くことを前提として設計されている。そこに想定外の人間が鎮座したらどうなるのか。この4年間は、そのような疑問への回答だった。
これから民主党は、トランプというバグに対する、大きなデバッグ作業に取り掛からなくてはならない。これは大変なことだ。バグの原因はトランプのみにあるのではない。システム自体にも見直しが必要だろうが、それ以前に、国民の内側にバグが潜んでいないとも限らない。
2
先日、ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞した日本映画《スパイの妻》を見てきた。1940年、神戸の貿易会社社長の福原優作は、当局からスパイと疑われてしまう。優作の挙動を疑う妻・聡子は一計を案じ、意外な行動に出る……。
この映画にはふたつの側面がある。ひとつは戦時下の日本を描いた初の歴史劇という点。もうひとつは夫婦の心理劇という点だ。監督の黒沢清はいわゆるシネフィルタイプで、特にホラーやサスペンスを好んでおり、社会的なテーマとは距離を取ってきた。
今回も、国家に振り回され、犠牲を強いられる個人を描いてはいるが、戦争の悲劇などに興味があるわけではない(企画・脚本は黒沢に師事した映画監督の濱口竜介と野原位)。それよりも、夫はスパイなのか/妻は何を考えているのかという夫婦の心理を描き出すことに力点を置いている。
黒沢が参照にしたと思しき先行作品として《三重スパイ》(2004)が挙げられる。1930年代のパリで実際に起きた事件をモデルにしたこの映画は、しかしタイトルから想像するようなスリルや活劇要素は一切ない。監督は数々の恋愛映画で知られるエリック・ロメールで、主要人物はスパイとその妻のみ。映画はほぼ夫婦のアパルトマンの中で終始する。
《三重スパイ》一般公開前に行われた上映イベントで、黒沢がトークショーに登壇するところに居合わせたことがある。その際彼が口にしたある発言が、おぼろげながら印象に残っている。アパルトマンの壁の向こうで大きな歴史のうねりが巻き起こっているが、内側では夫婦の生活が変わらず続いている。そのあいだには確かに繋がりがあるのだが、壁に遮られているためそれが容易には伝わってこない。おおよそこういった内容だったと思う。
《スパイの妻》も同じだ。多少は動きがあるものの、ドラマはふたりが住む屋敷を中心に進行する。黒沢は《三重スパイ》や、彼が高く評価するロバート・ゼメキス《マリアンヌ》(2016)などを踏まえており、そのせいか娯楽映画としては申し分ない。しかし一方で、これでは戦争という状況を壁の向こうに追いやり、その内側で夫婦のサスペンスを描きたかっただけなのではという疑問も残る。
3
妻・聡子はある建物の中に閉じ込められ、こう口にする。
私は狂っていません
だけど狂っていないことが、この国では狂っているということなんです
耳障りのいい言葉だ。今の世相にも通じると受け取る人もいるだろう。けれども自他を切り分け、一方を批難するような考え方は、現代では通用しにくい。わたしは間違っていない。間違っているのは彼らの方だ。混乱を招いたのは彼らが狂っているからで、わたしは正常だ。こういった思考は、あまりにも無防備だ。まるでトランプのツイートのように。
とはいえもちろん黒沢は、それを理解した上で《スパイの妻》を作っている。壁の向こう側は狂った世界かもしれないが、聡子だって狂っている。これが黒沢の認識だ。初期の代表作《CURE》(1997)や《カリスマ》(1999)で役所広司が演じた刑事は、仕事や日常生活から強いストレスに晒されており、やがて社会から逸脱していく。彼は狂っているかもしれないが、そこまで追いやった社会もまた狂っている。黒沢の初期作品は概ねこうした世界観の元にある。
けれど黒沢作品は、次第に表面上は変化していった。たとえば《アカルイミライ》(2003)や《トウキョウソナタ》(2008)では、狂気の淵に立った人物がどう周囲や社会と折り合いをつけていくかという主題へとシフトしており、態度を軟化させている。
しかし根本は変わっていない。聡子はやはり「狂っている」と考えた方がいい。彼女のセリフは分かりやすく戦争の非情さを表しているが、それは黒沢が仕掛けた罠だ。「戦争映画」という建前上、どちらともとれるセリフをわざわざ配置したのだろう。
4
蛇足ではあるが、もう少し続けたい。《スパイの妻》では劇中であるフィルムが上映され、それが現実に干渉し、スクリーンを見つめる人間の側こそ虚構の存在なのではないかという、世界が反転するような効果をもたらす。
現実は虚構であり、スクリーンの向こうにこそ真実がある。この構図は、聡子の「この国こそ狂っている」という言葉を暗示する。クエンティン・タランティーノの《ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド》(2019)もそうだが、シネフィリーな監督はこの手のアイデアを好む。
しかしこれはやはり自他に線を引く行為だ。それも映画への愛に支えられた仕掛けだけに、こちらの方が根が深い。初の歴史劇だとか銀熊賞というと作家としての成熟と感じるかもしれないが、黒沢は本質的には変わってはいない。それどころか映画の中に閉じこもることが、余計に未成熟という印象を抱かせる。
黒沢はそれを自覚しているフシがある。「私は絶対に成熟しない」。雑誌「ユリイカ」の黒沢清特集(2003年7月号)の対談のタイトルだ。哲学者の東浩紀や社会学者の宮台真司らと行ったシンポジウムの模様を収めた《日本的想像力の未来》(2010)の中でも、彼は未成熟について言及している。
成熟と未成熟。安直だが、江藤淳の《成熟と喪失》(1967)を思い出さずにはいられない。
彼が「喪失」し、「自由」になったということは、彼があらゆる役割から解放されたということである。彼は今、『夫』でも『子』でもなく、また『父』でも『大学講師』でもない。(中略)それは生の感覚であり、世界というものの重みであり、同時に俊介という完全に孤独な人間の視線がとらえたものの感触である。
「母の崩壊」と「アメリカの影」についての議論をそのまま黒沢映画に当て嵌めるつもりはないが、江藤が小島信夫の《抱擁家族》(1965)について述べたこの箇所は、《CURE》や《カリスマ》のラストにも通じている。この2本の映画は、社会から逸脱することで救済された主人公が街に舞い戻っていくシーンで終わる。彼はいつにもなく充足している。これは《スパイの妻》も同じで、聡子はすべてを失い、嘆きはするが、それは救済でもある。
江藤は「『喪失』とは一種の『充実』でもある」と続けている。アメリカのデモや草の根選挙を見ていると、支持政党に関わらず、これらの活動は彼ら自身を充足させているのではないかと思わせる。アメリカは今、それまでの常識が喪失しかねない状況にある。その渦中に飛び込めば、少なからず充実感に満たされることだろう。しかしここにきて、トランプ支持者はこれまで以上に喪失感を抱える結果となった。
トランプは支持者に何をもたらしたのだろう。職だろうか。昇給だろうか。それもあるだろうが、もっと大きいのは、トランプを信じ付いていくことで得られる充実感ではないだろうか。政府に見放され、誰にも必要とされていないと感じていた者が魅せられたのは、トランプだけがわたしたちを必要としているという救済だったのではないのか。
バイデンは彼らに職や補償を与えることはできるかもしれない。しかし救済や生きがいをもたらすことができるだろうか。さらなる深い喪失に晒された彼らは、これまで以上にトランプの影を追うことだろう。一方バイデンを大統領にすることで充足した民主党支持者は、その感覚を再度味わうため、ふたたびトランプ支持者と対峙するだろう。《スパイの妻》が訴えるものがあるとすれば、こういう人間の感情なのではないだろうか。
(2020/11/15)
————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中