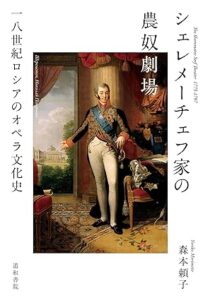Books | 体育会系 〜日本を蝕む病〜|谷口昭弘
サンドラ・ヘフェリン著
光文社新書
2020年2月出版 990円
Text by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)
「体育会系」というタイトルから出発して、日本にはびこっているネガティブな意味での「伝統」を感じさせる事例がたくさん挙げられている一冊である。いわゆる学問的な深みという方向性ではないけれど、社会問題とその背景を考える入り口としては絶好の内容ではないだろうか。
本書の取っ掛かりは学校の運動会における組体操やピラミッドである。身体の危険性が指摘されている出し物であっても、「感動ポルノ」の面から、こういった行為に対する強い支持があるということ、そしてその問題の根底には大人たちが卒業できない精神主義・根性論があることを著者ヘフェリン氏は指摘する。いみじくも本のタイトルに「体育」という言葉が使われているように、彼女が考えているのは国際的な視野を入れたスポーツ競技というよりは、学校の体育の授業であり、その背後には、修行・苦行といった宗教的なものへのコノテーションさえ思わせるような、理性とは別の「頑張り」を求めるマインドセットが私たちにあると、くり返し言われているようでもある。
号令に合わせてびしっと行動を共にする幼稚園の幼児たち、そしてそれを善しとする大人たちも、学校関係者よりはむしろ、学校外の人が考える問題だろう。思い出してみれば私の小学校時代においても運動会の行進を隊列揃ってやるだけの訓練に何時間もの勉強の時間を費やしたし、卒業式の一糸乱れぬ動作や言葉の発声のために何日も訓練させられた。学歴社会が問題とされながらも、こういった勉学とは関係のないことに時間を費やされる現状、すなわち学校に、家庭で養うのが海外では当たり前とされている「躾け」までが丸投げされている現状は、学校が世間から離れている・閉鎖的であるという一面もあるのだろうが、社会人の多くが学校教育のこれからのあり方について考えることをしていない、あるいは余裕がないことの証左なのではないだろうか。
管理教育や理不尽な校則についても本書は言及しているが、この問題自体は教育界では長く議論されてきたように思う。服装の乱れをもって心の乱れを考える、というのは一見効率的に見える。しかし心が乱れていても服装を整えれば何も分からないともいえる。そしてそういった見た目をむしろ「従順」として喜んでいるのかもしれない。「ブラック校則」のバカバカしさというのは、そのように教師を喜ばせるものだと、私自身割りきって考えていたことがあった。
ただ著者が指摘しているのは、もちろん「ブラック校則」の存在だけではない。そもそも子どもたちがその校則の是非や意義を考えたり、校則の制定あるいは廃止の意思決定に関われないことである。それは民主主義先進国を謳う日本において、他の国よりも大人の政治参加が低いことが指摘されていることにつながっているのではないかと思えるのだ。自分たちのルールは自分たちで決めることができるという主権者意識が足りないと指摘されることの多い日本の現状を学校から変えていくには、おそらく公民の勉強をしたり模擬選挙をすることでは不十分で、自分たちを実際に縛っている校則に対して意識を働かせることも必要なのだろう。ヘフェリン氏によればドイツの学校には校則がなく、そのために子どもたちが自由の制限に敏感になっているという。これも示唆的だ。先が読めない社会の中で、学校は(もちろん筆者がいるような大学も含めて)「考える個」としての「市民」を創造する場になることを今後も続けていくべきであるし、著者が指摘する通り、躾けは家庭に委ねることも考えねばいけないだろう。いわゆるライフ=ワーク・バランスとはそのような家庭を作るためにも必要だ。
また校則の中にある様々な項目を実現するための行動が人権侵害になり得るという指摘も重要だ。多文化共生が求められる今後の日本において、地毛の色を証明するプロセスが必要なのか、「強制的に髪の毛を先生に切られた」ことにどんな意味があるのか、「女子のスカートの長さが決まっている」ことが本当に必要なのだろうかなど。あるいは、校則とは離れるが、宗教的な理由から食べられない食材が給食に出された場合に「完食」を強要することをどう考えるべきか、そういった「グローバル化」の問題は、今後ますます大きくなっていくだろう。
そのほか著者から考えさせられることに、「やればできる」という言葉に存在する日本と欧米との意味の差異がある。著者はミュンヘン出身であるためドイツを主に述べることもあるが、これはアメリカと日本の間の差異を考えても明らかなこと。すなわち欧米の「やればできる」は、主に自分自身に対して唱える言葉だということである。その背後にある発想は英語で「セルフ=エスティーム self-esteem」という用語で表すことのできる考え方である。自分自身を励ますために、あるいは他人から言われるにしても、個々人が持つポテンシャルを引き出すために言われるのが「やればできる」なのである。さらにいえば、欧米のセルフ=エスティームには、本の著者のいうように「欠点を含めて自分をありのままに受け止め、前向きに進む」発想が強い。
一方日本の場合の「やればできる」は、著者の指摘するように、個々人のあり方を通り越して、やれないのは頑張りが足りないからだ、という他人を陥れる方向性に傾きがちであるということである。さらには日本には集団の利益を個人よりも上に置く傾向が強く、この言葉を組織の「上」に立つものが「下」にいるものに対して言いがちだという指摘もある。集団の中の論理に個人が合わせなければならないという同調圧力 (peer pressure) が日本に強いことも、著者が指摘しているし、筆者が住んだこともあるアメリカでの経験からも実感できる。
さらに共感してしまうのが「我慢」についての発想である。他人、あるいは「世間」に合わせて個人が何かを犠牲にすることが日本では往々にして美徳とされるということである。学校にエアコンを入れることについて、子どもに忍耐を与えるべきだから反対という大人の存在、あるいは素手でトイレ掃除させることで精神が鍛えられるという大人の非科学的発想である。なんでも西欧がよいと言う訳ではないが、理知的な発想よりも精神的苦行に意味を見出す怖さに、日本人はもっと自覚的になるべきだろうと本書を読んで考えさせられる。そして著者が指摘する通り、大人が揶揄する、我慢しない代表の「ゆとり世代」の行動こそ、グローバルな視点からはむしろ標準ともいえるのであり(だから「面倒」だというのもあるのだろうが)、こういった問題においても大人の方の価値観が正しいのかというのを考える局面に入ってきているという指摘も重要である。
音楽に関しては、激烈な吹奏楽部の練習に耐え切れず自殺した高校生の事例が取り上げられていた。筆者も高校で吹奏楽部に所属していたが、吹奏楽部は他の文化部に比較して「体育会系」的な側面が強く、運動系部活動でよく言われる「1年生は奴隷」とまではいかなくとも、練習が終わったあとに呼び出しを喰らい廊下で正座させられて上級生の説教を聞かされるということは日常的に体験している。大学のオーケストラの合宿では1年生は飲み会で寝てはいけないという「伝統」があったり、本書にも紹介されているイッキ飲みへの同調圧力もあった(さすがに「イッキ飲み」は減っただろうし、コロナ禍での会食の危険性は広く認知されているだろう)。
『体育会系 〜日本を蝕む病〜』で多く事例が挙げられている根性論や精神主義に由来する様々な事例は労働意識にも見られ、日本の前近代性がそこかしこに露わになっていることが自覚させられる。例えばそれは有給休暇が取りにくい問題であり、女性の扱われ方の問題(女性に対して極端に容姿に対する注文が出されることなど)であり、まだまだ改善すべきことは多い。
著者は「セルフ=エスティーム」としての「頑張り」は積極的に評価しようとしている。しかしそれは、本書が「欧米では…」といった、この手の本にありがちな一方向な欧米賛美の文化論に陥らないための、著者の配慮だろう。日本に居を構える大人(特に自分を含めた男性)たちは、そういった著書の言葉に甘えることなく(「甘えるな」は体育会系の人物が他人に強要にする時に好んで使う言葉だというが)、日本の現状と、その背後にあるマインドセットが孕む問題点を、謙虚な心を持って 読むべきであろう。
(2020/11/15)