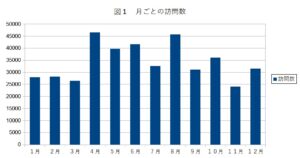私がものを書き始めたのは、そして書き続ける理由|藤原聡
私がものを書き始めたのは、そして書き続ける理由
Text by 藤原聡 (Satoshi Fujiwara)
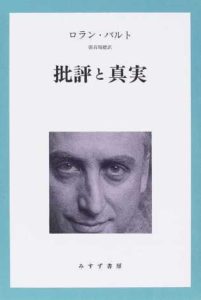 幼い頃から本を読むのが好きだった。とはいえ、夏休みの宿題における定番の読書感想文はあまり真面目に取り組んだ覚えがない。というよりもはっきりと嫌であった。指図されて提出しなくてはならないことが鬱陶しい(単にものぐさだっただけかも知れないが)。高校やら専門学校時代もこと文章を書くということに対しては好きやら嫌いやらではなく何も考えていなかったんじゃないか、仮に機会があったにせよ(今振り返ってもこの程度の記憶しかない)。
幼い頃から本を読むのが好きだった。とはいえ、夏休みの宿題における定番の読書感想文はあまり真面目に取り組んだ覚えがない。というよりもはっきりと嫌であった。指図されて提出しなくてはならないことが鬱陶しい(単にものぐさだっただけかも知れないが)。高校やら専門学校時代もこと文章を書くということに対しては好きやら嫌いやらではなく何も考えていなかったんじゃないか、仮に機会があったにせよ(今振り返ってもこの程度の記憶しかない)。
それがはっきりと意識して文章を書くようになったのは恐らくかなり後、某CDショップに就職してからだろうか。あの商品に添付するコメントカードという奴だ。筆者が働いていた頃はまさにCDの全盛期であり、毎日山のようにそれらが入荷しては沢山のお客様が買って行った。既に存在していたとは言えインターネットはさほど普及していなかったこの時代、店頭コメントの情報は買い手にしてみれば間違いなく重要な情報源だったはず。必要と思われる客観的なデータ。演奏の特徴。効果的なレトリック。字体、大きさ、色使いなど。有名なカリスマコメント師(笑)の書き方を真似てみたりもした。文字数に限りがあるもどかしさは付いて回ったが、そののち店舗単位で発行していたレビュー誌、あるいは会社として発行していたフリーペーパーへもレビューやら時には自ら行ったアーティストへのインタビュー記事(文字起こしは自分だ)を掲載し、長文を依頼された際には単なるレビューを超えて何やら批評めいたものになることもしばしば。現在にまで続く筆者の文章執筆は間違いなくこの際の蓄積がベースになっていよう。そののち上記CDショップは退社したけれど、その直前のタイミングでとある人脈と言うかご縁で本誌メルキュール・デザール(その前身であるJAZZ TOKYO誌)にお招き頂いて今に至る。
以上は極めて大雑把な事実の整理だけれど、では自らの「書くモチベーション」は何に由来するのか、を考えてみよう。それは非常に利己的な理由で、ある対象に接したのちの内なるカオスを分節化してとりあえずではあれ形として吐き出しておいた方が良いんじゃないか、というものだ。作者は何らかの内的なモチベーションがあって作品を制作する。しかし、そのモチベーションとやらは当の作者自身にしてからが必ずしも明確に言語化できるものでもあるまい(大島渚は「なぜこの映画を撮ったのか、そんなことを言葉で説明出来るなら映画なんか撮らない」と言う)。
先に書いた「内なるカオス」の分節化(=整理)。それは作者の意図に沿っていようがいまいが構わない。作者の意図に沿った(沿うであろう)読解をするにはそれ相応の知識や広範な教養が必要になる場合もあろう。しかし、それに汲々としていてはまるで国語ではないか。一応書いておくが、そういった努力は必要である。但し、それとは別に(言い換えれば作者の意図とは離れたところで)作品の受け手が独自の「読み」を行うこともまた重要だ(積極的あるいは戦略的な「誤読」)。それは単なる感想文になってしまう危険性を孕みつつも、そのロジックに整合性と独創性があるならば作者、もっと言えば作品からも離れてまたそれ単独の一個の「批評」(もしくは「文学」)という作品となりうる。ここで思い出すのがドイツの音楽学者であるアルノルト・シェーリング。彼はベートーヴェンの弦楽四重奏曲第14番を「シェイクスピアの『ハムレット』の音楽的実現」、またはシューベルトの『未完成』を「自身の見た夢の音楽化」だとしている(アーノンクールはこの説に基づいてウィーン響と録音を行っているほどだ)。学のない筆者はその正当性(そんなものがあるとして、の話だけれど)について云々できないが、しかし20世紀前半におけるロマンティックな読解だと切り捨てる立場はあるにせよ、その主張は当然シェーリングなりの根拠があってのものだろう。主観的読解と客観性、ここからの批評と文学の関係性という命題。実証主義かテクスト主義か。付随してバルト=ピカール論争などを思い出したり…。件の『ラシーヌ論』でも久々に引っ張り出してみるか。
本稿も与えられたテーマに沿っているのか分からないが(苦笑)、上に書いたようなあれやこれやの興味からいまだに何らかの文章を書いているのは確かなようだ。
(2020/10/15)