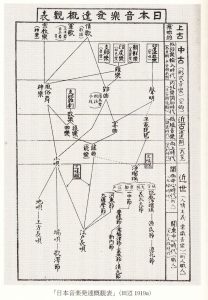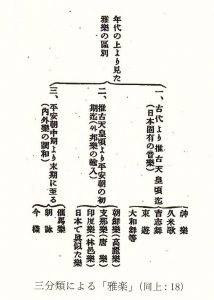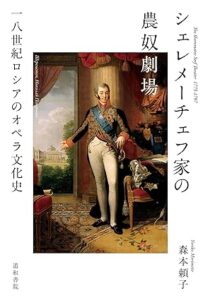Books|〈雅楽〉の誕生|齋藤俊夫
鈴木聖子 著
春秋社
2019年1月出版
3500円(税別)
Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)
本書のタイトルを見て、「ああ、きっともう定番となった〈創られた神話〉モノだな」と思って過ぎようとした人はちょっと待ってほしい。〈創られた神話〉モノの定番の粗筋は「昔からの伝統だと今現在思われているあるものは、よく歴史を調べると結構最近になって誰かが創ったものに過ぎない」といったものである。本書も確かにそのような〈創られた神話〉モノとしての定石は踏まえている。本書「はじめに」において、
「雅楽というのは、平安時代から変わらずにいまも皇室で演奏されている音楽です」
「雅楽には三種類の音楽があります。神楽など日本固有の音楽と、中国大陸から入ってきた音楽と、それらを基に作った日本の歌曲です」(本書「はじめに」i頁)
という雅楽を巡る定番の解説に疑問を持った所から研究が始まったと書いている。
だが、本書の本領は、田辺尚雄(1883~1984)の戦前・戦中の活動を丹念に調べ上げることにより、〈田辺によって創られた神話〉がどのような歴史的・政治的・科学的世界観を背景にして〈何故創られたか〉を丹念に解きほぐした所にある。
『第一部 「日本音階」の誕生』では、黒船来航以後、西洋からの眼差しを内面化させた日本の研究者たちが、その西洋の眼差しを〈日本音楽〉に向け、いかに〈日本が劣っていないか〉ということを〈科学的に証そう〉としたかが述べられる。
西洋の眼差しとは、具体的には「音階」「調律」という形をとって現れた。西洋の長短調という音階に出会った日本人が、〈では日本音楽における音階とはどういうものか〉と「日本音階」を見つけ出すために東奔西走する。
伊沢修二をトップとする音楽取調掛では西洋音階と日本音階は「毫も異なる所なし」と結論づけられ、(後年柴田南雄の『追分節考』でブーイングを鳴らされることとなる)上原六四郎『俗楽旋律考』では日本音階は五音音階であると主張されたりする中、「東京帝国大学理科大学物理学科」の科学者たちの活動、とりわけ田中正平の「純正調」が大きな歴史的意味をもって現れる。何故なら、純正調は西洋音楽を支配する「平均律」へのアンチテーゼと見なせるからである。
第二章で本書の主役・田辺尚雄が登場する。田辺は東京帝国大学理科大学に入学した一方で、東京音楽学校でヴァイオリンを学び、音響学、和声学、音楽史、音楽美学についての翻訳・論文をどしどしと書き続ける。その中に含まれる「俗楽音階理論」の「四分音」研究が田中正平の「純正調」と「アンチ・平均律」論として手を結ぶのである。
この「日本音階」を巡る歴史は、〈西洋に追いつき、追い越せ〉から〈実は既に日本は西洋を越えていた〉に滑り込む、〈創られた自覚の物語〉と言えよう。
『第二部 進化論と「日本音楽史」』では、20世紀はじめに世界を席巻した(今でも席巻し続けているのかもしれない)「社会ダーウィニズム」に基づく、「音楽進化論」、すなわち、単純な形態から複雑な形態へと音楽は「進化する」という「科学的史観」が登場する。
田辺もこの「科学的」な「音楽進化論」を説くヒューバート・パリー『音楽芸術の発達』に大きな影響を受け、以下のような「進化論的歴史物語」を創る。すなわち、「上古」に「宗教学(神楽)」「軍歌(久米舞・吉志舞等)」「情歌(歌謡)」が日本土着のものとしてあり、「中古前期」の「外邦楽輸入時代(奈良朝・平安朝前期)」に至って「朝鮮楽(高麗楽)」「印度楽(林邑楽)」「支那楽(唐楽)」の3つが合わさって「(カッコなしの)雅楽」を形成し、「中古後期」の「内外楽調和時代(平安朝後期)」で「上古」と「中古前期」のものが融合して「風俗舞」「神楽」と「郢曲(催馬楽、朗詠、今様)」が完成する、という「雅楽の誕生」の歴史物語である(本書171頁「日本音楽発達概観表」参照)。
この「進化論的歴史物語」に従って、本稿で先述した「雅楽には三種類の音楽があります。神楽など日本固有の音楽と、中国大陸から入ってきた音楽と、それらを基に作った日本の歌曲です」という「解説」が創られたのであり、それが今でも「正統な音楽史」として通用しているのである(本書179頁「三分類による「雅楽」」参照)。この「進化論的歴史物語」が現在の研究では誤りとされていることは序章とこれを比較参照することで明らかとなる。
第二部までならば本書は〈創られた神話〉モノで終わっていただろうが、『第三部 大東亜科学奇譚』に至って、(少なくとも筆者の目では)今から見ると諸星大二郎の民俗学マンガのような珍説が登場する。だがその珍説(昨今では「トンデモ」や「疑似科学」などと呼ぶのだろうか)が戦前から戦中の日本では「正統」であったことに震えるような気持ちがし、だからこそ更に興味深くなってくる。
正倉院所蔵の箜篌(くご)の起源を紀元前3000年頃のアッシリアに求め、かつ、台湾など東アジア植民地土着民族の音楽を「日本固有の音楽の起源」とした田辺は、東洋=黄色人種の音楽の最古層としてなんと紀元前5000年頃のシュメール(田辺の当時は「スメル」)文化を指定するのである。
「スメル」とは「スメラ尊」すなわち「天皇」である、というのだから牽強付会もほどほどにと思うが、この強引な憶測によってシュメール→アッシリア→シルクロード→東アジア→日本と、箜篌のミッシングリンクが繋がり、その終着点たる、皇紀2500年間の伝統を持つ日本は世界最古の文化古層を持ち、それと外来の音楽を融合・進化させて文化的頂点を極めた国とされるのである。その頂点に位置するものが、すなわち「雅楽」に他ならない。
そして、戦中に発売されたレコード集『東亜の音楽』において田辺はこう述べる。
日本音楽は決して東亜音楽の一系ではなくて、一面に於ては東亜音楽の集大成であり、一面に於ては世界音楽の集成である。(本書276頁)
しかし、このレコード集には雅楽は収録されていない。これを著者は「不在による顕在」と形容し
作る側も「大東亜音楽」が幻想にすぎないことを十分に理解していたことが見て取れる。すなわち、これらの収録曲に「大東亜音楽」として共通して言えることは何も言えないので、「血」という、今ならばおそらく「DNA」などと置き換えられたであろう言葉に願いを託すほかなかったのである。(本書278頁)
と述べている。空想・幻想でしかない「不在」の物語が現実を構築・支配するという、ポスト・トゥルースの時代などと呼ばれる昨今の世界にも通じる歴史的事実であろう。
本書を貫く問題意識は、〈音楽(=文化)や科学もまた歴史と政治の関数である〉〈自己の優越性の根拠付けと植民地支配の正当化のために、(疑似)科学を背景に置いた歴史物語が創られる〉と要約できよう。事実から歴史が構築されるのではなく、政治目的のためにあらかじめ終着点が決められた歴史物語が創られ、その補強のために音楽(=文化)が利用されるのである。
「あとがき」で著者は「フランスの人々に雅楽を説明するとき、もっとも理解してもらいやすいのは、田辺の進化論的な三分類の「雅楽」であった。(略)これから私たちは、これを越えるどのような雅楽像を作っていくことができるのだろうか」(本書350頁)と述べている。受け入れにくい「事実」より、わかりやすい「物語」に納得してしまう、その陥穽が今でも我々の前に大きな口を広げていることを知らしめられる、今こそ読むべき好著であった。
(2020/7/15)