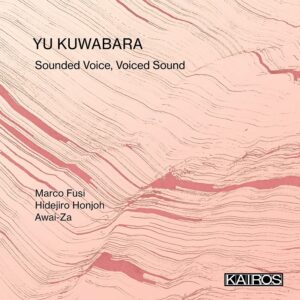Books|『写本の文化誌 ヨーロッパ中世の文学とメディア』|能登原由美
 『写本の文化誌 ヨーロッパ中世の文学とメディア』
『写本の文化誌 ヨーロッパ中世の文学とメディア』
Die literarische Welt des Mittelalters
クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ著、一條麻美子訳(白水社 2017年)
Text by 能登原由美(Yumi Notohara)
新型コロナ・ウィルスの世界的流行は、人々の生活様式にも大きな変化をもたらしている。とりわけ、感染拡大を防ぐための「社会的距離」の要請により、人と人とが直に接することなく「意思疎通する」手段として、インターネットの役割が一挙に高まった。誰かに何かを「伝える」ために、ネットがもはや欠かせないツールとなったのである。
それは、音楽を伝える行為にも当てはまる。その伝達ツールといえば、古くは口承。それから筆写、続いて活版印刷譜。さらに、19世紀後半のレコードの発明や20世紀初頭のラジオ放送の開始。楽譜ばかりか、演奏そのものも記録され、伝えられるようになる。そして、21世紀を前に始まったデジタル化とネットによる音楽配信。今、直面するのはまさに、コロナ禍により巨大なうねりとなったこのデジタルメディア、インターネットメディアによる変革の波である。
本書を紹介するのは、こうした現在の音楽状況が前提にある。中世ドイツ文学を専門とする著者によって書かれたこの本は、当時の写本を通して、ヨーロッパ中世の書物文化や文学作品を取り巻く社会の一端を明らかにしたもの。本の成立に関わるあらゆる人々―作者のほか筆記、彩飾、製本に携わる職人たち、また注文主など―の活動の様子を詳らかにするとともに、愛書家の図書室や当時の読書行為にまで触れることで、「作品」研究にとどまらない、幅広い視野から中世文学の世界を紹介するものとなっている。
だがそればかりではない。その緻密な史料研究を支える探求心の根底には、メディアとしての写本の役割に対する関心が第一にある。現代におけるデジタルメディアの浸透がもたらす変化に触れながら、「まだ予測はできないが、メディアの発展が知と記憶の宝庫の姿と、そこへのアクセス方法を変えてしまう文化的革命であることに異論はないだろう」(p. 8)と冒頭から明示する。訳者もあとがきの中で、「後の時代の人々がおそらくグーテンベルク以来のメディア史上の革新期と呼ぶであろう時代」(p. 252)と今を指して明言する。すなわち、単なるヨーロッパ中世文学研究どころか文化史にもとどまらない、メディア史としての視点が本書にさらなる広がりと現代的意義を与えているのである。
もちろん、著者自身も述べるように、中世の文学世界については「ひとつであるとは限らない」(p. 249)。ここで語られるのは、現存する史料から垣間見える一側面だ。そもそも、「中世」といっても700年(本書では「西暦800年から1500年」と定義)もの長いスパンを持つ。また、地域や書物が生まれたコンテクストの違いもあり、一概に論じられるものでもない。けれども、一つ一つの写本が照らし出すのは現代のそれとは大きく異なるものであり、むしろ我々の知る世界は広大な書物文化の一断面に過ぎないことを教えてくれる。それは、音楽文化においても同じであろう。
では、まずは本書の構成を示そう。
第1章 本ができあがるまで
1 材料の調達
2 書く・描く
3 写本製作の場
4 書記
5 本の外見
6 写本の値段
7 保管とアーカイブ化
8 印刷術という革命
第2章 注文製作
1 文学の中心地
2 文学愛好家とパトロン
3 文学マネージメント―――マネッセ写本
4 愛書家―――ある15世紀貴族の図書室
第3章 本と読者
1 聞く・読む
2 身体としての本
3 五感と読書
第4章 作者とテキスト
1 詩人―――匿名・自己演出・歴史性
2 作品―――伝承・言語・文学概念
第1章では、印刷術の発明に至るまでの書物の成立過程における、技術的・物質的側面に光を当てる。本の製作に携わる職人や詩人の位置付けの変化に、「芸術の世俗化」の黎明を見るとともに、世俗文学の需要の高まりによる「書記」という職業の商業化といった視点は、やがて始まる出版業の萌芽を示すとも言え、音楽にも共通する点だろう。一方、テキストを書き写す者について、「書記」、「編纂者」、「注釈者」、「作者」という分類が、13世紀半ばの文献にも見られるという(p. 72)。この分類の中にはすでに、のちの著作権意識に繋がるものがあると言えるのではないだろうか。
さて、愛好家やパトロンの存在は、文学に限らず音楽においても、そして中世だけではなく現在に至るまで欠かせないものだ。彼らの活躍を語る第2章では、文学が享受、あるいは収集の対象としての価値を帯び始めたことが明らかにされる。とりわけ中世ドイツ最大の写本、「マネッセ写本」(別名「大ハイデルベルク歌謡写本」)の成立過程や受容をめぐる状況は興味深い。1280年から1330年にかけて編纂され、それまでの150年間の叙情詩が収録されたものだ。描かれた肖像画や挿絵、装飾文字など、美術史的価値も極めて高い。けれども、最も私の関心を引いたのは、詩人ごとによる作品分類(しかも詩人の肖像画を伴う)やレイアウト、目次の存在、作者の社会的地位による配列など、一つの体系的な「作品集」のように計画された編纂意図がみられる点だ。やがて高まる作品の蒐集熱やコレクション趣味、言い換えれば芸術の「所有」への欲求が、この当時すでに存在していたことを示すものだろう。
ただし、写本の普及、すなわち口承文化から書記文化への移行は、たちまち「聞く」行為から「読む」行為への変化を受け手にもたらしたわけでもなさそうだ。第3章では、中世を通じてこれら2つの受容形態が長らく併存したことが語られる。文学のみならず中世音楽の世界にも豊かな実りをもたらしたミンネザングも、音楽とともに朗唱される一方で、時には「読むもの」としても享受されていたことを示す記録もあるという(p. 170)。文化の移行期に見られるこうした異なる要素の同時進行は、我々の時代も含めていつの世にも生じるようだ。
当初は名前の記されることのなかった「作者」も、この時代を通じて徐々にその意識が顕在化してくる。最終章では、中世写本に見られる「作者」や「作品」観に迫る。とはいえ、そもそも、近代以降でいうところの「創作」、「オリジナリティ」といった観念は当時には当てはまらないようだ。ここで求められたのは、「すでにある素材を取り上げて、それを新たに、これまでとは違う形で語ること」(p. 238)。ミンネザングについても、「その時々の上演状況に合わせて形を変える可能性のある『ワーク・イン・プログレス(進行中)』の作品」だった(p. 237)という。こうした作品の「流動性は、中世におけるテキスト伝承の一現象であるだけでなく、中世文学の本質」(p. 239)であるとする一方で、原典との記号論的、解釈学的な関係性がその前提にあることも強調する。
こうした中世の写本に見られる作品の伝承、芸術の伝達が、今直面するネット配信による変化に直ちに結びつくわけではもちろんない。「歴史は繰り返される」とは言うものの、数百年前と現代との状況はあまりにもかけ離れている。とはいえ、未曾有の変革がもたらされる可能性もあるなかで、これまで抱えてきた価値観を一旦脱ぎ捨てるには、我々の日常からすでに失われてしまった世界を垣間見ることも必要ではないだろうか。その点で、本書は新たな視点をもたらすとともに、予測できない未来に向かって歩き続ける際に、何らかのヒントを与えてくれるものとなるのではないだろうか。
(2020/6/15)