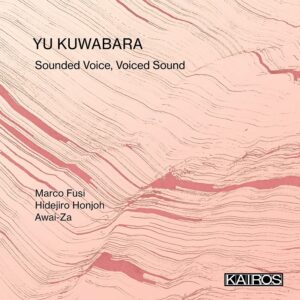Books|オペラで楽しむヨーロッパ史|小石かつら
オペラで楽しむヨーロッパ史
加藤浩子 著
平凡社新書
2020年3月出版
880円(税別)
Text by 小石かつら(Katsura Koishi)
オペラについての、入門書でも専門書でもない。本書は、ちょうど「その間」に位置する。この層の書籍は、私の知る30年ほどの間に、ずいぶん増えてきているように思う。
ドイツに留学したとき、歴史学の老教授に聞かれた。「学位を取ったら何になりたいんだ?ライター?研究者?学芸員?それとも?」。博士号を得ても仕事は無いと言われていた私には、研究者以外に選択肢があることが新鮮で、とりわけライターという選択肢は衝撃的だった。だから何度も問い直した。「専門的な本が売れて、読まれて、そして著者が、それ専業で生活していけるのか」と。驚いたのは相手も同じ。何が疑問なのか、なかなか理解してもらえなかった。ドイツでは、書籍だけではなく、新聞にも音楽(や文化)関連の記事が桁違いに多く、演奏会の批評などは早ければ演奏会の翌日の紙面を占領した。まるでスポーツ面のように前日の「試合」の詳細が記され、各新聞社には各分野に専門職としての記者がいた。当時の私は、隅々までオーガナイズされた文化の豊かさに驚いたのだった。
それ以来、そういう視点で日本の音楽関係の新刊書を眺め続けてきたのだが、著者が専業かどうかはともかくとして、「一般向けの専門書」は、冒頭に書いた通りずいぶん増えた。(ただし新聞には依然としてスポーツ欄しかない。)同時に、超のつく入門書も増えた。つまり、気軽に入門できて、気軽に知識や思索を深めていける環境になってきたと感じる。いや、もはや現在の状況が「普通」すぎて、かつて私がドイツで受けた衝撃が、なんのことかわからないという位かもしれない。そして、このような状況を牽引した立役者ともいうべき存在なのが、加藤浩子氏だ。オペラに関するものを中心に次々と音楽関連書籍を出版し、本書は15冊目になるという。
本書は全6章から成るが、前半と後半では少し趣向が異なる。ごく大雑把にまとめると、前半はフランス革命、イタリアの統一、ドイツの統一といった歴史的な事項に注目し、それぞれを、モーツァルト、ヴェルディ、ワーグナーのオペラと合わせて捉え直していく。歴史的な事情で「創られていく」エピソードと、その結果、我々が持つ「既成の」作曲家イメージを、鮮やかに暴いていく。たとえば「愛国オペラ作曲家」と理解されるヴェルディについて、そのイメージ形成の実態を丁寧に解きほぐして、既成の常識の危険性と、オペラをたのしむことで自然と得られる客観的思考のおもしろさを、さりげなく提示してくれる。
後半はジャポニズム、ジャンヌ・ダルク、シェイクスピアといった事例をあげる。第3章のドイツ統一から第4章のジャポニズムに移行するのは、同時代のこと故、とてもスムーズだ。その第4章で、《蝶々夫人》の主人公の描かれ方が、実際にはありえない設定になっていることを指摘する。これは、日本のことをよく知っている我々が抱く違和感であるが、それを出発点として、《ラ・ボエーム》等の他の作品の設定も、《蝶々夫人》と同様に「当時のイタリア・オペラ化」されていることに言及する。そしてこの前提の上に、ジャポニズム・オペラを1872年の《黄色い王女》や1876年の《コジキ》から順に解きほぐしていく。《蝶々夫人》も原作となった小説や戯曲だけでなく、初演版からの改訂の過程を丹念に解説する。
本書全体を貫いているのは、オペラが「甚だしく脚色された」事実を示しつつ、その理由を、題材となった時代や事柄と、オペラが書かれた時代を重ねることで浮き彫りにしていく手法だ。そしてそれが、著者本人の目で「見たこと」に基づいていることが、本書全体の力強さを形成している。圧倒されたのは、2017年のバイロイトにおけるバリー・コスキー演出のワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》で第3章を締めくくった点である。ワーグナーと政治の関連を16世紀ニュルンベルクから19世紀のドイツ統一、20世紀のナチス政権とその後の受容までについて、細かく拾いながら現在の実際の上演へと読者をいざなう。紹介された演出は、最後の場面で、群衆が去った舞台にオーケストラとワーグナーだけが残されるというもの。群衆を政治と読み、オーケストラとワーグナーを音楽そのものと読む。ディスクの紹介もあり、私はYoutubeでも確認できた。
本書の題名はオペラ「で」歴史「を」楽しむとあるが、歴史を俯瞰しつつ、音楽の本質を問うものだと感じた。音楽「を」楽しむことは、つみかさねられてきた文化や伝統、そして時に歪められてきた歴史をときほぐすことだという当たり前のことを、強くおしえてくれる一冊である。
(2020/5/15)