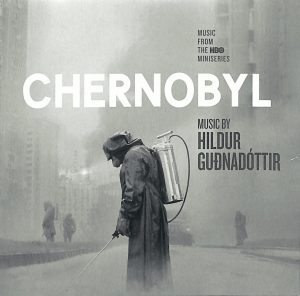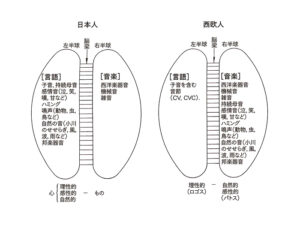評論|闇に潜む声:『ジョーカー』『チェルノブイリ』にみるヒドゥル・グドナドッティルの音楽|能登原由美
闇に潜む声:『ジョーカー』『チェルノブイリ』にみるヒドゥル・グドナドッティルの音楽
Voices in darkness : Music of Hildur Guðnadóttir in “Joker” and “Chernobyl”
Text by 能登原由美(Yumi Notohara)
今年2月の米アカデミー賞で作曲賞(正式名称はThe Best Original Score)を受賞したアイスランド生まれの作曲家、ヒドゥル・グドナドッティル(Hildur Guðnadóttir)。その受賞作となる映画『ジョーカー(英Joker)』は、さらに英アカデミー賞作曲賞、ならびにゴールデン・グローブ賞作曲賞も受賞。これらはいずれも、女性の単独受賞は初めてということもあり、映画音楽界で話題となった。だが、その名前が広く知られるようになったのはこのためだけではない。2019年にアメリカで放映され高い評価を受けたドラマ・シリーズ『チェルノブイリ(英Chernobyl)』の音楽により、エミー賞ならびにグラミー賞を受賞。『ジョーカー』での数々の栄誉はそれに続くものであった。つまり、彼女はわずかこの1年余りの間に、ドラマ/映画音楽界で一躍時の人となったのである。
1982年、アイスランドで音楽家の両親のもとに生まれた彼女は、幼少よりチェロを始め、その後進んだアイスランド芸術アカデミー、ベルリン芸術大学では電気音響学や作曲を学んでいる。チェリスト、ヴォーカリスト、そして作曲家という多様な活動に加え、手がけるジャンルも多彩。既存の枠組みで捉えるのは難しい。敢えて言うなら、実験的ポップミュージック、ポスト・クラシカル、前衛音楽などと言えるのだろう。さらに、クラシック音楽界においても、2019年10月にドイツ・グラモフォンと専属契約を結んだことから俄かに注目を集めている。
だが、そうしたジャンル区分など筆者にとってはあまり重要ではない。また、『ジョーカー』で用いられたHalldorophoneと呼ばれる電子楽器(1)が奏でる独特のサウンドも広く関心を集めるが、新奇性という以上の興味はかきたてない。むしろそれ以上に注目したいのは、彼女がその音楽によって顕在化させたものである。
知る人ぞ知るように、『ジョーカー』は、『バットマン(英Batman)』の悪役で狂気の殺人鬼「ジョーカー」が誕生する背景を描いたものだ。主人公のアーサーは、子供時代の凄惨な体験から精神障害を抱え、貧困と社会的疎外の果てに次々と殺人を犯すようになる。誰も耳を傾けようとしないアーサーの心の闇に映画は迫っていくのだが、そこで大きな役割を果たすのが、グドナドッティルの音楽である。ある程度出来上がった映像をもとに作曲が行われる通常のスタイルとは異なり、撮影の始まる数ヶ月前に送られて来た脚本のみから音楽を書くように依頼された彼女は(2)、そのスクリプトの中から「アーサーの声」(3)を見つける。こうして最初に書き上げられた音楽が、この物語最大の山場、すなわち「ジョーカー」誕生の瞬間を引き出すことになる。追い詰められたアーサーが、最初の殺人を犯した直後に逃げ込んだ公衆トイレで静かにダンスをする場面だ。
元々、ここにダンス・シーンはなかったという。が、アーサーからジョーカーへの変容を表すこの場面の撮影で、すでに録音されていた彼女の音楽が急遽流され始めると、アーサーを演じるホアキン・フェニックス(本作でアカデミー賞主演男優賞を受賞)の体がそれに反応したのだ。映画の中でその姿は、「殺人」という最後の一線を超えた後、得も言われぬ高揚感がアーサーの体の中から溢れ出し、その肢体を突き動かしているようにも見える。ただし、彼の内面は総じてセリフや文脈から比較的容易に読み取れるのだが、この場面だけは安易な説明を一切受け付けない。ただ、音楽とともに撓うアーサーの身体だけが全てを物語る。出来上がったこの場面を観たグドナドッティルは、「魔術のようだった」と答える。「彼の手の動きは、私自身が音楽を書いたときに感じたものと全く同じタイプのもので、目を疑った」とも(4)。誰も耳を傾けないアーサーの「声」を彼女の音楽が引き出し、フェニックスの体を通じて観るものに伝えた瞬間だったのではないだろうか。
このように、隠れた声を見つけて音にする行為を、彼女は「宝探しをしている(treasure hunting)」と表現する(5)。そして、『チェルノブイリ』で彼女が探し当てたものは、この『ジョーカー』をはるかに超える壮絶な「声」であった。
全5話からなるドラマ・シリーズ『チェルノブイリ』は、1986年4月26日にソビエト連邦のチェルノブイリ原子力発電所で発生した未曾有の大事故を追ったもの。アメリカのケーブルテレビ局(HBO)による制作で、会話は英語、また架空の人物を交えるなど、確かに創作/憶測の部分もあるだろう。政治的バイアスを指摘する声が上がるのも無理はない。だが、事故直後は隠蔽され、その後30年余りの間に徐々に明らかにされて来たもの―事故に至る経緯や直後の様子、除染作業、そして原因究明の過程など―が、見事な映像とともにリアリスティックに再現されていることは、やはり評価して良いのではないだろうか。さらに、現場の作業員、消防隊員や医療関係者、科学者、政府関係者など、様々な視点を交えつつ解き明かされていく手法も興味深い。そのあたりは、スベトラーナ・アレクシエービッチの『チェルノブイリの祈り』に範を得たのかもしれないが(6)、本作で一貫して表現されているのは、人間と社会を破壊する放射能の恐ろしさ、そして行き過ぎた権力構造がもたらす悪弊と歪み、欺瞞である。
このドラマで音楽を担当したグドナドッティルは、音楽を書き始める前にリトアニアのイグナリナ原発に足を運んでいる(7)。すでに廃炉となっているこの原発は、チェルノブイリと同型の原子炉を持ち、外観も近似していることから実際の撮影にも使われた。彼女は防護服に身を包みながら数時間滞在し、音を採取した。その時使用した機材の一部は、高濃度の放射能汚染により持ち帰ることが出来なくなったと言うが、それ程の危険を犯してまで欲したもの、それが、彼女が「放射能の声」(8)と呼ぶものであった。
ドラマの結尾で流れる東方正教会の古い聖歌《Vichnaya Pamyat》を除き、全編を通じて使用される音楽/音響はグドナドッティルによる。これらの大半は、彼女が採取してきた音を加工して作られたのであろう。いわゆる「楽音」はほとんど使用されない。鋼鉄が擦れる音、または巨大な空間内部を行き来する反響音のようにも聞こえる。あるいはタービンの回る音、放射線測定器のアラーム音かもしれない。実際、映像から聞こえてくる音と入り混じり、どこまでが現実の音なのか、どこまでが作られたものなのか判別できないこともしばしばだ。その素性の不確かさ、現実と虚構の曖昧さが、一層の恐怖を引き起こす。
さらに不気味なことに、これらの音は、気づいたときにはすでに鼓膜や皮膚を突き抜けて体の内部に存在している。まるで放射能のようだ…。いやまさに、これが、彼女が「放射能の声」というものであったに違いない。先に触れたアーサーの心は見えないのではなく、誰も見ようとはしないものであったが、ここでの主役は見ようとしても決して見えないもの、感じ取れないものであった。その存在が知られるのは、人間の体内に入り込んで体の中から組織を壊し始めた時だ。その量と距離によって体を脅かすまでの期間は異なるものの、早晩、誰もがその存在を知ることになる。
だが、彼女が探り当てた「放射能の声」の恐ろしさは、別のところにもあった。それは、「予測できない」という不安、恐怖である。
事故が起こった直後に、現場責任者や役人らの間で何度も飛び交う言葉がある。「アンダーコントロール(制御下にある)」。すなわち、近いうちに事故を収束させられること、その見込み/予測は立っているということを示す言葉だ。ただし、その言葉を口にしつつも状況を把握している者は誰もいない。国家の威信が最優先とされる社会体制においては、事故を過小に見せ、世界に周知される前に収束させることが第一に求められた。ましてや、その実態がわからないことなどあり得ない。ただ、その場を取り繕うためにこの言葉は使われたのである。
もちろんここには、ソ連という社会体制がもたらす歪みをこの言葉によって象徴させる意図が製作側にあったとも言えるだろう。だが一方で、それはどのような社会、どのような場面においても使用され得るものではないだろうか。というのも、この言葉の裏には、制御できないもの、予測できないものへの恐れと不安から逃れようとする心理も見え隠れする。人は制御できないもの、予測できないものに対して大きな不安を抱くものだ。
グドナドッティルの音はまさに、この予測の不可能性を聴き手に示してくる。その正体は何であるのか、どこから来たのかわからない。実態のわからない音の集積が、時空を漂い続けている。それはどこへ向かうのか、次に何が来るのかもわからない。予測できないのだ。そして、予測可能な音楽の形に飼い馴らされた現代人の我々の耳には、常にどこか違和感を残すとともに、このドラマの内容が伝える放射能の不気味さに一層の拍車をかけるものとなっている。
実態の不確かさと予測の不可能性―。それが、彼女が廃炉となった原発で見つけた「放射能の声」だったのではないだろうか。と同時に、この事故が残した教訓とも言えるだろう。つまり、「アンダーコントロール」という言葉によって人々の不安を取り払いつつも、実際には誰も制御できていない、予測も出来ないもの。9年前の3月11日、ここ日本のフクシマで起こった事故が再び教えてくれたことだ。
奇しくも、本論を書き始めた頃、日本は未知のウィルスの蔓延に晒され、多くの行事が延期や中止、また学校が休校を余儀なくされるなど、社会全体が脅かされるようになっていた。そのウィルスは2週間余りの間に世界に広がり、今や地球規模での脅威となりつつある。その正体についてはまだ把握されておらず、制御する術も得ていない。もちろん、この先どうなるのかさえ…。事故と疫病は異なるとは言え、制御も予測もできない不安はまさに、チェルノブイリとフクシマを想起させる。
(1)電子チェロの一種で、その名は発明者Halldór Úlfarssonの名前に由来すると思われる。その楽器の詳細とともに実際の演奏の様子は、下記のÚlfarsson自身へのインタビュー記事の中で見ることができる。
Terry Tyldesley, “Halldorophone – Interview with creator Halldór Úlfarsson”, KITMONSTERS, 19th Feb. 2020
(2)以下に述べる作曲の経緯は下記を参照。
Jack Giroux, “ ‘Joker’ Composer Hildur Guðnadóttir on the Magic of the Unsaid and That Stunning Final Scene [Interview]”, Film, 10th Oct. 2019;
Nina Pacent, “Meet ‘Joker’ and ‘Chernobyl’ Composer Hildur Guðnadóttir”, BMI, 23rd Oct. 2019;
Alex Godfrey, “Joker and Chernobyl composer Hildur Guðnadóttir: ‘I’m treasure hunting’”, The Guardian, 13th Dec. 2019;
黒田隆憲「映画『ジョーカー』の “不穏さ” と “安らぎ” が同居する劇中歌 アカデミー賞作曲賞受賞を機に解説」Real Sound, 2020/2/24
(3)Godfrey, ibid.
(4)Godfrey, ibid.
(5)Godfrey, ibid.
(6)ドラマの冒頭に登場する消防士とその妻は、アレクシエービッチのインタビュー内容を明らかに反映したものと思われる。
関連記事:Books|チェルノブイリの祈り|藤堂清
(7)以下に述べる作曲の経緯は下記を参照。
Pacent, ibid.;
Godfrey, ibid.;
Florian Zinnecker, “So klingt ein Atomkraftwerk”, DIE ZEIT Nr. 4/2020, 16th Jan. 2020.
(8)Godfrey, ibid.
(2020/3/15)