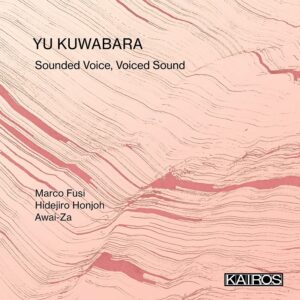Books|『第九』 祝祭と追悼のドイツ20世紀史|能登原由美
矢羽々崇著
現代書館
2018年
2300円(税別)
text by 能登原由美(Yumi Notahara)
作品は作者の手を離れると独り歩きを始める。そんなことが言われるようになって久しいが、歴史的大家が生み出したものではどうだろう。例えば音楽の場合、楽譜や当時使用されていた楽器を研究し、あるいは作曲家に関わるあらゆる資料を探し出して読み解こうとする。そうして、作曲の意図や作品にこめられた思いを明らかにしようとする。私自身もそうやって異国の地に足を踏み入れながら一次資料を探し出し、作品の内容をより深く「知る」べくそれらと対峙してきた。バッハやモーツァルト、ベートーヴェンといった巨人ともなれば、数え切れない人々の手によって気の遠くなるような発掘と解釈の作業が繰り返されてきたはずだ。だがこれはむしろ、一度産み落とされた作品を再び親の元に戻そうとする作業ではないか。今なお、作品研究に対する関心はこちらの方が根強いように思われる。
だが、本書の場合、まさに独り歩きを始めた作品のその後の運命に焦点が当てられている。その上で、何故こうした歩みが導かれたのか、その理由に目が向けられる。さらにその目は、作品を受容した時代や社会そのものにも向かっていく。そこには日本も含まれる。単に一人の音楽家やその地域、その時代にとどまらない。
その作品とは《第九》。そう、ベートーヴェンが作曲した《交響曲第九番》のことだ。その終楽章で歌われる詩の内容から、「歓喜の歌」、あるいは「喜びの歌」として知れ渡る大曲である。
周知の通り、この《第九》、日本では年末の恒例行事として定着してしまったかの感がある。今や、12月のオーケストラの公演で《第九》の入らないものを見つける方が難しいほど、年末の日本は《第九》一色に染められる。だが、いつの頃からそのようになったのだろう。何故日本では、《第九》が年末に演奏されるようになったのか。本書は、著者が前に著した『「歓喜に寄せて」の物語』(現代書館、2007年)の続編とも言えるものだが、全ての問いはここに始まるようだ。
著者によれば、《第九》を年末に演奏するのは、ドイツが先んじていた。あるいは、合唱に市民が参加する「参加型」の《第九》についても日本特有のものではなく、すでにドイツで行われていたという。その経緯について調べるうちに、そこには労働者運動が背景にあることが明らかになった。こうして、著者の発掘・解釈の作業はこの労働者運動と《第九》との関わりに費やされることになる。これが本書の骨子である。
もちろん、「すべての人間は兄弟になる」と高らかに謳った「歓喜の歌」の、人類の平等を掲げたそのメッセージを思い起こせば、19世紀終わりから活発になる労働者運動がこれに共鳴したとしても何ら不思議はない。が、実際にここで明らかにされていく詳細を読み進めると、それまでぼんやりとしていたものが確かな形を得ていった。さらには、それが日本で渦巻いていた社会主義運動と重なり、その中で発展していった可能性も示唆されている。実に興味深い。
ただし、ここで改めて《第九》という作品自体が放つ意味と、「《第九》を年末に演奏する」という行為が放つ意味を分けて考える必要があるのではないだろうか。というのも、その後ナチの台頭によって「年末の《第九》」が終焉を迎えることも指摘されるが、それはまさしく、これが労働者運動、あるいは社会主義運動と結びついていたゆえのことであろう。ナチは確かに前衛芸術やユダヤ系による作品や演奏を弾圧したが、「ドイツ民族」を至上とするその政策にあっては、ベートーヴェンや《第九》はむしろ民族の優位をアピールするものとして利用されたはずだ。つまり、ナチによって破壊されたのは《第九》やその演奏ではなく、あくまで労働者運動や社会主義運動に発する「年末の《第九》」であったことを見落としてはならない。その点において、本書は単なる《第九》の受容史とは異なる、「年末に演奏される《第九》」という特殊な受容状況に焦点を当てたものと言えるだろう。だが、それを考えると一層別の興味が駆り立てられる。というのも、それが20世紀の日本で一つの恒例行事となっていったのだ。日本の場合、こうしたドイツの状況とどの程度の近似性があるのだろうか。
さらに私の関心を引き付けたのは、こうした社会運動に連なる特殊性を超えて、《第九》の演奏が「忘却に抗して、想起」の装置として機能していることを指摘している点だ。ここまでいけば、単なる社会主義運動や20世紀ドイツ史、あるいは日本の《第九》の受容にとどまらない広がりをもつ。実際、発想のきっかけは、東日本大震災直後に全国各地で《第九》が追悼の曲として演奏されたことにあったようだ。一体、この作品の中にあるどのような要素がこのように人々を演奏へと駆り立てるのか。最終章ではこの点に考察が及ぶが、もちろん著者の答えを知りたいのであれば、本書を紐解くことをお勧めする。
(2019/7/15)