音楽にかまけている|京都賞と音楽|長木誠司
京都賞と音楽
text by 長木誠司(Seiji Choki)
京都の京セラ株式会社の創立者、稲盛和夫氏が創設した稲盛財団が、毎年京都賞という科学・文化にまたがる国際賞を出していることはご存じだろう。近年ではノーベル賞の登竜門のようなイメージが強くなってきており、昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞して世間への露出度が俄然高まった本庶佑氏をはじめ、それ以前にも山中伸弥氏や大隅良典氏が、ノーベル賞受賞前に京都賞を受賞していた。その受賞者選出の見識眼はなかなかのものだと思っている。
実は、この賞にはノーベル賞にない部門がある。「思想・芸術部門」というのがそれで、文系には文学賞しか設けられていないノーベル賞に比べると、思想や芸術のさまざまなジャンルに関係するはるかに広い分野のひとびとが受賞する機会を得ている。そのなかには音楽部門もあって、美術、映画・演劇、思想・倫理というほかの3分野と交替で、4年に一度受賞者が決定される。
記念すべき第1回京都賞である1985年には音楽分野から受賞者が出ていて、このときはすでに長老となっていたオリヴィエ・メシアンだった。その後、4年ごとの受賞者はジョン・ケージ、ヴィトルト・ルトスワフスキ、イアニス・クセナキス、ジェルジ・リゲティと続き、第二次世界大戦後の前衛・実験音楽の重鎮たちが——早くに亡くなったノーノや、なぜかシュトックハウゼンを抜かして——ことごとく受賞した。
2005年に例外的に古楽運動の先駆者で指揮者のニコラウス・アーノンクールが受賞したほか、次の2009年の受賞者はピエール・ブーレーズだったから、やはり「現代音楽」の作曲家が受賞することが決まっているような賞に、一般の目には映っていたようなところがある。
しかしながら、これは考えてみると変な話であろう。分野は「音楽」としてしか掲げられておらず、その意味では分野内のジャンルも領域も限定されていないにもかかわらず、世界には音楽で賞を取る資格のあるひとは作曲家、それもほとんどのひとが聴いたこともないような作品ばかり作っている、ある意味めちゃくちゃマイナーな現代作曲家だけというのは、賞への要らぬ偏見を産んでいたのではないかと思う。
実は、私はこの賞にリゲティのときから関わるようになっていて、初めて若輩者として審査に加わったとき、その選定に際しての審査員間でのバイアスの強さにはちょっと辟易した覚えがある。立場上、あまり詳しいことは書けないけれど、とにかく審査上での現代作曲家ありきというような暗黙の圧力にはずっと違和感を持っていた(審査員たちの顔ぶれも、現代音楽を研究対象にするひとが多かった)。
もっとも、クセナキスの次にリゲティが選ばれることに対して、なんの異議を感じたわけではない。この順番はたぶん正当なものだと思うし、年齢的なことを考えれば、次にブーレーズが来たっておかしくはなかった。でも、おそらくそういう自分の意識自体も、音楽という、時代・世界にまたがる大きな広がりのなかでは、偏見に満ちたものなのではないかと自問することがしばしばであった。京都賞の側から見ても、音楽部門が現代作曲家のためだけの賞だと思われるのは、あまり好ましいことではなかったろう。実際、ほかの部門や分野からは、多彩なひとびとが贈賞対象になっている。
そうした賞自体のあり方も考えながら、2013年にふたたび関わることになったとき、少し強く審査の場に求めたのは、もっと広く対象者を考えて欲しいということだった。そのためか、この年バラストは大きく逆方向に振れて、フリージャズ・ピアニストのセシル・テイラーが受賞者となった。たぶん、それまでの京都賞を眺め続けて来たひとはぎょっとしたろう。また、それ以前は京都賞に興味など持っていなかったひとにも、俄然注目度が増したのではないかと思う。
実際、この年のマスコミの反応はそれ以前に比べてはるかに強かったし、講演会やワークショップにも聴き手が殺到したと記憶する。当たり前だ。狭い現代音楽と、「フリー」が付くとは言えジャズの世界とでは、聴衆の層だけではなく厚みや広がりがぜんぜん違う。このときは、東京でもワークショップがあったが、その人気も推して知るべしである。その意味では、この年の受賞者選出は京都賞自体にとってとてもよかったのではないかと思っている。
ひるがえって、現代音楽という狭い領域を眺めてみても、もしかするともはやブーレーズまでのような、疑念を挟む余地の——とりあえずは——ないような、画期的な仕事をしたひとはもういないのかも知れない。その意味では、「現代音楽」という分野は、ある時期まで確かにひとつのおおきな時代を作っていたのだとは言える。まだ受賞者に名を連ねていないミニマル以降の作曲家が、これから受賞する機会があるとしても、彼らの活動した時代には、もはやヨーロッパやアメリカのような先進諸国の音楽が主流だとはとても言えなくなっていた。それゆえ、対抗する音楽ジャンルや地域の音楽家が多く出てきて、審査はきっと難しくなるだろうとも思っている。
2017年の受賞者は、初めて音楽学者であった。それも音楽学の伝統のあるヨーロッパではなく、アメリカ合衆国のリチャード・タラスキン。他の分野では当たり前の「研究者」の受賞であるが、実は音楽分野のみならず、「思想・芸術」部門のなかの音楽を含めた芸術関連分野全体として考えても、初めての「研究者」の受賞であった。美術や演劇・映画の研究者も評論家も、京都賞を受賞したことはない。だからこれは画期的なことだったと言える。セシル・テイラーに始まった賞の様変わりは、さらに進んだことになる。
タラスキンへの贈賞理由には次のように書かれている。
「リチャード・タラスキン博士は、古楽の演奏、研究から出発し、近代ロシア音楽に関する画期的かつ重要な研究を行い、さらに大部の西洋音楽史を発表して、読者を啓発し続けてきた音楽学者、批評家である。(中略)
タラスキン博士は、音楽に関する従来の批評と学問との境目を取り払い、また伝統的な音楽史学と民族音楽学との境目を取り払うという新たな次元を音楽研究に切り拓いた。音楽において、作曲や演奏だけではなく、緻密なことばを通して文脈化する作業がきわめて創造的であり、世界の音楽文化に貢献するものであるということを、きわめて高い次元で示した」
まさにその通りだと思う。文化としての音楽は、音の創作や演奏だけで成り立っているわけではなく、そうした行動を成立させるさまざまな文脈と、それを支えているあらゆる言説から成り立っている。どれが抜けても音楽は続いていかない。研究や評論は、その意味では広義における音楽の創造的プラクシスのひとつなのだ。実践(作曲・演奏)と理論(評価)を分けるという、あるいみヨーロッパ的な音楽伝統は、世界的な規模での音楽実践には当てはまらない。そのことを、京都賞は率先して確認したということになろう。
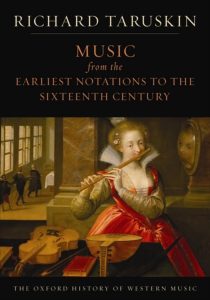 京都賞の各部門・各分野には対象領域が記されており、それぞれが事細かく厳密に他分野との境界を規定しているのであるが、こと音楽分野に関してはごくごく大ざっぱに、音楽に関係するさまざまな領域、くらいのことしか謳っていない。「音楽」の定義もしていない。できないし、しようとするとなにかが欠けてしまうからだ。
京都賞の各部門・各分野には対象領域が記されており、それぞれが事細かく厳密に他分野との境界を規定しているのであるが、こと音楽分野に関してはごくごく大ざっぱに、音楽に関係するさまざまな領域、くらいのことしか謳っていない。「音楽」の定義もしていない。できないし、しようとするとなにかが欠けてしまうからだ。
さて、受賞したタラスキン。なんと言ってもそのいちばん大きな仕事は、ひとりで書いた大部6巻(記述部分は全5巻)の『オックスフォード西洋音楽史』だろう。総ページが4000ページほどのこのきわめてオリジナルな音楽史は、2009年の完結時より機会あるごとに読み進めてきたが、目を通していない項目も多々あった。この機会にしっかりと読んでみようと思い立ち、今年度のゼミナルで採り上げて、2巻からなる20世紀の部分を読むことにした。19世紀の巻は、現在翻訳が進行中であると聞いたことでもあるし。さて、その顛末に関してはのちほど。
(2019/1/15)
———————————–
長木誠司(Seiji Choki)
1958年福岡県出身。東京大学大学院総合文化研究科教授(表象文化論)。音楽学者・音楽評論家。オペラおよび現代の日本と西洋の音楽を多方面より研究。東京大学文学部、東京藝術大学大学院博士課程修了。著書に『前衛音楽の漂流者たち もうひとつの音楽的近代』、『戦後の音楽 芸術音楽のポリティクスとポエティクス』(作品社)、『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』(平凡社)。共著に『日本戦後音楽史 上・下』(平凡社)など。



