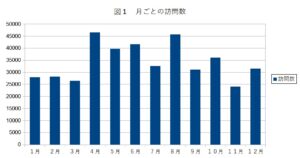忘れがたいコンサート|第3回ソビエト国際音楽祭 松村禎三「ピアノ協奏曲第2番」|丘山万里子
第3回ソビエト国際音楽祭 松村禎三「ピアノ協奏曲第2番」〜野島稔pf
text & photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)
1988年レニングラード(現サンクトペテルブルク)で開催された第3回ソビエト国際音楽祭での松村禎三『ピアノ協奏曲第2番』(野島稔pf)。共産圏はチェコ、ハンガリー、中国と行っており、物資・自由の乏しい生活ぶりにさほど驚くことはなかったが、ペレストロイカの風は音楽祭の演目にも感じられた。ケージ、ノーノ、リーム、クセナキスらの音にブーやブラボー、聴きながらぺちゃくちゃ即感想、前後の拍手もまばらだがいたって真面目な聴衆(小さな子供も含め)。コンサートホールでの音楽がいかに貴重な楽しみかがひしひし伝わる。
一柳慧、芥川也寸志、間宮芳生らの作品も演奏されたが、松村の時は空気が一変した。
オーケストラは最初手探り状態だったが、ピアノが凍光のような4度の6連音を鳴らし始めると「ん?」と全員(聴衆も)の耳が寄ってくるのがわかる。モチーフ同型反復が様々に変容しつつ松村オスティナートを撚り綯ってゆく、そのピアノの牽引力の凄さ。音魂を叩き込むとはこういうことだ。最弱音であれ最強音であれ、打鍵の全てに魂が宿り発光、それが楽員一人一人の背に火をつけ風を煽り、野火のようにめらめら広がってゆく。私は野島を凝視しっぱなし、ほとんど我が身、叩かれる鍵盤状態に(いや全員が彼の指の下、みんなそこに飛び散る音になり、だ)。第2楽章、深海の底に沈む梵鐘を思わせるピアノの静謐が、前章での烈しい拍動を鎮める。ホール、頭を垂れ。最後、響きの乱舞ののち現れるピアノのトリルとそのかそけき残光がしじまに消え入る・・・じっと深く長い人々の沈黙。ふと我に返ったような拍手が起こる。こんなシーンは他では見なかった。終演後、松村を取り巻く各国の大勢の人々の輪。
私は胸が膨れ上がって爆発しそうだった。
もちろん、音楽で。
だけでなく、どうだい、これが日本の誇る作曲家、ピアニストだぜ。
何が起きたのか。
知らないもの、でも、すごく深いところで知っているような気がするもの、そこに触れた。今まで触れられたことのない、でも、私たちの中に確かにある、そこに光を当てられた。そんな感じだった。
文化の相違とかなんとか、どうでもいい。あるようでないようなものだ。
欧米、中東、アジア、アフリカ64ヶ国400人を超す演奏家、作曲家たちの中に混じって1週間、一緒にどやどや送迎バスに乗り、ご飯を食べ、音楽を聴き、話せば、「ある、けど、ないかも」と感じるようになる。
「ある、けど、ない、けど、もっと深いところに・・・あった!」。
そういう了解の底の底を松村と野島はみんなに覗かせたのではないか。
私についてくれた若い女性通訳リュダは、自分たちは物がなくて不幸だと思っている、と言った。モスクワではデパートにも連れて行ってくれたが、化粧品なんて小さな薬屋程度のまばらな陳列、乳液も買えないと嘆く。日本からのお土産のありったけを彼女の手に押し込むと、恥ずかしい、私には何もあげる物がない、と俯いた。恥ずかしいのはこっちだ、何でもある、何でもできる、それにどっかとあぐらをかいて。
出会ったソビエトの作曲家、演奏家たちの「つて」を求める必死さ。国立エージェント(ゴス・コン)支配下で、西側へのわずかな可能性をつかもうとそっと連絡先の紙片を握らせる。チャンスが欲しい、チャンスが。
大スター、スピヴァコフは演奏前に客席に向かって聴衆からの手紙を読んだ。「どんなにか聴きたいのに切符が買えず、悲しい、もっと大きなホールでやって」。彼は言った。「私だってそうしたい、でも私を管理している人たちがそうさせてくれない。」
日本では彼のコンサート、満員盛況とはいかないのだけれど。
野心に目をギラギラさせた若きゲルギエフとのランチの席には松村も居たっけ。
がたぴしエアロフロートの後部座席で野島に、日本人が西洋音楽をやることについて少し聞いたら、こう答えた。
「そりゃあ僕らはどうしたって不利です。でも僕はいつでも音の生まれた最初の時のことを考える。西洋とか日本とかの枠以前の、人間が最初に声を出す、すごくプリミティブなところでの声。いつでもそこから音楽を発想して行くんですよね。」
鉄のカーテンが消えたのはその翌年、ソビエト崩壊は3年後の1991年だ。
リュダ、今は幸せ?
(2018/10/15)