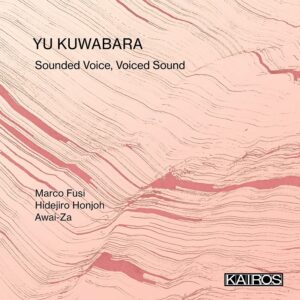Books|ショスタコーヴィチとスターリン|能登原由美
ソロモン・ヴォルコフ著
亀山郁夫・梅津紀雄・前田和泉・古川哲訳
慶應義塾大学出版会 2018年
Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)
今や交響曲のみならず、協奏曲や室内楽曲などでも演奏会レパートリーの定番になりつつあるショスタコーヴィチ。一部のファンの間での根強い支持は以前から見られたが、ここ十数年の間により幅広い層へと人気が広がってきているように感じられる。少なくとも、20世紀に生を受けた作曲家の中で、この人の作品ほど演奏されている人はいないのではないだろうか。たとえその音楽スタイルは19世紀的といわれても、である。
そうした人気の広がりを証明するかのように、この春、ショスタコーヴィチに関連する日本語の書籍が相次いで刊行された。つまり、ロシア文学者の亀山郁夫による評伝『ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光』(岩波書店)と、旧ソ連出身の音楽学者で批評家のソロモン・ヴォルコフによる『ショスタコーヴィチとスターリン』(慶應義塾大学出版会)である。後者は、先の亀山ほかロシア音楽の研究者や文学研究者によって邦訳された。両書籍ともに、ショスタコーヴィチの創作活動をソヴィエト連邦という特殊な政治体制から照射する点では同じだが、後者の場合は特に独裁者と芸術家との関係性に焦点を当てることで、個々の作品の背景やその深部に肉薄するとともに、音楽評伝の域を超えた人間ドラマとしても読むことができる。よって、ここでは後者について紹介したい。
まずは著者であるヴォルコフについて若干述べておく必要があるだろう。というのも、現在のショスタコーヴィチ受容の背景には、ヴォルコフもある意味で重要な役割を果たしているためである。すなわち、彼がアメリカに亡命した直後に出版した『ショスタコーヴィチの証言』は、それまでのショスタコーヴィチの評価を大きく覆すものとして話題を呼んだ。周知のように、ショスタコーヴィチについては、ソヴィエト共産党による一党独裁体制に従いその方針に則った創作や行動を取っていたがゆえに、多くの音楽学者や批評家などからソヴィエトのプロパガンダ作曲家との烙印を押されたという過去がある。そうしたなか、ヴォルコフは最晩年のショスタコーヴィチと交流をもち、その際に作曲家から得たという証言をもとにそれまでの行動の裏に隠されていた「反体制的な」心情を書籍の中で暴露することで、作曲家像の一大転換に大きく寄与したかに見えた。ところが、書籍の刊行直後からこれらの証言の信憑性に疑問が投げかけられるようになり、その内容もヴォルコフ自身の信頼性も地に堕ちるとともに、作曲家の真意や作品の解釈についても引き続き議論を残すことになったのである。こうした経緯については、ショスタコーヴィチの研究者やファンの間ではすでによく知られていることであろうが、『ショスタコーヴィチとスターリン』の訳者あとがきの中で亀山が簡潔にまとめた内容は、これまでのショスタコーヴィチをめぐる評価の変遷を改めて考える上で非常に興味深かった。
さて、2004年に英語版とロシア語版が相次いで刊行されたこの『ショスタコーヴィチとスターリン』は、その曰くつきの前作から25年を経て、ヴォルコフが名誉挽回を図るべく改めて世に問うたショスタコーヴィチ評伝ということになる。ただし、この中では前作の真偽についての踏み込んだ発言はなされていない。代わりに、彼は本書を「文化史の本」と明示した上で、その具体的な狙いを次のように表明する。すなわち、「ショスタコーヴィチとスターリンを結びつけた2つの中核的な出来事を、これまでで最も詳細に再構成する」というものである。その2つの出来事とはつまり、1936年の『プラウダ』紙上への、ショスタコーヴィチのオペラ《ムツェンスク郡のマクベス夫人》に対する批判的論説(「音楽ならざる荒唐無稽」と題される)の掲載、そして1948年の中央委員会共産党による作曲家たちへの批判決議である。とりわけ、無記名で書かれた『プラウダ』紙の論説については、ヴォルコフは数多くの一次資料や状況証拠の検証を踏まえて、これがスターリン自身によって述べたられたものであると主張する。
一方、本書の山場となるこの2つの出来事の裾野を形成するのが、知識人や芸術家に対するスターリンの粛清の様子である。そのなかでスターリンがどのように芸術を捉え、自らの立場を固めるべくそれを利用していったのかが細かく描写されていく。もちろん、こうした独裁者の行動がいずれは我らが作曲家にも及ぶだろうことを匂わせつつである。その結果、徐々に高められていく緊張の果てにこれらの出来事を迎えたときの衝撃は、作曲家のみならず読み手の我々にとっても決して小さくはならないのである。
とはいえ、ヴォルコフはショスタコーヴィチを単なる犠牲者として提示しているわけではない。むしろ、「聖愚者」、すなわち権力者に対峙する者としてロシア史に登場する特有の人格に見立てる。そればかりか、そこに「僭称者」、「年代記作者」の姿をも見い出し、「ショスタコーヴィチは、これら3つの仮面の全てをそれらが自分に合うように適応させ、多年にわたってそれらを操ることで、芸術的対話と皇帝との対決という、プーシキンやムソルグスキーによるロシア伝統の真の後継者に位置付けた」とみるのである。スターリンという独裁者のもとで身に纏っていったこれらの仮面は、本書におけるヴォルコフの主張のもう一つの重要な点であり、定まることのないショスタコーヴィチ像をもたらしているのがこの作曲家の「多面性」であることを示唆するのである。
このように、ヴォルコフは前作とは別の視点でもって、改めてショスタコーヴィチの姿を我々の前に示したといえる。しかも、作曲家よりもむしろ独裁者の心理に迫った本書では、権力(者)と芸術(家)の関係が浮き彫りになっている。そこでは、権力によって抑圧される芸術という一方向の構図だけではなく、権力を利用する芸術という逆向きの構図も透けて見え、まさに両者の「共犯」とも呼べる関係性が露わにされるのである。
だが改めて思う。こうした創作の背景は、現在の、そしてこれからのショスタコーヴィチの人気にそれほど大きな影響は与えないのではないかと。訳者あとがきにおいて「このブームも、第二段階に入りつつある」、すなわち「歴史的再評価の段階から、よい意味における大衆化、世俗化への段階への移行である」と亀山が述べるように、聴き手にとっては作品そのものが放つ強烈な魅力を前に、作曲家の実像は些細なことであるのかもしれないと。いや逆に、深まる謎は新たな好奇心を呼び起こす可能性もあるかもしれない。私自身、本書を読んでショスタコーヴィチを改めて聞き直してみたいと思ったものだ。音の響きの裏に隠された真意を想像しながら聞くと、これまでとは違った音楽が聞こえてくるかもしれない。
(2018/8/15)