小人閑居為不善日記|高畑勲の理想、矛盾、未来|noirse
高畑勲の理想、矛盾、未来
text by noirse
1
高畑勲が亡くなった。日本のアニメにおける高畑の存在は、クラシックで言えばバッハ、映画ならD・W・グリフィス、小説ならドストエフスキーや漱石、マンガなら手塚治虫。その程度には相当するだろう。ただちょっと事情が違うのは、高畑の片腕だった宮崎駿のほうが有名になってしまった点だ。チャーリー・パーカーよりディジー・ガレスピーのほうが有名になるようなものだろうか。
それにはそれ相当の理由がある。高畑は日本アニメの偉大なイノベイターだが、同時にハードコアでもあった。一切の妥協を許さないその姿勢が、かえって高畑を一定以上の人気から遠ざけてしまった。
では、高畑勲をハードコアたらしめるものとは何だったのだろうか。入念な取材に裏打ちされた迫真性、長大な議論の果てに積み重ねられた演出プラン、鋭い観察眼を元にした緻密で繊細な作画。これら技法面に関しては専門家による多くの分析があるし、付け加えることもない。ここでは、少し違った側面から見てみよう。すなわち、「労働」である。
2
 高畑勲の監督第一作《太陽の王子 ホルスの大冒険》(1968)は、子供向けアニメの体裁を取ってはいるが、ベトナム戦争を意識した反戦映画だった。と同時に、労働が本来持つべき喜びや理想を問う、労働者のための映画でもあった。
高畑勲の監督第一作《太陽の王子 ホルスの大冒険》(1968)は、子供向けアニメの体裁を取ってはいるが、ベトナム戦争を意識した反戦映画だった。と同時に、労働が本来持つべき喜びや理想を問う、労働者のための映画でもあった。
と、これだけだとよくある社会派映画だと思うかもしれないが、《ホルス》の重要な点は、制作現場にある。高畑は監督という特権的な位置から降りて、スタッフを平等に扱い、多く意見を取り入れる、民主主義的な体制を取った。労働者の自由や権利を謳う映画を、作品内だけでなく、作品作りのレベルからも実施したわけだ(まだキャリアの浅かった宮崎は、この時に制作に深く喰い込み、一目置かれるようになっていった)。
 それは世界的な気運でもあった。1960年代に吹き荒れた自由民権運動や反戦運動は、表現の分野にまで影響を与えた。たとえばヌーベルバーグだ。ジャン・リュック・ゴダールは、《女と男のいる舗道》(1962)や《軽蔑》(1963)など、初期から既に労働問題を取り扱っている。それはいつしか「映画の撮影現場における労働とは何か」という、実際的かつ自己言及的な問題にまで繋がっていく。
それは世界的な気運でもあった。1960年代に吹き荒れた自由民権運動や反戦運動は、表現の分野にまで影響を与えた。たとえばヌーベルバーグだ。ジャン・リュック・ゴダールは、《女と男のいる舗道》(1962)や《軽蔑》(1963)など、初期から既に労働問題を取り扱っている。それはいつしか「映画の撮影現場における労働とは何か」という、実際的かつ自己言及的な問題にまで繋がっていく。
このような問題意識は、高畑と共通するものだ。日本のアニメという観点から少し離れてみれば、高畑勲はゴダールと並ぶ、政治的な作家と位置付けることができる。
《ホルス》での試みは、のちの世界名作劇場三部作、《アルプスの少女ハイジ》(1974)、《母をたずねて三千里》(1976)、《赤毛のアン》(1979)で頂点に達する。三部作の中核にあるのは、「労働」だ。ハイジもマルコもアンも、子供ながら身を粉にして働き、その報酬として衣食住を得て生きていく。同様のテーマは、《火垂るの墓》(1988)、《おもひでぽろぽろ》(1991)から《かぐや姫の物語》(2013)まで、終生高畑作品の中核を為していく。
三部作は、ドラマティックな展開はさほど起こらず、日常の静かな時間が淡々と流れていく、見ようによっては地味なものだ。だがそれまでの日本のアニメになかったこの試みは、のちの作品に多大な影響を与えた。《となりのトトロ》(1988)も、昨年話題となった《この世界の片隅に》も、三部作なしでは存在しなかったかもしれない(宮崎は三部作にレイアウト担当で参加、後者の監督・片渕須直も、高畑の元でキャリアを積んでいる)。また、《けいおん!》(2009)など「日常系アニメ」と呼ばれる一群や、最近だと《ハクメイとミコチ》や《ゆるキャン△》といった作品も、高畑の系譜に連なるだろう。《ホルス》の高畑たちの強い意思が日本のアニメを豊かにしたことが、これだけでも分かるはずだ。
3
 とこれだけなら、美談で終わるかもしれない。だが世の中というものは、残念ながらきれいごとだけでは終わらないものだ。
とこれだけなら、美談で終わるかもしれない。だが世の中というものは、残念ながらきれいごとだけでは終わらないものだ。
ジブリの製作現場における宮崎駿の専制君主振りはとみに知られている。高畑勲もプロデューサー泣かせの監督として有名だ。とにかく納期に収まらない。《火垂るの墓》に至っては結局彩色が間に合わず、一部のシーンが「白い」ままで公開された(その後修正されている)。《ホルス》の完成は当初の予定を大幅に超過、三年もかかってしまい、責任を問われたプロデューサーは東映を退社している。
労働の喜びを声高に謳うのはいいが、集団制作の場でそれを維持することは難しい。高畑や宮崎のような才能をフルに発揮するには、やはりピラミッド式の現場とならざるを得まい。宮崎の《風立ちぬ》で語られる「ピラミッドのある世界とない世界のどちらがよいか」という問いが当時議論を呼んだが、高畑も宮崎も、明らかに「ピラミッドのある世界」の住人――それも頂点に君臨する者――だろう。天才が君臨する世界は、残念ながら平等にはなり得ない。
《ホルス》の理想は、高畑や宮崎自身の手によってくつがえされた。たとえばジブリスタジオを見れば分かる。ジブリは、アニメスタジオではめずらしくアニメーターの社員登用を推進していた。それだけならまだ、《ホルス》の理想を追いかけていたと言えるかもしれない。しかし《思い出のマーニー》完成後、宮崎駿の引退宣言と共に、ジブリは大半の社員を解雇した。もともとどういった契約形態だったかまでは分からないが、終身雇用の保証はなかったようだ。雇用に不安がある中で、労働の喜びは宿るのだろうか。高畑の作品はもちろん素晴らしいが、肝心な部分で矛盾を孕んでいる。
4
だが、高畑や宮崎を批判する気はない。アニメや映画制作などというものは、9時5時できっちり終わるようなものではないだろう。もちろんそういう現場もあるだろうが、そううまくいくものでもあるまい。特に完璧主義者・高畑の現場は、労苦を強いるものだったろう。しかし作品のクオリティを支える現場が、作品が訴える理想と矛盾するのであれば、我々はその作品をどういう思いで見ればいいのだろうか。
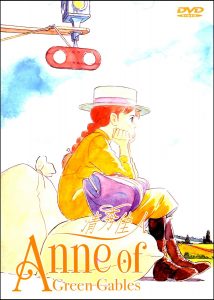 わたしは高畑の最高傑作は《赤毛のアン》だと考えている。作品自体が素晴らしいのは言うまでもない。ここで展開できる字数はもうないが、高畑のある判断と演出によって、この作品は名作とされる原作を越えていると思う。
わたしは高畑の最高傑作は《赤毛のアン》だと考えている。作品自体が素晴らしいのは言うまでもない。ここで展開できる字数はもうないが、高畑のある判断と演出によって、この作品は名作とされる原作を越えていると思う。
だが《赤毛のアン》は、こと作画面からのみ見れば、高畑のフィルモグラフィ中、最も不安定な作品でもある。過酷なスケジュールに追われ、制作に充分な時間をかけることができず、人物などがほぼ動かず、紙芝居のようだったり、デッサンが狂ったような箇所も、一箇所や二箇所ではない。このような事態は、高畑のキャリアの中で《赤毛のアン》だけだ。
こういう状態を、口さがないアニメ視聴者は「作画崩壊」と呼び、揶揄の対象としている。最近は視聴者の目も肥えて、作画の揺らぎに厳しくなってきている。今の目から見れば、《赤毛のアン》も作画崩壊した、出来損ないなのかもしれない。
そうした批判を生まないように、現場にはさらなるプレッシャーがかかる。ご存知の通り、日本のアニメの労働現場は、ただでさえ劣悪な状況にある。こうしていっそう、アニメの労働の場は理想から遠ざかっていく。
だが、作画が安定していないというだけで、その作品は失敗作なのだろうか。《赤毛のアン》は、作画こそ問題があるが、作者の意図を越えた解釈、計算され尽くした緻密な演出、高畑の期待に応えた声優陣、三善晃と毛利蔵人による主題歌や劇伴、その他様々な力によって、傑出した作品であると断言できる。高畑自身はそう思っていなかったろうが、彼の才能は、たとえ作画クオリティが標準以下だったとしても、作品にとって致命的な欠点ではなかったことを証明している。
アニメーションという言葉は、アニミズムが語源だとよく言われる。アニメにアニミズムを宿らせるのは、おそらく豊かな作画なのだろう。だがわたしは、良質なアニメを成立させるための条件に、作画の質は必ずしも必要ないと思っている。たぶんこうした意見はかなりの少数派で、アニメに詳しい人からすれば一笑に付されるだろうが、そういう声が少しくらいあってもいいだろう。
では、アニメーションの本質とは何なのか。これは難問だが《赤毛のアン》や高畑の作品にその答えがたしかに潜んでいる、そんな妙な確信だけはある。そしてその中核にこそ、若き高畑が掴もうと苦心した、アニメの理想の労働現場――見る者はもちろん、働く者も幸福を感じ取れる場所――へ到達するためのヒントが隠されているのかもしれない。
(2018/5/15)
————————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


