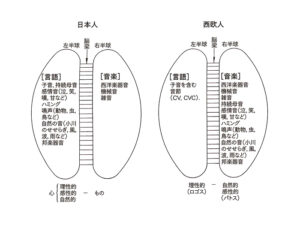小人閑居為不善日記|悪魔とカルトのカリフォルニア――サンダーキャット《Drunk》|noirse
悪魔とカルトのカリフォルニア――サンダーキャット《Drunk》
text by noirse
1
サンダーキャットの《Drunk》は、2017年、各プレスで最も高く評価されたアルバムのひとつだ。
サンダーキャットのキャリアは、カリフォルニアを代表するハードコア・スケーター・バンド、スイサイダル・テンデンシーズから始まった。その後、フライング・ロータスやケンドリック・ラマーの作品で注目を浴びる。ケンドリック・ラマーはL.A.南部のコンプトン出身。N.W.A.を輩出した同地は、西海岸ヒップホップ史上重要な街だ。
フライング・ロータスはジョン・コルトレーンとアリス・コルトレーンの甥。アリスは1970年代以降、カリフォルニアに活動の拠点を移した。フライング・ロータスもカリフォルニア出身だ。
サンダーキャットは、フュージョンの衣鉢を受け継いでもいる。彼が好むジョージ・デュークは、カリフォルニアのフュージョン・シーンの要だった。《Drunk》でゲストに迎えたケニー・ロギンスやマイケル・マクドナルドも、ウエストコースト・ロックを代表する存在で、カリフォルニアと縁が深い。
《Drunk》はエレクトロニカ、ジャズ、AORを高度に結晶化したと評されたが、こう並べると、豊かなカリフォルニア・サウンドの沃野こそが、このアルバムを支えていることが分かるだろう。
 フライング・ロータスも同様だ。《You’re Dead!》(2014)では同じくケンドリック・ラマーや、L.A.ジャズの最前線に立つカマシ・ワシントンを迎えた。
フライング・ロータスも同様だ。《You’re Dead!》(2014)では同じくケンドリック・ラマーや、L.A.ジャズの最前線に立つカマシ・ワシントンを迎えた。
だが《You’re Dead!》を手にしてまず印象に残るのは、マンガ家、駕籠真太郎が手掛けたジャケットだろう。これは「死後の世界」というアルバムのテーマを表現している。
死後の世界。フライング・ロータスが据えたこのテーマは、カリフォルニアという地を雄弁に語っている。
2
昨年の11月19日、稀代の犯罪者にしてカルトのリーダー、チャールズ・マンソンが病死した。ファミリーと名付けられた集団を率いてL.A.に現れた彼は、1969年8月9日、腹心の仲間に命じて、映画監督ロマン・ポランスキーの妻、シャロン・テートら5人を殺害した。ウッドストック・フェスティバルの6日前だ。マンソンとファミリーは逮捕され、彼は終身刑に処された。
 マンソンは弁護のしようのない犯罪者だが、サブカルチャーにおいては特別な処遇を受けた。ロック・バンド、マリリン・マンソンのネーミングの由来はマンソンだ。英国のバンド、カサビアンの名も、ファミリーのひとりリンダ・カサビアンから採られた。映画監督クエンティン・タランティーノの次回作はシャロン・テート事件を題材にしていて、トム・クルーズにオファーを出していると噂されている。
マンソンは弁護のしようのない犯罪者だが、サブカルチャーにおいては特別な処遇を受けた。ロック・バンド、マリリン・マンソンのネーミングの由来はマンソンだ。英国のバンド、カサビアンの名も、ファミリーのひとりリンダ・カサビアンから採られた。映画監督クエンティン・タランティーノの次回作はシャロン・テート事件を題材にしていて、トム・クルーズにオファーを出していると噂されている。
何故マンソンは「人気」があるのか。音楽面に限って言えば、マンソンがミュージシャンでもあったからだろう。マンソンは何枚かのアルバムを残している。大半は刑務所内でレコーディングされたものだが、逮捕前の音源を集めた《Lie》(1970)は一部で強い支持を受け、ガンズ・アンド・ローゼズやロブ・ゾンビ、レモンヘッズ、変わったところでは《バック・トゥ・ザ・フューチャー》(1985)で主人公マーティの父親を演じたクリスピン・グローヴァーらがカバーしている(クリスピンは実験映画の監督として活動している)。
L.A.にやってきたマンソンの目的は、音楽で成功を掴むためでもあった。マンソンは当時、多くの業界人と接触している。ニール・ヤングも面識のあったひとりで、〈Revolution Blues〉(1974)はマンソンについて歌ったものだ。とりわけ深く関わったのは、デニス・ウィルソンとテリー・メルチャーだった。
デニス・ウィルソンはビーチ・ボーイズのメンバーとして成功していたが、マンソンのカリスマ性とファミリーの女たちに魅了され、たちまち取り込まれていった。マンソンはデニスの屋敷に入り浸り、自分を売り込んだ。そこで紹介されたのが、テリー・メルチャーだ。
メルチャーはドリス・デイの息子で、その豊かな才能で、コロンビア・レコードの再興に大きく寄与した。バーズを見出し、ロックの歴史を変えていったのも彼だ。
メルチャーもマンソンの才能に目を付けたようだが、結局話は流れた。マンソンは激怒し、ファミリーにメルチャーの殺害を命じる。だが彼は既に転居していて、入れ替わりメルチャー邸に入居していたのがシャロン・テートだった。彼女は手違いで殺されたのだ。
3
 昨年話題になった作品としてもう1枚、ベックの《Colors》をピックしよう。マンソンとベックには共通点がある。
昨年話題になった作品としてもう1枚、ベックの《Colors》をピックしよう。マンソンとベックには共通点がある。
《ザ・サークル》(2017)という映画がある。グーグルやフェイスブックを彷彿とさせる企業「ザ・サークル」を巡り、SNSや巨大化するインターネット企業に警鐘を鳴らすといった内容だ。「ザ・サークル」のパーティでベックは、新曲〈Dreams〉を披露した。だがこのシーン、複雑な思いなしに見ることはできない。ベックはサイエントロジー教団の信者だからだ。
 サイエントロジーは、SF作家ロン・ハバードが著した自己啓発書から発展した新興宗教だ。有名人を勧誘し、熱心な信者に育て上げ、広告塔に仕立てるという方法論がハマり、L.A.を中心に、アメリカ中で支持を得ている。トム・クルーズやジョン・トラヴォルタ、ジェニファー・ロペスを始め、グレイトフル・デッドのメンバーやチック・コリア、ウィリアム・バロウズなどが信者として知られている。ベックの父親も音楽家だったが、サイエントロジーの初期から入信していた。ベックの信仰も親の影響だろう。
サイエントロジーは、SF作家ロン・ハバードが著した自己啓発書から発展した新興宗教だ。有名人を勧誘し、熱心な信者に育て上げ、広告塔に仕立てるという方法論がハマり、L.A.を中心に、アメリカ中で支持を得ている。トム・クルーズやジョン・トラヴォルタ、ジェニファー・ロペスを始め、グレイトフル・デッドのメンバーやチック・コリア、ウィリアム・バロウズなどが信者として知られている。ベックの父親も音楽家だったが、サイエントロジーの初期から入信していた。ベックの信仰も親の影響だろう。
マンソンもサイエントロジーに感化されたひとりだった。だが正確に言うと彼が出会ったのは、悪魔主義に接近したサイエントロジーの分派、プロミスという集団だったようだ。
当時、サタニズムはちょっとしたブームだった。たとえばローリング・ストーンズだ。《サタニック・マジェスティーズ》(1967)というアルバムを作り、ミック・ジャガーは《悪魔を憐れむ歌》(1968)で、ルシファーとして振る舞った。
カリフォルニアを代表する映画監督ケネス・アンガーは、魔術師アレイスター・クロウリーの思想を映像化するため、《ルシファー・ライジング》(1980)にミックとキース・リチャーズをキャスティングしようと試みた。これは実現しなかったが、やはりクロウリ―に傾倒していたジミー・ペイジは、楽曲製作を許諾した(後に頓挫したが)。
ミックの抜けた穴は、ボビー・ボーソレイユという若者によって埋められた。その後アンガーと決別した彼はマンソンと出会い、シャロン・テート事件の実行犯となる。アンガーは、ハリウッドのスキャンダル本《ハリウッド・バビロン》(1959)でも有名だが、これを再刊する際、自分と奇妙な接点を持ったテート事件にも言及した。このように、カリフォルニアの音楽や映画の裏側には、カルトやサタニズムがべったり貼り付いていたのだ。
4
60年代のカウンター・カルチャーとは、抑圧的な価値観からの解放、キリスト教からの自由を勝ち取るための戦いだった。主戦場はカリフォルニアであり、そのサウンドトラックがロックだった。
ヒッピーはキリスト教に変わる思想を探し求めた。だがそれは、カルトにとっての一大市場でもあった。サイエントロジー。チルドレン・オブ・ゴッド。ハレー・クリシュナ。統一教会(発祥は韓国だが、70年代以降のカリフォルニアで信者を増やした)。のちに集団自殺事件を起こした人民寺院。カリフォルニアは、新興宗教と自己啓発セミナーの温床となった。マンソンの事件は、それが極端なかたちで現れたものだ。
音楽家になるというマンソンの夢は潰えたが、その一端はビーチ・ボーイズの作品にも残っている。〈Never Learn Not To Love〉(1969)は、マンソンが書いた曲を元にしたものだ。この件でマンソンはデニスを恨み、殺すと脅して刑務所に入っていった。デニスは酒に溺れ、音楽活動にも支障をきたすようになり、39歳の若さで溺死した。テリー・メルチャーも事件後、ドラッグで仕事から遠ざかっていき、2004年に世を去った。彼らの人生を狂わせたのがマンソンなのは間違いないが、それはカリフォルニアのダークサイドでもあったろう。
革命に敗れた若者たちは、ネットに新天地を求めた。スティーブ・ジョブズが元ヒッピーで、ハレー・クリシュナの信者だったのは有名だ。ネットがカルト化するなどと安易に言うつもりはないが、ネットを取り巻く思想は、確かにカウンター・カルチャーの延長線上にある。そしてその中には、神秘思想やオカルトがもれなくセットされている。
 サンダーキャットの《Drunk》は、60年代のジャズ、70年代のフュージョン、80年代のAORやLAメタル、そして現代エレクトロニカの複合体としてある。まるでヒッピーのフロンティアからIT企業の拠点となった、カリフォルニアの歴史そのものだ。
サンダーキャットの《Drunk》は、60年代のジャズ、70年代のフュージョン、80年代のAORやLAメタル、そして現代エレクトロニカの複合体としてある。まるでヒッピーのフロンティアからIT企業の拠点となった、カリフォルニアの歴史そのものだ。
しかし一方その歌詞は、下品でトボけていてくだらなく、流麗なサウンドとのギャップが激しい。だがわたしは、そここそがこのアルバムの美点だと思う。
わたしもビーチ・ボーイズは好きだが、日常的に聞くことはあまりない。あまりに繊細すぎて、心の奥深くに沈められた、暗い感情が浮かび上がってくるように感じるからだ。
サンダーキャットのバカらしい歌詞は、カリフォルニアを相対化する。ビーチ・ボーイズの湛える繊細で美しい世界に、決して踏み込むことのないように。マンソンの如き男をも惹き付けてしまう、カリフォルニアのダークサイドに引きずり込まれることがないように。
このようなアティチュードは、2018年の今、かえって切実であるようにも思えるのだ。
(2018/1/15)
———————
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中