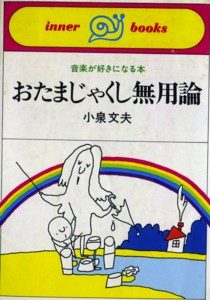Books | おたまじゃくし無用論|谷口昭弘
小泉文夫著
いんなあとりっぷ1973年5月出版 560円 (当時)
text by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)
小泉文夫といえば日本に「民族音楽」の愛好家を多く誕生させ、自らも音楽民族学者として世界中の音楽を調査し、日本古来からの音感を尊重するため「わらべうた」からの音楽教育を提唱した人である。また日本の伝統音楽の音階構造を分類してまとめたテトラコルド理論でも知られている。彼の元からは多くの音楽民族学者が生まれている。
そして『おたまじゃくし無用論』(以下『無用論』)は、小泉の数多くの著作の中でも、おそらく学校を中心とした音楽教育に携わる人々に大きな影響を与えたのではないだろうか。西洋音楽中心の画一的教育カリキュラム、その尺度でしか音楽を捉えない問題、わらべうたから始める音楽教育など、多くの注目すべき論点を提起している。残念ながら私自身はリアルタイムでこの『無用論』が出たときのインパクトを知らないのだが(私の持っている古本は1900年代初頭に入手したものだろう)、自分自身、音楽教育について学んでいた時期であったこともあり、特に学校教育の中で使われる教材が西洋の芸術音楽に偏重していることの問題については考えさせられることが多かった。私が大学学部を卒業した頃、まだ学校の音楽で日本の伝統音楽は必須のものとまではされていなかったように思う。
その後、大学で音楽を教える仕事を与えられ、この本のことを思い出した。「いまの学生たちは小泉の本をどのように捉えるのだろう?」そんなことに興味を持って、半ば自分自身の好奇心から、自分が受け持っている授業に、この『無用論』を読書課題として出すようになった。今回はこの本の書評とは言えないかもしれないけれど、いまどきの学生たちが読む小泉から、『無用論』について考えてみたい。
まず、西洋芸術音楽中心の価値観で作られた授業の中で「音痴」とされ音楽が嫌いになる子どもたちの問題を小泉は挙げているが、現在も学校の授業から音楽の退屈さを感じたり、音楽を嫌いになったという状況は変わっていないようだ。人前で歌う試験というのも行われており、中にはクラスメートから自分が歌った歌について「良い点・悪い点」を言われて評価され嫌な思いをしたという学生もいた。おそらく教室の環境や同級生との関係の問題もあるとは思うが、学校の成績に関わるテストのやり方には、まだまだ考慮すべき点があるようだ。日本の「恥の文化」というのもあるかもしれない。歌に限らず絵画や体育の世界でも、学校の授業で間違ったら、うまくいかなかったら、恥をかいたらどうしようという不安は常につきまとう。
またイマドキの習い事は多様化しているとは聞くが、やはりピアノやヴァイオリンを習ったという学生が多かったのは本が出版されてから45年たった現在も変わっていないようだ。その中に楽譜を自分の思うままに演奏したら強く怒られたという学生がいて、彼女は自分の気持ちを抑え、あるいは自分の気分と正反対の気持ちで楽器を弾かなければならず、しかも自然にふるまうようにさせられたため、ピアノが嫌いになったという。そのため小泉が「ピアノ・バイオリン教室は子どもを奇形児にするおそれがある」と述べたことに、この学生は強く共感していた。
これは難しい問題を孕んでいる。ことクラシック音楽は、もちろん様々な解釈の余地はあるが、「作曲者が考えていた音」「作曲者の心」を求める再現芸術であるからだ。もちろん子ども次第ではないかという意見も学生側にある。だが大人の私からすれば、やはり何かしら大人がケアすべき問題がそこにはあるように思えてくる。
「音楽に国境はある」という考えについては、おそらく専門家であれば、現在は当たり前のように受け入れられるが、最初は意外と抵抗があるようだ。海外アーティストのライブのコンサートは、例え歌詞が分からなくても楽しめたという学生もいる。日本人以上に日本文化を探求している海外の人々も多い。ただ実際に海外への渡航体験のある学生の場合、それが英語圏であっても、現地の人々と同じリズム感で音楽を味わえなかったり、あるいは音楽参加へのあり方の違いに直面することで、音楽の生まれる文脈に触れ、そこに「国境がある」体験を改めてする学生もいる。あるいはハンガリーのロマ(ジプシー)音楽から自らとは異なる人々について関心が及び、文化や伝統から音楽を捉え直す学生は、小泉の発想に共感するようだ。やはり非西洋音楽との出会いは大切なのかもしれない。こういった『無用論』が与えてくれる音楽のあり方に対する接し方は、マスメディアからの音楽にどっぷり浸かっている学生たちの音楽観に変革をもたらすという点では大きな意味がある。
そして『無用論』の根幹となっている「わらべうたからの教育」については「楽譜が読めなくてもわらべうたを歌うことができない子どもはいない」という点で小泉に賛同する学生がいた。誰かが歌っているのを聴けばすぐにうたうことができるからだ。また体全体でリズムを感ずる利点も指摘されていた。ただ洋楽がこれほど浸透した現代の日本において、伝統音楽の学習が新たな「型にはめた教育」に陥る危険性があると指摘する声もある。小泉の場合は、日本人がもともと持っていた音感が失われたことに対する問題の提起だったと思うのだが、雅楽や歌舞伎に「親しむ」というレベルだけでは、そういった問題の克服は確かに難しいのかもしれない。一方学校教員の大変さに共感する学生もいて、日本音楽の先生を体験学習のために学校に招くだけでなく、生徒と一緒に一定期間先生も学べばいいのではないかという解決法を提唱していた。おそらく学校教員向けの伝統音楽研修よりは、そういう形の方が効果的だろう。もっともそういった人材が確保できるのかなど、問題解決に至るにはたくさんの問題があるのだろう。
ほかにもいろいろ面白い論点はあるが、長くなるので、ここまでにしておこう。小泉の『無用論』には「オーケストラは奴隷的音楽だ」という、私的にも(学生も)首をかしげる部分もある。しかし今でも本書かれた内容からは多くのことを学ぶことができる。そしてその内容は、音楽の今日的問題を考える上でも、充分に役立つだろう。この『無用論』は、青土社や学研、ほるぷ出版からも再刊されている。改めて図書館などで手にとってみてはいかがだろうか(青土社版は現在オンデマンド版が入手可のようだ)。
(2018/1/15)