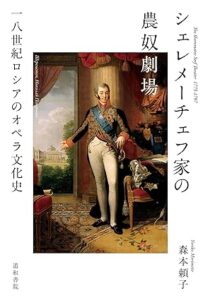Books|哲学としての美学|齋藤俊夫
ギュンター・ペルトナー著 渋谷治美監訳
晃洋書房
2017年4月出版
5000円(税別)
text by 齋藤俊夫 (Toshio Saito)
ギュンター・ペルトナーは1942年ウィーンに生まれ、一時期フライブルク大学で学んだ時期を除いて、ずっとウィーン大学で研究生活を送った哲学・美学学者。研究領域は中世哲学(教授資格論文ではトマス・アキナスを扱った)、ハイデガーの存在論、美学、生物学的認識論批判等々幅広い。現在はウィーン大学を定年退職し名誉教授としてゼミナールを開いている。
本書はドイツで『基礎叢書 哲学』シリーズの1冊として、哲学の1部門である美学の入門書として書かれた。それゆえ、本書は2部構成を取っている。第2章から第12章までは、ギリシアのプラトンから中世哲学、バウムガルテン、カントらの近代美学(哲学)、そしてショーペンハウアー、ニーチェを経てアドルノに至る西洋美学史の概説である。そして導入部に当たる第1章と、本書最後の第13、14章では、ハイデガーに負う所が大きいペルトナーの存在論的美学を論じている。
西洋美学史概説部分は極めて明晰に書かれているが(それは翻訳に負う所も大きい)、少々レベルが高いので、日本で読むのならば東大の『講座美学』、竹内敏雄『美学事典』を読了した程度の基礎学力が必要であろう。
また、この美学史概説も、著者の問題意識として、美学において「〈美〉とは何か」という主題が、「芸術哲学」となった現代の美学では従属的な役割しか演じなくなった、その歴史を批判的に辿るという視点があるのだが、本レビューにでは、より本書において個性的な、ペルトナーによる〈哲学としての美学〉である存在論的美学を概説したい。以下がその概説である。
まず、〈美しいもの〉が現れる(現在する)のは、それを我々が知覚し、認知することによってであり、〈美しいもの〉の〈美〉は我々の感知に先行するのでも後続するのでもなく、われわれが感知するとき、われわれの感知として生起する。つまり、例えば音楽(美しいもの)が音楽(美しいもの)として現れるのは我々が聴くこと(演奏すること、読譜することも広義の聴くことに含まれよう)によってであり、そしてその音楽の〈美〉は我々の中で生起する。
しかし、その〈美しいもの〉は我々なくしては現れないが、我々「によって」現れるものでもない。また〈美〉は我々の感知作用に起因するのではなく、〈美〉自身の根源から我々に己を示すのである。つまり、何かが〈美しい〉のは我々がそれを〈美しい〉と知覚するからでなく、それが〈美しい〉から我々はそれをそうと感じるのである。
従って、我々の美的経験は〈美しいもの〉の〈美〉に対して応答的なものである。しかし、この「応答」とは、〈美しいものとの出会いの経験〉に際して、我々がどれだけその〈美〉を受け入れ、生成・完成させる(本書では「現成(げんじょう)」という仏教用語を用いているが難解なので換言した)かによってその〈美〉がいかに光り輝くかが委ねられているということである。ここで「応答」とは「一致」の意味において、つまり、〈美しいもの〉の声に〈それを経験するもの〉が応答し、この2つのものが一致することにおいて美的経験をなすのである。
我々は常に何かと共に現在に存在する、つまり我々にとって〈世界全体は開かれ〉ており、その世界と共に我々は共―現在しているのである。〈美〉が現れることによって、通常は隠蔽されていたこの〈世界の開かれ〉が姿を現し、ただ〈現在している〉(現在あるように存在している)ものだけが見えていた世界において、〈明瞭に共―現在していること〉に我々の認識が至る、つまり我々が単独で現在に存在しているのではなく、他者、〈世界〉と共にあることが開けてくるのである。
我々が何かあるものについて〈美しい〉と口にするとき、我々が本当に考えているのは〈経験されていること〉自身である。この〈経験されていること〉自身が〈美しい〉のであって、それに付随するものが〈美しい〉のではない。例えば、愛の〈美〉は、愛を経験している者に愛がもたらす効果ではまったくなく、愛が経験されること自身が〈美しい〉のである。〈美しいもの〉が美しくあることは、その〈美しいもの〉の驚くべき顕現のうちに在る。
〈美〉の経験は1つの顕現を経験することである。存在すること(美しいものがあること)と現象すること(美しいものが美しく現れること)が根源的に一体であることが、存在の真理が〈美しい現れ〉のうちで実現することなのである。
〈美しいものとの根源的な出会いの経験〉は我々には予知できぬ、制御できぬものであり、その〈出会いの経験〉は我々を襲う。そしてこの襲われた出会いに〈驚く〉ことにおいて、現象することそのもの、存在自身が際立って現れる。そして驚く者は存在の事実に感動している。何が彼を驚かせるのか、それはこうしたことが「ある」ことなのだ。〈美〉に直面して驚く――それは存在が存在するということの奇蹟に寄せる感動である。
この〈美しいものとの根源的な出会いの経験〉は我々に感謝の念を生む。この経験は〈美しいもの〉を経験する機会を我々がもちうること、さらには、そもそも我々が現存在する(生きている)ことが可能であることに対する感謝の念である。存在することが可能であるということは〈美しい〉。〈美〉は〈現存在しうること〉に、つまり、そもそも我々が存在しうることに感謝の念を抱くように我々をうながす。
この感謝の念は特定の誰かに向けられたものではなく、〈存在しうること〉そのものに向けられる。そして〈存在しうること〉は〈与えられてある〉のだということが開示される。
〈美しいものとの根源的な出会いの経験〉は〈存在すること〉について思索するよう迫るのだが、その〈存在すること〉とは〈与えられてあること〉を意味する。このことを悟ったものは、さらに〈感謝することができること〉に感謝することができる。
以上、ペルトナーの存在論的美学を(評者なりに)概説したが、ここでペルトナーが明言していない視点について論じてみたい。我々の存在が〈与えられてあること〉の、その〈与える〉という能動態の主体は何ものなのか。プラトンから近代までならばそれは「神」であっただろうし、ショーペンハウアー・ニーチェではそれは「自己自身」であっただろう。しかし、ペルトナーにおいては、その主体はそれらではありえない。
(上記の概説の通り)ペルトナーにおいては我々は〈開かれた世界〉において〈共―現在している〉のであり、〈美しいもの〉〈美〉もまた、それ単独で存在し現れるのではなく、我々と共にあり、我々によって完成されるものであるのだから、我々も、〈美しいもの〉とその〈美〉も、それが存在しうることはただそれら単独の自己自身によるものではない。
美的経験が応答的であるが「一致的」であることと同じく、〈与える〉主体と〈与えられてある〉客体は一致的なものとして、我々の存在が〈与えられてあること〉は開示され、そのことは単独の存在ではなく開かれた世界に依る〈共―現在的〉存在である我々と、我々と共にあり、我々と一致する世界によって生成・完成(現成)されるのである。
近年日本においても(特にポピュラー音楽学において)芸術の社会学的研究や分析美学が急速に普及しつつあるが、そのような潮流に1石を投じるものとして本書とペルトナーの美学は有意義な思索体験、美学的視座を与えてくれるだろう。
(2017年12月15日)