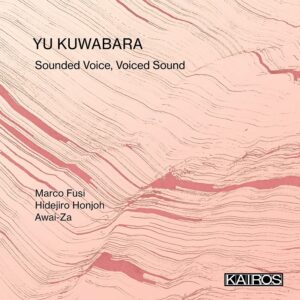Books|ある作曲家の生涯|片桐文子
カレル・チャペック(著)
田才益夫(訳)
青土社
2016年1月刊行 本体1600円
text by 片桐文子(Fumiko Katagiri)
アート関連のセレクトショップで見つけたこの本。色はタイトル文字の青だけ、白と黒のシンプルで美しい装幀。線描画がなんともしゃれている。「カレル・チャペック 最後の作品」という副題も気になり、つい買ってしまった。
チャペック(1890-1938)といえば、飼い犬のダーシェンカとの暮らしを愛情いっぱいに描いた『子犬の生活』が有名。何度も、いろいろな出版社から邦訳されている。チェコの国民的作家とは聞くけれど、恥ずかしながら他の作品は読んだことがない。考えてみれば、オペラ『マクロプロス家の事件』の原作者だった。そんな彼の人生最後の作品が「作曲家の生涯」? よほどの音楽好きだったのだろうか……。
巻末の訳者あとがきから読み始める。残念ながらこの物語は未完で、結末は妻オルガの補筆によること。テーマは、チャペックが20代に書き哲学博士の学位を取得した論文(芸術の鑑賞ないし体験における主観性と客観性、がテーマらしい)と響き合うもので、「原点回帰」の作品なのではないか、ということ。
若書きの文章が、その後の人生と創作の方向性を決定づけることは、なるほどあり得る。チャペックは、もちろん音楽好きだったのだろうが、彼の思索はもっと深く、「芸術とは何か」「創造とは何か」を生涯にわたる探究のテーマにした人だったらしい。がぜん、興味が湧く。
物語は、ベダ・フォルティーンという作曲家志望の青年が主人公。さまざまな関係者の証言という形で、彼の生涯が描き出されていく。青年時代の友人、付き合いのあった女性、同じ下宿の住人、のちの妻、彼が書きたかったオペラ『ユディット』の台本を依頼された博士、「後援者」として支援した音楽学生(しかし実際には『ユディット』の音楽を書かされる羽目になる)、など。
「作曲家志望」と書いたが、彼自身はすでに青年時代から、自分は並はずれた人間という自負心があって、振る舞いはまさに芸術家。
「あの方のウエーブのかかった美しい髪、澄んだ青い大きな瞳。長身というよりは、むしろ、ひょろりとした弱々しい体つき、遠くのほうに目を向け、帽子を手に、金髪を風になびかせながら、夢見るように歩く姿。」
周囲の人間は、危うさを感じながらも、彼の確信の強さに引きずられていく。妻となる女性は複数の貸家を所有する財産家の娘で、資金を手に入れたフォルティーンは自宅で音楽サロンを主宰し、いよいよオペラの作曲に邁進していく。しかし気の毒なことに、創造のアイデアは夢想的に過ぎ、それを形にする技術が身についていない。台本は結局、他人まかせ、音楽すらも3人の音楽学生に書かせた断片があるだけ。物語はオペラ上演へと向かっていくが……
ひたすら「イタい」フォルティーンの姿。嫌でも思い起こすのが佐村河内事件である。実際に本書のオビに文章を寄せているのは新垣隆氏だ。この事件が、チャペックのこの作品の邦訳刊行を後押ししたのかもしれない。出版の流れとしてはうなずけるが、オビは少々複雑な気持ち。
それはともかく、物語はいよいよ佳境、「創造とは何か」に切り込んでいく。チャペックの筆になる最後の証言者は、オペラ『ユディット』のオーケストレーションを担当した音楽家。この一事だけでも、チャペックの音楽に対する造詣の深さがうかがわれる。
「お前の中にあるもの、お前の人間性、お前の独自性(オリジナリティー)、それは単なる素材にすぎない。だから、それは決して形ではない。もしお前が芸術家なら、素材を増殖させるのではなく、むしろ素材に形と秩序を与えるような芸術家であるべきであろう。」
そしてなんと、ここで、聖書が登場するのだ。「初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が、水の表を動いていた。」天地創造の物語、まさに聖書巻頭の一文。おお、そこに来るか! これは面白くなるぞ!
身を乗り出すような思いで読み進めたが、チャペックの筆は次第に力を失っていき、文章はついに断片的なメモに……。その先は妻オルガの補筆で、生前のチャペックが語っていた言葉から類推して、オペラの実際の上演がいかなる結果に終わったかが描かれる。
上演はなるほどそういう結果に終わるだろう。でもいちばん読みたかったのは……チャペックが書きたかったのは……芸術とは何か、創造とは何かという、問いへの答え。
かえすがえすも残念である。
でも、短い(200頁に満たない)未完の物語なのに、実にさまざまなことを考えさせてくれる。音楽に関わる人なら、一読しておいてよい作品ではないかと思う。
装幀:松田行正
装画:チャペックの兄でのちにナチスの強制収容所で命を落とした、ヨゼフ・チャペック