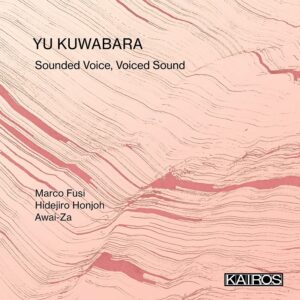Books|「オペラの20世紀」|齋藤俊夫
長木誠司著
平凡社 2015年10月発行
9200円
text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)
総ページ数約800(本文約700ページ、註・索引約100ページ)に及ぶが、しかし一字一句たりともおろそかにすることのない記述による、最後の最後までぎっしりと内容のつまった大著である。
本書は19世紀末のオペラとそれをとりまく状況の記述から始まって20世紀末までが基本的には時系列に沿って論述されているのだが、論じている主題の要となる作家・作品を取り上げる時にはそれらについて詳細な記述が紀伝体的に描かれ、ときには時代的に離れた作家・作品も同時に扱われる。本書で扱われたおよそ100年の歴史、それもヨーロッパからロシア、アメリカまで含めたそれを短くまとめることはおそらく不可能なので、少々長くなるが目次を引用し、その章で扱われた主な作曲家を記すことで本書の射程の広さを知ってもらいたい。
序章
第I部 オペラはヨーロッパのものだった
第1章 凋落するイタリア・オペラ
第2章 オペラのモダニズム(ヴァーグナー、R・シュトラウス、シュレーカー)
第3章 ヴェリズモからファシズムへ(ピッツェッティ、レスピーギ、カゼッラ、マリピエーロ、マスカーニ)
第4章 ポスト・ヴァーグナー――リヒャルトの遺産(ラフマニノフ)
第5章 ヴァーグナーの直系たち――メルヒェンと英雄と(フンパーディンク、ジークフリート・ヴァーグナー、R・シュトラウス、プフィッツナー、シュレーカー、ツェムリンスキー、コルンゴルト、ベルク)
第II部 オペラにおける中心の喪失
第6章 国民国家のオペラ(ヤナーチェク、マルティヌー)
第7章 新大陸のオペラ文化――文化的植民地から独自文化への道のり(スティル、コープランド、グルーエンバーグ、ジョプリン、ガーシュウィン、アンタイル)
第8章 二〇世紀の復古主義(ブゾーニ、ストラヴィンスキー)
第9章 オペラの危機――第一次世界大戦後の壊乱(1)
第10章 オペラ改革の二〇年代――第一次世界大戦後の壊乱(2)(ヒンデミット、シェーンベルク、クジェーネク、プーランク、ヴァイル、ミヨー)
第11章 ロシア・オペラの二〇世紀(プロコフィエフ、ストラヴィンスキー、デシェフォフ、モソロフ、ショスタコーヴィチ)
第III部 政治と暴力とセックスと
第12章 国民オペラの変容――ヴィシーを用意したオペラ(ブリュノー、オネゲル、ダンディ)
第13章 ファシズム時代のオペラ(クレーナウ、ダッラピッコラ)
第14章 シェーンベルク、ノーノ、ラッヘンマンのオペラへの〈道〉――無調と暴力の表象不可能性(シェーンベルク、ノーノ、ラッヘンマン)
第15章 オペラとセクシュアリティ(ベルク、シマノフスキ、ブリテン、ヘンツェ)
第IV部 変容するオペラ
第16章 室内オペラの誕生と展開(ブラッハー)
第17章 文学オペラの行方(ライマン)
第18章 レパートリーと演出の時代
第19章 二〇世紀の声
第V部 オペラはどこへ?
第20章 第二次世界大戦後のオペラの概況
第21章 戦後前衛のオペラ創作(オルフ、ツィンマーマン)
第22章 オペラの解体――〈オペラとドラマ〉から〈ポストドラマ〉としてのオペラへ(ベリオ)
第23章 アンチ・オペラ/アンチ・アンチ・オペラ(カーゲル、プスール、リゲティ)
第24章 わたしたちのオペラ/あなたたちのオペラ――一九七〇~八〇年代の転換と再燃(メシアン、シュトックハウゼン、ケージ)
第25章 オペラの逆襲/オペラへの逆襲――ミニマル・オペラと新ロマン主義(ヴァージル・トムソン、グラス、アダムズ、リーム、シュニトケ、ゴリホフ)
この浩瀚な書物が今日的な歴史書たり得ているのは、オペラをとりまく社会的・経済的なデータに基づく社会学的あるいは文化史的記述、作品と作家についての内在的・(狭義の)音楽学的記述、さらに、ナショナリズム、民族、コロニアリズム、人種、セクシュアリティなどの今日的な、また20世紀になってオペラの中にときに顕在化し、また多くの場合オペラの中に潜んだポリティカルな諸問題についての記述などの、複眼的な思考の軌跡によってである。
19世紀末イタリアの歌劇場のレパートリーの変化を、運営主体が興行主(インプレサーリオ)から出版社へと変化したことによると実証的に論じる。ベリオ『オペラ』のテクスト・コラージュから彼のコメンタール的音楽を解析する。シェーンベルクとノーノとラッヘンマンをベンヤミンの「神的暴力」のオペラによる表象、あるいはオペラによるその表象の不可能性の暴露として捉え直す。『ルル』からシマノフスキ、そしてブリテン、ヘンツェの同性愛というセクシュアリティの政治性を論ずる、といった現在の批評理論の先端を詰め込んだ音楽史の著作などこれまで日本にあったであろうか?
本書に通底し、これまでの音楽史の書物から別格のものとしているのは著者の持つ強靭な批評性、そしてその批評性の根底にある論理的・理論的堅固さである。ただのデータの羅列や感想ではなく、批評的論理に基づいてオペラとその歴史を読み解くことにより、「音楽」が、「オペラ」が歴史書の中から立ち現れてくるのである。「想像以上に裾野の広がるワンダーランドに多くのひとびとを招き入れたい」(あとがきより)という著者の意図は700ページを読破すれば十全に叶えられると言えよう。
ただ、1つだけ難を言わせてもらえば、著者の前著作である『戦後の音楽』(作品社)で開陳された「日本のオペラ」についての言及が序章の一部「日本の状況を踏まえつつ」と題された箇所でしか(それも否定的な形でしか)なされていないことは残念であった。世界史的な視点で日本のオペラをどう見ることができるのか?日本国内の視点に留まった前著作のその先にまだ肯定的な何かがあると評者には思えるのだが、これは過ぎた要求と言うものだろうか?