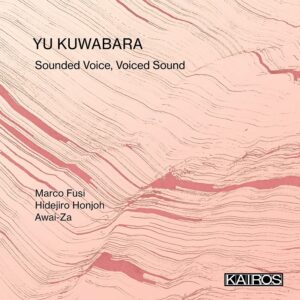Books|「黄昏の調べ」|丘山万里子
大久保 賢 著
春秋社 2016年5月発行
2700円
text by 丘山万里子( Mariko Okayama)
「この現代において、新たな音楽の創造は果たして可能なのか?そもそもそれが本当に必要なのか?仮に必要なのだとすれば、どんなものでありうるのか?逆に不要なのだとすれば、他にどんな道がありうるのか?」という問いが、本書の始発点であり、その筆者なりの答えが終着点である。
現代音楽の揺籃期、最盛期、衰退期を眺め、その「黄昏」の中に、何を見出そうとするか。
筆者は、現代音楽について「かなり強い愛着」と「相当辟易」の「愛憎相半ばする」、いや、「憎」の気持ちが今はやや強い、と告白しつつ、論を進める。したがって、歴史を客観的に語るというより、節々に滑り込んでいる筆者の愛憎のチラ見せが、本書を魅力的なものにしている。
筆者は「わかる者にしかわからない」現代音楽についてシェーンベルクの言葉を引く。
「芸術なるものであれば、それは万人のものではないのだし、万人のためのものだというのであれば、それは芸術ではない」
そうして、いや、シェーンベルクに限らない、バッハもモーツァルトもシューマンも、実はそう言ってのけているのだ、と述べる。例えばモーツァルト。父への手紙に「音楽通だけが面白いと思うようなパッセージもあちこちにあります」。とはいえ、「わからない者もそれなりに」という配慮があるのも見逃せない、モーツァルトはこれに、こう、続ける。「しかし、そのあたりはうまく書いてあるので、よく音楽を知らない人でも理屈なしに楽しめます。」
第1章<芸術の精神からの“現代音楽”の誕生>ののっけから、実に惹きつけられるではないか。
調性の崩壊から無調、12音技法、素材の自由化、多様化を語る第2章<昨日から今日へ>は第二次大戦まで。もはや目の前の物事には対応できない既存の言語への不信感と、それに代わって世界を記述する新しい言語への渇望は世界大戦で旧秩序が瓦解し始めるのに呼応する・・・。
第3章<ファウスト博士の仕事場>では、人為的に作り出された試験期間のような新しい方法、技法へ受け手が抱く「そりゃあ、まあ、ご自由ですけど、なんで・・・」という疑問などについて「作曲の前の作曲」といった観点から眺めたりする。
第4章<すばらしき新世界>は戦後〜60年代まで。偶然性や響きの探求、引用、反復などが挙がる。ここでビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のジャケ写にミュージシャンではボブ・ディランらのほか、誰あろうシュトックハウゼンが!と筆者は驚いてみせ、境界の溶解を指摘したりする。
第5章<聴けるものと聴けないもの>では、「耳だけではわからない」ゆえの耳の想像と創造について。引用される林光の言葉。「すべてを耳を通してだけ聴きとるというのを、たてまえとしている批評家もいるかも知れないが、こういう時代に書かれた、しかも世界ではじめて音になる曲に対して、自信をもってそのような態度をとれる批評家が、そう大勢いるだろうか。」筆者はつぶやく。「多くの作品が“一度演奏されて、それっきり”である可能性が極めて高かったにも拘らず、その“一度”で聴き手にはわからないような音楽を作るというのは、いったいどういうことだろう・・・」
第6章<宴のあと>は70年代〜世紀末まで。単純か、複雑か、聴きやすい現代音楽の登場の一方で、超絶技巧のとんでもない複雑さへの欲望。ノーノの豊かさを認めつつ、筆者は言う。しかし「何という息苦しさ」か。「そこでは身じろぎ一つすることを許されず、ただただ音楽に傾聴しなければならないような気分にさせられる。」
第7章<非人間的な、あまりに非人間的な>は演奏不可能な楽譜と新しい身体。演奏不可能な作品は「それらしく弾く」。正確に弾くのも「らしく」弾くのも、耳の方にはどうでもいいんだから、というある作曲家の言葉。指を脱臼した者なら、ひょっとしたらこのエチュードで直せるかも、なんていう批評の一節も紹介される。
第8章<芸術の些か耐えられない重さ>。で、岩城宏之が現代音楽を多くの人が「ピーポー、ドシン、バチャンみたいな」特殊な種類の音楽だ(正しい状況認識だ、現在でも通用する、と筆者はツッコミを入れる)と思っているのを認めた上で、パレストリーナ、バッハ、ハイドンなどなど、彼らだって当時は「現代音楽」だったのだと擁護するのに対し、「“特殊な種類の”ものだと思われ、さほど受け入れられていない音楽ならば、それは多くの人にとっては存在しないも同然であり、“現代の(同時代の)音楽などではない」とバッサリ。
そうして、今後のあり方として、「芸術家」であるより「職人」へ。「創造性」より既存のものを生かす「創意」へ。「発明」ではなく「発見」へ。芸術家たる作曲家はあくまで自分がつくりたいものをつくるべきだが、もっと演奏家や聴き手に配慮すべき、失われたコミュニケーションを回復すること、と結論する。
(「うまく書いてあるから、理屈なしに楽しめる」モーツァルトの言葉を思い出そう。)
随所に散りばめられる面白そうな言葉だけピックアップしたが、具体的な作品例の列挙と豊富な資料、それに沿った綿密な考察を重ねつつ、縦横に筆者の才知ひらめく本書を、私は実に楽しく読んだ。巻末に「現代音楽の名曲を聴く CD50選」が付いているのもいい。
最後にこんな言葉を引いておく。クラシック音楽の存在意義について。
「ひとえにそれが人々の生活の中で何らかの意味で(たとえ些細なことにすぎないとしても)“使える”ものであり、有益なものでありうる、ということに尽きるのであって、それ以上でも以下でもない。」
作曲家(演奏家も)の自己満足に付き合わされるのはごめんだ、と、たまに思わされる私としては、全く同感である。もちろん、「有益」性については深く真剣に考えるべきことがらだ、を前提として。
聴いて、なんかよかった、という感じを持てること、その感触からしか、批評だって生まれない。なんか変だった、を、なぜか、と問うのも、もちろん批評の仕事である。