特別寄稿|「歌」の簒奪者 ボブ・ディラン その2)|noirse
「歌」の簒奪者 ボブ・ディラン その2)
text by noirse
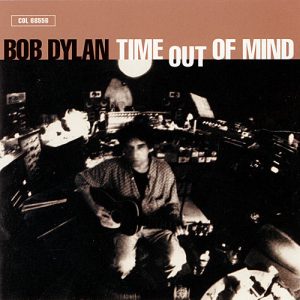 傑作『タイム・アウト・オブ・マインド』(1997)制作時、レコーディングされながらお蔵入りとなった、<レッド・リヴァー・ショア>という曲がある。アルバム中最高傑作と謳われながら、何故か未収録となり、しばらくのあいだ、誰も聞くことができなかった(現在は『テル・テイル・サインズ』〔2008]で聞くことができる)。
傑作『タイム・アウト・オブ・マインド』(1997)制作時、レコーディングされながらお蔵入りとなった、<レッド・リヴァー・ショア>という曲がある。アルバム中最高傑作と謳われながら、何故か未収録となり、しばらくのあいだ、誰も聞くことができなかった(現在は『テル・テイル・サインズ』〔2008]で聞くことができる)。
原曲はキングストン・トリオだが、ディランはそれを大胆に改変している。映画ファンなら、タイトルから、ハワード・ホークスの『赤い河』を連想するだろう。『赤い河』は、テキサスを流れ、ミシシッピに合流する「レッド川」を指すものと思われるが、アメリカには各地に「レッド・リヴァー」と呼ばれる川があり、ディランの曲がどれを想定しているのかについては、ジャッジは難しい。むしろ、アメリカの神話的な原風景を指し示すと考えたほうがいい。
象徴的なイメージが飛び交い、一見では意味の測りがたいディランの曲の中では、<レッド・リヴァー・ショア>の歌詞は明解なほうだ。『タイム・アウト・オブ・マインド』は、当時50代半ばだったディランの死生観が率直に表れたアルバムで、<レッド・リヴァー・ショア>にも、悲痛なトーンが漂いつつ、クラウスが説いたようなディランの問題も露わになっている。
以下では、野暮を承知で、<レッド・リヴァー・ショア>の稚拙な解題を試みてみよう。長尺曲の為、一部のみ抜粋する(訳詞は菅野ヘッケル氏による)。曲は、まずこのように始まる。
Some of us turn off the lights and we live
In the moonlight shooting by
Some of us scare ourselves to death in the dark
To be where the angels fly
月明かりが差し込んで来たので
ほっとして明かりを消す者もいれば
天使たちが舞う直前まで
暗闇の中で死ぬほど怖がる者もいる
語り部のように死のイメージを歌っているが、老いを迎えた自身の思いを投影してもいるのだろう。そのままディランは、「レッド・リヴァー」のほとりを舞台に、男女の恋を綴っていく。だが同時に、「ぼく」が焦がれ求める「レッド・リヴァーの娘」は、おそらく「音楽」そのものか、ミューズのメタファーであろうことが、徐々にほのめかされていく。
簡素なバッキングに、テックス・メックス(簡単に言えば、テキサス産のメキシコ音楽を指す)の使い手、オージー・メイヤーズが奏でる、もの悲しいアコーディオンの調べが絡む。彼の起用で、曲は南部の哀歌の趣きを帯び、伝承歌の如き演出が施される。穏やかに始まった恋の歌は、次第に凄みを増していく。
Well, I’m a stranger here in a strange land
But I know this is where I belong
I’ll ramble and gamble for the one I love
And the hills will give me a song
Though nothing looks familiar to me
I know I’ve stayed here before
Once a thousand nights ago
With the girl from the Red River shore
でもぼくはこの見知らぬ土地でただのよそ者
でもここが自分の居るべき場所だとわかっている
自分がこよなく愛した人のためにうろつき賭け続けることだろう
そして丘がぼくに歌を授けてくれることだろう
見覚えのあるものなど何ひとつないけど
かつて自分がここにいたってわかる
幾千もの夜が過ぎた遥か昔のこと
レッド・リヴァーの河辺からやって来た娘と共に
わたしたちが生きる現代は、ブルースやフォークが息衝いた1930年代から、遥か遠くまで来てしまった。だが、「幾千もの夜が過ぎた遥か昔」に、「かつて自分がここにいた」ことを、歌い手は知っている。
Well, I went back to see about her once
Went back to straighten it out
Everybody that I talked to had seen us there
Said they didn’t know who I was talking about
彼女のことを確かめに戻って行ったことがあるんだ
ちゃんと答えを見つけ出そうと
話をした誰もがぼくらのことを見ているはず
でもみんなぼくが誰の話をしているのかわからないんだ
歌い手にとって現代は「見知らぬ土地」で、「よそ者」に過ぎない。誰と話しても噛み合わず、答えはない。しかし、そこが「居るべき場所」と決まっていて、抜け出すことはできない。次が最後の二節となる。
Now I heard of a guy who lived a long time ago
A man full of sorrow and strife
That if someone around him died and was dead
He knew how to bring ‘em on back to life
Well, I don’t know what kind of language he used
Or if they do that kind of thing anymore
Sometimes I think nobody ever saw me here at all
Except the girl from the Red River shore
うんと昔にいたひとりの男の話を聞いたよ
悲しみと諍いにまみれて生きた男
その男のまわりにいた誰かが死んでしまった時
どうすれば生き返らせることができるかその方法を知っていたんだ
彼がどんな言葉を使っていたのかぼくは知らない
そんなことを今もみんながやっているのかどうかもね
ぼくのことを見かけた人なんて
誰ひとりとしていなかったように思えることがあるんだ
レッド・リヴァーの河辺からやって来たあの娘以外には
「男」とは、普通に考えれば、キリストに他ならないだろう。南部の荒野が、たちまち遠い昔のエルサレムの地へと接続していく(このイメージを、ディランは好んで使う)。
しかし歌の流れを踏まえるに、「男」の姿には、ディランにとってのかつてのソングスター、ハンク・ウィリアムスやジミー・ロジャース、ブラインド・ウィリー・マクテル、そしてウディ・ガスリーたちを連想せずにはいられない。彼らは、「方法」を知っていた。だが、その「言葉」は失われてしまったのだ。誰に聞いても、「誰の話をしているのかわからない」。いつしか、「ぼくのことを見かけた人なんて」「誰ひとりとしていなかったように」なるのだろう。
曲の最後、歌い手の姿は、「男」と共に掻き消えていく。彼はそのとき、「暗闇の中で死ぬほど怖がる」のだろうか。それともその側には、「レッド・リヴァーの河辺からやって来たあの娘」が寄り添うのだろうか。
 ディランにはマリブに豪邸があるが、年中ツアーの途にあり、ほとんど家には帰らない。そもそも、帰りを待つ家族もいない(はずである)。聞くところによると、移動中もリハーサル中も、メンバーとも誰ともほとんど口を利かず、公演が終わったら、打ち上げに興じる一行を残し、すぐにバスに乗り、次のツアー先に移動するらしい。ディランは、この生活を、20年続けている。
ディランにはマリブに豪邸があるが、年中ツアーの途にあり、ほとんど家には帰らない。そもそも、帰りを待つ家族もいない(はずである)。聞くところによると、移動中もリハーサル中も、メンバーとも誰ともほとんど口を利かず、公演が終わったら、打ち上げに興じる一行を残し、すぐにバスに乗り、次のツアー先に移動するらしい。ディランは、この生活を、20年続けている。
このような姿を、かつてのホーボー・シンガーに例える人も多い。ディランにとっては、レコードよりツアーのほうが――メディアを通してではなく、ステージで観客に歌いかけ、ディランの歌の向こうにいる、かつての「民衆の歌」に触れてもらうことのほうが――重要なのだ。
ディランは、類稀なる歌手にして表現者だが、同時に記号を弄ぶ簒奪者でもある。彼にとって、音楽に触れるとは、そういうことなのだ。稀代の天才でありながら、彼の手中には喪失感しかないのだろう。
だが彼の歌は、れっきとしてそこにある。そしてディランは、ステージに立ち続けることで、甦ることのない音楽に、「言葉」を与えんとし続ける。
ノーベル賞授与は、ファンとしては素晴らしいニュースではあるが、正直なところ、ディランには必要なかったとも思う。審査委員会による受賞理由は、「偉大な米国の歌の伝統に、新たな詩的表現を創造した」というものだ。たしかにディランの歌の後方には、「偉大な米国の歌の伝統」が広がっている。だがそれは、賞のお墨付きなどなくとも、人の記憶に残っていくはずだ。
ディランの前には、歴史の不可逆性が立ち塞がる。しかし彼の歌もまた、歴史の連続性の中にある。ディランが憑りつかれた1930年代を活写した『怒りの葡萄』に倣って言えば、「人々が苦しむとき、腹を立てるとき、笑うとき、食べるとき」、そして「歌うとき」、アメリカの民衆の歌は――ブルース、フォーク、そしてディランの歌は――「いつだってそこにいる」はずなのだ。
——————————————————————————-
noirse
同人誌「ビンダー」「セカンドアフター」にて、映画/アニメ批評を執筆


