カデンツァ|日本のマネジメント創成期|丘山万里子
日本のマネジメント創成期
text by 丘山万里子( Mariko Okayama)
 この5月に音楽事務所KAJIMOTOの会長、梶本尚靖氏が95歳で亡くなった。
この5月に音楽事務所KAJIMOTOの会長、梶本尚靖氏が95歳で亡くなった。
KAJIMOTOといえば、近くは<ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン>やマウリツィオ・ポリーニか。
2001年夏、広尾の米荘閣(堤清二が建てた広大な邸宅、10年余で消却された)で開かれた会社設立50周年パーティーに私は顔を出したが、どの部屋も溢れる人々と楽の音に満ちており、そのうちの一部屋の静寂にホッと引き入られると、50年の氏の仕事ぶりを回顧する資料がずらりと展示されていた。
今日の美麗なチラシやポスター、プログラムを見慣れた目には、初期のそれらはいかにも手作り感漂う絵柄や印刷物で、戦時に青年期を過ごした氏の世代の、音楽への情熱や畏敬がひしひしと伝わり、ああ、こういう働きがあってこそ、今の私たちの贅沢な音楽享受があるのだ、と、しみじみ見入った。
帰り際、手渡された氏の著書『音と人と〜回想の五〇年』を読み、日本の音楽マネジメント創成期について何かまとめておきたい、と思った。が、年月は瞬く間に流れ、氏の肉声を聞く機会を失った。
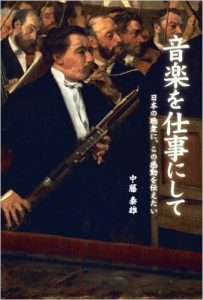 それから7年後の2008年、ジャパン・アーツの中藤泰雄氏が喜寿を迎え『音楽を仕事にして』という本を出した。
それから7年後の2008年、ジャパン・アーツの中藤泰雄氏が喜寿を迎え『音楽を仕事にして』という本を出した。
メトロポリタン・オペラやスビャトスラフ・リヒテルらを招聘、アーティストとともに歩んだ35年の歳月を記したもので、中藤氏は梶本氏より10歳下。二人にとっての「戦争」体験、音楽への道を重ね合わせながら、興味深く読んだ。私は1999年に創刊した批評紙で中藤氏にインタビューをしており、改めて、なるほど、思いつつ。(以下、両書を参照。また、氏、は略させていただく)
梶本と中藤のちょうど真ん中に、やはり創成期をになった神原音楽事務所の神原芳郎がいる。神原は2004年に亡くなり、その死の前年に事務所も解散された。
残念ながら神原に著書はなく、私の手元には何の資料もない。私が駆け出しだった頃、コンサート会場の受付付近に佇む氏を、あれが神原社長、と先輩に教えてもらったことぐらい。
梶本は1921年大阪生まれ、神原は1926年愛媛、中藤は1931年韓国・統営。ちなみに批評家、遠山一行は1922年生まれだ。
梶本と神原は、音楽マネジメントの出発点で遭遇している。場所は四国、終戦直後の1946年。
2001年、二人が対談した記事(『音楽の友』12月号/創刊60周年記念特集「証言1945」)によれば。
梶本の初仕事は、ヴァイオリニスト辻久子のコンサートのセールス。彼はなぜか四国へ行く。理由は忘れたそうだが、神原が言うには、四国へは大阪から関西汽船が出ていて、夕方出ると翌朝には四国へ着け、宿賃が助かったからだろう、とか。四国は正岡子規や夏目漱石の『坊ちゃん』など文学的気風が比較的盛んだった、とのこと。神原も文学青年もどきの銀行マンで、音楽関係のことに首を突っ込んでいた。紹介され、そのカンバラさんに会って話したところ、即座に「ああ、やりましょうや。」
「みんな何かを求めていたわけです。その頃は音楽にせよ文学にせよそういう文化運動が各地で起こってきてね。まあ文化というのが何物かもわからないままに、新しいアメリカの映画が入り始め、洒落た連中はダンス・パーティーなんてのを開くといったように、ワイワイ言いながら青年たちが今までやれなかったようなことをやって戦争中の憂さを晴らしてたんですな。そんなところに梶本さんの、音楽を聞こうじゃないかという話はとても魅力的でしたよ。」(神原)
「まあとにかく何もなくて、すべてに飢えている時代でしたから。だけど文化に触れたいという気持ちだけは漲っていた。」(梶本)
以降、四国には藤原義江、齋藤秀雄、井口基成ら、そうそうたる演奏家が訪れたという。食糧難の時代だったから、ふかし芋やご飯、瀬戸内の魚などを喜んで食べたそうだ。
梶本は戦前に映画『オーケストラの少女』を観てクラシック・ファンになり、混声合唱団で歌っていた。終戦の詔勅を姫路の陸軍病院(行軍の疲労が原因)で涙ながらに聞いた梶本一等兵は、帰郷、一面の焼け野原に立ち、まずは合唱団の再建を決め、それがマネジメントの基本を作ったという。
神原は子供の頃から足が悪く、兵隊にはならず銀行に徴用されており、そのまま終戦を迎えている。
中藤は満州で裕福な幼少時代を過ごし、終戦は大連、中学2年生だった。引き揚げ船を待つ間、一変した窮乏生活に路傍でお金を稼ぎ、貧しさを嫌という程味わう。が、一方で、トラックに乗ったロシア兵の合唱に聞き惚れ、悲しい歌には自分の悲しい気持ちが表現されるようで「民族や言葉が違っても皆同じ人間なんだ」と親しみを感じたという。
このロシア兵の歌声が、中藤の音楽への道の原点と、私もインタビューで聞いた。
辛い時、苦しい時こそ音楽が必要だ、という氏の強い思いは、その後の歩みを貫く一本線である。
中藤は帰国後、上京、高校、大学と合唱団(梶本と同じ、やはり合唱だ)に所属、就職した日本電波ニュース社で音楽関連の事業部を立ち上げる。1971年、大阪万博の翌年だ。
神原が東京で事務所を持ったのは1960年(61年にジャズピアニスト秋吉敏子を招聘)、梶本の東京進出は62年だから、やはり10年の開きで後を追っていることになる。
大阪国際フェスティバル(1958~)、万博と、世界各国の大演奏家、オーケストラが集ったこの時期、梶本は国際舞台へのステップを築いた。
遅れてやってきた中藤が着目したのは共産圏のヨーロッパ諸国。「すきま産業的発想」だったというが、私はやはりロシア兵の歌声が氏をそこへいざなった、と思う。
1976年、独立したジャパン・アーツの初仕事は<チェコスロヴァキア音楽祭>。以降、チェコとは強いパイプを築いたが、その底には「他国に侵略し続けられた人々の悲しみ」への共感があったという。
ソビエトを含む共産圏の官僚主義、演奏活動の制限・抑圧など、西側世界にない困難と向き合い続けた中藤の核にあるのは二つ。少年期に心に刻んだ「戦争は人間を変える。大義名分が吹き飛んだ後には、醜悪な現実だけが残されていた。戦争だけはもう二度と起こしてはならない」という決意と、「音楽を通して、異なる民族同士が同じ感情や感動を分かち合い、互いに共感し合うことこそが、平和への一歩につながる」という信念。
西側世界で華々しく事業を広げた梶本は、神原との対談で初期を振り返りつつ、「まぁ誠意が何より大切なこともあれば、度胸やハッタリでバンと押し切らなきゃどうしようもない場面もある。おっかないこともあったけど。(笑)、面白い時代ではありましたな。」といかにも大阪人らしく笑っているが、中藤との違いは、やはり戦時体験の相違だろう。内地と外地の差は大きい。
「何もない」状況を「だからといって停滞していたわけではなく」「限られた難しい条件の中で、ビジネスをどうやり繰りするか、どこに工夫のポイントをおくかーーそこに創意が生まれ、新しい展望が開ける道があった」と梶本は述べる。その、常にプラス思考のバイタリティと旺盛な野心は、戦後の日本の発展に必須のものであったろう。
「謙虚な姿勢」「人より一歩先んじてやること」「世間の人々が何を欲し、何を望んでいるかーーその大事な嗅覚を鍛えておかなければ」というビジネス・モットーは、「文化への飢え」を原点とした四国でのセールスの第一歩から、今日の音楽界の盛況、日本の文化的国際的地位向上を支え続けた。
梶本と神原の対談は NYテロの起きた年末に行われている。神原が「僕らの長い戦後生活の中でも、これは本当に大変な時期じゃないかな。」と懸念するのに、梶本は「だけどまあ、その辺は長い目で見れば最終的にはうまくいくんじゃあないかなと。」と返している。
今はもう、日本の音楽大学にもアートマネジメント科があり、専門知識に長けた人材を輩出、活躍もしている。
「飢え」や「感動」を原動力とした先達の仕事。
テロの恐怖と憎悪が世界を分断する今日的状況の中で、戦争を知らない私たちが、そこから何を受け継ぎ、育て、さらなる次の世代へと手渡して行くか。
本誌Back Stageコーナーへのコンサート企画・制作現場からの様々なご寄稿のそれぞれに、それが明かされているのではないか。
Back Stage コーナー
(2016/7/15)


