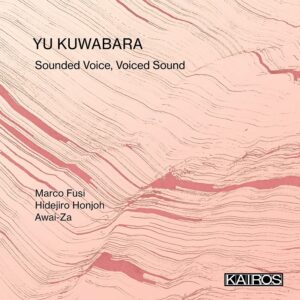Books|コンサートという文化装置 –交響曲とオペラのヨーロッパ近代|大田美佐子
宮本直美 著
岩波現代全書
2016年3月刊行 2200円+税
text by 大田美佐子( Misako Ohta)
私たちは普段意識をすることもなく、当然のように、お目当ての演奏家や演奏曲目を目指して演奏会に行き、あるいはオペラを観ている。この何気ない行為の背景に、どれだけの歴史的厚み(=経緯)が隠されているのか、そのことを思索することにどんな意味があるのか。本書は私たちのそんな「自明」の行為そのものに、問いを投げかけているのかもしれない。
音楽の「うち」と「そと」という表現があるように、社会の仕組みや様々な仕掛けは音楽作品とは切り離されていると思われがちだ。たとえば、学問領域で言うならば前者は楽曲分析、後者は音楽社会学といったように。しかし、実のところ社会システムは音楽そのものと分ち難く関わり合いながら、複雑に絡み合いつつ歴史を織りなしている。
昨今、歴史的にどのような演奏会が開かれてきたのか、という実証的なプログラム研究が注目されてきているが、それはとりもなおさず、「プログラム」というものが、音楽作品の存在論との関わりで重要な「聴取」という問題と直結しているからだ。
著者の出発点は明確だ。「ヨーロッパでコンサートという事業が市場で確立されてから交響曲を中心としたフォーマットに納まるまで」(3ページ)のその長く複雑な経緯である。
ここで分析されているのはプログラムの実態だけではない。まず、歴史的言説、E.T.A ホフマン、ウェーバー、ダールハウスなど、ドイツ語圏の音楽歴史学や音楽社会学の古典的な議論とボンズ、シュレフラー、ジョンソンなど、アングロサクソン系の音楽批評を背景にした議論も対置させ、丹念かつ簡潔に整理してある。
ダールハウスとクネプラーなど、壁で分断された東西ドイツの学問的志向の違いや、ナチスを克服しようとする戦後ドイツが「絶対音楽」への回帰を求めたという指摘も大変興味深い。
様々な言説、ヨーロッパ各都市のプログラムから見える実相、音楽組織の成り立ちの歴史、文豪のオペラ体験、オペラの著作権の問題など、コンサートを成り立たせている「文化装置」の各部に目を配り、かなり包括的に、しかし慎重に、そこにある時代的変化を読み取りつつ明確な論旨に編む作業は見事な力業である。
構成は序章と5章から成る。(序章 交響曲はいかにしてコンサートの主役になったのか 第一章 ことばにできない音楽、 第二章 オペラの覇権、第三章 コンサート市場を成立させたもの 第四章 交響曲の正当化と受容、そして第5章 言葉にできない音楽の言葉による領有)
歴史は語り直され、その新しい視点を私たちに問う。「言葉」の優位から「絶対音楽」へという安易な図式も、「オペラ」は貴族文化という簡潔にまとめられた定説も、200年前の聴衆と音楽との向き合いの実態を精査するなかで見直される。ヨーロッパにおける、言語も階級も超越したオペラの「普遍性」や、教養主義により作られた交響曲の「特権化」という新たな視点は、今日のコンサートの演目に何を言わんとしているだろうか。
最終章の「言葉にできない音楽の言葉による領有」では、音楽雑誌を中心とした「音楽批評」の重要な役割について指摘されている。まさに言葉を介さない音楽(=交響曲)が、「言葉」として解釈されることで普遍的な「教養」になり、ひとつのジャンルを護ってきた意味を考えさせられる。
あとがきで著者が指摘しているように、かつて音楽出版社が持っていた「売れない領域を存続させ、育てる」(252ページ)気概が、今の芸術を育てる「文化装置」には求められているのではないか、と。
本書は20世紀に特権的で排他的と感じられていた芸術音楽の状況を超えて「新しいオペラ運動」というかたちで「言葉」に近づいたヴァイルやアイスラーなどの作曲家たちの研究にとっても、参考になる点が多い。近代日本の西洋音楽受容を考察するうえにおいても、ヨーロッパ近代が生み出した「文化装置」への多角的な理解は重要な一助となるだろう。
もちろん、一般の読者にも開かれた学術書として、コンサートやオペラ好きの方々が、今なぜこのようなプログラムを聴いているのか、その歴史の経緯を実感をもって捉えられるのではないだろうか