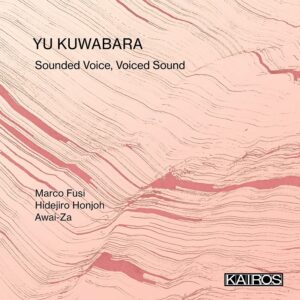注目の1枚|ショスタコーヴィチ:交響曲第9番 変ホ長調 OP.70|藤原聡
 ショスタコーヴィチ:交響曲第9番 変ホ長調 OP.70
ショスタコーヴィチ:交響曲第9番 変ホ長調 OP.70
同:交響曲第5番 ニ短調 OP.47
同:交響曲第8番 ハ短調 OP.65
同:劇音楽『ハムレット』からの組曲(抜粋)
ボストン交響楽団
指揮:アンドリス・ネルソンス
text by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)
録音:2015年10月(第9番)、11月(第5番)、2016年2月(『ハムレット』)、3月(第8番)
レーベル:DG
商品番号:479 5201(輸入盤/オープン価格)、UCCG1741(国内盤/¥3,780)
2014年よりボストン交響楽団の音楽監督を務めるアンドリス・ネルソンス。彼らはDGにショスタコーヴィチの交響曲シリーズを録音し始めた。その第1弾である10番に続き、この第2弾は第5番、第8番、第9番、劇音楽『ハムレット』組曲(抜粋)。2015年10月&11月、2016年2月&3月のライヴ。尚、ブックレットによれば第3弾の『レニングラード』もリリース待ちのようだ。
さてその演奏であるが、ネルソンスのショスタコーヴィチは基本的に理知的、純音楽的でストレートであり(しかし「深層」を垣間見せる瞬間がある)、その中で時に独自の読みやユニークな解釈を聴かせてくる、というタイプである。1978年生まれのネルソンスにとってはもはやショスタコーヴィチはそういう対象ということだろう(という発想自体が、同時代「ソ連」の指揮者たちの解釈を前提にしているとも言え、もうそういう論法もないとも思うが・・・)。第9番ではこの曲の諧謔味を意図的に出そうとは考えていないようで、第1楽章などは心持ちゆったりしたテンポを取ってていねいに演奏を構築していく。しかし、第2楽章ではクラリネットが主題を吹く主部の後に謎めいたヴァイオリンの上昇音階が繰り返し登場してくる箇所などではタメを持たせていかにも意味ありげで思索的な雰囲気を醸成したり、となかなか一筋縄では行かない(ちなみにバーンスタインはこの楽章をチェーホフを引き合いに出して説明しているが、これは示唆的かつ有用なヒントだ)。終楽章でもコーダ直前の乱痴気騒ぎがクライマックスに達する箇所でのシレっとしたユーモアやその後へのテンポ転換など、一歩引いた俯瞰的立ち位置から冷静な手つきで楽曲を眺める姿勢が、逆に曲の特異性を露にしているようだ。
第5は、総じて遅めのテンポでじっくり腰を据えた表現である。第2楽章中間部のフレージングや第4楽章冒頭のダイナミクスの扱い(最初のD音にメゾフォルテで入った後にスビトピアノ、そしてクレッシェンドする)は初めて耳にするもの。この演奏で特に印象的で優れていると感じたのは第3楽章、そのコーダの遅いテンポでの内面的な表現、そして終楽章コーダの巨大さ。この「身じろぎのしなさ」が、スケール極大であるほどに白々しい明るさを感じさせて秀逸だ(この曲だけ曲後の拍手入り)。
ディスク2の第8番。ネルソンスにはロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮した同曲の映像作品が先にあったが、ここでの演奏はそれよりも明らかに踏み込んでいる。第1楽章クライマックスでの間(ま)を徹底的に生かした凄絶な表現。第4楽章のパッサカリアでの重厚ながらも気分だけに流されない構築的な演奏。第5楽章はそもそも明るいのか暗いのかなんとも形容し難い音楽であるが、そのコーダは筆者は今まで聴いた中では最高の演奏の1つだ。テンポの極めて遅いデリケートな表現で、ここでの「ハ長調」がこれほど複層的な感情を聴き手に与える例もそうはないのではなかろうか。
『ハムレット』は、より有名なコージンツェフが監督した映画音楽の方ではなく、舞台作品用の音楽である。ここでは交響曲とはまた違った、肩の力を抜いた軽快なショスタコーヴィチの姿に出会える。ちなみに最後の「レクイエム」ではグレゴリオ聖歌の「怒りの日」がほぼそのまま引用されている。
録音はライヴながらノイズもほぼなく、ボストン・シンフォニー・ホールのあのいささかひんやりとした豊かな音響が上手く捉えられている(但し豊かな残響を取り入れているのでシャープさは若干後退した感)。このコンビで早く第4番を聴いてみたいものである。