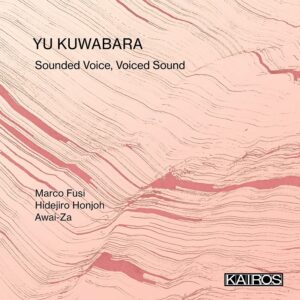Books | 武満徹・音楽創造への旅|佐伯ふみ
立花 隆
文藝春秋
2016年2月刊行 本体4000円
text by 佐伯ふみ(Fumi Saeki)
武満徹没後20年にあたり、伝説の連載がついに本になった。 総頁784頁、四六判で24行×2段、天と小口の余白はわずか数㎜、と書けば、出版・編集に携わったことのある人なら、どれだけの分量がこの1冊にぶちこまれているか、およそ想像がつくはずだ。 読んでも読んでも終わらない、しかしめっぽう面白い。何日かこの分厚い本を持ち歩く羽目になったが、苦にならなかった。筆者は当時の連載記事を読んでいたが、こうして今、まとめて読めるのが嬉しい。そして改めて圧倒された。武満の創造の苦闘に、作曲という営みを解き明かそうと食い下がる立花隆の執念に。
連載は『文學界』に合計66回、1992年6月号から1998年5月号まで6年弱。このために行われた武満と関係者へのインタビューは100時間を超えたという。ところが連載途上の1996年2月に武満が逝去。闘病はわずか2年で、「急逝」の衝撃がどれほど大きかったか、立花の筆は生々しく伝えている。 連載終了後、すぐに単行本として出版されるはずだった。すでにゲラ(校正刷)は組み上がっていたという。それなのに18年にわたり寝かされることとなった。その理由はあとがきの「長い長い中断の後に」に記されている。やはり途上での武満の死がそれだけ大きかったのだ。そのとき連載は、武満の『ノヴェンバー・ステップス』がついにニューヨーク初演という、まさに佳境にあった。
『ノヴェンバー・ステップス』までの記述は、いわば「メイキング・オブ・タケミツ」であり、「武満徹という作曲家が、いかにして生まれるにいたったかを時系列に沿って描」くもの。「武満の青春彷徨の記録であり、音楽的精神形成の歴史でもあった。そしてそれは武満の仲間たちの青春群像の軌跡を追う音楽的同時代史であった」。 立花自身のこの言葉は、さすが、この本の本質を的確に言い当てている。 しかしそれ以後、ある意味で「エスタブリッシュされた作曲家」として、武満はどう歩みを進めることになったのか。記述の方法を変えて、さらに探求されるはずだった。没後2年ほど継続された連載は、残された速記録から、テーマに沿って武満自身の含蓄ある言葉が集成されている。それはそれでもちろん面白いが、前半と比べればいかにも惜しい。著者としては、これを単行本にまとめてしまうのか、と、気持ちの踏ん切りがつかなかったのもよくわかる。
改めて読み通してみて、今、いちばん心に深く響くのは、終戦後の壮絶な「貧しさ」そして「病」の姿である。中学生で勤労動員に駆り出された武満少年が、基地で密かに聞かされた蓄音機の音楽。「これだけで、戦争が終わったら音楽をやろうと心に決めてしまったんです。」
どれだけの貧困も病も、その意志を曲げさせることはなかった。なんとか食べていけるようになったのは60年代になってから。それでも、自分の内なる音楽の探究をやめない。
こんな人生があるのか。
そこに改めて、深く深く心を揺さぶられる。
音楽家あるいは作曲家についてのドキュメンタリーは、崇拝者が描くサクセス・ストーリーになりがちである。立花はもちろん武満の音楽の崇拝者であり、だからこそ、あれだけの膨大な、かつ深い言葉を武満から引き出すことができた。しかし、本書をすこぶるつきの面白さにしているのはそれゆえではない。「なぜ? どうして?」の探究心の、あきれるばかりの強さだ。
なぜ、あのような曲を書いたのか?
その時、なにを考えていたのか?
それはおそらく、作曲家自身がつねに自分に投げかけている問いでもあろう。だからこそ、武満は、夜中まで電話をかけてきてしつこく食い下がる立花の問いかけを、「なんでも話す」と受けて立ったのだ。 単なる回顧ではない。あくまでも、これからの創造の糧として。
桁違いに貪欲な作家魂。両者ともに持ち合わせたその魂が共鳴しあい、このような対話が生まれた。その現場に立ち会わせてもらうがごとくのこの本。至福の読書体験である。