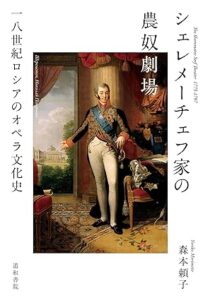Books|チェリスト、青木十良|丘山万里子
大原哲夫著
飛鳥新社
2011年7月出版
2200円+税
text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
本号コラム、カデンツァで『子供の科学』創刊の辞を孫引きさせてもらった本書は、編集、執筆、造形・絵画制作など幅広い活躍をする大原哲夫が2006年から2010年の間、青木と交わした会話の記録を元に著述した労作である。せっかくなので、ここできちんとご紹介したい。
私が青木と出会い、『翔べ未分の彼方へ』を出したのは1995年、青木80歳の時。献本した吉田秀和、遠山一行の両氏から「良い本ですね。」とお褒めの言葉をいただいた。(もちろん、青木の話が素晴らしかったのである)
大原がたまたま青木の米寿記念CD『バッハ無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調』を聴き、衝撃を受けたのは2002年。このCDはたちまち話題となり、大原はそれから4年後、青木との会話を開始している。
私は、CDの時も、本書が出た時も「ほうら、やっぱり。」とニンマリした。CD以降の青木のブレイクを、とっくの昔に私はわかっていたんだ、という気持ち。(ちょっと得意)
私がお話を聴いた、あれからほぼ15年後、描かれている青木は、やっぱりすごかった。50、60歳は一生懸命勉強、70で花を咲かせ、80はゆうゆうその流れに乗って、90まで行く、というその言葉。そうして氏は94歳でバッハの『第4番』を録音(2011年発売)、99歳までチェロとともに生きた。
大原の組み立てが見事なのは、対話とともに、青木の生きた時代、大正、昭和、平成にいたる流れの歴史的な事項を併置し、この言葉の背景にどんな世相があったのかを常に背後から響かせていることだ。
青木の出生、裕福だが孤独な幼少・少年期(これが青木のチェロの音、“哀”のもと)、チェロとの出会い(独学を貫いた)、夫人(17歳の花嫁)とのおままごとみたいな新婚生活、出征前夜、ひとりで弾いたシューベルト(たった一日で帰宅を許された!)、戦後のNHKから始まる幅広い活躍、齋藤秀雄(教え方は正反対)に招かれての桐朋での教育、そして現在、と年代を追っての記述の随所にはさまれる綿密な裏付け資料が、高貴で気骨ある青木の軌道を克明に浮かび上がらせる。周囲の人々へのインタビューも青木の音・人となりを浮き彫りにする。
驚きエピソード満載のなかでも、ふと私が立ち止まったのは1940年頃の山田耕筰と青木の出会い。山田は青木の音の独特にいちはやく気付き、「お前さんみたいな人が弾いても、聴衆に認められることはないから、日本の聴衆はあまり質がよくないから、まあ、失望しないでやるんだね。」と言ったそうだ。「そう言ってもらって、それが自分のよりどころ、頼りになりましたね。でも、こんなに時間がかかるとは思わなかった。あれから、70年はたっていますよ。(笑)」
山田は、青木独特のボーイングに注意を払った最初の人だったという。
山田は開戦時に「いいですね、今度の戦争はいいですよ。米英との戦いで一応古い文化を破壊し、その破壊によって新しい文化が必ず建設されますよ。」その新しい文化建設を我々の手で、と叫び、音楽挺身隊の隊長となり、軍需品としての音楽の先頭に立って旗を振り、戦犯と批判された音楽家だが、音楽、そのものについての洞察と理解はやはり第一級だったのだ、と思ったことだ。(といって、私は戦時の山田のふるまいを看過することはできない)
もう一つ、終章の「音楽を語る」での宝石のような言葉。チェロの魅力について、「<厳>という文字で表される言葉、<尊厳>だとか<威厳>だとか、これが、僕がチェロで表現しようとするものの大きな要素なんですね。それで、チェロという楽器に憧れて、<自己の尊厳><人間の尊厳>というものを表現しようと思ったんじゃないでしょうか。」
「音楽の仕事、芸術の仕事をしながら、自分が何を求めているんだろうと、ずっと考えてきているわけです。それが<エレガンス>なんだと、最近になってやっと発見しました。〜〜フランス語の<エレガンス>という言葉の根底にあるのは<自尊>です。そう、日本語の<気品><品格>にも通じるものだと思います。」
私は青木の音楽をどう表したらよいか、ずいぶん探し、「エレガンス」という言葉が思い浮かんだとき、これだ!と思った。青木が最後にそう語っているのを目にしたときは、またまた「やっぱり。」と嬉しかった。
ともかく、すごいな、すごいな、の連続の、読むにつれ、心が磨かれる本である。