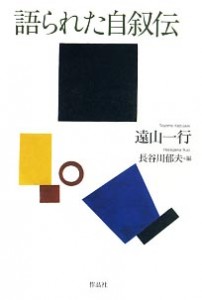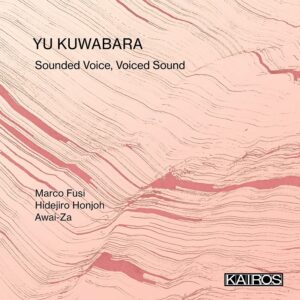Books| 語られた自叙伝|藤原聡
遠山一行 長谷川郁夫 編
作品社 2015年12月出版
定価:本体1,400円+税
text by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)
遠山一行の文章には、ある種の逡巡と知的な韜晦が常に通奏低音のように響いている。批評家であれば当然、と一概に言えるものでもなく、対象について愛をもって語っている時ですら、それに相対する冷静な視線、客観視するような雰囲気がある。これは何に由来しているのか。氏の最晩年の聞書き(生涯を俯瞰した内容)を中心に、2003年刊の『芸術随想』以降の未収録エッセイを発表順に編成して構成された『語られた自叙伝』を読んで、筆者なりに見えてきたのが、「戦争」と「キリスト教」に由来する自己分裂。
「私はわりに呑気なほうですが、当時は誰でも死に直面していたわけです」と淡々と(と読める)語る氏。昭和20年7月6日の甲府空襲の日、「暗号」を教えていた氏は兵隊を連れて東京へ出張する予定であったが、甲府駅に着いたところで空襲が始まる。止まっていた汽車の中で待っていたのだが、「・・・私がなんの気なしに座っていた席を立ち、席を移ったら、私の座っていた席にあとから来た人の頭の上に、焼夷弾の笠が落ちて来て、ギュウともいわず、即死でした」。氏が生まれた頃には兜町で成功を収め、後に日興証券を合併して社長になった父親のことを語る下りからも分るように、基本的には幼少の頃から裕福であり、恐らくは戦争が始まるまでは比較的平穏に生活していたと想像される。むろん遠山だけに限った話ではなかろうが、戦争がそれまでの生活を激変させ、明日も分らぬ状態へと叩き込まれるというような事態は、全く戦争経験のない筆者からすれば貧しい想像を膨らませてみても分るものでもない。そのような特殊な状況下では、従来の価値観や思考は即座に、何度でも180度転換させられうる。いやでも自分の中で事物を相対化する視線が生まれて来はしまいか。分裂。
「私は生まれたときからキリスト教の信仰に囲まれていました。祖父は若くして亡くなったのですが、祖母もそして両親もクリスチャン―プロテスタント―でした。子供のときから教会につれて行かれ、小さいころに幼児洗礼をうけていました」。にもかかわらず(だからこそ、と言うべきか)、その後の「信仰生活はかなり屈折したもので、自分の考えで信仰告白したのは、実はずっと後です」。その屈折の内容については詳らかではないが、この頃の遠山家のキリスト教には、いわゆるピューリタンの影響はかなりあった、とも書く。家の中にお酒がない禁酒の習慣。一種の禁欲主義的な雰囲気があった、子供の頃には映画などを見るのはよくない、といった感じを持っていた、と。「私はいわゆる終戦の直後に音楽批評の仕事をはじめ、幸いに順調に場所を与えられましたが、自分の気持ちのなかでは次第に迷いのようなものが深くなっていました。また(原文ママ)信仰告白はしていませんでしたが、神を求める気持ちは強くなっていました。そして、その気持ちが音楽や芸術に深入りする自分に対する疑問に結びついたといえるようです」。後のフランス留学を経て、こうした気持ちは次第にほぐれていったと氏は書くが、根源的に残る「自己分裂」。
本書で言及されているストラヴィンスキー、ショパン、ミケランジェリ、そして最近の演奏が気に入らない、という点。ストラヴィンスキー論においては、ロシア人、ロシアの音楽家としてのストラヴィンスキーという視点で書いた物で、その1番大切な点は彼の「音」。ロシア人としての音を確立して行く過程(この作曲家にあっては、音はただの「意匠」との側面が強い)。ショパン論でも中心は音の問題。ショパンの音は、例えばシューマンの場合のように彼の内部の声というのとは違う、むしろ作曲家の外部にある他者としての音(だからピアノという楽器にこだわった)。ミケランジェリでは、(ピアノの)音というものは演奏家の声をあらわすものだったはずなのに、それが唯の「もの」になった(さらには、氏のマチス論。マチスにとっての色における他者性)。これらは、キリスト教的に言えば「霊と肉の相剋」の問題である。精神のありようと、それが現前する際に必然的に具体的な物質として現れる、その現れ方。結びつき。「最近の演奏」ではむろん、問題は「音」それ自体になっている。極言すれば従来の「精神」の問題ではない。あるいはその関係性は古の演奏に比べてより多様かつ複雑である。後半の三善晃に関するエッセイでも論点は共通しているし、<河上徹太郎と音楽批評>では、遠山は高橋英夫の、河上とキリスト教の関係を論じた文章に触れ、「キリストという存在が神であり同時に人間であるという二重性を帯びたように、(音楽も)肉体的でありながら微妙に抽象的である」、こうした存在をえがくことが批評の生であって(後略)、との文章を引く。
遠山が、自身の根本にある自己分裂と二重性に親和性のある対象に対して敏感に反応するのは明らかであろう。そして自己に引き寄せて解釈する(批評というものは対象を通して自身を語るものだ)。数多くはないものの、遠山の批評に幾らかは親しんできた筆者だが、『語られた自叙伝』を読むことにより、遠山一行という大批評家の本質的な面に少しでも接近できた、ような気がする。