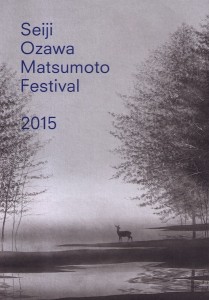セイジ・オザワ松本フェスティバル オーケストラ・コンサート|相原穣
Concert Review
 セイジ・オザワ松本フェスティバル
セイジ・オザワ松本フェスティバル
オーケストラ・コンサート Aプログラム
2015年8月28日 キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)
Reviewed by 相原穣(Minoru Aihara)
Photos by 相原穣(Minoru Aihara)
<出演>
ファビオ・ルイージ(指揮)
サイトウ・キネン・オーケストラ
<演目>
ハイドン:交響曲第82番 ハ長調 Hob.I:82「熊」
マーラー:交響曲第5番 嬰ハ短調
毎年8月半ば、夏の夜空に一つの奇跡が現れる。星がこぼれるように次々と流れ落ちるペルセウス流星群だ。それから半月あまり経つと、松本にもう一つ奇跡が現れる。サイトウ・キネン・オーケストラである。例えば、8月28日に聴いたAプログラムのハイドン『交響曲第82番《熊》』。突き抜けるようなハ長調の明るさと歯切れよいリズムが印象的な曲だが、この時の演奏は、めくるめく音の展開には星が流れる刹那の「ハッ」とした驚きがあり、驚きの積みかさねの先には、星座の綾なす壮大な音空間が広がった。
経験的にも、これほどニュアンスの細やかなハイドンはめずらしい。曲の始まりから示される第1楽章の第1主題にしても、せりあがる音の凝縮感、スタッカートの洗練された響き、レガートの優美さが一連の流れの中で意識的に表現される。特筆すべきはフレーズの末尾の味わい。思えば、流星群の味わいの一つは、眼に残る痕跡の余韻にあり。それがあってこそ、次の光が流れた瞬間に心が動く。現在、メトロポリタン歌劇場(首席指揮者)とチューリヒ歌劇場(総音楽監督)を率いるファビオ・ルイージは、明晰なテクスチャーのうちに多彩なニュアンスを浮かび上がらせ、ハイドンだけでもこの日のコンサートを深く記憶に残るものにした。
ルイージの登場は、昨夏に続くもので、オーケストラとの信頼関係はマーラーの『交響曲第5番』でも大きな推進力となった。若手奏者の割合が増えるも、日本を代表するソリストや各オーケストラの首席クラスが弦セクションを埋め、ベルリン・フィルの元首席や現役の首席ら名手が管セクションに居並ぶ圧巻の光景は、演奏にもじかに反映される。日本の通常のオーケストラでは聴くことのない弦セクションの重厚さは、齋藤秀雄門下によるサイトウ・キネンならではのアンサンブル力とルイージのタクトで、一つの生命体を思わせる、エネルギッシュで流麗な躍動感へと変換される。冒頭楽章では緩急の巧みな扱いからマーラーがスコアに込めた有機的な音の重なりや連鎖を引き出し、低弦と管楽器のドラマを演出した第2楽章、不協和な響きにもバランス感覚が光った第3楽章、歌謡的なフレージングで魅せた第4楽章を経て、グランド・フィナーレの第5楽章を迎える。ここでも勢いに任せず明晰さを保つことで、このオーケストラが誇るアンサンブルの本領を最大限に発揮させた。
1992年に始まった「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」は、今年、「セイジ・オザワ松本フェスティバル」として再出発した。名称の変更は、メンバーの世代交代が少しずつ進む中で、今後、対外的に同音楽祭のアイデンティティをどう表明するのかを見据えたものと思われ、運営面からも大きな意味を持つに違いない。世界に名だたる客演メンバーや歌手の出演も小澤征爾の魅力に負うところが大きい。同時に、「サイトウ・キネン」の名をオーケストラに残したことも、音楽祭のDNAを再確認するための重要な決断だったと言える。伝統ある音楽祭は世界にいくつもあれど、1人の音楽家の思いがこれほどまで音に結実した音楽祭はない。この「年一度の奇跡」を本質的に支えているのは、リハーサルで指揮者が指示するものとは別次元の、教育という長い時間軸を通じて演奏者の身体の一部となった音楽性である。齋藤秀雄の没後40年余りが過ぎた今、オーケストラのそうしたバックグランドも少しずつ変わっていかざるを得ないだろう。それを思うと、現在立ち会える演奏を「奇跡」と呼ぶのも、決して大げさではない。