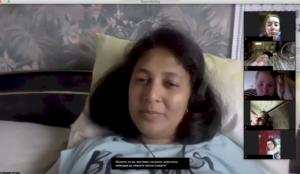Rimini Protokoll 『Call Cutta At Home』|田中里奈
Rimini Protokoll 『Call Cutta At Home』
Text by 田中 里奈 (Rina Tanaka)
画像提供:Rimini Protokoll
舞台のローカル性はいったいどこに顕れるのだろうか。近くと遠くがあべこべになってしまった現状において、ローカル性とはいったい何を指すだろうか。パフォーマンス学者のリチャード・シェクナーは7月の時点で、「日常性が中断され自己を隔離しながらも、極端なまでにリーチアウトが可能である状態」と形容したi。なるほど、自宅から外に出ることを最小限に抑え、物理的に身近な相手と対面で会うことが稀になったが、それと同時に、地球の裏側にいるはずの人やそこで行われたパフォーマンスを見聞きする機会は格段に増えた。 けれど、新型コロナウイルス感染症の流行によって生じたかのように見える問題の多くがずっと前からそこにあったように、今日の私たちを取り巻く〈あべこべのローカル性〉も、単に当たり前すぎて鑑みられて来なかっただけかもしれない。
ドイツ語圏のパフォーマンス集団リミニ・プロトコルによる『コール・カッタ Call Cutta』(2005)は、〈あべこべのローカル性〉という問題を、ユニークな方法で扱った「携帯電話演劇」だii。インド北部・コルカタ(旧称:カルカッタ Calcutta)市中で初演されたこの作品には、参加者1名と演者1名の計2人しか登場しない。参加者は、携帯電話でコールセンターのオペレータ(=演者)とつながる。電話越しに聞こえてくる英国(または米国)風アクセントの利いた声に応じて、街の中を移動する。自分がいま存在している場所を、見知らぬ誰かが何万km彼方からナビゲートしてくれて、自分以上に詳しく教えてくれる。それは日常や当たり前と感じてきた対象を、別のフィルタを通してみる体験に他ならない。
『コール・カッタ』はその後、ベルリン市・西クロイツベルクで再演された。今度は、ベルリンにいる参加者がコルカタのコールセンターで働くオペレータ(インド風アクセント付き)につなげられた。その3年後、上演の場を街中からオフィスの一室に移したアップデート版『コール・カッタ・イン・ア・ボックス Call Cutta in a Box』(2008)がベルリンで上演された。同作は、スイスやフィンランドをはじめ、韓国やアメリカ、南アフリカといった世界各地に波及した。普段通りの生活を送っていたら、多くの人が出会うべくもなかった2つのローカル、すなわち外部委託先と顧客を、プライベートな個人通話という形でつなぎ直す本作が再演を繰り返してグローバルになってしまったのだから愉快である。
Zoomで行った「携帯電話演劇」
さて、ようやく本題だ。コロナ危機による海外渡航の制限が解けぬ中、リミニ・プロトコルは今年の春に突如として主役に躍り出たビジネスツールを、最新版『コール・カッタ』に採用した――Zoomである。
新作は『コール・カッタ・アット・ホーム Call Cutta At Home』と名付けられた。パフォーマンスの会場は個々人の自宅に移ったというわけだ。今年7月にロシア・サンクトペテルブルクの国際夏季芸術祭「アクセス・ポイント The Access Point」の枠内でまず初演されたが、私が参加したのは、米マサチューセッツ州ウィリアムズタウンの’62 センター・フォー・シアター・アンド・ダンスにおける11月の公演だ。
では、どうやってパフォーマンスは執り行われたか。まず、参加エントリーを済ませると、公演主催者から一通のメールが届く。そこには、Zoomミーティングへのリンクと共に、次のような注意書きが書かれている。
このパフォーマンスでは、あなたにとって可能な範囲で、課題を遂行したり歩き回ったりすることがあなたに求められます。パフォーマンスの視聴には、携帯端末(携帯電話、タブレット、ノートパソコンなど)とヘッドセットの使用を推奨します。メモ用紙とペンの用意もお願いします。
Zoom経由での視聴型ないし参加型演劇に何度も触れてきたし、リミニ作品の知識もある程度あった。そのはずなのに、開演までの時間がこんなに不安になったことは未だかつてない。歩き回る? この狭い家の中を? 日本時間で夜中の2時に? 先に言っておくと、無茶ぶりに対するこの不安は的中した――あなたのベランダの向こうに見えている隣家の住人が、夜中の2時にカーテンと窓を開けて、外の様子をスマホで撮影し始めたら、あなたはどうするだろうか? …そっと見なかった振りをしてくれていたらいいのだが。
それはさておき、定刻にZoomミーティングに入室すると、2名の演者と十数名の観客(その多くがヨーロッパからの参加者だった)、そしてテクニカルスタッフの計20名がそこにいた。演者のSunnyとMadhuは、いずれも『コール・カッタ』の旧バージョンに出演しており、コルカタのコールセンターで働いていたオペレータだ。Madhuはコルカタにいて、Sunnyはエストニアのタリンに引っ越した。住む場所は違えど、今や二人ともリモートワーカーだ。そういった状況が、二人の会話の内容から断片的に読めてくる。
「断片的に」と言ったのは、全編がインド英語であり、なおかつMadhuのインターネット回線が最初の15分間、なかなか安定しなかったからだ。オリジナルのバージョンが国際電話を用いたのだから、不安定なメディアを介したコミュニケーションもまた作品の本質なのだろうが、参加者への指示を聞き取ることの難易度がすでに高い。とはいえ、75分間の上演は15分毎に流れるジングルとアニメーションで細かいパートに区切られるので、ウッカリ指示を聞き洩らして置いてきぼりを食らっても、復帰しやすいことは確かだ。
机の下に隠れて。台所に行ってお茶を淹れてきて。窓の外をカメラで写して。家族の写真を見せて。部屋の中で横になって…数多の指示を完全に遂行できた観客は、私の参加した回ではそう多くなかった。マイクを頑なにオンにしない参加者もいたし、パソコンで入室してしまったために、「自宅内を歩き回る上演」を実現できない人もちらほらいた。私はと言えば、「あなたの中に、インド人のオペレータと電話したことのある人はいる?」という問いかけの最中、Zoomの操作を誤ってマイクをオンにしてしまった。慌ててオフにしたが、Sunnyは私のマイクのシンボルが一瞬点灯したのを目敏く察知したようだった。「リナ?さあ、答えて!リナ!」と言われて、私は答えるつもりのなかったことをマイクに向かってやけっぱちで話した。たしかに、私が幼い頃、住家の固定電話の番号がどこかの誰かとよく似ていたらしく、電話口からさまざまな言語が聞こえてきたのは事実だ。
「参加型演劇における参加しない観客」という点で思い出されたのは、今年9月にムーゾントゥルム芸術家センターで上演された、ゴブ・スクワットによるハイブリッド演劇『ショウ・ミー・ア・グッド・タイム』だiii。この作品では、劇場内にいる俳優と観客たち、劇場の外、フランクフルト市内とイギリスに散らばった俳優たち、そして画面または電話越しに召集された視聴者たちが、さまざまな形でパフォーマンスに参加する。同作では、即興系のミッション――風呂に入ったり、食事を摂ったり、落ち着ける場所を見つけたり等々――は専ら俳優が担当することになっていた。それは賢い選択だったかもしれない。なぜなら、パフォーマンス中の俳優につながる電話番号を画面の向こうの視聴者に提示してもなお――YouTubeで全世界に配信しているのに電話連絡!?というツッコミは置いておいて――、視聴者の反応が遅く、機を逸してしまうことがあったからだ。
観客参加型演劇をリモートで行う場合、参加者が関与しなければならないシチュエーションを明確に設定しない限り、参加の強度はどうしても下がってしまうiv。そうでなくとも、『コール・カッタ・アット・ホーム』というパフォーマンスは私的領域にすっぽりと収まっているので――私たちは普段、Zoomで見知らぬ他者と会議をする時に机の下に隠れたりしないし、家族の写真を相手に見せたりもしない――、参加に対する戸惑いはいっそう大きくなる。過去の『コール・カッタ』『コール・カッタ・イン・ア・ボックス』との決定的な違いは、リモートワークや公演配信が急速に認知されつつある現実と同じく、上演空間の公的性質がいっそう薄められ、私的領域がオンラインを経由して流出していることの弊害といえるのかもしれない。
音声のローカル性
ところで、『コール・カッタ』シリーズでは、演者と参加者の間に乗り越えがたい距離が横たわっていて、お互いを肉眼や肉声で視認することが不可能な状況がパフォーマンスを形作っている。にもかかわらず、パフォーマンスを通じて相対する相手を、なんとなく生身の人間だと感じることができるのはいったいなぜだろうか。電話口や画面越しに語られる〈どこか遠くの物語〉が、参加者の目や耳に届く頃には、幾分か血肉の通った〈語り〉になるという過程を考えた時、そこに介在するのは声であり、その声に含まれるアクセント――「訛り」である。
「訛り」という単語に私は苦手意識がある。「方言」や「訛り」といった語には、正しいというお墨付きをもらえる中心があって、まるでダーツのように、そこから同心円状に離れていけばいくほど点数が下がっていくような気がする。ある言葉や表現の伝播を追っていくには適した図式だが、誰かの話すことばを「訛り」と称するのはなんだか心許無い。
多和田葉子は著書『エクソフォニー』の中で、「現代では、一人の人間というのは、複数の言語がお互いに変形を強いながら共存している場所であり、その共存と歪みそのものを無くそうとすることには意味がない」と述べているv。ここでの「なまり」は、「わたしという個体がこの多言語世界で吸収してきた音の集積」という鮮やかなイメージと共に読み替えられている。ことばに備わった複数の音楽性が、ひとつの身体の中でシンフォニーを奏でている状態だ。
『コール・カッタ・アット・ホーム』では二度、Madhuの歌を聴くことになる。耳慣れないベンガル語の旋律が、終幕に際して上演の半ばで聴いた時よりもやわらかで親しげに響くのは、パフォーマンスを通じて築かれた即席の関係性に因るものかもしれないし、「訛り」の体系から一時解放されるからかもしれないし、「もう無茶な指示に答えなくていい」という単なる安心感に由来するものかもしれない。
『コール・カッタ・アット・ホーム』は2021年1月にチリのサンティアゴで上演される。前作『コール・カッタ・イン・ア・ボックス』のように長期シリーズとなるか否かは、この作品の基礎にあるリモートワークという概念がいつまで当たり前に居座り続けるかどうかにかかっている。そうなってほしくはないが、時代のエアポケットで生じたこの作品の行方を見守っていたくはある。
(2020/12/15)
——————————————————
Rimini Protokoll, Call Cutta At Home
at 62 Center for Theatre & Dance, Williamstown (Virtual), November 5-6 & 7-8, 2020
Based on
Idea of Call Cutta (produced in 2005 by Goethe Institut Kolkata, HAU Hebbel am Ufer Berlin, Rimini Protokoll) and Call Cutta in a Box (produced in 2008 by Hau Hebbel am Ufer Berlin)
Idea, Text, Direction by Helgard Haug / Stefan Kaegi / Daniel Wetzel (Rimini Protokoll)
Performers: Madhusree Mukherjee, Sunayana Roy
Technical Director: Ksenia Kozhevnikova
A production of Rimini Apparat, co-produced by
VI International Summer Festival of Arts “The Access Point”
——————————————————
田中里奈 Rina Tanaka
東京生まれ。明治大学国際日本学研究科博士課程修了。博士(国際日本学)。博士論文は「Wiener Musicals and their Developments: Glocalization History of Musicals between Vienna and Japan」。2017年度オーストリア国立音楽大学音楽社会学研究所招聘研究員。2019年、International Federation for Theatre Research, Helsinki Prize受賞。2020年より明治大学国際日本学部助教。最新の論文は「変容し続けるジュークボックス・ミュージカル──ヴィーンにおけるミュージカルとポップ・ミュージックの関係を例に」(『演劇と音楽』、森話社)。
——————————————————
i TDR Editors, “Forum: After Covid-19, What?”, The Drama Review, vol. 64, No. 3, p. 224. 内野儀による日本語翻訳版がソーシャルディスタンスアートマガジン『かもべり』上で閲覧可能である。
ii Rimini Protokoll, “Call Cutta,”
iii Gob Squad, “Show Me A Good Time,”
iv この点で言うと、今年4月にオーストリアのイマーシヴシアター劇団Nestervalが実施したZoom演劇『クライスキー・テスト』は参加者の関与度を高めた作品だ。参加者は二人一組になってブレイクアウトルームに入れられ、そこに次々と送られてくる「被験者」を、チャット経由で送られてくる質問文を使って「審査」するよう指示される。
v 多和田葉子「ハンブルク――声を求めて」(『エクソフォニー:母語の外へ出る旅』岩波現代文庫、pp. 82-93)、2012(初刊:岩波書房、2003年)。