小人閑居為不善日記|ジョーカーたちのホワイト・ルーム――吾妻ひでお追悼に代えて|noirse
ジョーカーたちのホワイト・ルーム――吾妻ひでお追悼に代えて
Joker’s White Room
Text by noirse
1
駅の近く、黒いカーテンのかかった白い部屋
黒い屋根の街並みと汚れた舗道、疲れ切った椋鳥が見える
君の黒い瞳の中、月光を浴びながら、銀色の馬が駆けていく
朝日が君に笑いかけて、ぼくは満ち足りた気持ちだ
陽の光の入らない、この部屋でぼくは待っている
影さえも消えてしまうこの部屋で、いつまでも待ち続けている
 10月6日、英国を代表するドラマー、ジンジャー・ベイカーが逝去した。この曲はエリック・クラプトン、ジャック・ブルースとの名トリオ、クリームの代表曲〈ホワイト・ルーム〉(1968)の一節だ。作詞はジンジャーが引き入れた詩人、ピート・ブラウンによる。ビート詩人の影響下にあった彼らしい、当時の混沌とした状況をそのまま反映させたような詩だ。
10月6日、英国を代表するドラマー、ジンジャー・ベイカーが逝去した。この曲はエリック・クラプトン、ジャック・ブルースとの名トリオ、クリームの代表曲〈ホワイト・ルーム〉(1968)の一節だ。作詞はジンジャーが引き入れた詩人、ピート・ブラウンによる。ビート詩人の影響下にあった彼らしい、当時の混沌とした状況をそのまま反映させたような詩だ。
〈ホワイト・ルーム〉は、現在世界中でヒットを記録している映画《ジョーカー》で、群衆が暴動を起こすシーンで使用されている。ジョーカーはバットマンの宿敵で、映画化される度に誰が演じるのか話題を呼んできた。
アメコミ映画に馴染みがなければ、歌舞伎やオペラを想像してほしい。ジョーカーはひとつの素材で、そこに様々な演出家や脚本家、俳優によって新解釈が課されていくわけだ。今回は特に趣を変え、ジョーカーの誕生を描く作品として企画された。
 ピエロとしてわずかな収入を得ているアーサーの夢は、人気のコメディアンになることだった。しかしアーサーには笑いの才能はなく、病気や貧困、周囲の無理解により、彼の精神は追い詰められていく。
ピエロとしてわずかな収入を得ているアーサーの夢は、人気のコメディアンになることだった。しかしアーサーには笑いの才能はなく、病気や貧困、周囲の無理解により、彼の精神は追い詰められていく。
ある日酔っ払ったエリート証券マンに絡まれたアーサーは、彼らを射殺してしまう。ところが社会に不満を抱いていた群衆はアーサーを英雄視し、街は暴動に包まれていく。
監督のトッド・フィリップスはアイヴァン・ライトマンやジョン・ランディスのファンで、《ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い》(2009)で成功を収めるなど、喜劇志向の作風だった。一転、《ジョーカー》はどシリアス。180度方向性が変わっている。
トッドは《ジョーカー》の製作開始前後の2014年、ウォーク・カルチャーを巡る発言で「炎上」している。ウォーク・カルチャーの「ウォーク」とは「walk」ではなく「woke」、つまりwakeの過去形で、差別などの問題に関して自覚的にふるまおうという動きのことだ。トッドはVanity Fair誌に寄せたコメント――コメディは本来不謹慎なものなのだから、ウォーク・カルチャーが広まる中で作るのは難しい――が曲解され、批判の的となった。トッドはコメディを捨て、それ以外の方法で「不謹慎なもの」を作ろうと考えた。それが《ジョーカー》だ。
2
 さて、先程の「解釈」という点から、《ジョーカー》を見てみよう。トッドはもともと名門・ニューヨーク大学映画学科を卒業しており、マーティン・スコセッシの《タクシードライバー》(1976)、《キング・オブ・コメディ》(1983)や《レイジング・ブル》(1980)や、シドニー・ルメットの《セルピコ》(1973)、《狼たちの午後》(1975)、《ネットワーク》(1976)といった、ニューヨークを代表する監督たちの作品群を参照し、アーサーの苦悩を重厚に表現してみせた。
さて、先程の「解釈」という点から、《ジョーカー》を見てみよう。トッドはもともと名門・ニューヨーク大学映画学科を卒業しており、マーティン・スコセッシの《タクシードライバー》(1976)、《キング・オブ・コメディ》(1983)や《レイジング・ブル》(1980)や、シドニー・ルメットの《セルピコ》(1973)、《狼たちの午後》(1975)、《ネットワーク》(1976)といった、ニューヨークを代表する監督たちの作品群を参照し、アーサーの苦悩を重厚に表現してみせた。
 これまでのジョーカー像で最も高く評価されているのは、クリストファー・ノーラン監督による《ダークナイト》(2008)の解釈だった。ヒース・レジャー演じるジョーカーも自らの悲惨な半生を語っていくが、言った側からすべて嘘だったと翻していく。結局、映画の最後まで彼の出自は謎のままだ。ジョーカーの素顔は誰にも分からず、残るのはピエロのメイクだけ。このジョーカー解釈は、9.11以降、これほど「匿名の悪」を的確に表現した例は他にないと絶賛された。
これまでのジョーカー像で最も高く評価されているのは、クリストファー・ノーラン監督による《ダークナイト》(2008)の解釈だった。ヒース・レジャー演じるジョーカーも自らの悲惨な半生を語っていくが、言った側からすべて嘘だったと翻していく。結局、映画の最後まで彼の出自は謎のままだ。ジョーカーの素顔は誰にも分からず、残るのはピエロのメイクだけ。このジョーカー解釈は、9.11以降、これほど「匿名の悪」を的確に表現した例は他にないと絶賛された。
それを踏まえると、《ジョーカー》でのジョーカー解釈は古典的だ。しかし格差や低賃金に苦しみ、希望も余裕もない生活を続けている人の多い今、ストレートなアプローチこそ訴えるのだろう。
一方で批判も多い。《ダークナイト》より劣るとか、ニューシネマのエピゴーネンであるとか以外にも、差別を助長するだとか、暴動や事件を誘発するなど、倫理的な観点からも問題視されている。
だが、それはすべて折り込み済みだろう。方法論が古かろうが、内容がベタだろうが、ここまで観客が欲しているものを敏感に察知し、見事に映像化してみせた例はめずらしい。その前ではこうした批判は的外れだ。
ジョーカーには政治的背景はなく、ただの愉快犯だ。その点、テロリストの衣装を施した《ダークナイト》よりも、感情の赴くままに行動するアーサーの方が、観客の教官を得やすいだろう。アーサーのように孤独で、失うものを持たず、何も恐れない犯罪者。 日本では 彼らを、主にネットにおいて「無敵の人」と呼ぶようになった。
アーサーは、ただ人を傷つけて喜ぶような人間ではなかった。彼をそこまで追い詰めたのは誰だったのか。アーサーのように孤独で、未来がなく、何も持たず、だからこそ何も恐れなくなった「無敵の人」に、観客は共感する。
だからといって彼らが犯罪に走るようなことはないし、むしろいいガス抜きになるだろう。これも映画のひとつの役目だ。
しかしわたしは、また別の意味で、《ジョーカー》への不満を拭えないのだ。
3
「人生はクローズ・アップにすれば悲劇だが、ロング・ショットで見れば喜劇」。喜劇王チャップリンの有名な言葉だ。
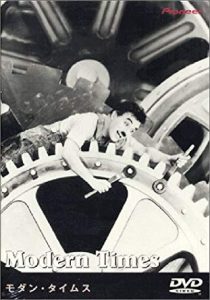 映画で大道芸人と言えばチャップリンだ。《ジョーカー》でもチャップリンが引用されている。だが《ジョーカー》は、チャップリン的なありかたとは遠い。それはチャップリンのこの言葉に集約されている。
映画で大道芸人と言えばチャップリンだ。《ジョーカー》でもチャップリンが引用されている。だが《ジョーカー》は、チャップリン的なありかたとは遠い。それはチャップリンのこの言葉に集約されている。
アーサー役のホアキン・フェニックスの演技は、たしかに一世一代の名演だ。苦悩に押し潰され歪む表情、痩せこけて悲壮感の漂う裸身、ひきつって痙攣する笑い。見ていて痛々しくなるほどだ。
先程のチャップリンの言葉は、主観的に表現するか(クローズ・アップ)、それとも客観的に突き放すか(ロング・ショット)ということになるだろう。チャップリンは客観的に自己を相対化して笑いを誘ってみせる。
表情ひとつ取ってもそうだ。チャップリンに限らず、キートンやモンティ・パイソンも、どんな状況下でも無表情を貫いていた。その落差が笑いを生むと分かっているからだ。《ダークナイト》のジョーカーも、最後まで素顔を見せはしなかった。だがアーサーは、率先して素顔を晒し、悲劇に身をゆだねてしまう。
ここでひとりのマンガ家の話をしたい。10月13日、吾妻ひでおが世を去った。70年代後半から80年代前半にかけて、先端を走っていたSFを取り込み、不条理マンガという領域を開拓し、のちの「萌え」文化への道筋を築いていった、マンガ史上に残る特異な才能だ。
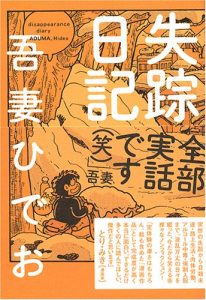 しかし、一般的によく知られているのはそうした作品群ではなく、《失踪日記》(2005)だろう。ギャグマンガ家は精神を病みやすいと言われるが、吾妻も限界まで追い詰められて何度か失踪し、ホームレス生活を送っていた。その体験をエッセイ風に綴った作品だ。
しかし、一般的によく知られているのはそうした作品群ではなく、《失踪日記》(2005)だろう。ギャグマンガ家は精神を病みやすいと言われるが、吾妻も限界まで追い詰められて何度か失踪し、ホームレス生活を送っていた。その体験をエッセイ風に綴った作品だ。
自殺に失敗し、ゴミ箱を漁り、道行く人に軽蔑され、マンガ家に復帰してからも酒がやめられず、アル中治療のため強制的に入院させられる。話は悲惨そのものだが、マンガ自体は吾妻特有の丸っこくシンプルな筆記で淡々と描かれている。
印象的なのは、吾妻の顔に張り付いた笑顔だ。吾妻作品には、「不気味」や「ナハハ」、「のた魚」など、笑顔だが目は笑っていないとか、終始無表情のキャラが多い。マンガ批評家の夏目房之介は、その向こうに虚無が横たわっていると評した(別冊宝島EX《マンガの読み方》)。
吾妻はどんな絶望の中でも、「ロング・ショット」で自分を見つめ、客観的に捉えることでバランスを取り、あまつさえ笑いの対象にしてみせた。それは口でいうほど簡単なことではなかったはずだ。
彼の訃報はショックだったが、病死と聞いて、不謹慎にもこう思ってしまった。吾妻ひでおは、自らの嵐をくぐり抜け、最後まで生き抜いたのだと。自殺せず、なんとか生を全うしたのだと。
4
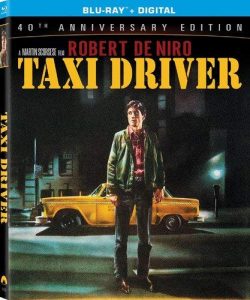 追い詰められ、自暴自棄になった「無敵の人」を救済できるのか。これはドストエフスキーの昔から、長らく文学や映画の命題だった。《タクシードライバー》もその系列にある(スコセッシはそれまで《地下室の手記》の映画化を構想していた)。
追い詰められ、自暴自棄になった「無敵の人」を救済できるのか。これはドストエフスキーの昔から、長らく文学や映画の命題だった。《タクシードライバー》もその系列にある(スコセッシはそれまで《地下室の手記》の映画化を構想していた)。
 この主題は、テロの時代に突入した現在、かつてより重要度を増しているだろう。《タクシードライバー》の脚本家ポール・シュレイダーも近作《魂のゆくえ》(2017)で、「無敵の人」の救済をテーマにしてみせた。だが内容は、愛だけが「無敵の人」を救うという、残念なものだった。愛がそんなに簡単に手に入れば、「無敵の人」など生まれはしないのだ。
この主題は、テロの時代に突入した現在、かつてより重要度を増しているだろう。《タクシードライバー》の脚本家ポール・シュレイダーも近作《魂のゆくえ》(2017)で、「無敵の人」の救済をテーマにしてみせた。だが内容は、愛だけが「無敵の人」を救うという、残念なものだった。愛がそんなに簡単に手に入れば、「無敵の人」など生まれはしないのだ。
もちろん現実的には、地道に法律や福祉などの手段を取っていくのが妥当なのだろう。しかしそれだけしかないのだろうか。日本で「無敵の人」というと真っ先に秋葉原事件が連想されたが、今はやはり京都アニメーションの事件の犯人になるだろう。吾妻ひでおが開拓した「萌え文化」を代表するスタジオが、その作品にのめり込んだのであろう「無敵の人」によって被害を受けた事実には、言いようのない虚しさが漂う。これは文化の問題でもあるはずだ。
冒頭の《ホワイト・ルーム》は、病院を想起させる「白い部屋」という言葉や、暗い場所で待ち続けるというイメージが、ジョーカーにふさわしいと解釈されたのだろう。だが実はこの「白い部屋」とは、作者のピート・ブラウンがアルコールやドラッグ漬けの日々から足を洗うため転居したアパートのことだった。彼はクリームの仕事で評価され、メンバーのジャック・ブルースとタッグを組み、自身でもバンドを率いて、成功を手にした。その後スコセッシと出会い、シナリオさえ手掛けるようになった。「陽の光さえ入らない部屋」に留まり続けるかどうかは、住人次第だ。
《ジョーカー》も優れた映画だと思う。だが、「無敵の人」の苦しみを取り除く手助けにはならない。黒いカーテンに閉ざされた部屋を照らす光明のような作品が、ひとつやふたつあってもいいのではないだろうか。
(2019/11/15)
———————-
noirse
佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中


