音楽にかまけている|タラスキンの音楽史|長木誠司
タラスキンの音楽史
text by 長木誠司(Seiji CHoki)
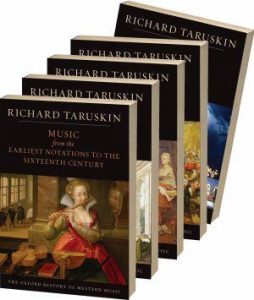 リチャード・タラスキンの『西洋音楽の歴史』は、本体の5巻すべてに同じ「導入」が置かれている。そこで語られているのが彼の音楽史記述の骨子なのであるが、「何の歴史なのか?」というそのタイトルからして、彼がかなり思い切った意図で浩瀚な「音楽史」を書き始めようとしていることが伝わってくる。その基本的な精神は、モットーのように掲げられているフランシス・ベイコンの『学問の進歩(科学の威厳および進歩について)』(1623)からの引用でも明らかである。
リチャード・タラスキンの『西洋音楽の歴史』は、本体の5巻すべてに同じ「導入」が置かれている。そこで語られているのが彼の音楽史記述の骨子なのであるが、「何の歴史なのか?」というそのタイトルからして、彼がかなり思い切った意図で浩瀚な「音楽史」を書き始めようとしていることが伝わってくる。その基本的な精神は、モットーのように掲げられているフランシス・ベイコンの『学問の進歩(科学の威厳および進歩について)』(1623)からの引用でも明らかである。
曰く、あらゆる時代の記録から、どの時代どの地域で、どのような個々の学問と芸術(アルス)が繁栄したか。遺物、発展、移動、崩壊、消失、再興という要素を視野に入れながら、すべてにおいて、その発生の要因(起こり)を結びあわせる。歴史的な方途によって、そして批評のマナーに従って、単純に事実を歴史的に語る、そこに個人的な判断も多少取り混ぜながら。
音楽史記述が、ともすると作曲家の個人史になったり、あるいはせいぜい作曲家の称賛に終わることが多く――「偉大な」作曲家がいるのではなく、多く、周到に記述されることが「偉大さ」を産み出してきた、一種の「作られた伝統」として――、さもなければ事実の列挙に終わってしまうことがせいぜいか、あるいはひとつのジャンルの有機体的な歴史記述――どのように発生して、どのように繁栄し、どのように衰退していったのかということの、「客観的な」記述――に終始することが多いのに対し、タラスキンはそれらとは異なった音楽史を書こうとした。
かつて、ドイツの碩学とされる音楽学者のカール・ダールハウスは、やはり19世紀の音楽史を記述しようとして、まずなにを「対象」に記述するのかを明確にするために、その方法論についてだけで一冊の本を記述することになった。翻訳もされている『音楽史の基礎概念』というのがそれだが、タラスキンの持っている問題意識はそれと似ているようで、かなり異なっている。
タラスキンは、ダールハウスが一見正当なように立てるあらゆる二項対立の構造に、まったく共感していない。例えば、ダールハウスの問いかけはこうだ――芸術史は芸術の「歴史」なのか「芸術」の歴史なのか。こうした対立構造は、きわめて人為的であり、立てたことでなにか主張しているように見えて、その実それらは弁証法的な歴史記述のタテマエにしかなっていない。そのおおもとにはヘーゲルに始まり、20世紀にはアドルノによって混濁させられた歴史記述の大きな硬直性があるとタラスキンは見ているようだ。2巻にわたる20世紀音楽の記述に際して、何度もアドルノが引用され、その記述の非正当性が批判されているのだが、それは同時にこの哲学者にして社会学者、文芸批評家、音楽学者にして音楽家であったアドルノの影響力が、かつてのドイツ語圏を超えて、1970年代以降英米圏にも大きな影響力を持っていたことを裏付けるものなのではあるが、それをタラスキンは苦々しく思っているフシがある。
いずれにしても、こうした人為的で硬直した二項対立は「無意味な区別」として捨て去るところから、タラスキンは出発することになる。
彼が求めるのは、アドルノ~ダールハウスのような「あれかこれか」路線ではなく、言ってみれば「あれもこれも」路線である。歴史的な資料は、とにかく引用されるだけではなく分析されることが必要で、それもcatholic(全般的)に、exhaustive(網羅的)にであって、因果的説明と技術的説明の両者が求められている。それによって、さまざまな事象の設立理由と道筋を明確にしていくことが記述の大要となる。それゆえ、あらゆる音楽史上の「事象」が採り上げられるわけではなく、かなり限定された記述であることも理解されよう。ヨーロッパ音楽全体を採り上げることが音楽史記述の目的ではなく、価値判断はいちおう度外視しながらも――採り上げるか否かは価値とは無関係――、記述からは多くの有名な作曲家や作品が漏れていくことになるが、それを冒頭に宣言している音楽史というのも画期的だ。
例えば、タラスキンがもっとも力を入れているロシア音楽のいろいろな章があるが、「証言」論争に始まるショスタコーヴィチ像について、彼はどちらかの立場を取るということをしない。明確なショスタコーヴィチ像は、むしろそのどちらもあり得るところ正像を結んで成立し、そのどちらかを正当化するところにはないからである。むしろ、その両者が成り立つ要因を「説明」することが歴史だという考え方が、記述すべてを支配している。
20世紀の記述でいつも問題になる「モダニズム」に関しても、タラスキンは二項対立ができないようなスタンスを取っている。「モダニズム」ではなく「マキシマリズム」という用語が頻出する。モダニズムが暗黙のうちに内包し、歴史記述を内側から限定してしまうような「新しさ」の含蓄を排除しておくためだ。新しいか古いかが問題ではない。それよりも、あらゆる現象が最大限の可能性で登場するという意味での「マキシマリズム」が20世紀の音楽事象を支配している。それで、いたるところにこのことばによる記述が登場することになる(まあ、ちょっと水戸黄門の印籠のような印象がないわけではないけれど)。
対象となるものがliterate(文字化された)な音楽文化であることも、タラスキンのこだわる点である。要するに、文字として残されているものしか扱わない。これはある意味で歴史学の基本ではあるのだが、徹底して音楽史記述に採り入れられたことがなかったのは不思議と言えば不思議かも知れない。「文字」と言っても、もちろん、字義通りのそれではなく、記譜された音符を含めての、大きな広がりを持つものだが、その世界は首尾一貫しており、その伝統があるところでは「始まり」が知られ、説明でき、先も予見できる。それがいわゆる音楽のハイアートに限られることも事実であるが、例えば記譜されない民俗音楽からの影響関係のようなものが無視されるかというと、バルトークやストラヴィンスキーについての記述の際にも明らかなように、残されたリテラルなものからの判断が縦横に駆使されていく。
ある意味、非常に割り切った記述方法であり、記述対象の捉え方がそこに見える。対象はリテレイトなものが現れ始め、非リテレイトなものとの相関があったころから、20世紀末にそれが壊れて、音楽のメディアが文字や書かれたもの一般から離れ始めるまでに限定され、対象はハイアート、すなわち一種の高級文化である。そこだけ見ると、いろいろな批判が考えられるかも知れない。しかし、「書」によって散種される音楽という、その潔いまでの限定のなかで、その歴史の主人公は社会史であり、いわゆるマスターナラティヴは回避され、あらゆるシングル・ストーリーは否定されて、芸術の自律性を求める美学的ナラティヴも、目的論的なネオ・ヘーゲル的な歴史的ナラティヴも却下され、独特の歴史の読み直しが図られていく。
その個別の詳細は、あえてここでは書かないが、すべての章で非常にスリリングでエキサイティングな記述がなされていくことだけは指摘しておこう。毎週大学のゼミでタラスキンを読んでいたことは前回書いたけれど、60~70ページほどの英語記述をゼミで読むのは、とりたててたいへんだとは思わないものの、たぶんそれによって他の仕事や作業はかなり犠牲になった。でも、楽しいゼミ生活の1年間であった。
19世紀の巻(第3巻)が、現在邦訳中という話も耳にする。それがうまく市場で回転すれば、20世紀の2巻(第4,5巻)の邦訳も可能かも知れない。いや、かなり難しいという予感も感触もあるけれど――
(2019/3/15)
———————————–
長木誠司(Seiji Choki)
1958年福岡県出身。東京大学大学院総合文化研究科教授(表象文化論)。音楽学者・音楽評論家。オペラおよび現代の日本と西洋の音楽を多方面より研究。東京大学文学部、東京藝術大学大学院博士課程修了。著書に『前衛音楽の漂流者たち もうひとつの音楽的近代』、『戦後の音楽 芸術音楽のポリティクスとポエティクス』(作品社)、『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』(平凡社)。共著に『日本戦後音楽史 上・下』(平凡社)など。



