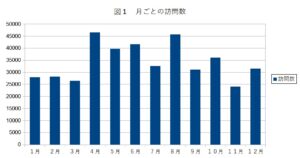私がものを書き始めたのは|過去、現代、未来との対話|大田美佐子
過去、現代、未来との対話
Text & Photo by 大田美佐子(Misako Ohta)
2年目から関わらせて頂いているMercures des Artsも5周年を迎えたとのこと。丘山万里子編集長をはじめ、素晴らしい執筆者の仲間とご一緒でき、表現できる場を頂いていることに、学ぶことの喜びも感じ、あらためて感謝しています。
私が音楽について書くことをはっきりと意識したのは、おそらく吉田秀和さんのホロヴィッツ評がきっかけだったと思います。「ひび割れた骨董品」と酷評された時の批評です。戦中世代の父がクラシック好きだったことからピアノを習っていた私は、初来日を果たした1983年、NHKホールに両親とホロヴィッツのリサイタルを聴きに行きました。演奏で特に覚えているのはスカルラッティ。当時高校生で、将来について、漠然と新聞記者か音楽界で仕事をしたいと考え始めていた私は、この時のことを文章に書き、後に高校の文集に掲載されることになりました。その時、ショパンコンクールを通して一躍時の人となっていたスタニスラフ・ブーニンのコンサートにも行き、ブーニンの超絶技巧で型破りのショパンに熱狂し、その若々しいロックのライブのような熱気に包まれたコンサートでの演奏と、ホロヴィッツの円熟し完成された音楽性とを対比して書いてみようと思ったのでした。そして結果的に、直感的に、ホロヴィッツのスカルラッティの渋さと繊細なピアニッシモの陰影を、谷崎潤一郎が「陰翳礼讃」で表現した暗闇で見た蒔絵の放つ鈍い光の陰影になぞらえて書いたことを覚えています。
そうして、大学で音楽学を学ぶことになった私が、次に音楽について書くことの意味を意識したのは、卒論、修論、博士と研究してきた亡命作曲家、クルト・ヴァイルに向き合ったからです。ヴァイル作品について、指揮者のデニス・ラッセル・デイヴィスは「《マハゴニー市の興亡》に最終稿はない」と言い、共作者のブレヒトは、つねに「ワーク・イン・プログレス」の劇作家だったと評され、ヴァイルの音楽劇は毎回、演者や音楽家、演出家によってまったく異なる姿を見せます。音楽劇としての「三文オペラ」は、つねに社会情勢を反映して流転するのです。オペラと演劇というある意味で水と油を内包したこの作品は、上演されるたびに新たな光を放つと言えます。そして、その光源がどこから来るのか、動悸がするほど毎回、書き手は本気で試されます。そして、結果としてはまったく違う姿を見せる舞台でも、そのひとつひとつの実験の根っこは、やはり音楽と言葉の刺激的な関係性を追い求めたヴァイルとブレヒトの《三文オペラ》の世界と、どこかで深く共鳴しあっていると気づくのでした。《三文オペラ》が「どんな作品なのか」を語ることは、書き手としてひとつの大きな挑戦といつも感じています。(写真は恩師、故岩淵達治学習院大学名誉教授の最終講義で《スラバヤ・ジョニー》を歌う筆者)
ちょうど、ウィーン大学でヴァイルの音楽劇についての博士論文を書いていたころ、クシェネクに作曲を師事し、現代音楽界の立役者でもあったローター・クネッスル先生の現代音楽の講義を受講しました。クネッスル先生はウィーンの教養人らしく、クラシックからジャズ、現代音楽と守備範囲が幅広く、授業のはじめには必ず学生たちに「この一週間で何を聴いたか?」と問いかけました。このウィーンで生の音楽を聴かない人は、この授業も聴く必要がない、とでも言うように。後になって、音を生み出す側にも、音を受け止める側にも、音楽を通した関係性のなかに音楽が存在するのだ、と気づかされたのはこの授業のおかげでした。
演奏評を書き始めたのは、5年半のウィーンでの留学生活を終えて日本に帰国し、大学に勤め始めた2003年のことです。1本目はびわ湖ホールで上演されたトリエステ・オペラの《ルチア》。年に数本ではありましたが、オペラとオーケストラを中心に新聞の関西版の夕刊に書き始めました。担当の記者の方は理想的な伴奏者で、よく一緒に聴いた音楽について、それを表現する言葉遣いについて話し合い、勉強になりました。書き手にとって、編集者の重みは絶大です。しかし、私自身はつねに「未熟者が批評を書くというスタンス」について、自分なりに悩み続けていました。その問いに答えをくれたのは、自分自身の研究を通した出会いがきっかけでした。1920年代にヨーロッパで活躍し、ウィーンの音楽雑誌「アンブルッフ」に執筆していたアドルノやエルンスト・ブロッホ、オスカー・ビーやパウル・シュテファンなど、数々の批評家たち、あるいはニューヨーク・タイムズの劇評家ブルックス・アトキンソンなどの批評です。彼らの仕事は、あたかも現地で観たような興奮を再現してくれる劇評、音楽評で、そこから得られる知見があってこそ、音楽劇の歴史研究が進められるからです。彼らから学んだことの恩返しのつもりで、現代の素晴らしい舞台、その一期一会を記録していきたい。今、読んでくださる方にも、もしかして未来に読んでくださる方のためにも、そこに、時代と場所を超えて、対話が生まれるというのが音楽評、舞台評の意味だと感じています。
アドルノが「音楽社会学序説」で指摘したように、聴取には経験によって様々なレベルがあると思います。しかし、誰にでも「聴くこと」自体は開かれています。何を受け止めることができるのか、私はプロフェッショナルで構造的な聴取が絶対的なものであるとは思いません。できれば、そこにヒエラルキーを築き、分断や断絶を作ってしまうよりも、開かれた聴取に対話をもたらし、その複雑性を楽しむことができるような、そんな表現の記録をこれからも続けていければ、と願っています。
(2020/10/15)