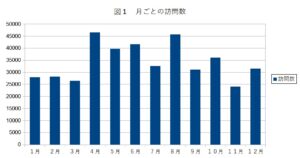忘れがたいコンサート|超・弦楽四重奏団|藤原聡
超・弦楽四重奏団
text by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)
昔の自分がとある演奏に感銘を受けたとして、それを今現在の自分が聴いても同様の感銘を受けるかどうか―それは分からない。演奏行為とは1回限りのものだから完全に同じ音楽を聴くことは不可能だ。録音されていたとしても無論それは完全に別のものである。例えばまた、20歳の時の自分と40歳の時の自分は当然同じではないので、前者の年齢時に東京文化会館の1階席で感動と共に接したカラヤンとベルリン・フィルの音楽を後者の年齢の自分がタイムスリップでもして聴き得たとしてどう感じるのかもまた分からない。だから、「忘れられない名演奏」という企画が仮にあるとして(と言うかこれがそうなのだが‐笑)、その感銘をどこかで相対化しようとする意識が常に働く。後生大事に胸の底に抱いている美しい記憶に浸りがちな自分を別の自分が上から眺めている、「そんなに感銘を受けるほどの演奏だったの?」。しかし、こんな事を書いておいてなんだが、その疑念に拘泥しても仕方ない。その時の自分はそう感じた。それで十分な話なのだ。だから記憶は美しく、そして絶対だ。歴史には美化させてはいけない記憶もあるだろうし、批評においてもまた客観性と個人的な審美性の兼ね合いは常に問題になる。だが、その手の話はとりあえずここでは脇にどけておこう。
本稿に取り掛かるにあたり、とりあえず11のコンサートが思い出された。敢えてあまり挙げられないようなものを書いてみようか。「敢えて」とは書いたが、衝撃度はおさおさ他の10に劣るものではない。しかしこれがはっきりとした日付が思い出せない。調べても出てこない(しかし夢ではないはずだ‐笑)。1990年代半ば~後半辺りに彩の国さいたま芸術劇場で行なわれたアルバン・ベルク四重奏団(ABQ)によるコンサートでのシューベルト:『死と乙女』がそれである。当時の筆者は既にかなりクラシックを聴き込んでいたのだが、室内楽は未開拓に近い状態であった。そんな時、当時の職場の上司から件のコンサートのチケットが訳あって1枚余っている、よければどう? というような感じで誘われたと記憶している。正直、前半に何が演奏されたのかは全く覚えていない(苦笑)。しかし、後半の『死と乙女』には文字通り腰を抜かした。ABQの『死と乙女』には既に録音が存在しており、これには耳を通していたが実演ではそのインパクトがまるで違う(演奏解釈自体もテンポやデュナーミクのコントラストをより強調するものになっていた)。何という濃厚さ、表現の幅の広さ、迫力。音色の豊潤さにも圧倒された。たった4本の弦楽器でここまで出来てしまうものなのか。確か後方の席で聴いたような記憶があるのだが、まるで目前で演奏しているかのような音の届き方、とにかく音がでかい。4本の楽器はそれぞれが極限まで雄弁に語りながらも、その合奏は全く破綻せずに不思議と融和している。しかし、その融和とは基本的に1stのピヒラーが前面に出んとし、それに負けじとvaのカクシュカが食らい付き、そしてその合間を縫って冷静に、しかしミリ単位の正確なタイミングでバス声部を順応させにかかるvcのエルベン、そしてそれらとは一見無関係にガシガシと弾き倒す2ndのシュルツ。合わせることが優先なのではなく、互いが「盛りにかかって」山が高くなって行く。そこに中庸の安全運転という概念はまるでない(ピヒラーはとあるインタビューで、シェイクスピアのセリフを引き合いに出しつつ「悪平等は死の道へ繋がる」と言う意味のことを述べている)―と、このようなアルバン・ベルクSQの特徴を意識したのは後知恵がついてからのことだったが、要はそんな理屈とは関係なく、目の前でえらいことが行なわれているのだということだけは分かったのだった。このコンサート以降、筆者はABQのいわば「信奉者」となった。その後の来日コンサートは行ける限りは行った。サントリーホールで2008年6月に行なわれたあの解散公演にも当然参加した。録音も全て持っている。その後こちらの聴体験に厚みが増してくるにつれ、ABQはやり過ぎとも思う瞬間が生まれたし、果たしてこれは「室内楽」なのか? という考えも脳裏をよぎった(いわゆる「室内楽」ではないから駄目だという話ではない)。だが、それでもあのさいたま芸術劇場音楽ホールの後方座席に身じろぎ1つせずに体を沈ませていた筆者の体験は「絶対」だ。これは今後も変わることはないだろう。私は、こういう記憶の蓄積を求めて今日も性懲りもなくコンサートホールに向かう。
(2018/10/15)